太陽の神様といえば、古代エジプトのラーやギリシャ神話のヘリオスなど、男性の神を思い浮かべる人が多いかもしれません。
でも実は、世界の神話を見渡すと、太陽を司る「女神」がかなりの数存在しているんです。日本の天照大御神をはじめ、北欧、バルト、中国、ケルト、そして極北の地イヌイットの伝承まで、太陽は女性として語られてきた長い歴史があります。
神話学者のブライアン・ブランストンは、もともと太陽神は女神のほうが主流だったのではないかとさえ論じています。ギリシャ神話やエジプト神話の男性太陽神があまりにも有名になったために、「太陽=男神」という先入観が生まれたにすぎないという見方です。
この記事では、世界各地の神話に登場する太陽の女神たちを一覧で紹介していきます。それぞれの女神がどんな存在で、どのような物語を持っているのか、原典や出典を確認しながら見ていきましょう。
天照大御神(アマテラスオオミカミ)|日本神話
日本神話における最高神であり、高天原(たかまがはら)を統べる太陽の女神です。皇祖神としても知られ、伊勢神宮に祀られています。
天照大御神は、伊邪那岐命(イザナギノミコト)が黄泉の国から帰還した際、左目を洗ったときに生まれたとされています。『古事記』と『日本書紀』にそう記されており、月読命(ツクヨミノミコト)、須佐之男命(スサノオノミコト)とともに「三貴子(みはしらのうずのみこ)」と呼ばれます。
もっとも有名なエピソードは「天岩戸(あまのいわと)の神隠れ」でしょう。弟の須佐之男命の乱暴な振る舞いに怒った天照大御神が天岩戸に閉じこもってしまい、世界が暗闇に包まれるという物語です。困り果てた八百万の神々は岩戸の前で宴会を開き、天鈿女命(アメノウズメノミコト)が踊って大笑いを起こしました。不思議に思った天照大御神が岩戸から顔をのぞかせたところ、鏡に映った自身の姿に見入っている隙に神々が引き出し、世界に光が戻ったのです。
この「太陽の消失と復活」というモチーフは、日食や冬至など太陽にまつわる自然現象を物語として説明したものとも解釈されています。
なお、天照大御神は現在では一般に女神とされていますが、古来から男神とする説も存在します。朝廷が伊勢神宮に男性用の装束を献上していた記録や、別名「天照坐皇大御神御魂(あまてらしますすめおおみかみのみたま)」が男神と同一視される例があるなど、性別をめぐる議論は現在も続いています。
羲和(ギカ / Xīhé)|中国神話
中国神話における太陽の女神であり、「太陽の母」として知られる存在です。
羲和に関するもっとも古い記述は『山海経(せんがいきょう)』の「大荒南経」に見られます。そこには次のように記されています。
「東南海の外、甘水の間に羲和の国がある。女性がいて、名は羲和といい、甘淵で太陽に水浴びさせた。羲和は帝俊の妻であり、十の太陽を生んだ」
つまり、羲和は天帝・帝俊(ていしゅん)の妻として十個の太陽を産み、毎日それらを世話する母親として描かれているんです。十の太陽は東方の海にそびえる「扶桑(ふそう)」という巨大な世界樹に掛けられ、一日に一つずつ交代で天を巡るとされていました。
一方で、屈原の『楚辞(そじ)』の「離騒」では、羲和は太陽の戦車を駆る御者(日御)としても登場します。六頭の龍が牽引する戦車に乗って太陽を東から西へ運ぶ姿が描かれており、「太陽の母」とはまた異なる側面を見せています。
中国思想史学者の御手洗勝(みたらいまさる)氏は、羲和はもともと太陽神そのものだったのが、時代を経て太陽と御者が別の存在として分離し、「太陽の母」と「太陽の御者」という二つの姿に変化したのではないかと考察しています。
なお「羲和」という名前について、姜亮夫(きょうりょうふ)氏は「羲」の本字は「曦」(日の光の意味)であり、「和」は旋転を意味するとしています。つまり「羲和」とは「旋転する日光」を意味する名前なのです。
2021年には、中国初の太陽観測衛星が「羲和号」と命名されました。太陽の母である女神の名を冠した探査機が、現代の宇宙から太陽を観測しているというのは、なかなか壮大なロマンがありますね。
アリンナの太陽女神(Arinniti / Wurunšemu)|ヒッタイト神話
古代アナトリア(現在のトルコ)に栄えたヒッタイト帝国において、最高神として崇拝された太陽の女神です。「あらゆる国の女王」という称号で呼ばれていました。
この女神の起源はヒッタイトよりもさらに古く、先住民であるハッティ人の時代にまで遡ります。ハッティ語では「エシュタン(Eštan)」と呼ばれ、「大地の母(Wurunšemu)」という称号も持っていました。ヒッタイト人がアナトリアに進出した後、この女神は彼らの国家神として取り込まれたのです。
アリンナの太陽女神は嵐の神タルフンナ(Tarḫunna)を配偶神とし、二柱でヒッタイト国家の最高位に位置していました。王は太陽女神を「母」と呼び、自らをその神官として日々夕暮れ時に祈りを捧げたと記録されています。王妃は女神の巫女として仕えました。
ヒッタイト新王国時代の女王プドゥヘパの祈りの文言が粘土板に残されており、そこには「アリンナの太陽女神よ、わが女王、すべての国の女王よ!」という呼びかけが刻まれています。
崇拝の中心地は聖都アリンナ(現在のトルコ中部アラジャホユック付近とされる)で、ヒッタイト初期の王の戴冠式もここで行われました。女神は太陽の円盤として表現されることが多く、金・銀・銅の太陽円盤が毎年奉納されていたことが記録に残っています。また、鹿は太陽女神の聖獣とされ、鹿の形をした祭祀用の器も発見されています。
古代の近東世界において、太陽神を女神として崇め、しかも国家の最高神に据えたという例は非常に珍しく、ヒッタイトの宗教観の独自性を示す象徴的な存在といえるでしょう。
ソール(Sól / Sunna)|北欧・ゲルマン神話
北欧神話における太陽の女神で、ゲルマン語圏では「スンナ(Sunna)」とも呼ばれます。実は英語の「Sun」という単語も、この女神の古英語名「Sunne」に由来しています。
『古エッダ』の「巫女の予言(ヴォルスパー)」や「ヴァフスルーズニルの言葉」などの詩篇によれば、ソールはムンディルファリという人物の娘です。ムンディルファリは娘の美しさに感嘆してその子に太陽の名を付けましたが、神々はこれを傲慢とみなし、ソールを天に上げて実際に太陽の御者にしてしまいました。
以来、ソールは馬に牽かせた戦車で毎日天空を駆け巡っています。しかし彼女には恐るべき宿命がありました。フェンリルの眷属である魔狼スコール(Sköll)が、絶えず彼女を追いかけているのです。スコールが太陽に迫るとき日食が起こるとされ、やがて世界の終末ラグナロクにおいてソールは狼に飲み込まれてしまいます。
ただし物語は絶望では終わりません。『古エッダ』「巫女の予言」では、終末の前にソールは一人の娘を産むと予言されています。その娘は母よりもさらに美しく輝かしい存在で、新しい世界において母に代わって天を照らすのだとされています。
ソールの兄弟であるマーニ(Máni)は月の神で、こちらも魔狼ハティに追われています。太陽が女神、月が男神という構図は、ギリシャ神話など多くの神話体系とは逆の関係にあたります。
サウレ(Saulė)|バルト神話(リトアニア・ラトビア)
リトアニアとラトビアに伝わるバルト神話において、もっとも崇敬された女神の一柱です。リトアニア語・ラトビア語で「Saulė / Saule」は太陽そのものを意味し、「世界」を意味する単語(リトアニア語 pasaulis、ラトビア語 pasaule)は「太陽の下」という語源を持っています。
サウレは地上のすべての生命を司る存在として崇拝され、とりわけ孤児や不幸な人々の守護女神とされていました。銅の車輪を持つ黄金の戦車を疲れ知らずの馬に牽かせて毎日天空を横断し、夕暮れには海に降りて馬を洗い、夜は黄金の船で海を渡るとも語られています。
サウレの神話でよく知られているのは、月の神メーネシス(Mėnulis)との結婚と離別のエピソードです。サウレとメーネシスは夫婦となり、大地の女神ジェミナ(Žemyna)をはじめ、多くの星々を子供としてもうけました。ところがメーネシスは明けの明星の女神アウシュリネー(Aušrinė)と浮気をしてしまいます。
ある伝承では、怒ったサウレがメーネシスの顔を引っ掻いたため月には傷跡が残り、私たちが見る月面の模様はその名残だとされています。別の伝承では、雷神ペルクーナス(Perkūnas)がサウレに代わってメーネシスを切り刻んだとも語られ、月が満ち欠けを繰り返すのはこの罰によるものだとされています。
サウレに関する記録の中でもっとも古いものの一つは、1261年のスラヴ語訳による『ヨアネス・マララス年代記』で、鍛冶の神テリアヴェリス(Teliavelis)が太陽を鍛造して空に投げ上げたという神話が記されています。
バルト地域ではキリスト教化以降もサウレの信仰は民間に根強く残り、夏至祭(リトアニアではラサス / Rasos、ラトビアではリーゴ / Līgo)では現在もサウレにまつわる儀礼が行われています。2024年12月には、リトアニア議会がバルト多神教の復興運動「ロムヴァ(Romuva)」を正式な伝統宗教として国家承認し、サウレを含む古代バルト信仰が改めて注目を集めました。
オーニュ(Áine)|ケルト神話(アイルランド)
アイルランド神話において、太陽・夏・豊穣・愛・主権を司る女神です。妖精の女王としての側面も持っており、アイルランド南西部のリムリック県にある「ノカイニー(Cnoc Áine)」という丘を住まいとしているとされています。
夏至の日にはこの丘の上に姿を現すと伝えられ、ときに誰にも追いつけないほど俊足の赤い牝馬に姿を変えるとも言われます。オーニュにまつわる伝説の多くは、人間の男性との間に子をもうけるという内容で、多くのアイルランドの家系が彼女を先祖として敬っています。
ケルト神話圏には、ほかにも太陽との関連が指摘されている女神がいます。ブリギッド(Brighid)は火と鍛冶と詩の女神で太陽との結びつきが論じられ、エターン(Étaín)は太陽の輝きを象徴する女神として古い物語に登場します。ウェールズのオルウェン(Olwen)も、もともとは太陽の女神だったのではないかと研究者の間で推定されています。
また、イギリスのバースに祀られていた女神スリス(Sulis)の名前は、印欧祖語の「太陽」を意味する語根に由来しており、ギリシャ語のヘリオス、北欧のソール、ヒンドゥーのスーリヤと同じ語源を持つとされています。ケルト世界における太陽信仰の実質的な中心にいた女神とも言われています。
ベイヴェ(Beaivi / Beiwe)|サーミ神話
スカンジナビア半島北部からロシア北西部にかけて暮らすサーミの人々が信仰する太陽の女神です。
北極圏に暮らすサーミの人々にとって、冬の数か月間にわたって太陽がほとんど昇らない「極夜(きょくや)」は厳しい試練の時期でした。ベイヴェはそんな暗闇の季節に終わりを告げ、光と温もりを取り戻してくれる存在として深く崇められてきたのです。
ベイヴェは太陽だけでなく、豊穣と正気の女神でもあるとされています。太陽の光が精神の健康を保ち、暗闇が人の心を蝕むという考えは、極北の環境で暮らす人々にとってとりわけ切実な感覚だったのでしょう。
娘のベイヴェ・ニエイダ(Beaivi-nieida、「太陽の乙女」の意味)とともに描かれることが多く、その周囲にはトナカイの角があしらわれるのが伝統的な表現です。これはサーミの人々にとってトナカイが生活の中心であり、太陽の帰還がトナカイの出産期と草木の再生をもたらすことを反映しています。
冬至のころにはベイヴェへの特別な儀式が行われ、バターや脂肪を戸口に塗って太陽の帰還を祈る習慣がありました。
マリナ(Malina)|イヌイット神話
グリーンランドを中心としたイヌイットの伝承に登場する太陽の女神です。月の神である兄アニンガン(Anningan、またはイガルク / Igaluk)との関係で語られることが多く、二人の追いかけっこが太陽と月の動きを生み出しているとされています。
伝承によれば、マリナとアニンガンは幼いころとても仲が良く、成長するにつれて女性の住居と男性の住居に分かれて暮らすようになりました。ある夜、正体不明の人物がマリナのもとを訪れて暴行を加えます。暗闇の中で犯人の顔が見えなかったマリナは、次に同じことが起きた際にランプの油煤を手に塗り、相手の顔に擦りつけました。
明かりの下で煤まみれの顔をしていたのは、兄のアニンガンでした。衝撃を受けたマリナは松明を手に空へと逃げ、太陽となりました。アニンガンもまた松明を持って追いかけましたが、途中で転んで火が弱まり、月となったのです。
太陽が月よりも明るいのはマリナの松明が消えなかったから、月が満ち欠けするのはアニンガンが追いかけるうちに食事を忘れて痩せていくから、とイヌイットの人々は語ります。そしてアニンガンが力尽きて地上に降りて食事をとると、再び太った月として空に戻るのだとされています。
日食のときは男性が外出してはならず、月食のときは女性が外出してはならないという慣習もあり、マリナとアニンガンの確執が日常の決まりにまで影響を与えていたことがわかります。
グノウィー(Gnowee)|オーストラリア先住民の神話
オーストラリア南東部のウォジョバルク(Wotjobaluk)の人々に伝わる太陽の女神です。実はオーストラリアの先住民の多くの部族では、太陽は女性、月は男性として語られています。これは世界的に見ても珍しい特徴です。
グノウィーの神話は、母の愛の物語です。
まだ世界に太陽がなかった太古の時代、人々は樹皮の松明を頼りに暗闇の中を歩いていました。ある日、グノウィーは幼い息子を寝かせたまま、食料の山芋を掘りに出かけます。食べ物がなかなか見つからず、どんどん遠くへ歩いていくうちに、大地の果てまで到達し、地球の反対側に出てしまいました。
息子の元に帰れなくなったグノウィーは、少しでも遠くを見渡そうと大きな松明を持って空に昇りました。その松明の明かりこそが太陽であり、彼女は今も毎日、空の上から息子を探し続けているのだとされています。
残念ながらグノウィーは今に至るまで息子を見つけられていません。だから太陽は毎日東から西へと旅をし続けるのだ、とこの物語は伝えています。
ペイヴェタル(Päivätär)|フィンランド神話
フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』に登場する太陽の女神です。名前は「太陽の娘」あるいは「太陽の女性」を意味し、フィンランド語で太陽を意味する「päivä」に由来しています。
『カレワラ』の世界では、ペイヴェタルは織物や紡ぎの名手として描かれ、虹の上に座って金や銀の糸を織るとされています。彼女の紡ぐ輝く糸は太陽の光そのものであり、地上に温もりと生命力を届ける象徴として歌われています。
世界の太陽の女神|まとめ一覧
ここまで紹介した女神も含め、世界各地の太陽の女神を一覧にまとめました。
| 女神の名前 | 神話体系 | 特徴 |
|---|---|---|
| 天照大御神(アマテラス) | 日本神話 | 高天原の主宰神、皇祖神、天岩戸の神隠れで有名 |
| 羲和(Xīhé) | 中国神話 | 十の太陽の母、太陽の御者、時暦の女神 |
| アリンナの太陽女神(Arinniti) | ヒッタイト神話 | 「すべての国の女王」、ヒッタイト帝国の最高神 |
| ソール / スンナ(Sól / Sunna) | 北欧・ゲルマン神話 | 太陽の戦車を駆る女神、魔狼スコールに追われる |
| サウレ(Saulė) | バルト神話 | 孤児の守護女神、月の神と離別、バルト信仰の中心的存在 |
| オーニュ(Áine) | ケルト神話(アイルランド) | 太陽・夏・豊穣・愛の女神、妖精の女王 |
| スリス(Sulis) | ケルト神話(ブリテン島) | 温泉と太陽の女神、名前は印欧祖語の「太陽」に由来 |
| ブリギッド(Brighid) | ケルト神話(アイルランド) | 火・鍛冶・詩の女神、太陽との関連を指摘される |
| ベイヴェ(Beaivi) | サーミ神話 | 太陽・豊穣・正気の女神、極夜からの解放を司る |
| マリナ(Malina) | イヌイット神話 | 兄の月神から逃れて空に昇った太陽の女神 |
| グノウィー(Gnowee) | オーストラリア先住民神話 | 迷子の息子を探して空を巡る太陽の女神 |
| ペイヴェタル(Päivätär) | フィンランド神話 | 太陽の光を紡ぐ織物の女神 |
| タパティ(Tapati) | ヒンドゥー教 | 太陽神スーリヤの娘、太陽の女神 |
| ウネラヌヒ(Unelanuhi) | チェロキー神話 | 北米先住民チェロキーの太陽の女神 |
| チュプ・カムイ(Chup Kamui) | アイヌ神話 | もとは月の女神だったが兄と入れ替わり太陽の女神に |
| トカプチュプカムイ | アイヌ神話 | 「日中に輝く太陽のカムイ」の意味 |
| エキ(Ekhi) | バスク神話 | 太陽の女神、人類の守護者 |
| テン・マット・チョイ(Thần Mặt Trời) | ベトナム神話 | 天の神オン・チョイの娘、太陽の化身 |
| ビラ(Bila) | オーストラリア先住民神話(アドニャマタニャ) | 太陽の女神、炎と光の起源 |
| イー(Yhi) | オーストラリア先住民神話(カラウル) | 太陽・光・創造の女神 |
太陽の女神はなぜ見落とされがちなのか
一覧で見ると、太陽の女神は世界中に幅広く存在していることがわかります。にもかかわらず、「太陽神=男性」というイメージが根強いのはなぜでしょうか。
一つの理由として、ヨーロッパの知的伝統が長くギリシャ・ローマ神話を基盤としてきたことが挙げられます。ギリシャ神話ではヘリオスやアポロンが太陽を司る男神であり、その影響力が西洋文明全体の「常識」を形作ってきた面があるのです。
印欧祖語の研究者の中には、もともと原インド・ヨーロッパ語族の太陽神は女性だったとする説を唱える人もいます。ケルトのスリス、北欧のソール、バルトのサウレ、ヒンドゥーのスーリヤの語源はいずれも共通しており、原初の太陽神が女神だった可能性を示唆しています。
太陽を男性と見るか女性と見るかは、文化によって大きく異なります。世界の神話を網羅的に見てみると、「太陽=男性」というのは一つの見方にすぎず、普遍的な法則ではないということがわかるのです。
参考情報
この記事の作成にあたり、以下の情報源を参照しました。
百科事典・辞典
- Wikipedia「太陽神一覧」 – 各神話の太陽神の基本情報
- Wikipedia “List of solar deities” – 世界の太陽神の包括的なリスト
- Wikipedia「羲和」 – 中国神話における羲和の詳細
- Wikipedia「太陽神」 – 太陽神の概説と性別論争
- Wikipedia “Sun goddess of Arinna” – ヒッタイトの太陽女神の詳細
- Wikipedia “Saulė” – バルト神話のサウレに関する詳細
- Britannica “Saule” – バルト神話の太陽女神に関する百科事典的解説
- Britannica “Arinnitti” – ヒッタイト太陽女神に関する解説
- 百度百科「羲和」 – 中国語による羲和の詳細情報
学術的資料・専門サイト
- Encyclopedia.com “Saule” – バルト太陽女神の学術的考察
- Wikipedia “Sun and Moon (Inuit myth)” – イヌイット神話のマリナに関する学術的情報
- Mythlok “Malina: The Sun Goddess” – イヌイット太陽女神の解説
- Mythlok “Arinnitti: The Sun Goddess” – ヒッタイト太陽女神の解説
- Mythlok “Saule: The Sun Goddess” – バルト太陽女神の解説
一般参考
- Batsford Books “Solar deities: Gods and goddesses of the sun” – 太陽神の概説(天照・サウレ・ソールを含む)
- Mythos Blog “Sun Goddesses Around the World” – 世界各地の太陽の女神の紹介
古典文献
- 『古事記』『日本書紀』 – 天照大御神に関する日本の原典
- 『山海経』(大荒南経) – 羲和に関する中国の原典
- 『楚辞』屈原「離騒」 – 羲和を日御として描いた作品
- 『古エッダ』(「巫女の予言」「ヴァフスルーズニルの言葉」など) – 北欧神話のソールに関する原典
- 『カレワラ』 – フィンランド神話のペイヴェタルに関する原典




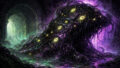


コメント