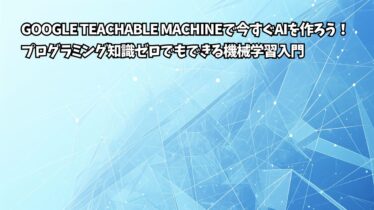 AI
AI Google Teachable Machineで今すぐAIを作ろう!プログラミング知識ゼロでもできる機械学習入門
「AIを作ってみたいけど、プログラミングは難しそう...」「機械学習って、数学の知識が必要なんでしょ?」そんなふうに思っていませんか?実は、Google Teachable Machine(ティーチャブルマシン) を使えば、プログラミング知...
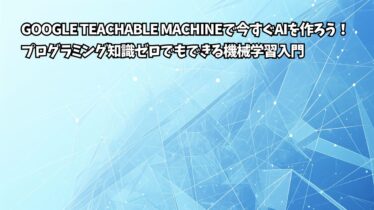 AI
AI 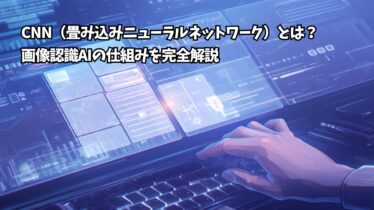 AI
AI 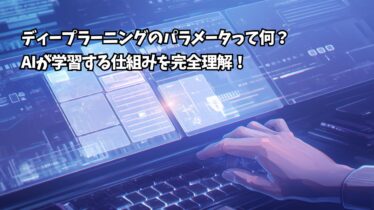 AI
AI 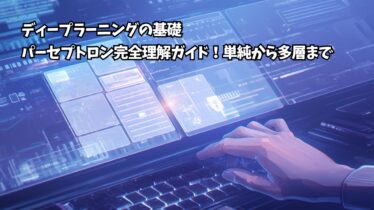 AI
AI  AI
AI  AI
AI  AI
AI 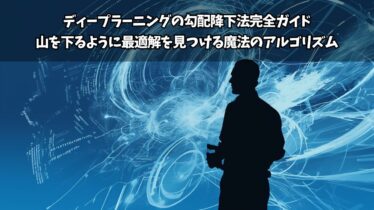 AI
AI  AI
AI  AI
AI 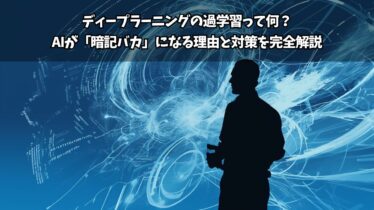 AI
AI  AI
AI  AI
AI  AI
AI