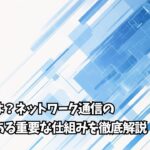「Webサイトが開くのが遅い…」
「オンラインゲームが途中でカクカクする…」
こんな経験、ありませんか?
ネットワークのトラブルを調べるとき、traceroute(トレースルート)というツールが大活躍します。
tracerouteは、あなたのパソコンから目的地のサーバーまで、データがどんな経路を通って届くのかを可視化してくれるコマンドなんです。
例えるなら、宅配便の荷物が「どの配送センターを経由して届いたか」を追跡するような機能ですね。
この記事では、tracerouteの基本的な使い方から、結果の読み方、実践的な活用方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
ネットワークの仕組みを知りたい方、トラブルシューティングに興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
tracerouteの基本的な役割
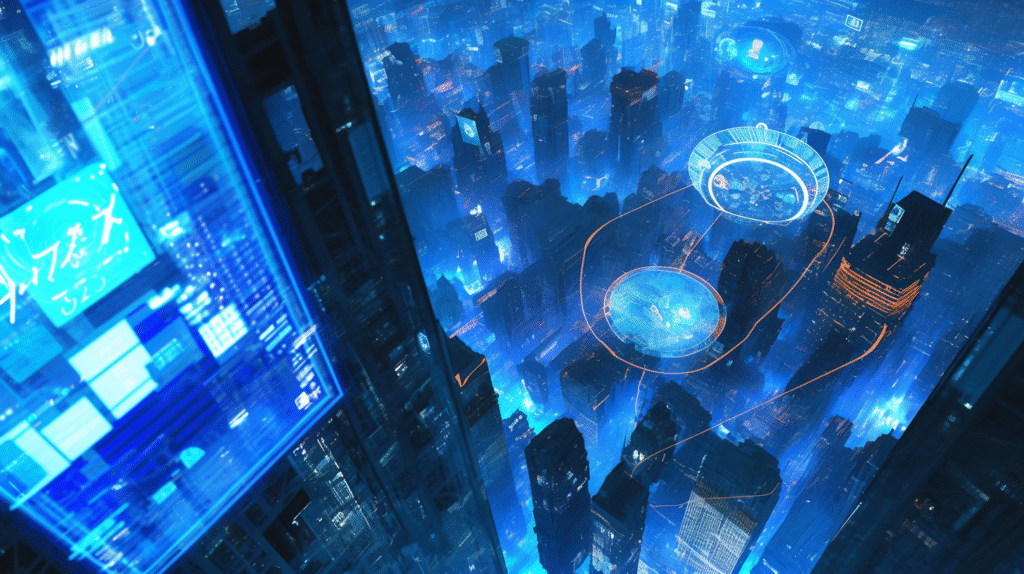
インターネットは「中継」の連続
インターネットで通信するとき、データは送信元から目的地まで一直線に届くわけではありません。
実際には、複数のルーター(中継地点)を経由して、バケツリレーのように次々とデータが渡されていきます。
例えば、日本からアメリカのWebサーバーにアクセスする場合:
- 自宅のルーター
- プロバイダーのルーター
- 国内の通信事業者のルーター
- 海底ケーブルの接続ポイント
- アメリカ国内の通信事業者のルーター
- 目的のサーバー
このように、たくさんの中継地点を通過するんです。
tracerouteが教えてくれること
tracerouteは、この中継地点をすべて表示してくれるツールです。
具体的には、以下の情報が分かります:
- どのルーターを経由しているか(IPアドレスやホスト名)
- 各地点までの応答時間(ミリ秒単位)
- 何回の中継で目的地に到達したか
これらの情報から、ネットワークのどこで遅延が発生しているか、問題がある箇所はどこかを特定できるんですね。
tracerouteの仕組みと動作原理
TTL(Time To Live)を利用した賢い方法
tracerouteは、TTLという仕組みを巧みに利用して経路を調べます。
TTLは「生存時間」という意味で、データパケットがネットワーク上を無限にループしないための安全装置です。
データパケットには、最初にTTL値(例:64)が設定されます。
ルーターを1つ通過するたびに、このTTL値が1ずつ減っていきます。
そして、TTL値が0になったルーターは、そのパケットを破棄して送信元にエラーメッセージを返すんです。
tracerouteの動作手順
tracerouteは、この仕組みを次のように活用します。
ステップ1:TTL=1のパケットを送信
まず、TTL値を1に設定したパケットを送ります。
最初のルーター(1つ目の中継地点)で、TTLが0になってパケットが破棄されます。
そのルーターから「TTLが切れました」というエラーメッセージ(ICMP Time Exceeded)が返ってきます。
これで、1つ目のルーターのIPアドレスと応答時間が分かります。
ステップ2:TTL=2のパケットを送信
次に、TTL値を2に設定したパケットを送ります。
1つ目のルーターを通過し、2つ目のルーターでTTLが0になります。
2つ目のルーターからエラーメッセージが返ってきます。
これで、2つ目のルーターの情報が分かりますね。
ステップ3:TTL値を増やしながら繰り返す
この作業を、目的地に到達するまで繰り返します。
最終的に目的地のサーバーに到達すると、通常の応答が返ってきて、tracerouteは完了します。
このように、少しずつTTL値を増やしながら、経路上のルーターを1つずつ発見していくのがtracerouteの仕組みなんです。
tracerouteの実際の使い方
基本的なコマンド
tracerouteの使い方は、とてもシンプルです。
macOS・Linuxの場合:
traceroute example.comWindowsの場合:
Windowsでは「tracert」という名前のコマンドを使います。
tracert example.comターミナルやコマンドプロンプトを開いて、上記のコマンドを入力するだけです。
実行例と結果の見方
実際にtracerouteを実行すると、こんな感じの結果が表示されます:
traceroute to example.com (93.184.216.34), 30 hops max
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.234 ms 1.123 ms 1.098 ms
2 10.0.0.1 (10.0.0.1) 5.678 ms 5.543 ms 5.421 ms
3 172.16.0.1 (172.16.0.1) 12.345 ms 12.234 ms 12.156 ms
4 93.184.216.34 (93.184.216.34) 25.678 ms 25.543 ms 25.421 msそれぞれの行が、1つの中継地点(ホップと呼ばれます)を表しています。
結果の読み方を詳しく解説
各行の情報を分解してみましょう。
左端の数字(1, 2, 3…):
何番目のルーターかを示す「ホップ数」です。
IPアドレスとホスト名:
そのルーターの識別情報です。
ホスト名が分かる場合は、IPアドレスと一緒に表示されます。
3つの時間(ms):
そのルーターまでの往復時間(レイテンシ)です。
msは「ミリ秒」(1000分の1秒)の単位を表します。
3回測定した結果が表示されるため、通常は3つの時間が並びます。
この時間が大きいほど、そのルーターまでの通信に時間がかかっているということですね。
よく見る特殊な表示
アスタリスク(*)が表示される場合:
5 * * *これは、そのルーターから応答がなかったことを意味します。
原因としては:
- ルーターがICMPパケットに応答しない設定になっている
- ファイアウォールでブロックされている
- 一時的なネットワーク障害
アスタリスクが出ても、その後のホップで正常に応答があれば、通信自体は問題なく行われています。
tracerouteの便利なオプション
基本的な使い方だけでなく、様々なオプションで動作をカスタマイズできます。
よく使われるオプション
最大ホップ数の指定(-m):
traceroute -m 15 example.comデフォルトは30ホップですが、これを変更できます。
国内のサーバーなら15ホップ程度で十分な場合が多いですね。
待機時間の設定(-w):
traceroute -w 3 example.com各ホップからの応答を何秒待つかを指定します。
デフォルトは5秒ですが、速度を重視する場合は短くできます。
ICMPの代わりにUDPを使用:
traceroute -I example.comデフォルトではUDPパケットを使いますが、-Iオプションで明示的にICMPを指定できます。
パケットサイズの指定:
traceroute example.com 100送信するパケットのサイズ(バイト)を指定できます。
大きなパケットでの挙動を確認したい場合に便利です。
tracerouteの実践的な活用方法

ネットワーク遅延の原因特定
Webサイトへのアクセスが遅いとき、tracerouteで原因を探れます。
各ホップの応答時間を見て、どこで急激に遅延が増えているかをチェックしましょう。
正常なパターン:
1 1.2 ms
2 5.4 ms
3 12.3 ms
4 25.6 ms徐々に時間が増えていくのは正常です。
問題のあるパターン:
1 1.2 ms
2 5.4 ms
3 250.8 ms ← ここで急増!
4 255.3 ms3つ目のホップで急激に遅延が増えている場合、そのルーターやその周辺に問題がある可能性が高いです。
経路の変化を観察
同じ目的地でも、時間帯やネットワーク状況によって経路が変わることがあります。
定期的にtracerouteを実行することで:
- 通常時の経路を把握できる
- 障害時に経路がどう変わったかを確認できる
- ISP(インターネットサービスプロバイダー)のルーティング変更に気づける
複数の時間帯で試してみると、面白い発見があるかもしれません。
地理的な経路の把握
IPアドレスやホスト名から、データがどの地域を経由しているか推測できます。
例えば、海外のサーバーにアクセスする場合:
- 国内の都市名が入ったホスト名
- 「pacific」「trans-pacific」などの海底ケーブル名
- 海外の都市名やISP名
このような情報から、物理的な経路をイメージできるんですね。
tracerouteとtracertの違い
WindowsとUnix系OSでは、コマンド名や動作が少し異なります。
基本的な違い
コマンド名:
- Unix系(macOS、Linux):traceroute
- Windows:tracert
使用するプロトコル:
- Unix系:デフォルトでUDPパケット
- Windows:ICMPパケット
この違いにより、同じ目的地でも結果が若干異なることがあります。
オプションの違い:
Unix系のtracerouteは豊富なオプションがありますが、Windowsのtracertはシンプルなオプションのみです。
Windows tracertの主なオプション:
-d:ホスト名の逆引きをしない(高速化)-h:最大ホップ数の指定-w:タイムアウト時間の指定
tracerouteを使う際の注意点
結果が実際の通信を完全に反映するとは限らない
tracerouteが使用するICMPやUDPパケットは、実際のWebアクセス(HTTPやHTTPS)とは異なるプロトコルです。
そのため:
- 実際のWeb通信とは異なる経路を通る可能性がある
- 優先度が低く設定されている場合がある
- ファイアウォールでブロックされることがある
あくまでも参考情報として活用しましょう。
プライバシーとセキュリティへの配慮
tracerouteの結果には、ネットワーク構成に関する情報が含まれます。
企業ネットワークなどで:
- 内部のネットワーク構造が推測される
- 使用している機器やISPが分かる
公開の場でtracerouteの結果を共有する際は、プライバシーに配慮して、必要に応じて情報をマスキングしましょう。
過度な実行は避ける
tracerouteは、複数のパケットを連続して送信します。
短時間に何度も実行すると:
- ネットワーク帯域を消費する
- 一部のシステムでは攻撃と見なされる可能性がある
必要な範囲内で、適度に使用することを心がけてください。
tracerouteと組み合わせると便利なツール
ping(ピン)
tracerouteと並んで基本的なネットワーク診断ツールです。
pingの特徴:
- 目的地までの到達性を確認
- 往復時間(RTT)を測定
- パケットロス(損失率)を確認
tracerouteで経路を確認し、pingで安定性を確認するという使い分けができます。
mtr(My Traceroute)
tracerouteとpingを組み合わせたような高機能ツールです。
mtrの特徴:
- リアルタイムで継続的に経路を監視
- 各ホップのパケットロス率を表示
- より詳細な統計情報を提供
長期的なネットワーク監視や、より深い分析をしたいときに便利ですね。
Webベースのツール
コマンドラインを使わなくても、Webブラウザから利用できるtracerouteサービスもあります。
- 世界各地のサーバーから実行できる
- 視覚的に経路を表示してくれる
- コマンドの知識がなくても使える
「online traceroute」などで検索すると、様々なサービスが見つかります。
まとめ:tracerouteでネットワークの経路が丸見え
traceroute(トレースルート)は、データがどんな経路を通って目的地に届くかを可視化してくれる便利なツールです。
この記事の重要ポイントをおさらいしましょう:
- tracerouteはデータが通る中継地点を順番に表示してくれる
- TTL値を利用した賢い仕組みで経路を発見する
- 各ホップまでの応答時間を測定できる
- ネットワーク遅延の原因特定に役立つ
- WindowsではtracertというコマンドMacOS・Linuxではtracerouteを使う
- ping、mtrなどの関連ツールと組み合わせると効果的
ネットワークトラブルに遭遇したとき、tracerouteを使えば問題の所在を絞り込めます。
「なんとなく遅い」という感覚を、「このルーターで遅延が発生している」という具体的な情報に変えられるんですね。
インターネットの裏側で、データがどんな冒険をしているのか、tracerouteで覗いてみてください。
意外な発見があるかもしれませんよ!