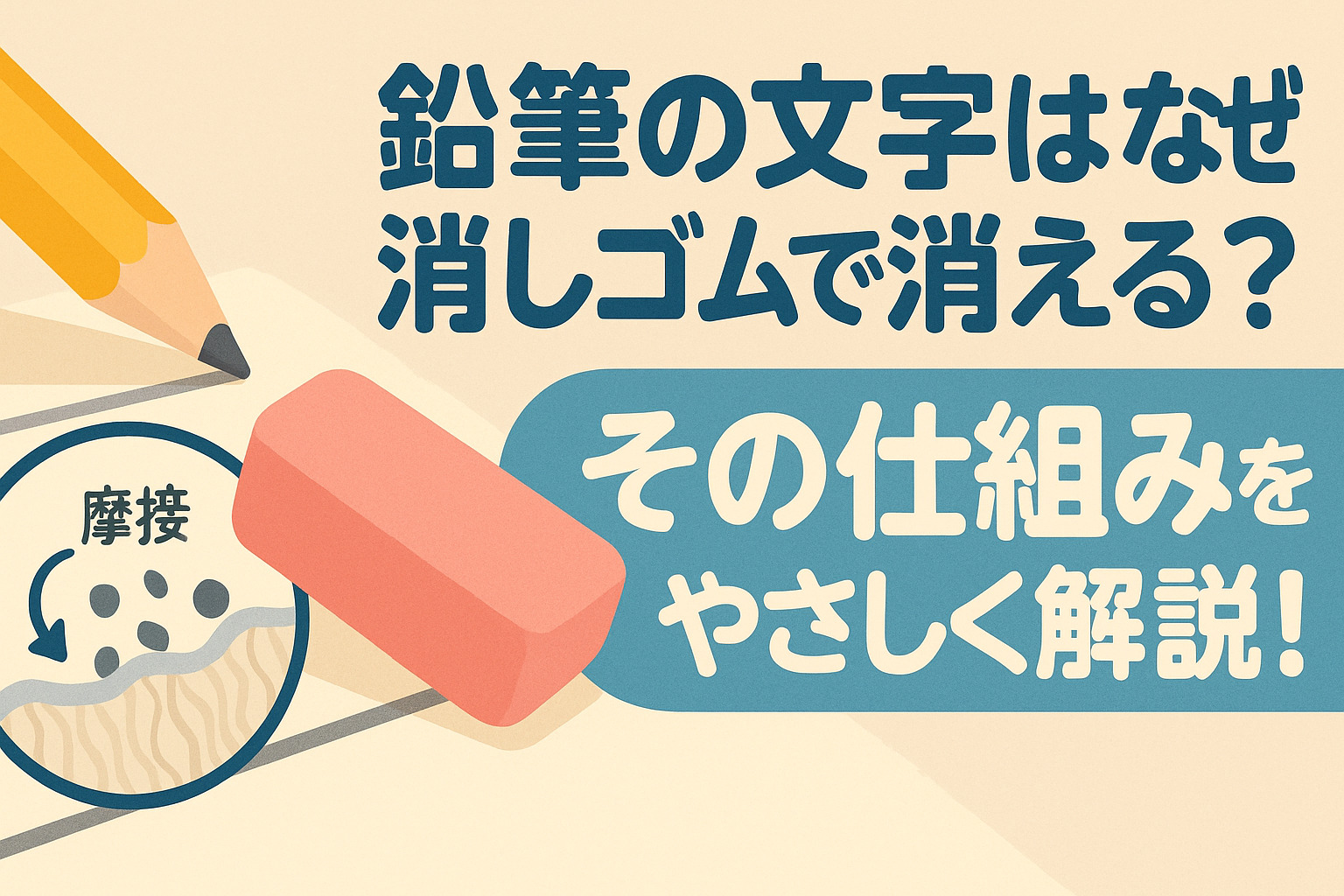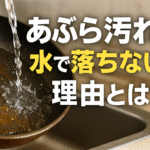勉強中に字を間違えて、消しゴムで「シュッシュッ」と消す。そ
んな何気ない動作を、今まで当たり前だと思っていませんでしたか?
でも、よく考えてみると不思議ですよね。
「なぜ鉛筆の文字だけが消しゴムで消えるの?」
「ボールペンが消えないのはどうして?」
「消しゴムはどうやって文字を消してるの?」
実は、この身近な現象には面白い科学の仕組みが隠されています。
この記事では、鉛筆と消しゴムの秘密をやさしく解説します。
鉛筆の芯って何でできているの?
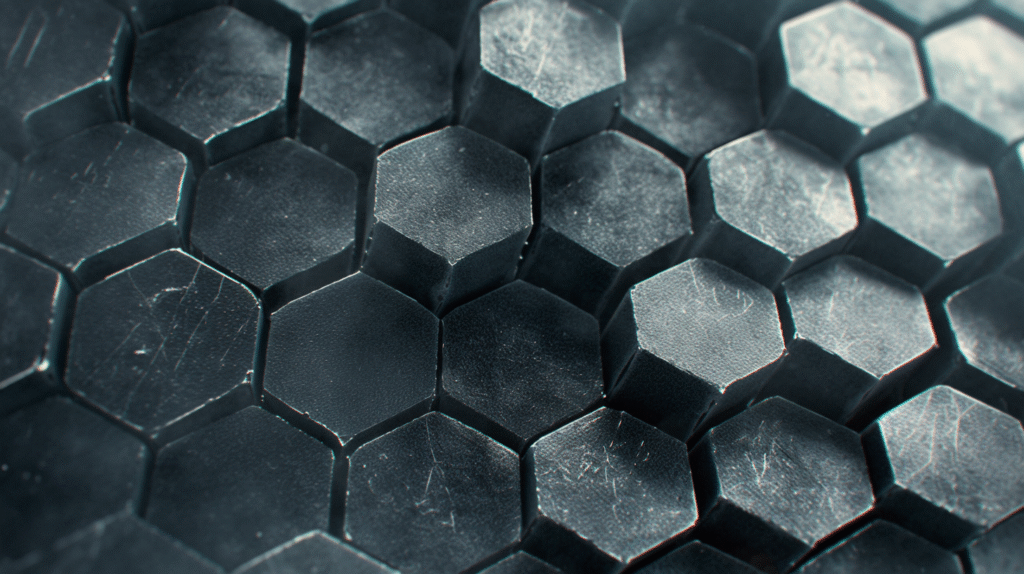
鉛筆の芯は、黒鉛と粘土で出来ています。
黒鉛ってなに?
黒鉛は、炭素(カーボン)という原子が集まってできた物質です。
黒鉛の特徴
- 色:きれいな銀黒色
- 硬さ:やわらかくて、簡単にこすれる
- 構造:薄い板がたくさん重なったような形
- 性質:電気を通す、熱に強い
身近なところでは、乾電池の中にも黒鉛が使われています。
なぜ黒鉛で字が書けるの?
黒鉛は面白い性質を持っています。薄い板がたくさん重なったような構造になっていて、この板同士がはがれやすいんです。
文字が書ける仕組み
- 鉛筆を紙にこすりつける
- 黒鉛の薄い板がはがれる
- はがれた板が紙の表面に残る
- 黒い粒がたくさん集まって「文字」に見える
例えるなら、黒い積み木を紙の上でこすって、積み木のかけらを紙に残すような感じです。
HとBの違いは粘土の量
鉛筆には「H」「B」「HB」などの記号がありますが、これは黒鉛と粘土の割合で決まります。
H(Hard:硬い)
- 粘土が多い
- 芯が硬くて薄く書ける
- 線が細くて薄い
B(Black:黒い)
- 黒鉛が多い
- 芯がやわらかくて濃く書ける
- 線が太くて濃い
HB(Hard Black)
- 中間的な硬さ
- 一般的な用途に最適
粘土が多いほど硬く、黒鉛が多いほどやわらかくなるんです。
消しゴムが文字を消す秘密

消しゴムって何でできてるの?
消しゴムにも、実はいろいろな種類があります。
主な消しゴムの材料
- 塩化ビニル樹脂(PVC):プラスチック消しゴム
- 天然ゴム:昔ながらの消しゴム
- 合成ゴム:特殊な用途の消しゴム
最近よく使われているのは、塩化ビニル樹脂でできたプラスチック消しゴムです。
消しゴムの「消す力」の秘密
消しゴムが文字を消せるのは、2つの力が働いているからです。
1つ目:摩擦力(まさつりょく)
- 消しゴムと紙がこすれあう力
- 紙の表面についた黒鉛をこすり取る
- やすりで木を削るような感じ
2つ目:吸着力(きゅうちゃくりょく)
- 消しゴムが黒鉛をくっつけて取り込む力
- 消しゴムのカスと一緒に黒鉛を持ち去る
- 掃除機でゴミを吸い取るような感じ
実際に消える流れを見てみよう
消しゴムで文字を消すとき、実はこんなことが起きています。
文字が消える手順
- 消しゴムを紙にこすりつける
- 摩擦で紙の表面の黒鉛がはがれる
- 消しゴムの表面が少しずつ削れる
- 消しゴムの粒ができる
- 消しゴムの粒が黒鉛を巻き込む
- はがれた黒鉛が消しゴムのカスにくっつく
- 消しゴムのカスを払い落とす
- 黒鉛も一緒に取り除かれる
- 文字が消えて見える
- 紙の表面から黒鉛がなくなる
消しゴムのカスが汚れているのは、黒鉛が混じっているからなんです。
なぜ消しゴムのカスが出るの?
「消しゴムのカスって邪魔だな」と思ったことありませんか?
でも、実はこのカスがとても大切な役割を果たしています。
カスの重要な役割
- 黒鉛を包み込んで持ち去る
- 紙を傷つけないクッションになる
- 消した部分を再び汚さないようにする
カスが出ない消しゴムもありますが、それは特殊な仕組みを使っているんです。
なぜペンの文字は消えないの?
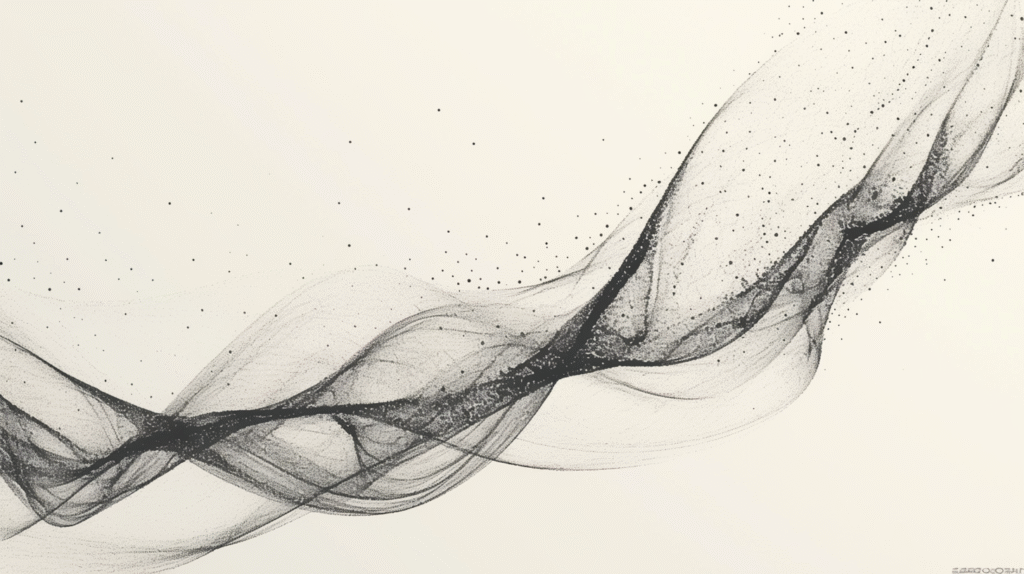
ペンと鉛筆の決定的な違い
同じ「文字を書く道具」でも、ペンと鉛筆では全く違う仕組みで文字が残ります。
鉛筆の場合
- 黒鉛の粒が紙の表面に乗っている状態
- 物理的にこすり取ることができる
- 紙の奥まで入り込んでいない
ペンの場合
- インクが紙の奥に染み込んでいる状態
- 紙の繊維と化学的に結合している
- 表面をこすっても取れない
例えるなら、鉛筆は「紙の上にものが乗っている」状態で、ペンは「紙に色水がしみ込んでいる」状態です。
インクが染み込む仕組み
ペンのインクは、どうやって紙に染み込むのでしょうか?
インクが染み込む流れ
- ペンから液体のインクが出る
- インクが紙の繊維の隙間に入り込む
- 水分が蒸発してインクの色素だけが残る
- 色素が繊維にくっついて固定される
一度染み込んだインクは、消しゴムでこすっても取れません。
紙の奥にしっかりと入り込んでいるからです。
特殊なペンの仕組み
最近は、消すことができるペンもあります。
フリクションペン(こすると消えるペン)
- 摩擦の熱でインクが透明になる
- 実際には消えていない(冷やすと復活する)
- 鉛筆とは違う「熱変色」の仕組み
修正ペン・修正液
- 文字を消すのではなく「隠す」
- 白い塗料で文字を覆い隠す
- 修正液の下に元の文字は残っている
これらは鉛筆の「物理的に取り除く」消し方とは全く違います。
いろいろな消しゴムとその特徴
プラスチック消しゴム
最もよく使われている一般的な消しゴムです。
特徴
- 材料:塩化ビニル樹脂(PVC)
- 良い点:よく消える、長持ちする、安い
- 使う場面:学校、オフィス、家庭
おすすめの使い方
- 軽い力で優しくこする
- 汚れた面を使わず、きれいな面を使う
- 定期的にカッターで表面を削って清潔に保つ
砂消しゴム
ザラザラした感触が特徴の、特殊な消しゴムです。
特徴
- 材料:ゴムに研磨剤(さいまざい)を混ぜたもの
- 良い点:インクやボールペンも消せる
- 注意点:紙も一緒に削ってしまう
使う場面
- ボールペンの文字を消したいとき
- 濃い鉛筆の文字を消したいとき
- ただし、紙が薄い場合は穴が開く危険性
ねり消しゴム
粘土のようにやわらかい、特殊な消しゴムです。
特徴
- 材料:特殊なゴム素材
- 良い点:カスが出ない、形を変えられる
- 使う場面:デッサン、精密な作業
使い方
- 文字に押し当てて黒鉛を「吸い取る」
- 汚れた部分を内側に折り込んで清潔に保つ
- 細かい部分は先端を細くして使う
- より詳しい仕組みを学ぶことができます。
まとめ
鉛筆の文字が消しゴムで消える仕組み、いかがでしたか?
今日学んだポイント
- 鉛筆の芯は黒鉛と粘土でできている
- 文字は紙の表面に黒鉛が「乗っている」状態
- 消しゴムは摩擦力と吸着力で黒鉛を取り除く
- ペンのインクは紙に「染み込む」ので消しゴムでは消えない
- 消しゴムにはいろいろな種類がある
何気なく使っていた消しゴムですが、その仕組みには面白い科学が隠されていました。