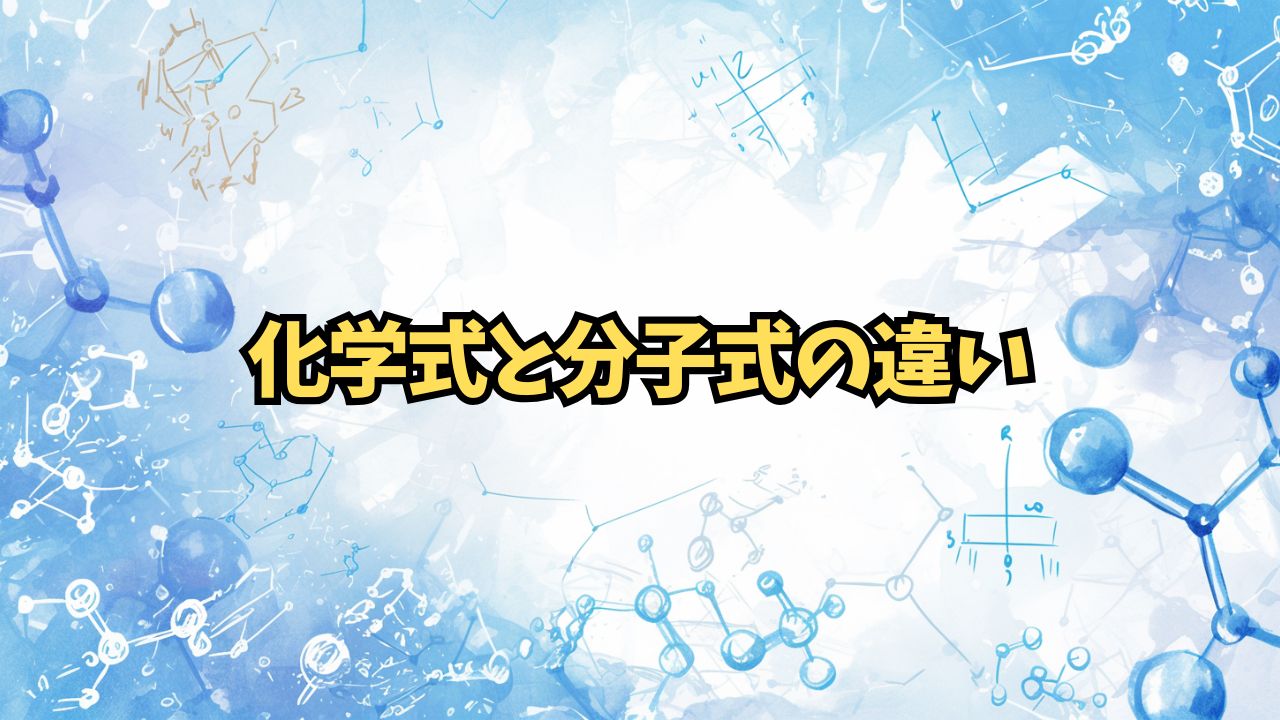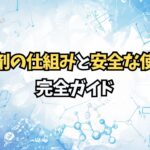化学式と分子式って、よく似た言葉ですよね。
でも実は、この2つには明確な違いがあるんです。
簡単に言うと、化学式は物質を表すすべての書き方の総称で、分子式はその中の一つの方法なんですよ。
この違いが分かると、化学の世界がぐっと身近に感じられるようになります。
化学式って何だろう?

化学式(chemical formula)は、物質がどんな原子でできているかを表す記号のことです。
世界中の科学者が同じルールで書くから、どの国の人でも理解できる「共通言語」みたいなものですね。
たとえば、水をH₂Oと書けば、日本でもアメリカでも「ああ、水のことか」と分かります。
化学式にはいろんな種類があって、それぞれ違う情報を教えてくれるんです。
- 分子式(分子に含まれる原子の数)
- 組成式(原子の比率)
- 構造式(原子のつながり方)
- イオン式(イオンの組み合わせ)
- 電子式(電子の配置)
これらすべてが「化学式」という大きな仲間に入っているわけです。
ちょっとした歴史の話をすると、今の化学式のシステムは1814年にベルセリウスという科学者が考えました。
それまでは錬金術師が使っていた、まるで暗号のような複雑な記号だったんですよ。
分子式は分子の設計図
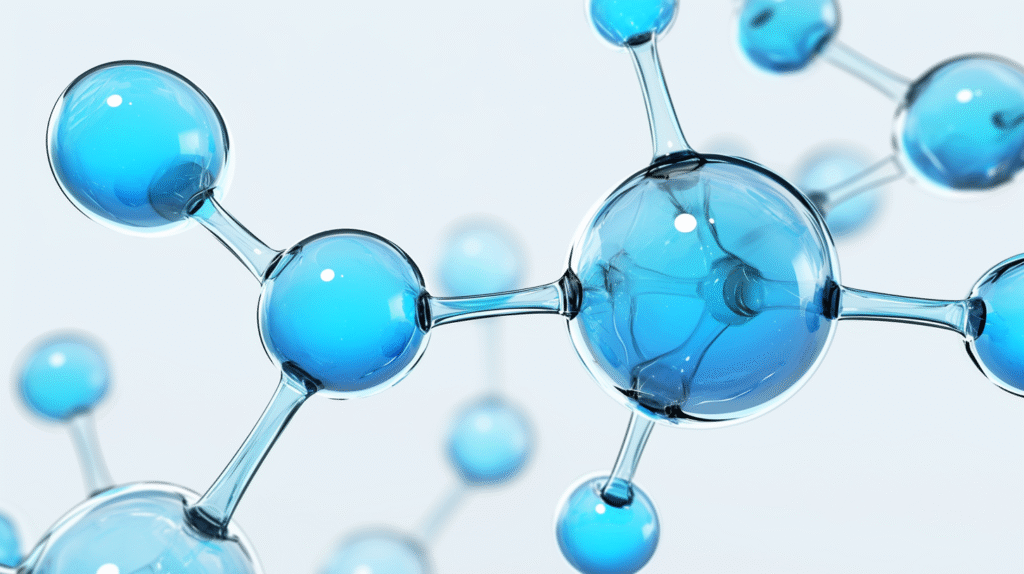
分子式(molecular formula)は、1つの分子にどの原子が何個入っているかを正確に示します。
分子というのは、原子がくっついてできた小さな粒子のことで、物質の性質を保つ最小の単位なんです。
たとえばブドウ糖の分子式C₆H₁₂O₆を見てみましょう。
これは「炭素6個、水素12個、酸素6個でできている」という意味です。この情報があれば、ブドウ糖1個の重さも計算できるし、化学反応でどれだけの量が必要かも分かります。
面白いことに、同じ分子式でもまったく違う物質になることがあるんです。
C₂H₆Oという分子式は、お酒のアルコール(エタノール)にもなるし、麻酔に使うジメチルエーテルにもなります。
原子の数は同じでも、つながり方が違うと性質も変わっちゃうんですね。
組成式は「比率」を教えてくれる
組成式(実験式ともいいます)は、原子の比率を一番簡単な整数で表したものです。
実験で求めることが多いから「実験式」とも呼ばれるんですよ。
ブドウ糖を例にすると、分子式はC₆H₁₂O₆でしたね。
これを最も簡単な比にすると、6:12:6は1:2:1になるので、組成式はCH₂Oになります。
実は酢酸(C₂H₄O₂)も同じCH₂Oという組成式になるんです。つまり、組成式からは実際の分子の大きさまでは分からないということですね。
ここで大切なのは、イオン化合物の話です。
食塩(NaCl)のようなイオン化合物は、個別の分子として存在しません。
代わりに、イオンが規則正しく並んだ結晶を作っています。
だから食塩には分子式がなくて、組成式だけを使うんです。
いろんな化学式で構造が見えてくる
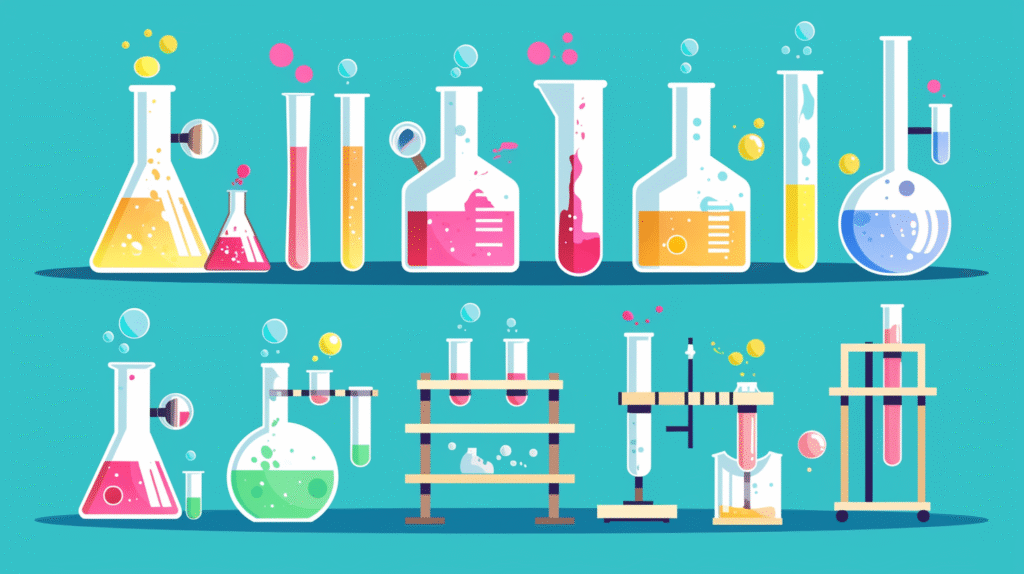
構造式は、原子同士のつながり方を線で表します。
単結合は一本線(−)、二重結合は二本線(=)、三重結合は三本線(≡)で書きます。
エタノールの構造式CH₃−CH₂−OHを見れば、「OH基があるからアルコールだな」とすぐ分かりますね。
示性式という書き方もあります。
これは分子の中で重要な部分を強調する方法です。酢酸をCH₃COOHと書くと、COOH(カルボキシル基)があることが分かって、「これは酸性の物質だ」と理解できます。
電子式(ルイス構造式)は、原子の周りの電子を点で表す方法です。
1916年にルイスさんが考えたこの方法を使うと、原子がどうやって結合するかが目で見て分かるようになりました。
身近な物質で考えてみよう
水(H₂O)は一番シンプルな例ですね。
分子式も組成式も同じH₂Oです。構造式のH−O−Hを見ると、水素が104.5度の角度でついていることが分かります。この形が、水の不思議な性質の秘密なんです。
ベンゼン(C₆H₆)はもう少し複雑です。
分子式から炭素6個と水素6個は分かりますが、実際は六角形の環になっているなんて、構造式を見ないと想像できませんよね。
過酸化水素(H₂O₂)と水(H₂O)を比べると面白いです。
同じ元素でできているのに、まったく違う物質になります。水は飲めるけど、過酸化水素は消毒薬として使われる強い薬品です。
構造式H−O−O−Hを見ると、酸素同士がつながっている不安定な形だと分かります。
化学式を書くときの大切なルール
化学式を正しく書くには、いくつかルールがあります。
まず元素記号の順番ですが、基本的により金属っぽい元素を先に書きます。
有機化合物では、炭素(C)→水素(H)→その他(アルファベット順)という順番が一般的です。
数字の書き方も大切です。
原子の個数は元素記号の右下に小さく書きます。H₂Oの「2」がそうですね。1個のときは数字を書きません。
括弧を使うときは要注意です。
Ca(OH)₂の場合、括弧の外の「2」は括弧内全体にかかるので、OH基が2個あるという意味になります。
イオン化合物では、必ず陽イオン→陰イオンの順で書きます。
硝酸マグネシウムはMg(NO₃)₂と書いて、MgNO₃₂とは書きません。括弧を忘れると意味が変わってしまうので気をつけましょう。
分子式で分かること、分からないこと
分子式から分かることはたくさんあります。
- どんな元素が何個あるか
- 分子の重さ(分子量)
- 化学反応での量の関係
- 組成式への変換
たとえばC₆H₁₂O₆なら、1モル(6×10²³個)で180グラムになることが計算できます。
でも、分子式だけでは分からないこともあります。
- 原子の配置や立体構造
- 物質の性質(融点、沸点、味、におい)
- 化学反応のしやすさ
同じC₆H₁₂O₆でも、ブドウ糖と果糖では甘さも体内での働きも違うんです。
分子式は化学の「住所」みたいなもので、そこに何があるかは分かっても、どんな建物かまでは分からないと考えると良いでしょう。
他の化学式との違いをまとめよう
イオン式は、イオン化合物の組成を表します。
NaClやCaCl₂は個別の分子ではなく、たくさんのイオンが集まった結晶を表しているんです。
電子式を使うと、化学結合の仕組みがよく分かります。
共有結合では電子を共有し、イオン結合では電子が移動します。
水の電子式を見ると、酸素の周りに電子のペアがあって、これが水素結合を作る理由だと分かります。
立体化学を表す方法もあります。
くさび形表記では、手前に出る結合を太い線、奥に向かう結合を破線で書きます。これで立体的な分子の形が紙の上でも表現できるんです。
学習ポイント

化学式を理解するコツは、身の回りのものと結びつけることです。
水を飲むときは「H₂Oの集まりを飲んでいる」、砂糖を溶かすときは「C₁₂H₂₂O₁₁が水分子に囲まれている」と想像してみましょう。
段階的に理解することも大切です。
- まず原子という粒子を理解する
- 原子が結合して分子になることを学ぶ
- 化学式はその構成を表す記号だと理解する
分子模型を作ったり、レゴブロックで遊ぶ感覚で分子を組み立てたりすると、楽しく学べますよ。
よくある間違いに注意しましょう。
2H₂Oは「水分子が2個」、H₂Oは「1個の水分子に水素が2個」という違いがあります。化学反応式では係数は変えられますが、下付き数字は絶対に変えてはいけません。物質そのものが変わってしまいますからね。
料理も化学の実験です。
重曹(NaHCO₃)と酢(CH₃COOH)を混ぜると泡が出るのは、二酸化炭素(CO₂)が発生するから。
こんな身近な反応を化学式で理解すると、勉強が楽しくなりますよ。
まとめ:化学式で見えない世界が見えてくる
化学式と分子式の違いを理解することで、化学の世界への扉が開きます。
化学式という大きなグループの中に、いろいろな表記法があって、それぞれが物質の違う面を見せてくれるんです。
分子式は正確な原子の数を、組成式は最も簡単な比を、構造式は原子のつながり方を教えてくれます。これらが協力して、物質の全体像を描き出しているんですね。
水という単純な物質でさえ、H₂Oという分子式、H−O−Hという構造式、そして電子式によって、その特別な性質が説明できます。
化学式は単なる記号じゃありません。目に見えない原子や分子の世界を理解するための、とても便利な道具なんです。
これからも身の回りの物質を化学式で考えてみてください。きっと世界が違って見えてくるはずですよ。