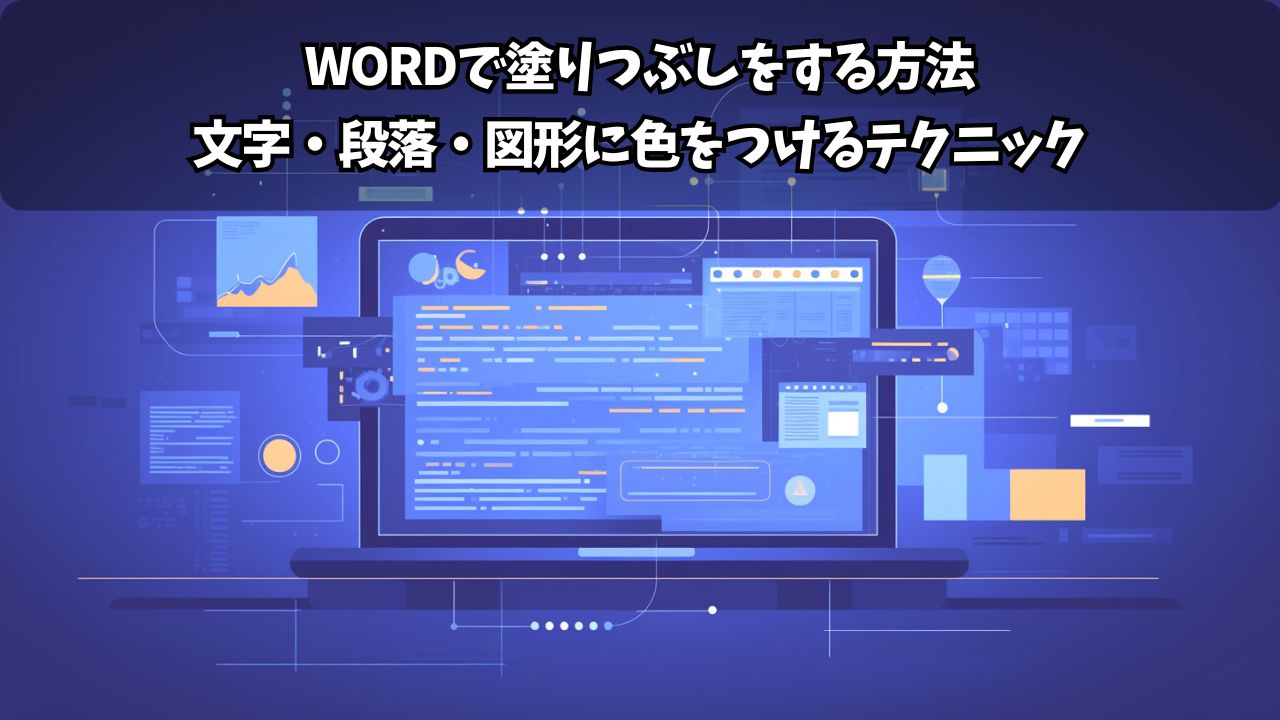「Wordで一部に背景色を付けたい…」 「図形や文字を強調するために色を付けたい!」
そんなときに便利なのが「塗りつぶし」機能です。背景に色をつけることで、見た目のわかりやすさや資料の印象をぐっと高めることができます。
この記事では、Wordで文字や段落、図形などを塗りつぶす具体的な方法を、初心者でもわかるように丁寧に解説します。読み終わる頃には、プロのようなきれいな文書が作れるようになります。
塗りつぶし機能でできること

基本的な塗りつぶしの種類
Wordでは以下のようなものに色を付けることができます:
- 文字の背景:重要な文字を目立たせる
- 段落全体:見出しや注意書きを強調
- 表やセル:データを見やすく整理
- 図形の内部:説明図やフローチャートを作成
- ページ全体:特別な文書の背景設定
塗りつぶしを使う場面
- 重要なポイントを強調したいとき
- 見出しを目立たせたいとき
- 表のデータを分類したいとき
- 図形やイラストを作成するとき
- 読みやすい資料を作りたいとき
文字や段落に色をつける方法
文字の背景色を変える(蛍光ペン機能)
基本的な手順
- 色を付けたい文字をマウスでドラッグして選択
- 「ホーム」タブの「蛍光ペンの色」ボタンをクリック
- 表示される色の中から好きなものを選択
- 文字の後ろに色が付きます
蛍光ペンとペイントブラシの違い
- 蛍光ペン:マーカーで線を引いたような効果
- ペイントブラシ:文字の背景をべた塗りする効果
より詳しい操作方法
- 連続して塗りつぶしたい場合
- 蛍光ペンボタンを先にクリック
- マウスポインタがペンの形に変わる
- 色を付けたい部分をドラッグ
- 終了するときはEscキーを押す
- 色を変更したい場合
- 蛍光ペンボタンの右側の▼をクリック
- 色の一覧から新しい色を選択
注意すべきポイント
- 蛍光ペンは文字にだけ色が付きます
- 印刷するときは「背景の色と画像を印刷」をオンにする必要があります
- 色を付けすぎると読みにくくなるので注意
段落全体の背景色を変える(網かけ機能)
段落の背景色を付ける手順
- 色を付けたい段落をクリック(または段落全体を選択)
- 「ホーム」タブの「段落」グループにある「網かけ」ボタンをクリック
- 「塗りつぶし」タブを選択
- 好きな色をクリックして「OK」を押す
段落選択のコツ
- 段落の一部をクリック:その段落全体が対象になる
- 複数段落を選択:最初の段落から最後の段落までドラッグ
- 文書全体を選択:Ctrl+Aで全体選択
網かけのパターンも選べる
- 「網かけ」ボタンをクリック
- 「パターン」で網目の種類を選択
- 「背景の色」と「前景の色」を設定
- プレビューで確認してから「OK」
実用的な使い分け
- 見出し:濃い色で目立たせる
- 注意書き:薄い黄色やオレンジ
- 重要な段落:薄い青や緑
- 引用文:グレーで区別
表やセルを塗りつぶす方法
基本的なセルの塗りつぶし
単一セルの塗りつぶし
- 色を付けたいセルをクリック
- 「ホーム」タブの「塗りつぶし」ボタンをクリック
- 好きな色を選択
複数セルの塗りつぶし
- 塗りつぶしたいセルをドラッグして選択
- 「ホーム」タブの「塗りつぶし」ボタンをクリック
- 色を選択すると選択したセル全てに適用
行や列全体の塗りつぶし
- 行全体:行番号をクリックして行を選択
- 列全体:列の上部をクリックして列を選択
- その後、塗りつぶしボタンで色を設定
表ツールを使った高度な塗りつぶし
表デザインでの塗りつぶし
- 表のどこかをクリック
- 「表ツール」の「デザイン」タブが表示される
- 「塗りつぶし」ボタンで詳細設定が可能
おすすめの表の色付けパターン
- 見出し行:濃い色(紺色、深緑など)
- データ行:薄い色を交互に(薄い青と白など)
- 合計行:中程度の色(グレーなど)
自動的な色付けテンプレート
- 表を選択
- 「表ツール」→「デザイン」タブ
- 表のスタイル一覧から好みのデザインを選択
- 自動的に見やすい色付けが適用される
図形の塗りつぶし方法
基本的な図形の作成と塗りつぶし
図形を作成する手順
- 「挿入」タブをクリック
- 「図形」ボタンをクリック
- 使いたい図形(四角、円、矢印など)を選択
- 文書上でドラッグして図形を描く
図形の色を変える方法
- 作成した図形をクリックして選択
- 「図形の書式」タブが表示される
- 「図形の塗りつぶし」ボタンをクリック
- 好きな色を選択
高度な塗りつぶしテクニック
グラデーション(段階的な色の変化)
- 図形を選択
- 「図形の塗りつぶし」→「グラデーション」
- プリセットから選ぶか「その他のグラデーション」で詳細設定
テクスチャ(質感のある背景)
- 図形を選択
- 「図形の塗りつぶし」→「テクスチャ」
- 木目、石材、布地などの質感を選択
画像を図形の背景にする
- 図形を選択
- 「図形の塗りつぶし」→「図」
- パソコン内の画像ファイルを選択
- 図形の形に合わせて画像が配置される
図形の枠線も一緒に設定
枠線の色や太さを変える
- 図形を選択
- 「図形の枠線」ボタンをクリック
- 色、太さ、線の種類を設定
デザインのコツ
- 塗りつぶし色と枠線色のバランスを考える
- 同系色でまとめると統一感が出る
- コントラストを付けると目立ちやすくなる
ページ全体の背景色を設定する方法
ページの背景色を変える
基本的な手順
- 「デザイン」タブをクリック
- 「ページの色」ボタンをクリック
- 好きな背景色を選択
背景にグラデーションを付ける
- 「ページの色」→「塗りつぶし効果」
- 「グラデーション」タブで設定
- 色の組み合わせと方向を選択
注意点
- 印刷時の設定:背景色を印刷するには設定が必要
- 読みやすさ:背景色が濃すぎると文字が読みにくくなる
- 用紙の無駄:色付き背景は印刷コストが高くなる
よくあるトラブルと解決方法

色が付かない場合の対処法
選択範囲の確認
- 問題:色を付けたい部分が正しく選択されていない
- 解決法:もう一度正確に選択し直す
- コツ:選択した部分が青くハイライトされることを確認
書式の競合
- 問題:他の書式設定が邪魔をしている
- 解決法:
- 「ホーム」タブの「書式のクリア」をクリック
- 既存の書式をリセットしてから色を付け直す
スタイルの影響
- 問題:文書のスタイル設定が色付けを妨げている
- 解決法:
- 対象部分を選択
- スタイル一覧から「標準」を選択
- その後で色を付け直す
印刷時に色が出ない場合
プリンター設定の確認
- 「ファイル」→「印刷」
- 「プリンターのプロパティ」をクリック
- カラー印刷の設定を確認
Word側の設定確認
- 「ファイル」→「オプション」
- 「表示」を選択
- 「背景の色と画像を印刷する」にチェックを入れる
印刷プレビューでの確認
- 印刷前に必ずプレビューで色の表示を確認
- 色が表示されない場合は上記の設定を再確認
色が想定と違って見える場合
モニターとプリンターの色の違い
- 原因:画面で見る色と印刷される色は異なることがある
- 対策:重要な文書は事前にテスト印刷を行う
色の組み合わせの問題
- 見にくい組み合わせ:赤と緑、青と紫など
- 見やすい組み合わせ:青と白、黒と黄色など
- 推奨:コントラストの高い組み合わせを選ぶ
効果的な色使いのコツ
色選びの基本原則
読みやすさを最優先
- 背景色は薄く:文字が読みやすい薄い色を選ぶ
- 文字色とのコントラスト:はっきりとした色の違いを作る
- 使用色数を制限:3〜4色程度に抑える
色の心理効果を活用
- 赤:注意、警告、重要度が高い情報
- 青:信頼性、安定性、ビジネス文書
- 緑:安心感、成功、ポジティブな情報
- 黄:注意喚起、明るさ、エネルギー
- グレー:中立、落ち着き、補助情報
文書の種類別おすすめ配色
ビジネス文書
- 基本色:青系統(濃い青、薄い青)
- アクセント色:グレー、白
- 避けるべき色:ピンク、オレンジなどの明るすぎる色
教育資料・説明書
- 基本色:緑系統(深緑、薄緑)
- アクセント色:黄色、オレンジ
- 使い分け:重要度に応じて色の濃さを変える
案内・お知らせ
- 基本色:暖色系(オレンジ、黄色)
- アクセント色:赤(注意喚起)
- 補助色:グレー(詳細情報)
アクセシビリティ(使いやすさ)への配慮
色覚に配慮した色選び
- 赤と緑の組み合わせは避ける
- 青と黄色の組み合わせは多くの人に見やすい
- 明度の差を大きくして識別しやすくする
印刷時の配慮
- 白黒印刷でも読めるように設計
- グレースケールでも情報が伝わるかチェック
- 濃淡だけでなく模様も併用する
まとめ
Wordの「塗りつぶし」機能は、文書を視覚的に整理し、強調したい部分を引き立てるために非常に便利なツールです。
覚えておきたい基本操作
- 文字の背景色:蛍光ペン機能を使用
- 段落の背景色:網かけ機能を使用
- 表の塗りつぶし:セル選択後に塗りつぶしボタン
- 図形の塗りつぶし:図形選択後に「図形の塗りつぶし」
効果的に使うためのポイント
- 読みやすさを最優先に考える
- 色の数は3〜4色程度に抑える
- 印刷時の見え方も考慮する
- 文書の目的に応じて色を選ぶ
目的に応じて、文字・段落・セル・図形と使い分けることで、誰が見てもわかりやすい資料に仕上がります。色の使いすぎには注意しつつ、見やすく効果的なレイアウトを目指しましょう。
これらのテクニックを使えば、単調な文書が見違えるようにきれいで読みやすくなります。まずは簡単な色付けから始めて、徐々に高度なテクニックにチャレンジしてみてください。