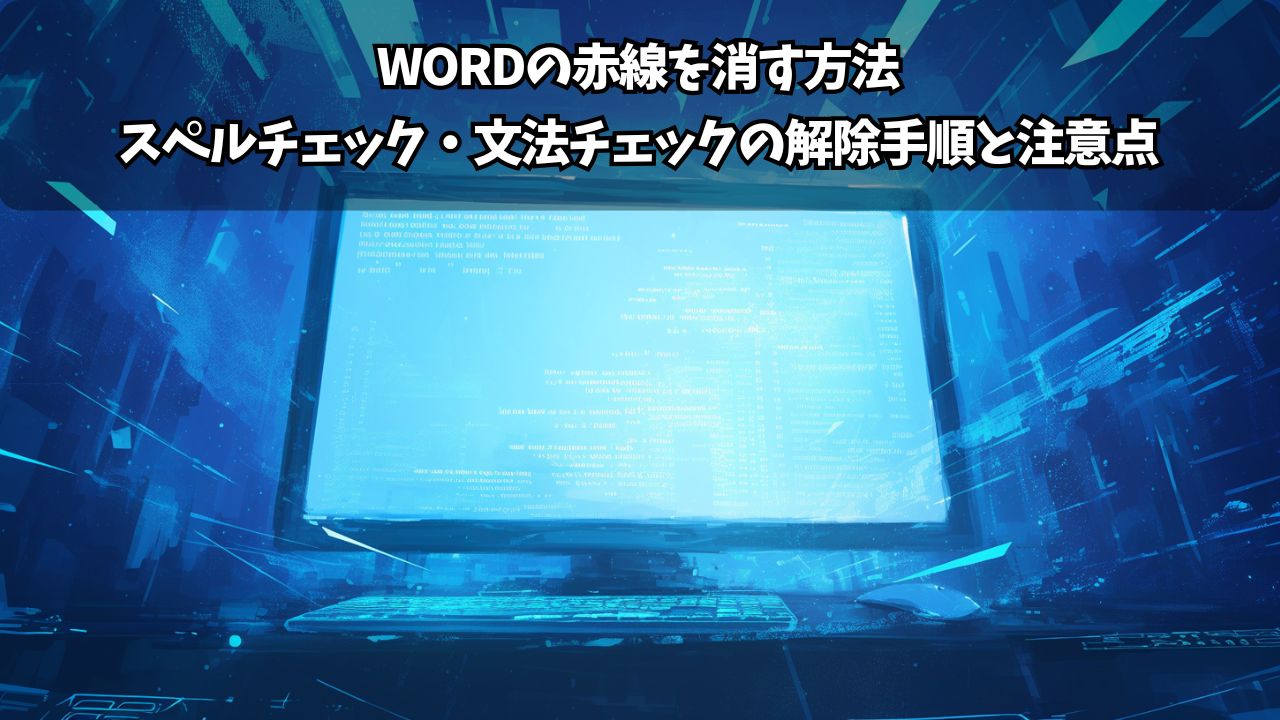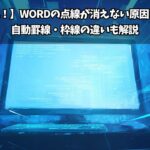「Wordで入力したら、下に赤いなみ線が出てきて気になる」
「文章の意味には問題ないのに、赤線や青線が出るのを止めたい」
Wordには、スペルミスや文法ミスを自動でチェックしてくれる機能があります。便利な機能ではありますが、日本語や専門用語を多用する文書では、本来正しい文章にも赤線が入ってしまい邪魔になることがあります。
この記事では、Wordに表示される赤線(スペルチェック)の消し方・一時的な無効化・高度な設定までをわかりやすく解説します。
急いでいる人は、赤線を右クリックして「この語をすべて無視」を選んでみてください。その単語の赤線が一時的に消えます。
Wordの赤線とは?

各色の線が示す意味
Wordには3種類の下線があり、それぞれ異なる意味を持っています:
赤いなみ線
- スペルチェック(主に英語)
- 未知の単語やスペルミスと判断された語に表示される
- 例:「つく」を「tuku」と入力した場合など
青いなみ線
- 文法チェック
- 文法的に間違っていると判断された箇所に表示
- 例:「です・ます調」と「だ・である調」が混在した場合
緑のなみ線
- スタイルや表現の提案
- より良い表現がある場合のアドバイス
- 例:同じ語の繰り返しなど
なぜ正しい言葉にも線が出るの?
Wordの辞書にない語
以下のような単語は、Wordの標準辞書に登録されていないため、正しくても赤線が表示されます:
- 人名、地名、会社名
- 新しい言葉(IT用語、流行語など)
- 方言や話し言葉
- 専門用語や業界用語
日本語の特殊性
日本語は以下の特徴があるため、英語中心のスペルチェック機能では正確な判定が困難です:
- ひらがな、カタカナ、漢字の混在した文
- 敬語の複雑な使い分け
- 文体の統一性チェック
- 助詞の微細な使い分け
一時的に赤線を消す方法
単語単位で無視する方法
特定の単語だけを一時的にチェック対象から外すことができます。
手順
- 赤線が表示されている単語を右クリック
- 「この語を無視」または「この語をすべて無視」を選択
- クリックするとその単語の赤線が消える
効果の範囲
- 「この語を無視」: その場所だけ赤線が消える
- 「この語をすべて無視」: 同じ単語すべてで赤線が消える(その文書内のみ)
使用すべき場面
- 固有名詞(人名、会社名、商品名)
- 一時的に集中して作業したいとき
- 他の人に見せる前の体裁調整
注意点
- 新しい文書では同じ単語にまた線が出る
- 本当のスペルミスも見逃す可能性がある
- 設定は文書ごとに保存される
辞書に追加する方法
よく使う単語は辞書に追加することで、今後同じ線が出なくなります。
手順
- 単語を右クリック
- 「辞書に追加」を選択
- その単語がWordの辞書に登録される
メリット
- 新しい文書でも同じ単語で線が出ない
- 会社名や専門用語の一括対応が可能
- チーム内での辞書共有も可能
文書全体で赤線を非表示にする方法
完全に無効化する設定
すべてのスペルチェック・文法チェック機能を無効にする方法です。
詳しい手順
- 「ファイル」タブをクリック
- 「オプション」を選択
- 「文章校正」をクリック
- **「Wordのスペルチェックと文法チェックのオプション」**で以下のチェックを外す:
外すべき項目
- 「入力時にスペルチェックを行う」
- 「文法エラーを表示する」
- 「文章校正中にスペルチェックを行う」
- 「入力時に文法チェックを行う」
- 「文章校正中に文法チェックを行う」
結果
これですべての赤線・青線・緑線が非表示になります。
元に戻す方法
- 同じ設定画面を開く
- 外したチェックをもう一度入れる
- 「OK」ボタンを押す
部分的に残す設定
すべてを無効にするのではなく、必要な機能だけを残すことも可能です。
スペルチェックのみ残す場合
- 「入力時にスペルチェックを行う」だけにチェック
- 文法チェックやスタイル提案は無効
文法チェックのみ残す場合
- 「文法エラーを表示する」だけにチェック
- スペルチェックは無効、文法のみチェック
おすすめの設定
初心者の場合は、スペルチェックのみを有効にしておくことをおすすめします。これにより、明らかなタイプミスは検出しつつ、文体や表現への過度な指摘を避けられます。
特定の範囲だけ赤線を非表示にする

選択した部分のみを対象外にする
文書の一部分だけをスペルチェックの対象外にする方法です。
手順の詳細
- 対象の文章を選択
- マウスでドラッグして範囲選択
- Shift + 矢印キーでの選択
- Ctrl + A で全体選択
- 右クリック →「言語」→「校正しない言語に設定」
- 「スペルチェックと文法チェックを行わない」にチェック
- 「OK」ボタンを押す
効果
選択した部分のみ赤線が非表示になります。他の部分はそのまま残ります。
活用場面
例1:英語の文章を引用するとき
日本語の文書内で英語を引用する際、その部分だけを対象外にできます。
日本語の文章です。
"This is an English quote from a research paper."
(この部分だけ校正無効)
また日本語が続きます。
例2:専門用語が多い段落
特定の段落に専門用語が集中している場合に便利です。
一般的な内容です。
IoT、AI、DXなどのIT用語が多い段落の内容。
クラウドコンピューティングやマシンラーニングについて。
(この段落だけ校正無効)
再び一般的な内容です。
例3:プログラムコードや数式
コードや数式の部分は校正対象外にするのが適切です。
説明文です。
function calculateArea() {
return width * height;
}
(プログラムコード部分を校正無効)
説明の続きです。
より細かい制御方法
段落ごとの設定
- 段落全体を選択(段落内で3回クリック)
- 「校閲」→「言語」→「言語の設定」
- 「校正しない」を選択
セクションごとの設定
- セクション区切りを挿入
- そのセクション全体を選択
- 言語設定を変更
スタイルベースの設定
- 「ホーム」タブのスタイルを選択
- スタイルを右クリック→「変更」
- 「書式」→「言語」で設定
注意点と特別な状況への対応
校正機能を無効にするときの注意点
問題点
- 実際の誤字や脱字にも気づきにくくなる
- タイプミスを見逃す可能性が高まる
- 提出前のチェックがおろそかになりがち
- 文章の品質低下のリスク
対策方法
- 文書完成後に手動でチェックする
- 他の人に読んでもらう
- 音読して確認する
- 一度校正機能を有効に戻してチェック
- 印刷して紙で確認する
再度表示させたいとき
全体設定を戻す方法
- 「ファイル」→「オプション」→「文章校正」
- 外したチェックを入れ直す
- 「OK」ボタンを押す
部分的に元に戻す方法
- 対象範囲を選択
- 右クリック→「言語」
- 「自動的に言語を検出する」を選択
特殊な状況への対応
多言語文書の場合
各言語ごとに校正設定を変更できます:
- 対象部分を選択
- 「校閲」→「言語」→「言語の設定」
- 適切な言語を選択
- その言語の校正設定を調整
共同編集の場合
重要なポイント:
- 自分の設定は他の人に影響しない
- 各ユーザーが個別に設定する必要がある
- コメントや提案機能とは別の設定
- OneDriveやSharePoint上でも個人設定が適用
テンプレートの場合
テンプレート作成時の注意:
- テンプレートに校正設定も保存される
- 新しい文書で自動的に適用される
- 必要に応じてテンプレートを更新
- 利用者向けの設定ガイドも準備
活用場面と具体的な対応例
場面1:学術論文の執筆
よくある問題
- 専門用語に赤線が多数表示される
- 英語の引用文に青線が出る
- 参考文献の書式にスタイル提案が入る
- 数式や記号に赤線が表示される
解決策
- 専門用語部分を部分的に校正無効化
- 引用文は言語設定を英語に変更
- 参考文献欄はスタイル提案のみ無効化
- 数式部分は完全に校正対象外に設定
場面2:ビジネス文書の作成
よくある問題
- 会社名や製品名に赤線が出る
- 略語(IT、AI、IoTなど)に線が表示される
- 硬い文体と柔らかい文体の混在を指摘される
- カタカナ用語の使用を指摘される
解決策
- 固有名詞を「すべて無視」で処理
- 略語リストを事前にWordの辞書に追加
- 文体統一後に校正機能で最終チェック
- 業界標準のカタカナ用語は辞書に登録
場面3:クリエイティブライティング
よくある問題
- 創作的な表現にスタイル提案が入る
- 方言や話し言葉に線が表示される
- 意図的な文法変則に指摘が入る
- 擬音語や造語に赤線が出る
解決策
- 創作部分のみ校正完全無効化
- セリフ部分は部分的に無効化
- 最後にスペルチェックのみ有効にして確認
- 重要な語は辞書に追加して統一
より高度な設定とカスタマイズ

カスタム辞書の作成と管理
辞書の作成手順
- 「ファイル」→「オプション」→「文章校正」
- 「カスタム辞書」をクリック
- 「編集」で よく使う単語を追加
- 「新規作成」で専用辞書を作成
辞書の活用メリット
- 会社名や専門用語を事前登録
- チーム全体で同じ辞書を共有可能
- 新しい文書でも自動的に適用
- プロジェクトごとの辞書管理
辞書の共有方法
- カスタム辞書ファイル(.dic)をエクスポート
- チームメンバーと共有
- 各自のWordにインポート
- 一貫した校正基準を維持
オートコレクト機能との連携
オートコレクトの設定
- 「ファイル」→「オプション」→「文章校正」
- 「オートコレクトのオプション」をクリック
- よくあるミスタイプを事前登録
効果的な使用例
- 「teh」→「the」の自動修正
- 会社名の略称から正式名称への変換
- よくある誤変換の自動修正
マクロによる自動化
基本的なマクロ例
Sub DisableSpellCheck()
' 現在の文書のスペルチェックを無効化
ActiveDocument.SpellingChecked = True
ActiveDocument.GrammarChecked = True
' 表示設定も変更
Options.CheckSpellingAsYouType = False
Options.CheckGrammarAsYouType = False
End Sub
Sub EnableSpellCheck()
' スペルチェックを再有効化
Options.CheckSpellingAsYouType = True
Options.CheckGrammarAsYouType = True
End Sub
マクロの活用場面
- 同じ設定を繰り返し適用したい場合
- 複数の文書を一括処理したい場合
- テンプレート作成時の自動設定
トラブルシューティング
よくある問題と解決法
設定したのに赤線が消えない場合
原因1: 設定が正しく適用されていない
- 解決法:Wordを再起動して設定を反映させる
原因2: 文書が保護されている
- 解決法:「校閲」→「編集の制限」で保護を解除
原因3: テンプレートの設定が優先されている
- 解決法:テンプレートの校正設定を確認・変更
一部の単語だけ線が残る場合
原因: 言語設定が混在している
- 解決法:全体を選択して言語を統一
他の人と設定が同期されない場合
原因: 個人設定とファイル設定の混同
- 解決法:文書固有の設定と個人設定を明確に分ける
まとめ
Wordの赤線(スペルチェック)は便利な反面、正しい単語や固有名詞にも誤判断されることがあるため、作業中に気になる場合は非表示にする方法を活用するとストレスが軽減されます。
主要なポイント
使い分けの基本:
- 一時的な解除: その場しのぎに便利
- 特定範囲のみ: 部分的な調整に最適
- 文書全体の設定: 効率的な作業のため
- 最後は必ずチェック: 文書の質を保つため
推奨する作業フロー:
- 執筆中: 集中のため校正機能を無効化
- 初回チェック: スペルチェックのみ有効化
- 最終確認: すべての校正機能を有効化
注意すべきポイント:
- 完全に無効化した場合は手動チェックを忘れずに
- 重要な文書では必ず最終確認を実施
- チーム作業では設定の統一を図る
- カスタム辞書を活用して効率化を図る