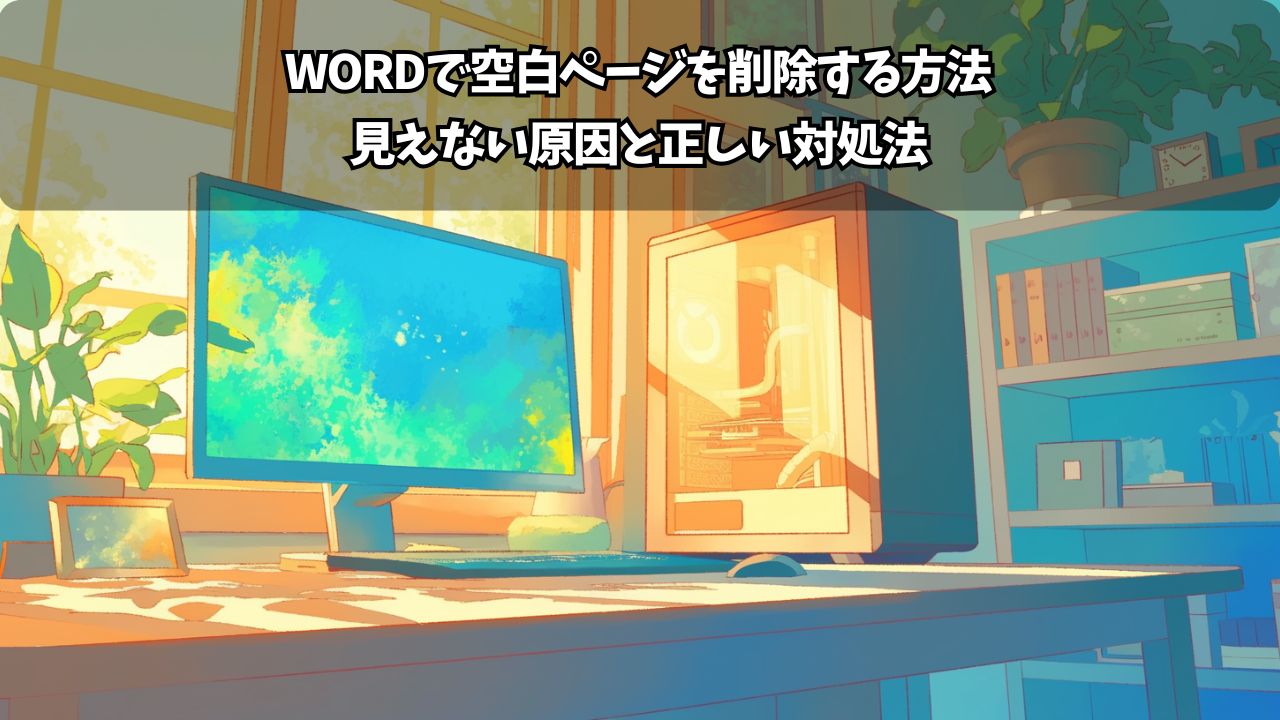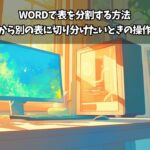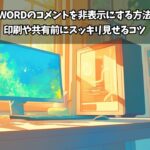Word(ワード)文書を仕上げたのに、なぜか最後に空白ページが残ってしまう。そんな経験はありませんか?
印刷時に余分なページが出たり、PDF化したときに不格好になったりと、意外と悩ましい問題です。
この記事では、Wordの空白ページを確実に削除する方法と、ページが残る原因ごとの対処法をわかりやすくご紹介します。
空白ページが発生する場面と影響

よくある空白ページの問題
発生しやすい文書:
- レポート・論文:表やグラフ挿入後
- 契約書・提案書:セクション区切り使用時
- マニュアル:章立て構成での改ページ
- 案内文・通知書:レイアウト調整後
空白ページがもたらす問題:
- 印刷コストの無駄:不要な用紙とインク消費
- 文書の見栄え悪化:プロフェッショナルな印象の損失
- ファイルサイズ増大:PDF化時の無駄な容量
- 読み手の混乱:文書構成の不明確さ
空白ページができる主な原因
原因の分類と特徴
| 原因 | 特徴 | 表示方法 | 解決難易度 |
|---|---|---|---|
| 改ページの挿入 | ページ途中に強制改ページ | --- 改ページ --- | 易 |
| セクション区切り | 新しいセクションで改ページ発生 | === セクション区切り === | 中 |
| 表の直後の改行 | 表の後に空白行が挿入 | ¶(段落記号) | 易 |
| 複数の改行記号 | Enterキーの連打で行が下がっている | 連続する¶ | 易 |
| ページ末尾の段落設定 | 段落の間隔設定による押し出し | 段落後の間隔 | 中 |
より詳細な原因分析
テキストベースの原因:
- 連続する段落記号:Enter キー多用
- 非表示文字:タブ、スペースの蓄積
- 段落書式:段落前後の間隔設定
- 行間設定:過大な行間による押し出し
オブジェクトベースの原因:
- 表の配置設定:表後の自動改ページ
- 図・画像の配置:オブジェクト周りの設定
- テキストボックス:配置による影響
- ヘッダー・フッター:内容による押し出し
構造的な原因:
- セクション設定:改ページ強制設定
- スタイル設定:見出しスタイルの改ページ
- ページ設定:余白や用紙サイズの影響
- テンプレート:既定設定による影響
基本の確認手順|まずは編集記号を表示
編集記号表示の重要性
なぜ編集記号が必要か: 編集記号を表示することで、何が空白ページの原因かを目で見て判断できます。
編集記号の表示方法
基本手順:
- 「ホーム」タブをクリック
- **「編集記号の表示(¶)」**ボタンをクリック
- すべての非表示文字が表示される
ショートカットキー:
- Windows:
Ctrl + Shift + 8 - Mac:
⌘ + 8
主要な編集記号の意味
重要な記号一覧:
- ¶: 段落記号(Enterキーで改行)
- →: タブ記号
- ·: スペース記号
- — 改ページ —: 手動改ページ
- === セクション区切り ===: セクション区切り
- |: 任意指定の行区切り(Shift + Enter)
効果的な確認手順
段階的チェック:
- 文書の最後にスクロール
- 空白ページの内容を確認
- 編集記号の種類を特定
- 原因に応じた対処を実行
原因別の詳細な対処法
1. 改ページが原因のとき
識別方法: --- 改ページ --- の表示を確認
削除手順:
- 改ページ記号をクリックして選択
- DeleteキーまたはBackspaceキーで削除
- 空白ページの消失を確認
注意点:
- 手動改ページは意図的に設定されている場合が多い
- 削除前に改ページの必要性を確認
- 代替手段(段落設定での改ページ)の検討
2. セクション区切りが原因のとき
識別方法: === セクション区切り(次のページ)=== の表示
削除手順:
- セクション区切り記号を選択
- Deleteキーで削除
- ページ設定の変化を確認
重要な注意事項:
- ページ設定が統合される可能性
- ヘッダー・フッターが変更される場合
- 余白や用紙の向きが変わる可能性
- 削除前にバックアップを推奨
安全な削除方法:
- 文書のバックアップを作成
- 現在のセクション設定をメモ
- 段階的に削除して影響を確認
- 必要に応じて設定を復元
3. 表の直後に空白ができているとき
よくあるパターン: 表の作成・編集後に自動で空白ページが発生
対処法A:段落記号の削除
- **表の直後の段落記号(¶)**を確認
- 不要な段落記号を選択
- Deleteキーで削除
対処法B:表プロパティの調整
- 表を右クリック → 「表のプロパティ」
- 「表」タブで配置を確認
- 「段落後の間隔」をゼロに設定
- **「OK」**で確定
対処法C:文字列の折り返し設定
- 表のプロパティを開く
- **「文字列の折り返し」**を確認
- **「なし」**に設定して様子を見る
4. 複数の改行でページが押し出されているとき
問題の特定: 連続する段落記号(¶¶¶)が原因
解決手順:
- 不要な段落記号を特定
- 複数選択(ドラッグまたはShift + 矢印キー)
- Deleteキーで一括削除
- 適切な行間設定に調整
予防策:
- 段落の間隔設定を活用(段落後:6pt~12pt)
- スタイル機能で統一された間隔設定
- Enter連打の習慣を改める
高度な削除技術

段落設定による空白の除去
段落間隔が原因の場合:
- 空白ページの段落を選択
- 右クリック → 「段落」
- **「段落前」「段落後」**の間隔を0ptに設定
- **「OK」**で適用
検索・置換機能の活用
複数の改ページを一括削除:
- **
Ctrl + H**で置換ダイアログを開く - 検索する文字列:
^m(改ページ) - 置換後の文字列: (空白)
- **「すべて置換」**を実行
複数の段落記号を整理:
- 検索する文字列:
^p^p(2つの段落記号) - 置換後の文字列:
^p(1つの段落記号) - 複数回実行して重複を除去
ナビゲーション機能の活用
ページ構造の把握:
- 「表示」タブ → 「ナビゲーションウィンドウ」
- 「ページ」タブでページ一覧を表示
- 空白ページを視覚的に特定
- 該当ページをクリックして移動
表示モードを活用した効率的な作業
下書き表示モードの活用
下書きモードのメリット:
- 「表示」タブ → 「下書き」
- レイアウト要素が簡略化
- 編集記号が見やすい
- ページ境界が明確
効率的な確認作業:
- スクロールが軽快
- 原因の特定が容易
- 削除作業がスムーズ
Webレイアウト表示での確認
連続表示での全体把握:
- ページ境界がない表示
- 文書全体の流れを確認
- 不自然な空白を発見
特殊なケースの対処法
ヘッダー・フッターが原因の場合
問題の特徴:
- ヘッダー・フッター内容が多すぎる
- 本文領域が圧迫される
- 自動改ページが発生
対処方法:
- 「挿入」タブ → 「ヘッダーとフッター」
- 内容の削減またはフォントサイズ縮小
- 余白設定の見直し
脚注・文末脚注が原因の場合
確認と調整:
- 「参考資料」タブ → 「脚注」
- 脚注の配置設定を確認
- 不要な脚注の削除
- 脚注の書式設定を調整
図表の配置が原因の場合
図表の設定確認:
- 図表を右クリック → 「配置」
- **「文字列の折り返し」**を調整
- **「詳細設定」**でページ区切り設定を確認
最終確認とトラブル防止
印刷プレビューでの最終チェック
確認手順:
- 「ファイル」 → 「印刷」
- プレビュー画面で全ページを確認
- 空白ページの有無をチェック
- 必要に応じて修正
PDF出力での品質確認
PDF変換チェック:
- 「ファイル」 → 「エクスポート」 → 「PDF/XPS の作成」
- オプションでページ範囲を確認
- 空白ページを除外する設定があるか確認
- 最終的な仕上がりを確認
設定の標準化
今後の予防策:
- スタイル設定の標準化
- テンプレートの作成と活用
- 作業手順のルール化
- 定期的な確認習慣
まとめ
Wordの空白ページは、編集記号を確認すればほぼ確実に削除できます。
主要な原因と対処:
- **「改ページ」「セクション区切り」「改行」**が原因の代表格
- 編集記号を表示して、正しく削除することが重要
- 表や改行後の余白もチェックポイント
効果的な削除手順:
- 編集記号の表示で原因を特定
- 原因別の適切な対処法を実行
- 表示モードを活用した効率的作業
- 最終確認で品質を担保
予防のポイント:
- 段落設定での間隔管理
- スタイル機能の活用
- Enter連打の習慣改善
- 定期的な文書構造確認
実務での価値:
- プロフェッショナルな文書品質
- 印刷コストの削減
- ファイルサイズの最適化
- 読み手への配慮
応用テクニック:
- 検索・置換での一括処理
- マクロによる自動化
- テンプレートでの標準化
- 品質管理システムの構築