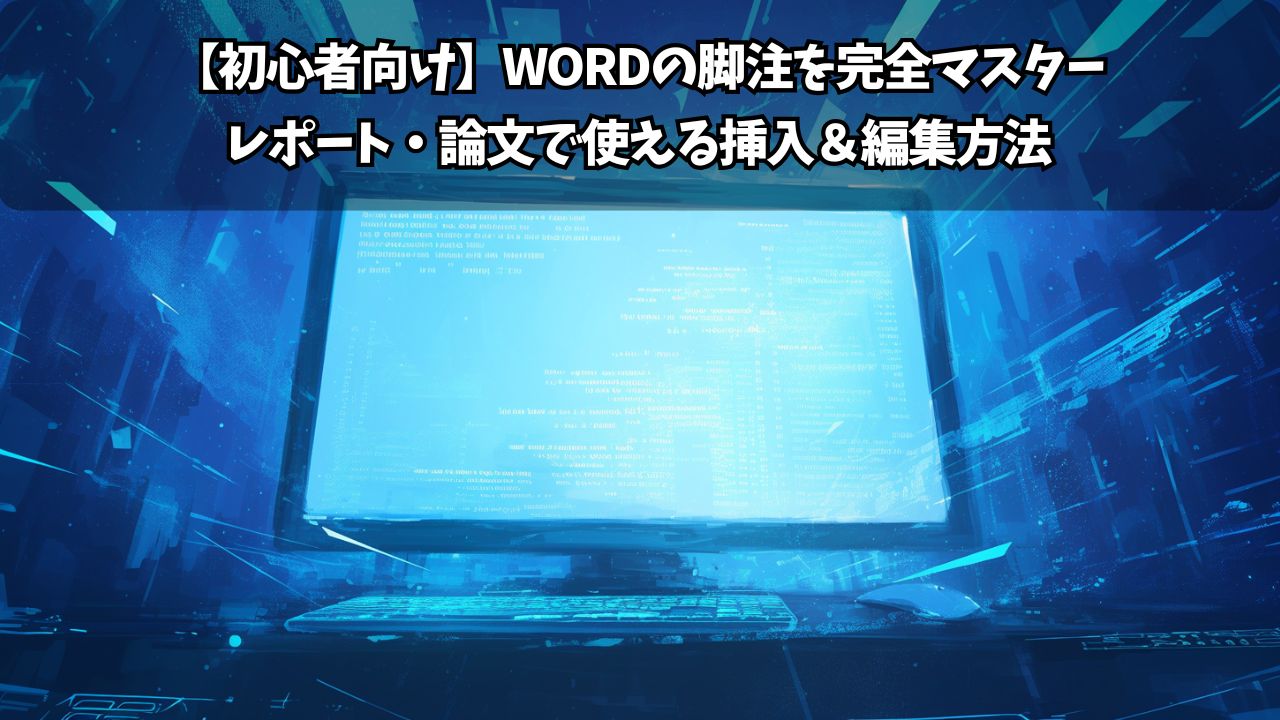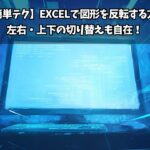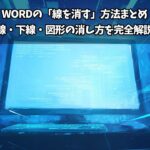「レポートに補足情報を入れたいけど、どこに書けばいい?」
「引用元を明記する脚注ってどうやって付けるの?」
Word(ワード)で論文・レポート・報告書を作成するときに欠かせないのが「脚注(きゃくちゅう)」です。本文の補足説明や出典の表示として広く使われていますが、初めての人には「どこから操作すればいいの?」と戸惑うこともあるかもしれません。
この記事では、Wordで脚注を正しく挿入・編集・書式変更する方法を初心者にもわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 脚注の基本的な挿入方法
- 脚注と文末脚注の使い分け
- 書式設定とカスタマイズ方法
- よくあるトラブルと解決策
脚注とは?基本知識を理解しよう

脚注の定義と役割
脚注とは、本文中の語句や文章の補足情報や出典などを、ページ下部に小さく表示する機能です。学術論文やレポートでは、情報の信頼性を高めるために必要不可欠な要素となっています。
脚注の表示例
本文中の表示:
経済学の古典的理論では¹、需要と供給の均衡が重要とされる。
ページ下部の表示:
¹ アダム・スミス『国富論』(1776年)より
このように、本文中には小さな数字(上付き文字)が表示され、ページの下部に詳細な説明が記載されます。
脚注を使うメリット
- 本文の流れを妨げない:詳細情報を別の場所に配置
- 文書の信頼性向上:出典や根拠を明確に示す
- 読者の利便性:必要に応じて詳細を確認可能
- 学術的な体裁:論文やレポートに適した形式
Wordで脚注を挿入する基本手順
脚注をつけたい位置にカーソルを置く
まず、補足説明や出典を付けたい語句や文の直後にカーソルを合わせます。通常は、句読点の前に配置することが多いです。
配置位置の例
- 正しい:「経済成長¹は重要である。」
- 間違い:「経済¹成長は重要である。」
「参考資料」タブを開く
Word画面上部のリボンメニューから「参考資料」タブをクリックします。このタブには、脚注以外にも目次や索引などの文書作成に役立つ機能がまとめられています。
「脚注の挿入」をクリック
「参考資料」タブ内の左側にある「脚注の挿入」ボタンをクリックします。するとすぐに以下の変化が起こります:
- 本文中:カーソル位置に上付き数字(¹、²、³…)が自動挿入
- ページ下部:脚注入力欄が自動的に表示
- カーソル移動:脚注入力欄にカーソルが移動
脚注の内容を入力
ページ下部に表示された脚注欄に、補足情報や出典を書き込みます。入力が完了したら、本文中をクリックすると元の位置に戻ることができます。
脚注の書き方例
出典の場合
¹ 田中太郎『現代経済学入門』東京出版、2023年、45頁
補足説明の場合
² この理論は1980年代に提唱され、現在でも広く支持されている
脚注と文末脚注の違いと使い分け
表示場所と用途の違い
| 種類 | 表示場所 | 主な用途 | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| 脚注 | 各ページの下部 | 補足説明・短い注釈 | 一般的なレポート・論文 |
| 文末脚注 | 文書の最後 | 参考文献・詳細な出典 | 長い論文・書籍 |
脚注を選ぶべき場面
- 短いレポート(10ページ以内)
- 補足説明が主の場合
- 読者がすぐに確認したい情報
- ページごとに完結させたい文書
文末脚注を選ぶべき場面
- 長い論文(20ページ以上)
- 参考文献が多い場合
- 詳細な出典情報を記載する場合
- 印刷時のページ数を抑えたい場合
脚注から文末脚注への変換方法
既に作成した脚注を文末脚注に変更することも可能です:
- 「参考資料」タブをクリック
- 「脚注と文末脚注」グループの右下矢印をクリック
- 「すべて変換」ボタンをクリック
- 「脚注を文末脚注に変換」を選択
脚注の書式設定とカスタマイズ
脚注ダイアログボックスの開き方
より詳細な設定を行いたい場合は、「参考資料」タブの「脚注と文末脚注」グループ右下にある小さな矢印アイコンをクリックします。これにより「脚注と文末脚注」ダイアログボックスが開きます。
番号形式の変更
脚注の番号形式は、文書のスタイルに合わせて変更できます:
選択可能な番号形式
- アラビア数字:1, 2, 3, 4…(標準)
- ローマ数字(小文字):i, ii, iii, iv…
- ローマ数字(大文字):I, II, III, IV…
- 英字(小文字):a, b, c, d…
- 英字(大文字):A, B, C, D…
学術分野別の慣例
- 人文科学:アラビア数字またはローマ数字
- 理工系:アラビア数字が一般的
- 法学:ローマ数字を使用することが多い
開始番号の設定
複数の章がある文書では、各章の脚注番号を1から始めたい場合があります。「番号」セクションで「各ページで番号を振り直す」または「各セクションで番号を振り直す」を選択できます。
脚注の配置設定
- 位置:ページ下部(標準)または本文直下
- 段組み:1段組み(標準)または2段組み
- 区切り線:表示・非表示の選択
よくあるトラブルと解決方法
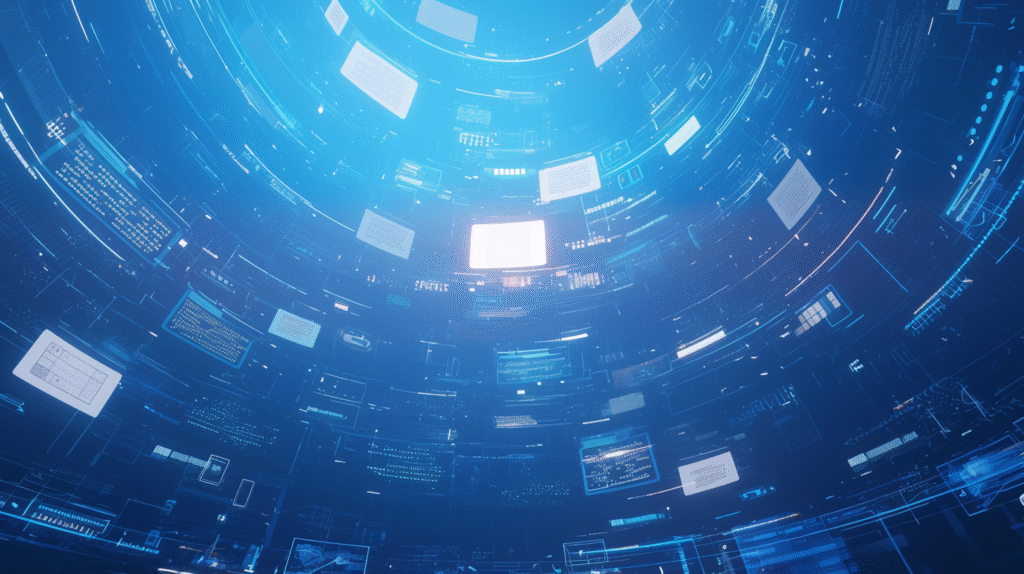
脚注番号がずれる・飛ぶ
問題の原因
脚注を削除した際に、番号が自動更新されないことがあります。
解決方法
- F9キーを押す:文書全体のフィールドを更新
- 「編集」→「すべて選択」→F9:全フィールドの強制更新
- 文書の再保存:ファイルを保存し直す
- Word再起動:アプリケーションを再起動
脚注がページをまたいでしまう
問題の原因
脚注の文章が長すぎて、次のページにはみ出してしまう現象です。
解決方法
- 脚注を簡潔にする:不要な文章を削除
- 文末脚注に変更:長い引用は文末脚注が適している
- ページ余白の調整:下余白を少し広げる
- フォントサイズの縮小:脚注の文字を小さくする
脚注の位置を移動したい
移動方法
本文中の上付き数字(脚注番号)をドラッグ&ドロップで移動させると、脚注も自動的に新しい位置に連動します。
注意点
- 番号は自動更新:移動後の番号は自動的に調整される
- 複数脚注の移動:順序が変わると全体の番号も変更される
脚注が表示されない
確認すべきポイント
- 表示設定:「表示」タブで「印刷レイアウト」になっているか
- ページ設定:下余白が十分確保されているか
- セクション区切り:複雑な文書構造になっていないか
脚注のスタイルと書き方のルール
出典記載の基本ルール
書籍の場合
著者名『書籍名』出版社、出版年、ページ数
例:田中太郎『現代経済学入門』東京出版、2023年、45頁
雑誌論文の場合
著者名「論文タイトル」『雑誌名』巻号、出版年、ページ数
例:佐藤花子「デジタル経済の展望」『経済研究』第15巻2号、2023年、23-35頁
ウェブサイトの場合
著者名「記事タイトル」サイト名、最終閲覧日、URL
例:山田一郎「AI技術の現状」テクノロジー情報サイト、2023年12月1日閲覧、https://example.com
補足説明の書き方
- 簡潔性:本文の流れを妨げない程度の長さ
- 関連性:本文と直接関係のある内容のみ
- 客観性:主観的な意見は避け、事実を中心に記載
脚注の活用場面と実例
学術レポート・論文での活用
出典の明記
研究論文では、引用した情報の出典を明確にすることが求められます。
例文:
近年の研究では、リモートワークの普及により生産性が向上することが明らかになっている¹。
脚注:
¹ 労働研究所『2023年働き方調査報告書』、124頁
専門用語の説明
専門的な内容を一般読者にもわかりやすく説明する際に使用します。
例文:
この現象はパラダイムシフト²と呼ばれている。
脚注:
² 既存の理論や方法論が根本的に変化すること
ビジネス文書での活用
詳細情報の提供
契約書やマニュアルでは、本文をシンプルに保ちながら詳細情報を提供できます。
例文:
当サービスは24時間365日利用可能³です。
脚注:
³ ただし、毎月第2日曜日の午前2時〜4時はメンテナンス時間のため利用不可
翻訳・文学作品での活用
文化的背景の説明
原文の文化的な背景や歴史的な文脈を説明する際に使用します。
例文:
彼は盆と正月⁴が一緒に来たような気分だった。
脚注:
⁴ 日本では盆(8月)と正月(1月)は一年で最も重要な行事のため、「とても嬉しいこと」の例えとして使われる
より効率的な脚注作成のコツ

ショートカットキーの活用
脚注挿入のショートカットキー:
- Ctrl + Alt + F:脚注の挿入
- Ctrl + Alt + D:文末脚注の挿入
これらのキーを覚えることで、マウス操作なしで素早く脚注を追加できます。
スタイルの一貫性を保つ
文書全体での統一
- 番号形式:文書全体で同じ形式を使用
- フォント:脚注のフォントサイズや種類を統一
- 書式:出典の書き方ルールを一貫
テンプレートの活用
よく使う脚注の書式をテンプレートとして保存しておくと、効率的に作業できます。
相互参照の活用
同じ文献を複数回引用する場合は、「相互参照」機能を使用して「前掲書」や「同上」として処理することができます。
まとめ
Wordの脚注機能を正しく使いこなすことで、文書の信頼性と読みやすさが大きく向上します。
この記事のポイント
- 基本操作:「参考資料」タブ→「脚注の挿入」で簡単追加
- カスタマイズ:番号形式や配置も自由に変更可能
- 使い分け:脚注と文末脚注を適切に使い分け
- トラブル対策:よくある問題の解決方法を把握
脚注活用の効果
- 学術的信頼性:出典明記による情報の裏付け
- 読みやすさ向上:本文をすっきりと保持
- 情報の補完:必要な詳細情報を適切に提供
- 専門性の向上:学術論文に必要な体裁を整備