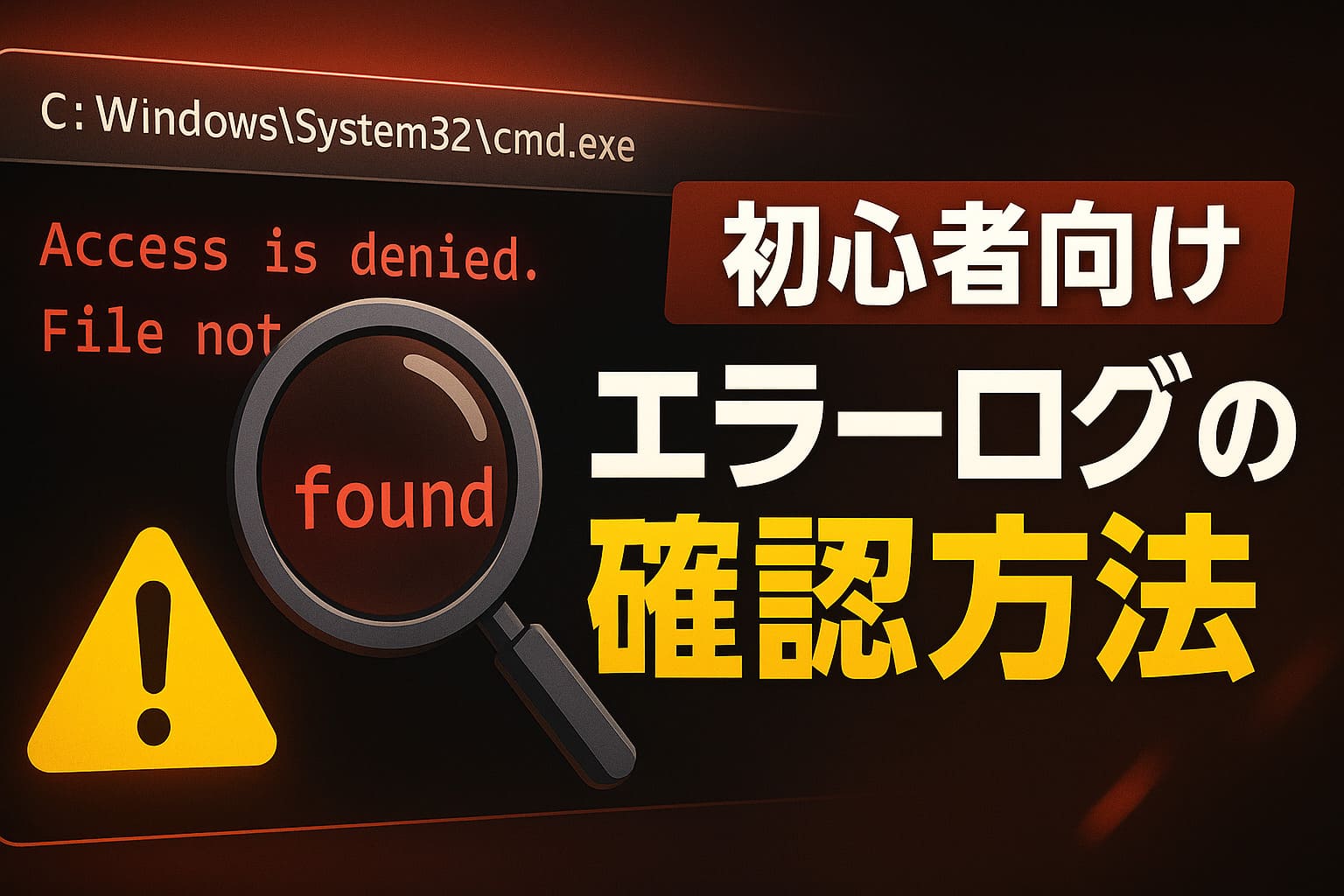「バッチファイルが動かない…」
「コマンドは打てたけど、何が起きたのか分からない」
そんなとき、エラーログの確認はトラブルシューティングの第一歩です。
Windowsのコマンドプロンプト(CMD)には、標準出力や標準エラー出力といったログの流れが存在します。
本記事では、初心者でも理解できるように、コマンドプロンプトでエラーログを表示・記録・活用する方法を丁寧に解説していきます。
コマンドプロンプトでのエラーログとは?
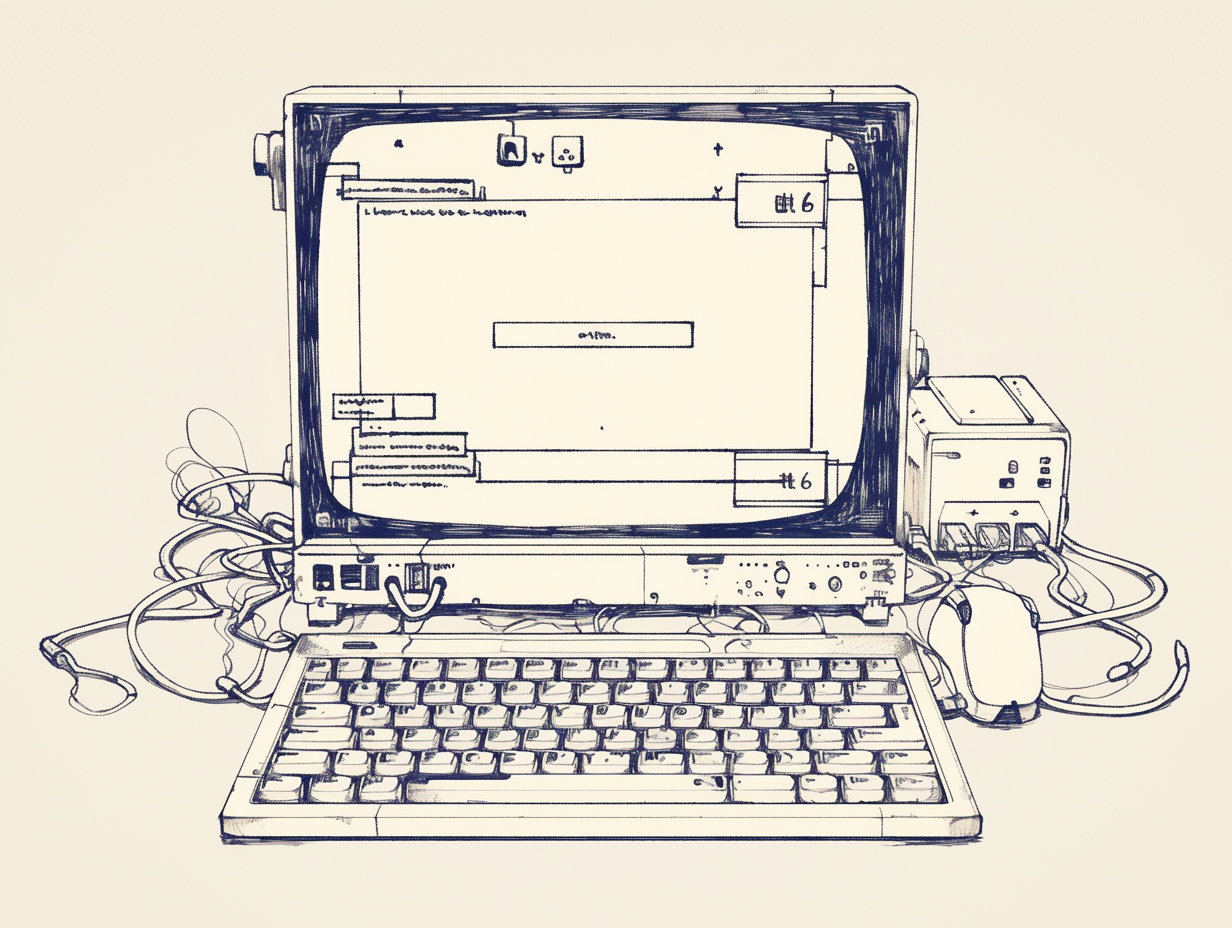
Windowsのコマンドプロンプトでは、実行結果が「出力」として表示されます。
ですが、その中には通常の出力(標準出力)と、エラー時の出力(標準エラー出力)の2種類があります。
例)存在しないディレクトリに移動しようとした場合:
cd C:\not_exist_folder表示されるエラー:
指定されたパスが見つかりません。これはエラー出力(stderr)として扱われます。
多くの場合、エラーメッセージは赤色で表示されますが、コマンドプロンプトの設定によって異なる場合もあります。
この区別を理解することで、何が正常な出力で何がエラーなのかを判断できるようになります。
エラーメッセージをその場で表示する方法
通常、エラーは自動的に画面に表示されますが、一部のツールやバッチでは無視されることも。
明示的に確認したい場合は、次のようにすると安心です。
somecommand || echo コマンドが失敗しました||は直前のコマンドが失敗した場合に続く処理を実行します。
これを利用すると、エラー発生時に独自のメッセージを表示できます。
例えば、存在しないコマンドを実行した場合:
notexist || echo このコマンドは存在しません実行結果:
'notexist' は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
このコマンドは存在しません
これにより、エラーが発生したことを明確に確認できます。
エラーログをファイルに出力する方法

コマンドの出力やエラーをログファイルとして保存しておくと、あとから確認できて便利です。
基本的なリダイレクト
your_command > output.log 2> error.log>は標準出力(stdout)をファイルに保存2>は標準エラー出力(stderr)を別ファイルに保存
例えば、コピーコマンドでエラーを発生させる場合:
copy nonexistent.txt destination.txt > success.log 2> error.logこの場合、error.logにエラーメッセージが保存されます。
両方の出力をまとめて記録する場合:
your_command > all.log 2>&1これはエラーも通常出力もすべて all.log に保存します。
2>&1 は「エラー出力を標準出力と同じ場所に送る」という意味です。
現在の出力に追加する場合:
既存のログファイルに上書きではなく追加したい場合は、>> を使います:
your_command >> output.log 2>> error.logこれにより、ファイルの内容を消去せずに新たな出力が追加されます。
標準出力と標準エラー出力の違い
| 出力の種類 | リダイレクト記号 | 意味 |
|---|---|---|
| 標準出力(stdout) | > | 成功時など通常の出力 |
| 標準エラー(stderr) | 2> | エラーや警告の出力 |
この違いを理解することで、トラブル原因を的確に切り分けられるようになります。
例えば、何かのプログラムやコマンドが実行されたとき:
- 通常の処理結果は標準出力として出力される
- エラーや警告は標準エラー出力として出力される
これらを別々のファイルに保存することで、成功した処理とエラーを分けて記録・確認できます。
応用:バッチファイルでエラーを記録する方法
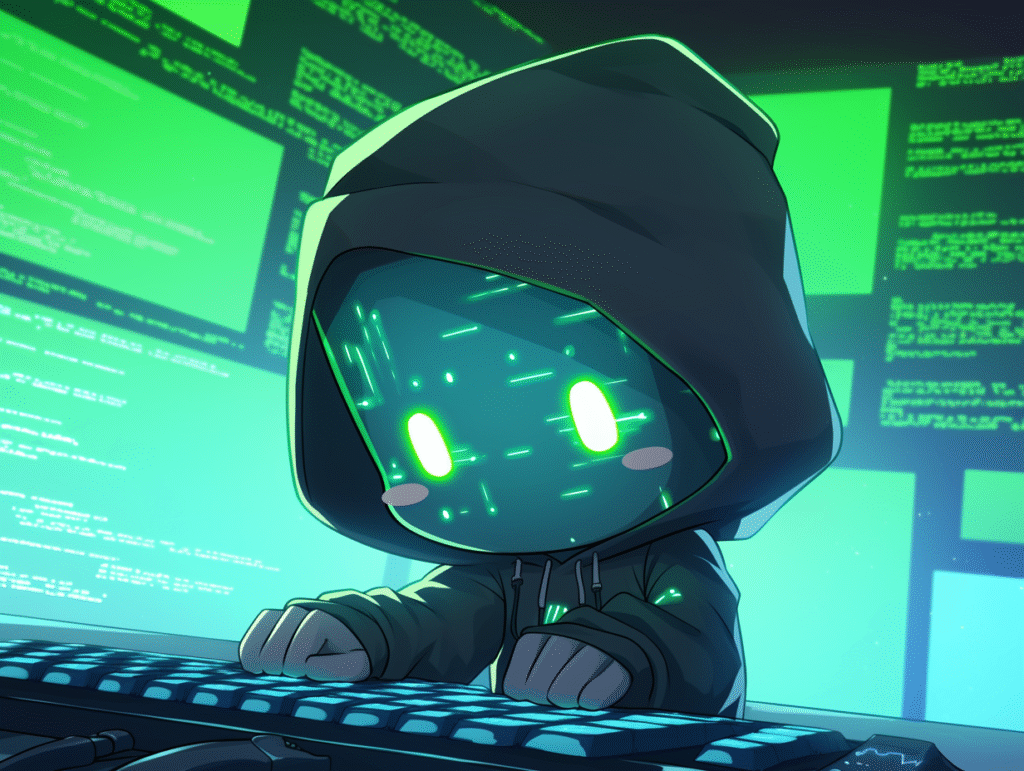
バッチファイルでも以下のように記述すれば、エラーログが保存できます。
@echo off
echo 処理を開始します... > output.log
your_command >>output.log 2>error.log
if errorlevel 1 (
echo %date% %time% - エラーが発生しました >> error.log
echo 詳細はエラーログを確認してください
) else (
echo 処理が成功しました
)
errorlevelは直前のコマンドの終了コードを確認する仕組みです。1以上ならエラーと判断されます。
より詳細なエラーログを作成する例:
@echo off
echo ===================================== > error.log
echo 実行日時: %date% %time% >> error.log
echo ===================================== >> error.log
echo. >> error.log
your_command > output.log 2>> error.log
if errorlevel 1 (
echo エラーコード: %errorlevel% >> error.log
echo 処理が失敗しました。error.logを確認してください。
) else (
echo 処理が正常に完了しました。
)
これにより、いつ、どのようなエラーが発生したかを詳細に記録できます。
便利なコマンドとトラブル対処のヒント
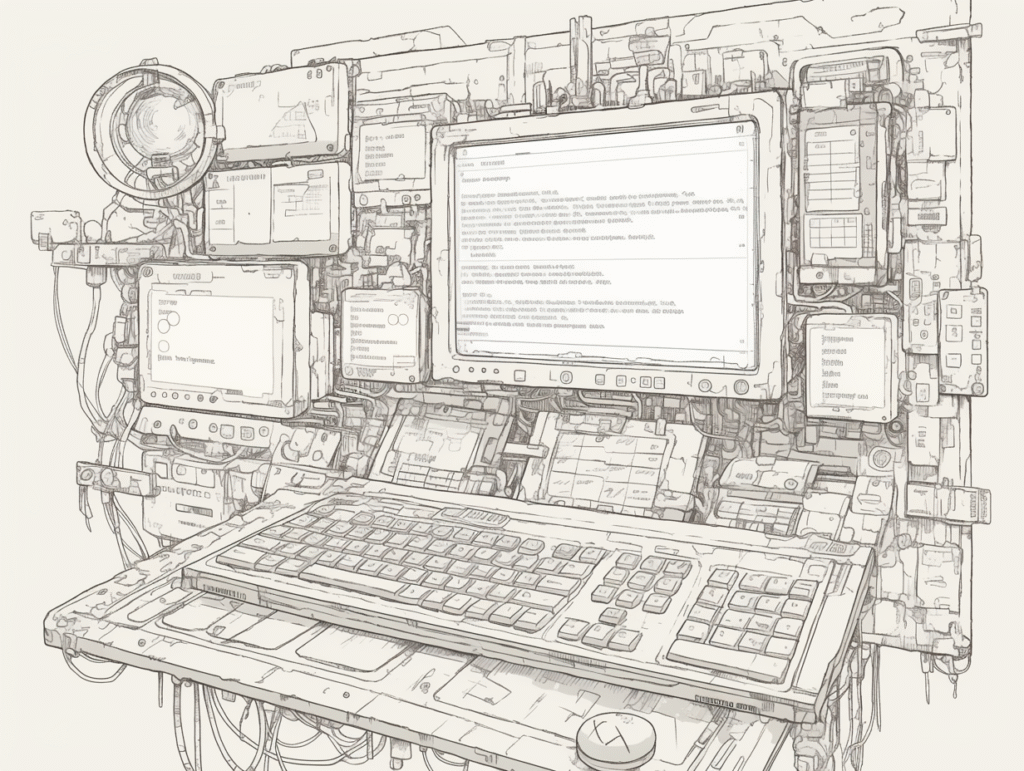
エラー情報を取得する便利なコマンド
echo %ERRORLEVEL%:直前のコマンドの戻り値確認(0は成功、1以上はエラー)pause:バッチファイルの終了を一時停止(エラーを見逃さない)timeout /t 5:数秒待つ(ログ確認の余裕を持たせる)findstr "エラー" error.log:ログファイルからエラーを含む行を検索
エラーメッセージを読みやすくする方法
find /c /v "" ファイル名:ファイルの行数をカウント(長いログの把握に便利)more < error.log:長いログファイルを1画面ずつ表示type error.log | findstr /i "エラー 失敗 警告":重要なキーワードだけを抽出
補足:エラー内容が意味不明なときは?
日本語のエラーメッセージはあいまいな場合も多いです。英語表示にすると検索性が上がることもあります:
chcp 437※元に戻すには:
chcp 932英語のエラーメッセージはインターネットでの検索結果が豊富で、解決策を見つけやすくなる利点があります。
よくあるエラーと対処法
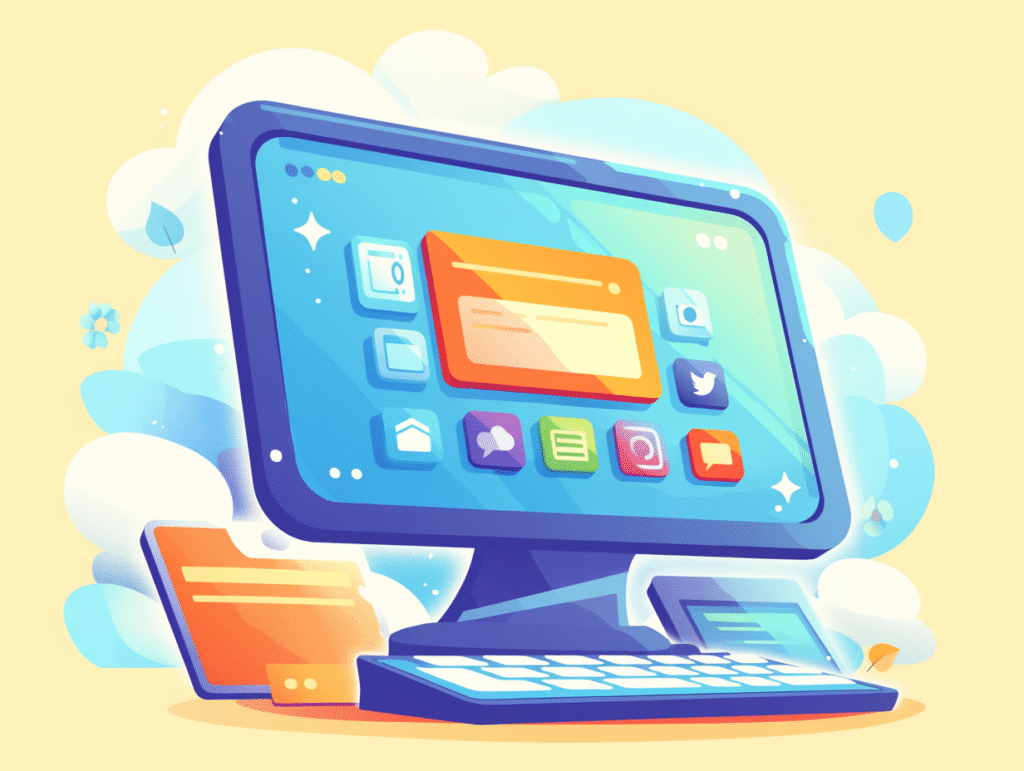
「アクセスが拒否されました」
- 原因:権限不足
- 対処:コマンドプロンプトを「管理者として実行」する
「ファイルが見つかりません」
- 原因:パスが間違っているか、ファイルが存在しない
- 対処:
dirコマンドでファイルの存在を確認、絶対パスで指定する
「システムは指定されたデバイスを認識できません」
- 原因:存在しないドライブやデバイスへのアクセス
- 対処:
wmic logicaldisk get nameでドライブ一覧を確認
まとめ
Windowsのコマンドプロンプトでのエラーログ確認は、初心者にとってはやや敷居が高く感じられるかもしれません。
しかし、標準出力とエラー出力の違いを理解し、適切にログを保存・表示するテクニックを覚えれば、トラブル対応力は格段に上がります。
覚えておきたいコマンド
| 目的 | コマンド |
|---|---|
| 標準出力をファイルに保存 | command > output.log |
| エラー出力をファイルに保存 | command 2> error.log |
| 両方をまとめて保存 | command > all.log 2>&1 |
| ファイルに追加で保存 | command >> log.txt 2>&1 |
| エラーコードの確認 | echo %ERRORLEVEL% |
「何が起きているのか分からない」状態を脱するために、今回紹介したコマンドをぜひ実践してみてください。問題の原因を特定し、解決への第一歩を踏み出しましょう。
エラーを見つけて対処することは、コマンドプロンプトを使いこなす上での重要なスキルです。繰り返し練習して、トラブルにも慌てず対応できるようになりましょう!