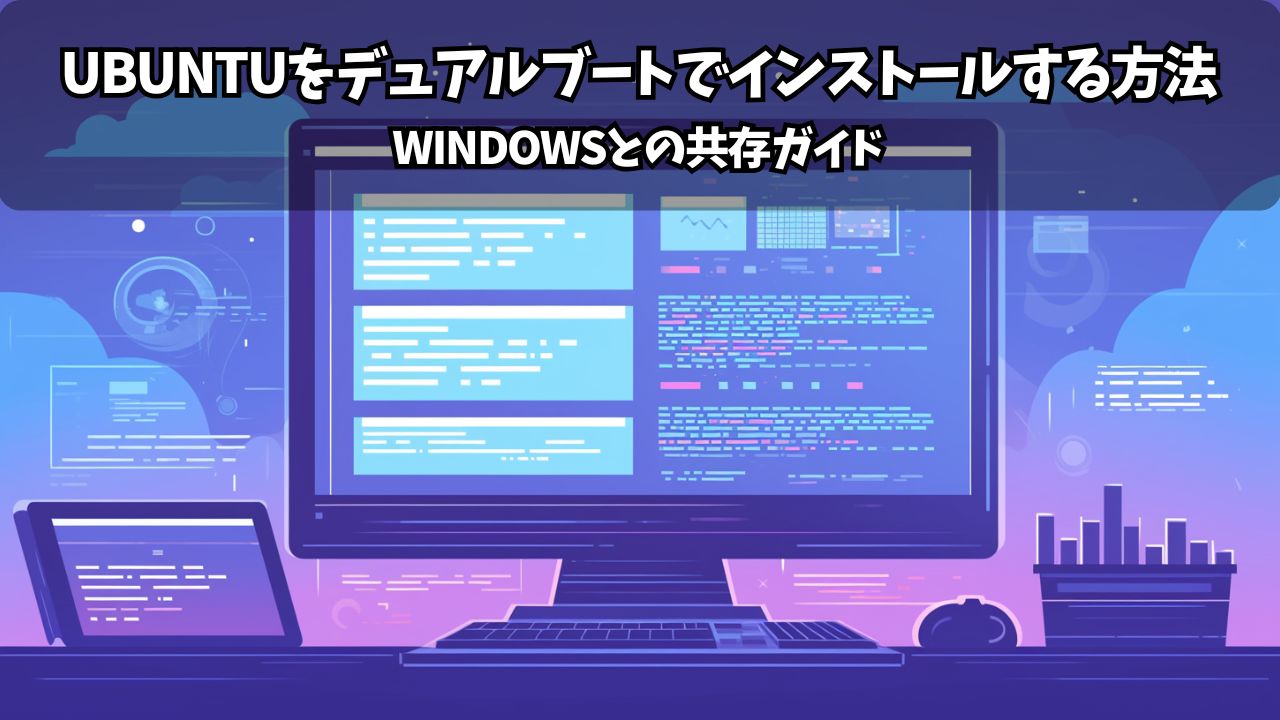「Ubuntuを使ってみたいけど、Windowsも残したい」
そんなあなたにおすすめなのが「デュアルブート」という方法です。
デュアルブートとは何か デュアルブートとは、ひとつのパソコンに2つのオペレーティングシステム(OS)をインストールして、起動するときにどちらを使うか選べるようにする設定のことです。
今回はWindowsとUbuntuを共存させる方法を学びます。
この記事で学べること
- デュアルブートの基本的な仕組み
- UbuntuをWindowsと一緒にインストールする具体的な手順
- よくあるトラブルと解決方法
- 安全にインストールするための注意点
LinuxディストリビューションのなかでもUbuntuは初心者にやさしく、オープンソースソフトウェアの入門としても最適です。
この記事では、パーティション管理やブートローダーの設定も含めて、段階的に説明していきます。
事前準備:必要なものとバックアップ
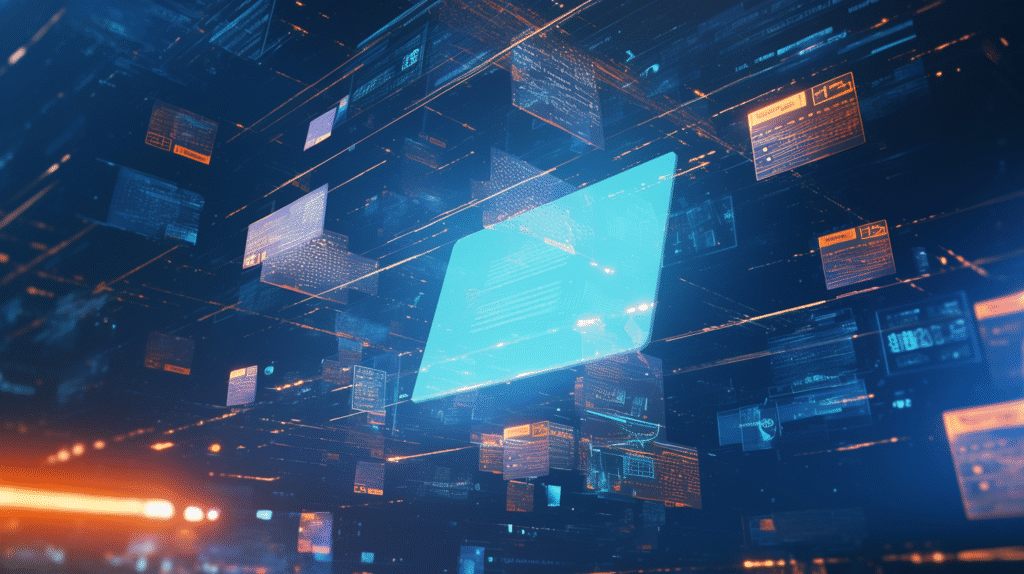
必要なものをそろえよう
ハードウェア要件
- 空き容量が20GB以上あるWindowsパソコン
- 8GB以上の容量があるUSBメモリ
- インターネット接続環境
ソフトウェア
- UbuntuのISOファイル(Ubuntu公式サイトから無料でダウンロード)
- USB起動ディスク作成ツール(RufusやbalenaEtcherなど)
ISOファイルって何? ISOファイルとは、CDやDVDの中身をまるごとひとつのファイルにまとめたものです。Ubuntuの場合、OSのすべてのファイルが含まれています。
データのバックアップは必須
なぜバックアップが必要か デュアルブートのインストール中に、何らかの理由でWindowsのデータが消えてしまう可能性があります。大切なファイルや写真、ドキュメントは必ず別の場所に保存しておきましょう。
バックアップの方法例
- 外付けハードディスクやUSBメモリにコピー
- クラウドストレージ(Google Drive、OneDriveなど)にアップロード
- Windows標準のバックアップ機能を使用
ステップ1:UbuntuのインストールUSBを作成
ISOファイルのダウンロード
手順の説明
- Ubuntu公式サイト(ubuntu.com)にアクセス
- 「Download」ページで最新のLTS版をダウンロード
- ファイルサイズは約3GB程度なので、ダウンロードには時間がかかります
LTS版とは LTS(Long Term Support)は長期サポート版という意味です。5年間アップデートが提供されるため、安定して使いたい人におすすめです。
起動可能なUSBディスクの作成
Rufusを使った作成手順
- Rufus公式サイトからソフトウェアをダウンロード・インストール
- USBメモリをパソコンに接続
- Rufusを起動し、「デバイス」でUSBメモリを選択
- 「ブートの種類」で先ほどダウンロードしたUbuntuのISOファイルを選択
- 「スタート」ボタンをクリックして書き込み開始
重要な注意点 USBメモリの中身はすべて消去されます。大切なデータが入っている場合は、事前に別の場所にコピーしておきましょう。
ステップ2:Windowsのディスクを縮小して空き領域を確保
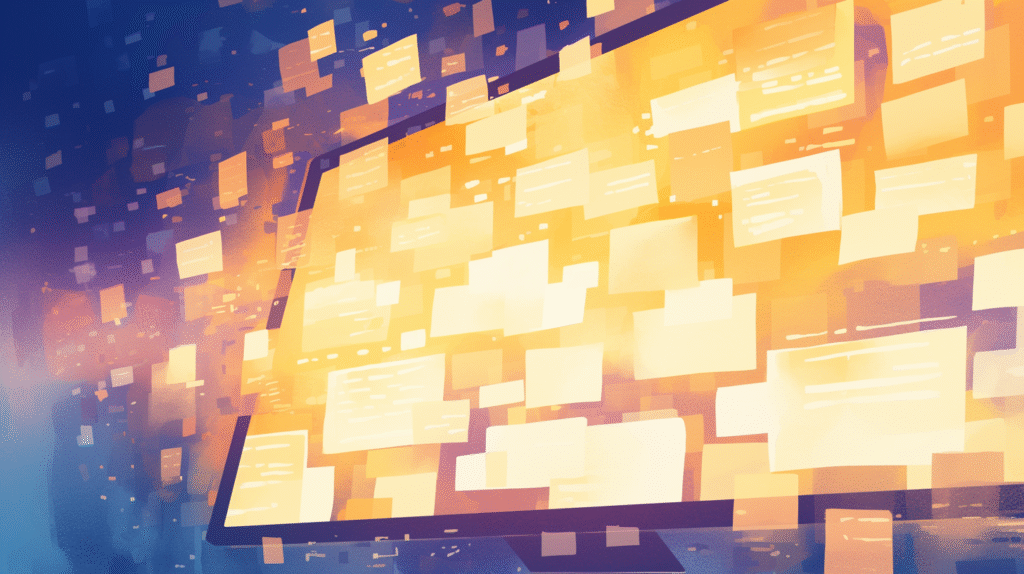
ディスクの管理ツールを使おう
パーティション操作の基本
パーティションとは、ひとつのハードディスクを複数の区画に分ける技術です。WindowsとUbuntuがそれぞれ別の区画を使うことで、互いに干渉せずに動作できます。
ディスク縮小の手順
- Windowsキー + Xを押して「ディスクの管理」を選択
- Cドライブ(通常はメインのパーティション)を右クリック
- 「ボリュームの縮小」をクリック
- 縮小サイズを入力(最低20GB、推奨50GB以上)
- 「縮小」ボタンをクリックして実行
どのくらいの容量が必要?
- Ubuntu本体:約6GB
- ソフトウェアやファイル用:14GB以上
- 快適に使うなら:50GB以上がおすすめ
ステップ3:Ubuntuのインストールとシステム設定
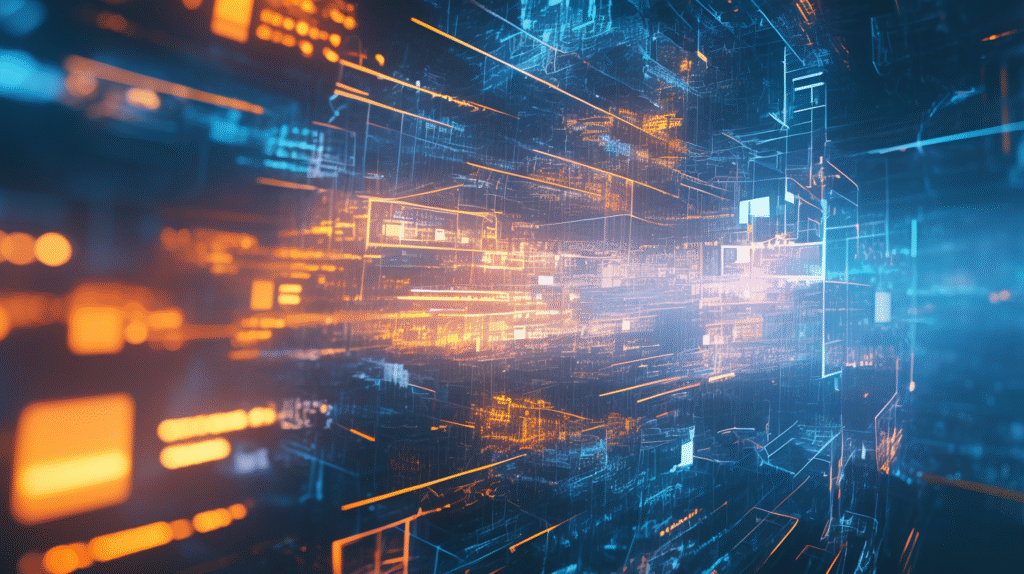
USBから起動してインストーラーを開始
BIOS/UEFI設定での起動順序変更
- パソコンの電源を入れてすぐにF12キー(機種により異なる)を連打
- ブートメニューが表示されたらUSBメモリを選択
- Ubuntuのライブ環境が起動します
ライブ環境とは ハードディスクにインストールしなくても、USBから直接Ubuntuを体験できる機能です。この状態でUbuntuの使い心地を確認できます。
インストールタイプの選択が重要
推奨設定の説明
- デスクトップに表示される「Ubuntuをインストール」アイコンをダブルクリック
- 言語とキーボード配列を選択(日本語・日本語キーボード)
- インストールタイプで「WindowsBootManagerと一緒にUbuntuをインストール」を選択
手動パーティション設定(上級者向け) より詳細な制御が必要な場合は「それ以外」を選択し、以下のパーティションを作成します:
/(ルートパーティション):ext4ファイルシステム、20GB以上swap:スワップ領域、RAM容量と同じサイズ/home(オプション):ユーザーデータ用、残り容量
ファイルシステムの違い
- NTFS:Windows標準のファイルシステム
- ext4:Linux標準のファイルシステム、Ubuntuで使用
- swap:仮想メモリ用の特殊な領域
ユーザー情報とロケール設定
設定すべき項目
- ユーザー名とパスワード(英数字で設定推奨)
- コンピューター名(ネットワーク上での識別用)
- タイムゾーン(Asia/Tokyo)
- 自動ログインの有無
インストールには15~30分程度かかります。完了まで電源を切らずに待ちましょう。
ステップ4:起動テストとブートローダーの確認
GRUBブートローダーの動作確認
正常な起動シーケンス インストール完了後の再起動時に、GRUBという画面が表示されます。ここで以下の選択肢が現れます:
- Ubuntu(最新カーネル)
- Ubuntu(リカバリモード)
- Windows Boot Manager
- システム設定
デフォルト設定の理解 何も選択しないと10秒後に自動的にUbuntuが起動します。この設定は後から変更可能です。
両方のOSが正常に動作するかテスト
確認すべきポイント
- Ubuntuからの起動テスト:ネットワーク接続、音声、グラフィック
- Windowsからの起動テスト:以前と同様に動作するか確認
- OSの切り替えテスト:再起動してGRUBから別のOSを選択
注意点とセキュリティ設定
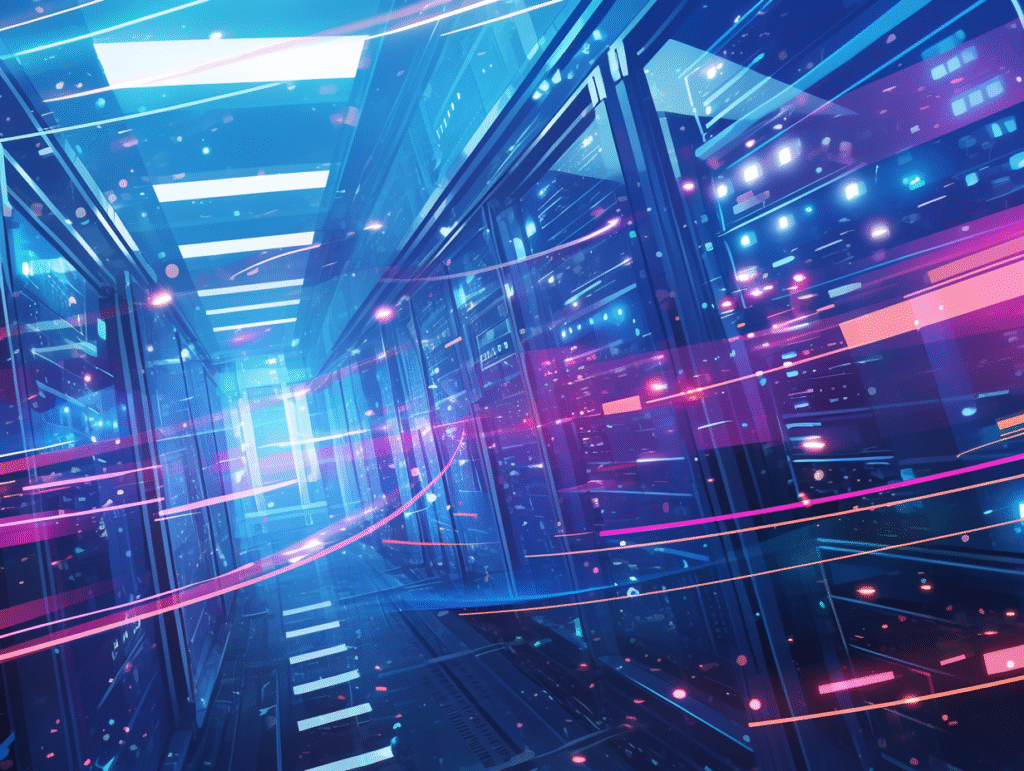
UEFIとセキュアブート
セキュアブートとは 不正なソフトウェアの起動を防ぐセキュリティ機能です。Ubuntuをインストールする際、この機能が邪魔をすることがあります。
設定変更が必要な場合
- UEFI設定画面でセキュアブートを一時的に無効化
- Ubuntuインストール後、必要に応じて再度有効化
- 最新のUbuntuはセキュアブートに対応しているため、通常は問題ありません
ファストスタートアップの無効化
Windowsの設定変更 Windowsの「ファストスタートアップ」機能が有効だと、デュアルブートで問題が生じることがあります。
無効化手順
- コントロールパネル → 電源オプション
- 「電源ボタンの動作の選択」をクリック
- 「現在利用できない設定を変更します」をクリック
- 「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す
トラブル対策と解決方法
よくある問題と対処法
GRUBが表示されない場合
- 原因:UEFI設定でWindowsが優先されている
- 解決法:UEFI設定でubuntuを起動優先順位の最上位に設定
Windowsが正常に起動しない場合
- 原因:ブートローダーの設定ミス
- 解決法:Windows回復ディスクを使用して修復
Ubuntu起動時にフリーズする場合
- 原因:グラフィックドライバーの不具合
- 解決法:GRUBメニューで「セーフグラフィックスモード」を選択
復旧用ツールの準備
Windows回復ディスクの作成 デュアルブート設定前に、Windowsの回復ディスクを作成しておくことを強く推奨します。
作成手順
- コントロールパネル → 回復 → 回復ドライブの作成
- 別のUSBメモリ(8GB以上)を用意
- システムファイルのバックアップも含めて作成
パフォーマンス最適化とカスタマイズ
起動時間の短縮
GRUBタイムアウトの調整 デフォルトの10秒待機を短縮して、素早く起動できるように設定変更が可能です。
設定変更方法
- Ubuntuでターミナルを開く
sudo nano /etc/default/grubコマンドを実行GRUB_TIMEOUT=10をGRUB_TIMEOUT=3に変更sudo update-grubコマンドで設定を反映
ストレージ最適化
ディスク使用量の監視 デュアルブート環境では、それぞれのOSが使用するディスク容量を定期的にチェックしましょう。
Ubuntuでの確認方法
- コマンド:
df -hでディスク使用量を表示 - GUI:「ディスク使用量アナライザー」アプリを使用
まとめ
デュアルブートのメリット
得られる利点
- Windowsの使い慣れた環境を維持
- Ubuntuでオープンソースソフトウェア開発を体験
- リナックスコマンドラインやシェルスクリプトの学習機会
- プログラミング環境の多様性
安全な運用のポイント
継続的な注意点
- 定期的なシステムアップデート(両OS)
- データのバックアップ習慣
- パーティション容量の監視
- セキュリティソフトウェアの導入