会社のパソコンで朝ログインすると、その日1日、様々なサービスが使えますよね。
ファイルサーバー、メールシステム、社内のWebサイト…。どれを使う時も、いちいちパスワードを入力する必要はありません。これって、すごく便利だと思いませんか?
この「一度ログインすれば、色々なサービスが自由に使える仕組み」の中心にあるのが、TGS(Ticket Granting Service:チケット発行サービス)なんです。
「チケットって何?」「どうやって発行されるの?」「セキュリティは大丈夫なの?」
この記事では、そんな疑問に答えながら、TGSについて初心者の方にもわかりやすく解説します。企業ネットワークのセキュリティを理解したい方に、ぴったりの内容です。
前回のAS(認証サービス)の記事と合わせて読めば、さらに理解が深まりますよ!
TGS(Ticket Granting Service)とは?
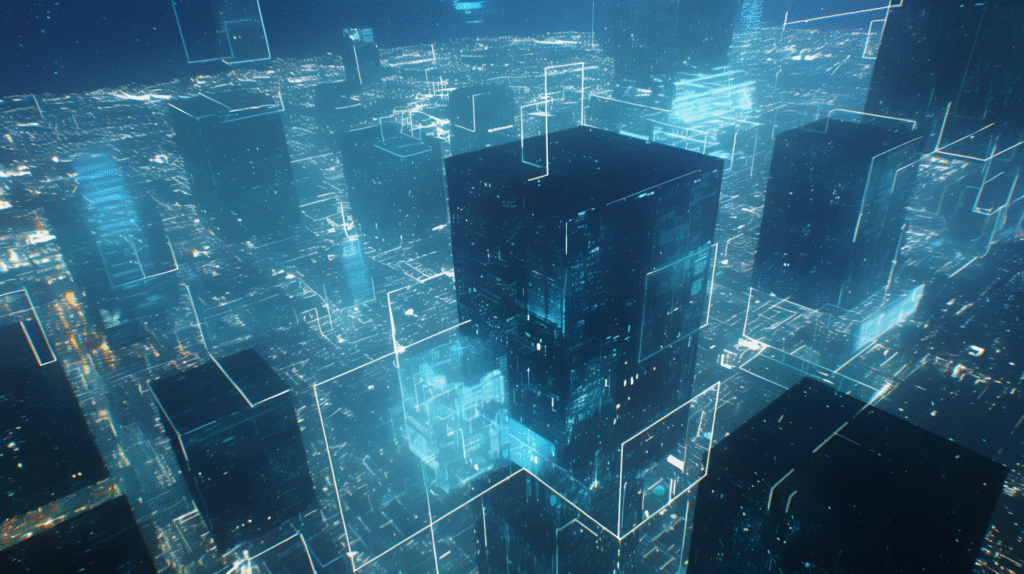
まず、TGSの基本から説明しましょう。
TGSの正式名称と意味
TGSは「Ticket Granting Service(チケット・グランティング・サービス)」の略です。
日本語では「チケット発行サービス」と呼ばれます。
ネットワーク上で、各サービスを使うための「許可証(チケット)」を発行する役割を担っています。
TGSの役割
TGSの主な仕事は、次の通りです。
- ユーザーが特定のサービス(ファイルサーバーなど)を使いたい時に要求を受け取る
- ユーザーの身元を確認する(TGTという引換券をチェック)
- 問題なければ、そのサービス専用の「サービスチケット」を発行する
- ユーザーはそのチケットを使って、サービスにアクセスできる
簡単にいえば、TGSは各サービスへの入場券を販売する窓口のようなものです。
Kerberosの中のTGS
TGSは、Kerberos(ケルベロス)認証システムの一部として動いています。
Kerberosには、主に3つの重要な要素があります。
- AS(Authentication Service):最初にログインを確認する入り口
- TGS(Ticket Granting Service):各サービスへのチケットを発行する窓口 ← 今回のテーマ
- Application Server:実際のサービス(ファイルサーバー、プリンターなど)
この3つが連携して、安全で便利なネットワーク環境を作っているんですね。
ASとTGSの違いと連携
TGSを理解するには、AS(認証サービス)との違いを知ることが大切です。
ASとTGSの役割分担
AS(Authentication Service)の役割
- タイミング:ログインする時(1日に1回)
- 確認するもの:ユーザー名とパスワード
- 発行するもの:TGT(Ticket Granting Ticket:チケット発行チケット)
- 例え:遊園地の「入場ゲート」
TGS(Ticket Granting Service)の役割
- タイミング:新しいサービスを使う時(何度でも)
- 確認するもの:TGT(ASが発行した引換券)
- 発行するもの:サービスチケット(各サービス専用の許可証)
- 例え:遊園地の「チケット販売機」
2段階認証の仕組み
なぜASとTGSに分かれているのでしょうか?
実は、これには重要な理由があります。
セキュリティの向上
パスワードを使った認証(AS)は、最初の1回だけ。
その後は、TGTという「引換券」を使ってチケットをもらう仕組みです。
つまり、パスワードをネットワークに何度も流さなくて済むんです。
効率性の向上
ASは全ユーザーの認証を担当するので、負荷が高いです。
サービスごとのチケット発行をTGSに任せることで、役割分担して効率化できます。
連携の流れ
ASとTGSの連携を、簡単に整理しましょう。
- ユーザーがログイン → ASが認証 → TGTを発行
- ユーザーがファイルサーバーを使いたい → TGSに依頼 → サービスチケットを発行
- サービスチケットを持ってファイルサーバーにアクセス → 使える!
ASは入り口、TGSは案内所、というイメージですね。
TGSの動作プロセス:詳細解説
それでは、TGSが実際にどう動いているのか、ステップごとに見ていきましょう。
前提条件
ユーザーは既にASで認証を済ませて、TGT(Ticket Granting Ticket)を持っています。
このTGTは、「TGSを使う権利」を証明するものです。
サービスチケット取得の流れ:4つのステップ
ステップ1:サービスへのアクセス要求
ユーザーが「ファイルサーバーを使いたい」と思った時、パソコンが自動的にTGSに連絡します。
この時、以下の情報を送ります:
- TGT(ASからもらった引換券)
- Authenticator(本人証明のための暗号化されたタイムスタンプ)
- 使いたいサービスの名前(例:ファイルサーバーA)
ステップ2:TGSがTGTを検証する
TGSは、受け取ったTGTが本物かどうかチェックします。
- TGTは暗号化されているので、正しい鍵でないと読めない
- 有効期限が切れていないか確認
- Authenticatorのタイムスタンプが新しいか確認(リプレイ攻撃の防止)
すべて問題なければ、次のステップに進みます。
ステップ3:サービスチケットの作成
TGSは、要求されたサービス専用の「サービスチケット」を作ります。
サービスチケットには、次の情報が含まれます:
- ユーザーの名前
- サービスの名前
- セッション鍵(一時的な暗号化鍵)
- 有効期限(通常5〜10時間)
- アクセス権限の情報
これらを、サービスの秘密鍵で暗号化します。
つまり、そのサービスだけが読める形式になるんですね。
ステップ4:チケットをユーザーに返す
TGSは、次の2つをユーザーに返します:
- サービスチケット(サービスの秘密鍵で暗号化されている)
- セッション鍵(ユーザーの鍵で暗号化されている)
ユーザーは、これらを持ってサービスにアクセスします。
サービスチケットを提示すれば、パスワードなしでサービスが使えるんです!
チケットの使い方
取得したサービスチケットは、こう使われます。
サービスにアクセスする時
- ユーザーがサービスチケットをサービスに提示する
- サービスは自分の秘密鍵でチケットを復号化(解読)
- チケットが有効なら、アクセスを許可する
- セッション鍵を使って、安全に通信する
これで、ファイルを開いたり、プリンターを使ったりできるわけです。
サービスチケットの仕組み
TGSが発行する「サービスチケット」について、もう少し詳しく見てみましょう。
サービスチケットとは?
サービスチケットは、特定のサービスを使う許可証です。
ファイルサーバー用、プリンター用、メールサーバー用…と、サービスごとに別々のチケットが必要です。
なぜサービスごとにチケットが必要?
セキュリティのためです。
もし1枚のチケットですべてのサービスが使えたら、チケットが盗まれた時に被害が大きくなります。
サービスごとに分けることで、被害を最小限に抑えられるんですね。
サービスチケットの構造
サービスチケットには、様々な情報が詰まっています。
基本情報
- ユーザーID:誰のチケットか
- サービスID:どのサービス用か
- 発行時刻:いつ発行されたか
- 有効期限:いつまで使えるか
セキュリティ情報
- セッション鍵:ユーザーとサービスの間で使う一時的な暗号化鍵
- IPアドレス(オプション):どのパソコンから接続するか
- 権限情報:読み取り専用か、書き込みもできるか
これらすべてが暗号化されて保存されています。
チケットの有効期限
サービスチケットには、必ず有効期限があります。
一般的な期限
- TGT:8〜10時間(1日分)
- サービスチケット:5〜10時間
なぜ期限があるのでしょうか?
理由1:セキュリティリスクの軽減
もしチケットが盗まれても、期限切れになれば使えなくなります。
無期限だと、盗まれた時の被害が甚大です。
理由2:定期的な再認証
毎日ログインし直すことで、不正利用を早期に発見できます。
退職した社員のアカウントが、いつまでも使われることを防げるんですね。
チケットの更新(リニューアル)
期限が切れたら、新しいチケットをもらう必要があります。
TGTの更新
TGTが期限切れになったら、再度ASで認証(パスワード入力)が必要です。
通常、朝ログインして夕方まで使えるように設定されています。
サービスチケットの更新
サービスチケットが期限切れになっても、TGTがあれば自動的に再取得できます。
ユーザーは何もする必要がありません。便利ですね!
TGSのセキュリティ機能
TGSには、様々なセキュリティ対策が組み込まれています。
対策1:暗号化
TGSとクライアントの通信は、すべて暗号化されています。
使われる暗号化技術
- AES(Advanced Encryption Standard):現在の標準
- 鍵長:128bit以上(256bitが推奨)
- 対称鍵暗号:同じ鍵で暗号化と復号化を行う
これにより、通信を盗聴されてもチケットの中身は読めません。
対策2:タイムスタンプによる保護
TGSは、各要求に含まれるタイムスタンプを厳密にチェックします。
リプレイ攻撃の防止
リプレイ攻撃とは、過去の通信を記録して、後から再送する攻撃手法です。
タイムスタンプを確認することで、「古いデータの使い回し」を検出できます。
時刻の同期
Kerberosでは、すべてのマシンの時刻が同期している必要があります。
5分以上ずれていると、認証が失敗するんです。
厳しいように思えますが、これが重要なセキュリティ機能なんですね。
対策3:相互認証
TGSの仕組みでは、双方向の認証が行われます。
ユーザー → サービスの認証
ユーザーがサービスチケットを提示して、「私は正規ユーザーです」と証明します。
サービス → ユーザーの認証
サービス側も、「私は本物のサービスです」とユーザーに証明します。
これにより、偽のサーバーへのアクセスを防げるんです。
対策4:権限の細かい制御
サービスチケットには、アクセス権限の情報が含まれます。
権限の種類
- 読み取り専用:ファイルを見るだけ
- 書き込み可:ファイルの作成・編集ができる
- 削除可:ファイルを削除できる
- 管理者権限:設定変更などもできる
ユーザーごとに適切な権限だけを与えることで、セキュリティを高めています。
対策5:チケットのキャッシュ管理
取得したチケットは、クライアントのメモリに一時保存されます。
キャッシュのセキュリティ
- メモリ上でも暗号化されている
- ログアウトすると自動的に削除される
- 他のユーザーからはアクセスできない
これにより、共有パソコンでも安全に使えます。
TGSが使われる実際の場面

TGSは、どんな場面で活躍しているのでしょうか。
場面1:ファイルサーバーへのアクセス
一番よく使われるのが、ファイル共有です。
流れ
- 朝、パソコンにログイン(AS認証) → TGTをもらう
- 共有フォルダを開こうとする → TGSにサービスチケットを要求
- サービスチケットをもらう
- ファイルサーバーにアクセス → ファイルが開ける
この一連の流れが、裏側で自動的に行われています。
ユーザーは何も意識する必要がありません。
場面2:プリンターの使用
ネットワークプリンターを使う時も、TGSが動いています。
プリント処理の流れ
- 「印刷」ボタンを押す
- TGSにプリンター用のサービスチケットを要求
- チケットをもらってプリントサーバーに接続
- 印刷ジョブを送信
プリンターごとに別のチケットが必要なので、セキュリティも守られます。
場面3:メールシステム
社内のメールシステム(Exchange Serverなど)でも、TGSが活躍します。
メールアクセスの流れ
- Outlookなどのメールソフトを起動
- TGSにメールサーバー用のチケットを要求
- チケットを使ってメールサーバーに接続
- メールの送受信ができる
パスワード入力は不要です。
場面4:Webアプリケーション
社内のWebシステムでも、Kerberos認証が使われることがあります。
Webアクセスの例
- 勤怠管理システム
- 経費精算システム
- 社内ポータルサイト
ブラウザがTGSからチケットを取得して、Webサーバーに提示します。
シングルサインオン(SSO)が実現できるんです。
場面5:データベースへのアクセス
業務アプリケーションがデータベースにアクセスする時も、TGSが使われます。
データベース認証の流れ
- アプリケーションがデータベースにクエリを送りたい
- TGSにデータベース用のチケットを要求
- チケットを使ってデータベースサーバーに接続
- データの読み書きができる
アプリケーションごとにパスワードを埋め込む必要がないので、セキュリティが向上します。
TGSのトラブルシューティング
TGSがうまく動かない時の対処法を紹介します。
問題1:「チケットを取得できません」というエラー
原因
- TGTの有効期限が切れている
- TGSサーバーにアクセスできない
- ネットワーク接続の問題
対処法
- ログアウトして再ログインする
- TGTを新しく取得し直す
- 多くの場合、これで解決します
- ネットワーク接続を確認する
- Wi-Fiやケーブルが繋がっているか
- 社内ネットワークに接続できているか
- TGSサーバーの状態を確認する
- IT部門に問い合わせる
- サーバーがメンテナンス中でないか確認
問題2:特定のサービスだけアクセスできない
原因
- そのサービスへのアクセス権限がない
- サービスチケットの有効期限が切れた
- サービス側の問題
対処法
- 権限を確認する
- 管理者に「このサービスを使う権限がありますか?」と確認
- 必要なら権限を付与してもらう
- サービスを使い直す
- 一度サービスを閉じて、もう一度開く
- 新しいサービスチケットが自動取得される
- サービスの状態を確認する
- サービス自体が停止していないか
- 他の人も使えないなら、サーバー側の問題
問題3:時刻のエラーが出る
原因
Kerberosは時刻のズレに厳しいシステムです。
クライアントとTGSの時計が5分以上ずれていると、認証が失敗します。
対処法
- パソコンの時刻設定を確認する
- 右下の時計を確認
- 明らかにずれていたら修正
- 自動時刻同期をオンにする
- Windows:設定 → 時刻と言語 → 「時刻を自動的に設定する」をオン
- macOS:システム設定 → 日付と時刻 → 「日付と時刻を自動的に設定」をオン
- タイムサーバーと同期する
- 企業ネットワークには、通常タイムサーバーがあります
- IT部門に設定を確認してもらう
問題4:チケットのキャッシュが壊れた
原因
チケットを保存するキャッシュが、何らかの理由で壊れることがあります。
対処法
- ログアウトして再ログインする
- キャッシュがクリアされる
- 新しいチケットが取得される
- キャッシュを手動でクリアする
- Windows:
klist purgeコマンドを実行 - 管理者権限が必要な場合があります
- パソコンを再起動する
- メモリ上のキャッシュが完全にクリアされる
問題5:TGSサーバーが応答しない
原因
- サーバーの障害
- ネットワークの問題
- ファイアウォールのブロック
対処法
これは個人では解決できません。
すぐにIT部門に連絡してください。
TGSが動かないと、ネットワーク全体が使えなくなる可能性があります。
よくある質問
Q1:TGTとサービスチケットの違いは?
TGT(Ticket Granting Ticket)
- ASが発行する「引換券」
- TGSを使うための許可証
- 1日に1枚だけもらう
- すべてのサービスチケットを取得できる
サービスチケット
- TGSが発行する「許可証」
- 特定のサービスを使うためのチケット
- サービスごとに必要
- 必要な分だけ何枚でももらえる
例えるなら、TGTは「遊園地の入場パス」、サービスチケットは「各アトラクションの乗車券」です。
Q2:サービスチケットは何枚まで持てる?
制限はありません。
必要な数だけ、いくらでも取得できます。
ファイルサーバー3台、プリンター2台、メールサーバー1台…なら、合計6枚のサービスチケットを持つことになります。
すべて自動的に管理されるので、ユーザーは気にする必要がありません。
Q3:TGSはどこにある?
企業内のサーバー上で動いています。
通常、Active Directory(Windows Serverの機能)の一部として稼働しています。
物理的には、サーバールームやデータセンターにあるサーバーマシンですね。
冗長化のため、複数台のTGSサーバーが用意されていることも多いです。
Q4:TGSの処理は遅くない?
ほとんど気にならない速度です。
サービスチケットの取得は、通常1秒以内に完了します。
しかも、一度取得したチケットは有効期限まで使い回せるので、毎回取得する必要もありません。
ネットワークが遅い場合は、多少時間がかかることもありますが、日常的には問題ないレベルです。
Q5:TGSはクラウドでも使える?
使えます。
最近では、クラウド上でKerberos(TGSを含む)を提供するサービスもあります。
- Azure Active Directory:マイクロソフトのクラウド認証サービス
- Google Cloud Identity:グーグルのクラウド認証サービス
オンプレミス(自社サーバー)とクラウドを組み合わせた「ハイブリッド環境」も増えています。
Q6:TGSが停止したらどうなる?
新しいサービスチケットが取得できなくなります。
ただし、既に持っているチケットは有効期限まで使えます。
つまり:
- すでに開いているファイルは使い続けられる
- 新しいファイルやサービスにはアクセスできなくなる
企業では、TGSの冗長化(複数台用意)により、1台が故障しても他が代わりに動く仕組みを作っています。
まとめ
TGS(Ticket Granting Service:チケット発行サービス)は、Kerberos認証システムの中核を担う重要なコンポーネントです。
一度ログインすれば複数のサービスが自由に使える便利さと、高いセキュリティを両立させています。
この記事のポイント
✓ TGSは各サービスへのアクセスチケットを発行する
✓ ASが入り口、TGSがチケット販売窓口という役割分担
✓ サービスごとに別々のチケットが必要(セキュリティのため)
✓ チケットには有効期限があり、定期的に更新される
✓ 暗号化、タイムスタンプ、相互認証などで安全性を確保
✓ ファイルサーバー、プリンター、メール、Webアプリなど幅広く使われる
✓ ユーザーは意識せず、裏側で自動的に動いている
✓ トラブル時は再ログインで解決することが多い
普段は意識しない裏側の仕組みですが、TGSがあるおかげで、私たちは便利にネットワークを使えています。
会社でファイルを開く時、プリンターで印刷する時、「今、TGSがチケットを発行してくれているんだな」と思い出してみてください。
AS(認証サービス)の記事と合わせて読めば、Kerberos認証システム全体の理解がさらに深まりますよ。
安全で快適なネットワーク環境を支える技術、それがTGSなんです!







