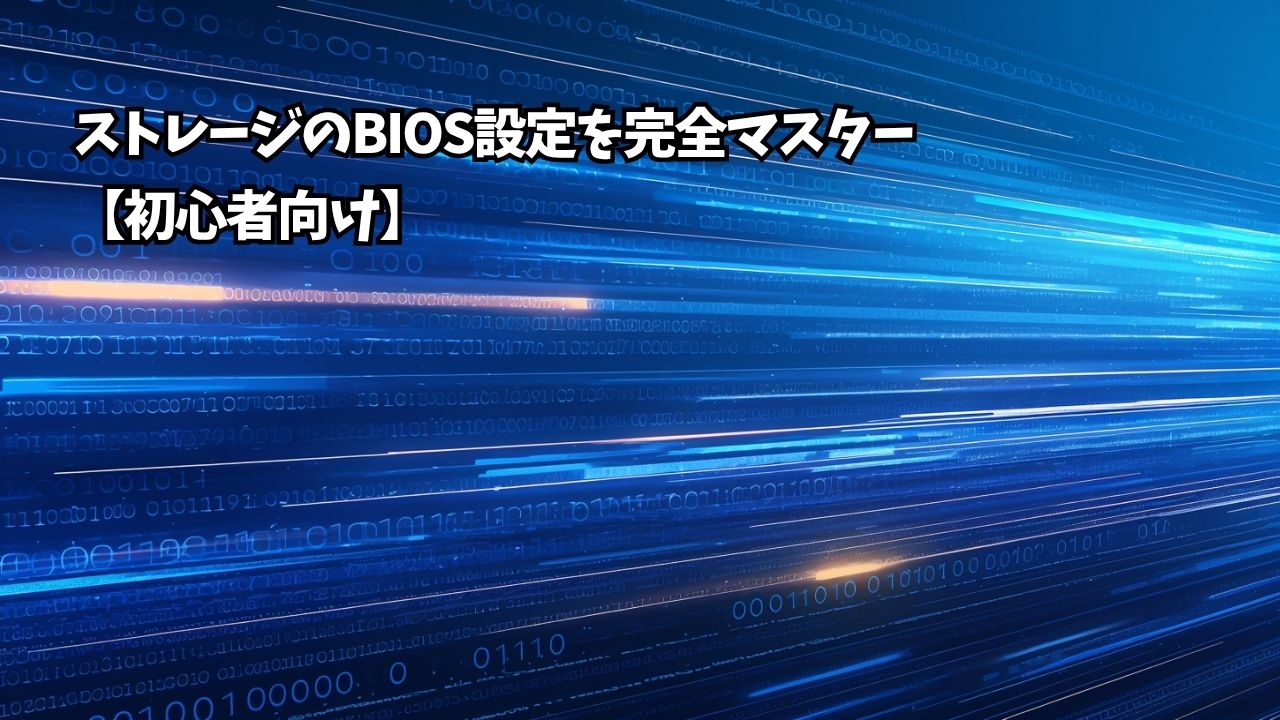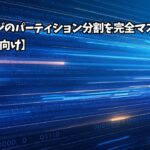パソコンに新しいSSDやハードディスクを追加したとき、Windowsが起動しなくなったり、ドライブが表示されなかったり。
「ちゃんと接続したのに、なぜ?」と困った経験、ありませんか?
実は、ストレージを正しく使うには「BIOS」という場所での設定が必要なんです。
この記事では、BIOSでのストレージ設定について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
パソコンが起動する前の「黒い画面」で何をすればいいのか、一緒に見ていきましょう。
BIOSとは何か

パソコンの司令塔
BIOS(バイオス)は、パソコンの電源を入れた直後に起動する、最も基本的なプログラムです。
正式名称は「Basic Input/Output System(基本入出力システム)」。
役割
- ハードウェアの初期化
- 起動デバイスの選択
- ハードウェア設定の保存
- OSへの橋渡し
Windowsが起動する前に、すべてのハードウェアをチェックしているんです。
UEFIとの違い
最近のパソコンは、従来のBIOSではなく「UEFI」を使っています。
UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)
- BIOSの後継規格
- より高速な起動
- マウス操作が可能
- 日本語表示に対応
- 2TB以上のディスクに対応
ただし、一般的には「BIOS」と呼ばれることが多いです。この記事でも「BIOS/UEFI」を「BIOS」と表記します。
なぜBIOS設定が必要?
ストレージを追加したり変更したりする場合、BIOSで以下のことを確認・設定する必要があります。
主な設定項目
- ストレージが正しく認識されているか
- どのドライブから起動するか
- ストレージの動作モード(AHCI/IDE/RAIDなど)
- セキュアブートの設定
これらの設定が間違っていると、パソコンが起動しなくなることもあるんです。
BIOSの起動方法
メーカー別の起動キー
パソコンの電源を入れた直後、特定のキーを押すとBIOSが起動します。
主要メーカーの起動キー
デスクトップPC
- 自作PC(ASRock):F2 または Delete
- 自作PC(ASUS):F2 または Delete
- 自作PC(MSI):Delete
- 自作PC(Gigabyte):Delete
- Dell:F2
- HP:F10 または Esc
ノートPC
- ASUS:F2
- Lenovo(ThinkPad):F1 または Enter
- Dell:F2
- HP:F10 または Esc
- Acer:F2
- Toshiba:F2
- Panasonic:F2
- NEC:F2
タイミング
電源ボタンを押した直後、メーカーロゴが表示されている間に、連打するのがコツです。
Windows 10/11から起動する方法
キーを押すタイミングが難しい場合、Windows から起動できます。
手順
- スタートメニューから「設定」を開く
- 「システム」→「回復」を選択
- 「今すぐ再起動」をクリック(PCの起動をカスタマイズ)
- トラブルシューティング → 詳細オプション → UEFIファームウェアの設定
- 「再起動」をクリック
自動的にBIOSが起動します。
起動できない場合
高速スタートアップが有効
Windows 10/11では、完全にシャットダウンされていないことがあります。
Shiftキーを押しながら「シャットダウン」を選ぶと、完全にシャットダウンできます。
ノートPCの場合
Fnキーと組み合わせが必要な場合があります。例:Fn + F2
ストレージ認識の確認
メイン画面での確認
BIOSを起動すると、最初の画面に接続されているストレージが表示されることが多いです。
表示例(ASUS UEFI BIOS)
SATA Port 1: Samsung SSD 860 EVO 500GB
SATA Port 2: WDC WD10EZEX-00BN5A0 1TB
SATA Port 3: Not Detected
M.2_1: WD Black SN850 1TBここに表示されていれば、物理的には認識されています。
詳細情報の確認
より詳しい情報を見る場合は、「Advanced」や「詳細設定」メニューに入ります。
確認できる情報
- ドライブのモデル名
- シリアル番号
- 容量
- ファームウェアバージョン
- 接続モード(SATA、NVMe、IDEなど)
ストレージが表示されない場合
確認ポイント
物理的な接続
- ケーブルがしっかり挿さっているか
- 電源ケーブルも接続されているか
- SATAポートが有効になっているか
BIOSの検出
一部のBIOSでは、手動でストレージを検出する機能があります。
「Auto Detect」や「ストレージの検出」などの項目を探してみましょう。
起動順序(Boot Order)の設定
起動順序とは
パソコンは、設定された順番でストレージをチェックして、最初に見つかった起動可能なOSを起動します。
デフォルトの順序(例)
- USBドライブ
- CD/DVDドライブ
- ハードディスク/SSD
- ネットワーク起動
設定方法
メニューの場所
- 「Boot」タブ
- 「起動」メニュー
- 「Boot Priority」
- 「Boot Order」
などの名称で見つかります。
変更手順
- Bootメニューを開く
- 起動させたいドライブを選択
- +/- キーや矢印キーで順番を変更
- 一番上に移動させる
- F10キーで保存して終了
複数のOSがある場合
Windows と Linux を両方インストールしている場合など、起動順序が重要になります。
推奨設定
- メインで使うOSのドライブを1番目に
- その他のドライブは2番目以降に
間違えて別のOSが起動してしまうのを防げます。
ブートモード(Legacy/UEFI)
起動方式にも設定があります。
Legacy(レガシー)モード
- 古い方式
- MBRパーティションを使用
- 2TB以下のディスクに対応
UEFI モード
- 新しい方式
- GPTパーティションを使用
- 2TB以上のディスクに対応
- 高速起動
重要
Windowsをインストールしたときのモードと、BIOSの設定を一致させる必要があります。
不一致だと起動しません。
SATA設定(AHCI/IDE/RAIDモード)
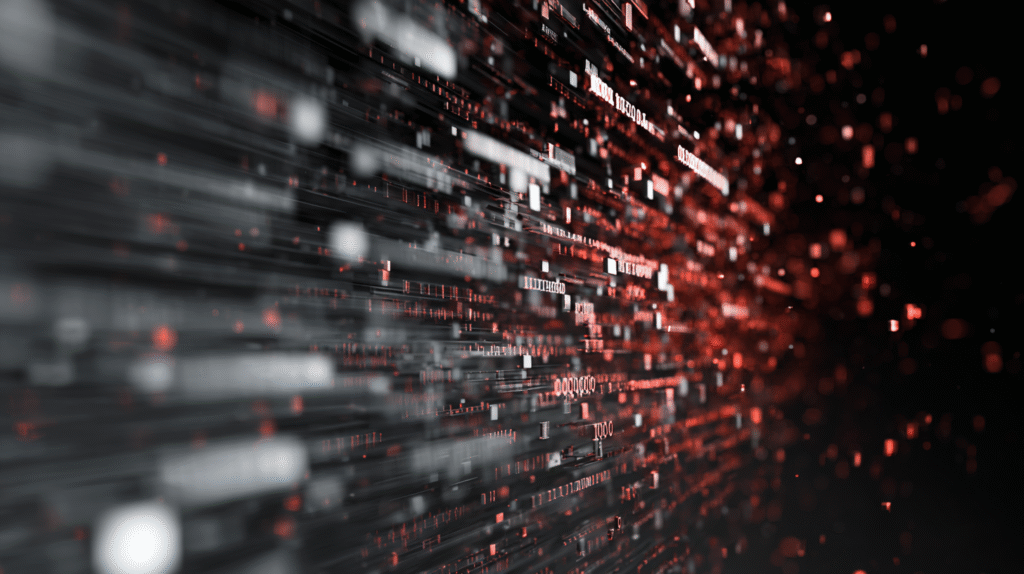
各モードの違い
SATAドライブの動作モードを選択できます。
IDE モード(互換モード)
- 古い方式
- 低速だが互換性が高い
- Windows XP以前のOSで必要
- 現在はほぼ使わない
AHCI モード(推奨)
- 標準的な高速モード
- NCQ(ネイティブコマンドキューイング)対応
- ホットスワップ対応
- Windows Vista以降で推奨
RAID モード
- 複数のドライブを組み合わせて使う
- RAID 0(高速化)やRAID 1(ミラーリング)
- 専用のドライバーが必要
- 高度な用途向け
推奨設定
一般的な使用
AHCIモードを選んでください。最も高速で、現代的な機能が使えます。
変更時の注意
Windowsインストール後にモードを変更すると、起動しなくなることがあります。
変更する場合は、事前にWindowsの設定を変更する必要があります。
モードの確認方法(Windows)
現在のモードを確認できます。
手順
- デバイスマネージャーを開く
- 「IDE ATA/ATAPI コントローラー」を展開
- 表示される項目を確認
- 「標準 SATA AHCI コントローラー」→ AHCIモード
- 「標準デュアルチャネル PCI IDE コントローラー」→ IDEモード
M.2 SSDとNVMe の設定
M.2スロットの有効化
M.2 SSDを使う場合、BIOSで有効にする必要があることがあります。
設定場所
- 「Advanced」→「Onboard Devices Configuration」
- 「M.2 Configuration」
- 「Storage Configuration」
設定項目
- M.2_1 Slot:Enabled
- M.2_2 Slot:Enabled
- M.2 Mode:NVMe または Auto
PCIeレーンの共有問題
M.2スロットを使うと、他のSATAポートが無効になることがあります。
よくあるパターン
- M.2_1を使うと、SATA5とSATA6が無効
- M.2_2を使うと、SATA3とSATA4が無効
マザーボードのマニュアルで確認しましょう。
NVMe SSDの認識
NVMe SSDは、通常のSATAドライブとは別の場所に表示されます。
表示場所
- 「PCIe Storage Device」
- 「NVMe Configuration」
- 「M.2 Information」
BIOSがNVMeに対応していない古いマザーボードでは、認識されません。
セキュアブートの設定

セキュアブートとは
不正なOSやマルウェアの起動を防ぐセキュリティ機能です。
Windows 11では、セキュアブートが必須要件になっています。
仕組み
- デジタル署名のあるOSだけを起動
- 署名のないOSはブロック
- マルウェアからの保護
有効化の方法
設定場所
- 「Security」タブ
- 「Boot」タブ内
- 「Secure Boot Configuration」
手順
- セキュアブートの項目を探す
- 「Enabled」または「有効」を選択
- OSタイプで「Windows UEFI mode」を選択
- 保存して再起動
無効化が必要な場合
以下の場合は、セキュアブートを無効にする必要があります。
該当ケース
- Linuxをインストールする場合
- 古いOSを使う場合
- 一部のハードウェアドライバー
- 自作のOSを起動する場合
無効にしても、通常は問題ありません。
トラブルシューティング
ストレージが認識されない
原因1:ケーブルの接続不良
- SATAケーブルを挿し直す
- 別のSATAポートを試す
- 別のケーブルを試す
原因2:電源不足
- 電源ケーブルを確認
- 電源ユニットの容量不足
- 複数ドライブがある場合は一時的に外す
原因3:BIOSが古い
- BIOSを最新版にアップデート
- 特に大容量ドライブや新しいNVMe SSDで重要
Windows が起動しない
原因1:起動順序が間違っている
正しいドライブを1番目に設定してください。
原因2:ブートモードの不一致
WindowsをUEFIモードでインストールしたなら、BIOSもUEFIモードにする必要があります。
原因3:Fast Boot が有効
Fast Boot(高速起動)を一時的に無効にしてみましょう。
パフォーマンスが出ない
原因1:IDEモードになっている
AHCIモードに変更してください。ただし、既にWindowsがインストールされている場合、事前準備が必要です。
原因2:SATA 2.0 ポートに接続
マザーボードに複数世代のSATAポートがある場合、高速なポートに接続しましょう。
原因3:省電力モードが有効
BIOSの電源管理で、省電力設定を無効にしてみてください。
BIOSのアップデート
アップデートが必要な場合
新しいストレージが認識されない場合、BIOSのアップデートで解決することがあります。
メリット
- 新しいハードウェアへの対応
- バグ修正
- パフォーマンス改善
リスク
- 失敗すると起動しなくなる
- 慎重な作業が必要
アップデート方法
事前準備
- マザーボードのメーカーサイトから最新BIOSをダウンロード
- ファイルをUSBメモリにコピー
- 重要なデータをバックアップ
手順(ASUS の例)
- BIOSを起動
- 「Tool」または「ツール」メニューへ
- 「EZ Flash」や「Q-Flash」を選択
- USBメモリのBIOSファイルを選択
- アップデート開始
- 完了まで絶対に電源を切らない
所要時間
通常3〜10分程度。この間は何もしないでください。
BIOS設定のバックアップと復元
設定のバックアップ
複雑な設定をした場合、バックアップしておくと安心です。
方法1:プロファイル保存機能
多くのマザーボードで、設定をプロファイルとして保存できます。
- 「Save Profile」または「プロファイルの保存」
- 名前を付けて保存
- USBメモリに保存することも可能
方法2:写真撮影
スマートフォンで各設定画面を撮影しておくのも有効です。
設定の復元
設定を間違えた場合、元に戻せます。
方法1:プロファイルの読み込み
保存したプロファイルを選んで読み込みます。
方法2:デフォルト設定に戻す
- 「Load Optimized Defaults」
- 「デフォルト設定の読み込み」
- 「F5」キー
これで工場出荷時の設定に戻ります。
よくある質問
BIOSで設定を変更したら起動しなくなった
対処法
- パソコンの電源を完全に切る
- CMOSクリア(BIOSリセット)を実行
- マザーボードのマニュアルでジャンパーピンの位置を確認
- または、CMOSバッテリーを10秒間外す
デフォルト設定に戻ります。
ストレージは認識されているのにWindowsで見えない
BIOSで認識されていても、Windowsで初期化されていないと使えません。
対処法
- 「ディスクの管理」を開く
- 未割り当て領域として表示されているか確認
- 右クリックで「新しいシンプルボリューム」
- ウィザードに従ってフォーマット
RAID設定は難しい?
初心者には推奨しません。
通常の使用なら、AHCIモードで十分です。RAIDは、データの冗長性や高速化が必要な上級者向けです。
SSDとHDDを両方使いたい
問題ありません。
推奨構成
- SSD:Windowsとアプリケーション
- HDD:データ保存
起動順序で、SSDを1番目に設定してください。
まとめ:BIOSでストレージを正しく設定しよう
ストレージのBIOS設定について、基礎から実践まで解説してきました。
この記事のポイント
- BIOSはハードウェアの基本設定を行う場所
- 起動時に特定のキーでBIOSに入れる
- ストレージの認識確認が最初のステップ
- 起動順序の設定が重要
- AHCIモードが現代の標準
- M.2/NVMe SSDは専用の設定が必要
- トラブル時はCMOSクリアで初期化
BIOSの設定は、最初は難しく感じるかもしれません。
でも、基本的な項目を理解すれば、そこまで複雑ではありません。
安全に設定するコツ
- 変更前に設定をメモや写真で記録
- 一度に複数の項目を変更しない
- 分からない項目は触らない
- 保存前に確認する
ストレージを追加したり、パソコンが起動しなくなったとき、この記事を参考に、落ち着いて対処してください。
正しい設定で、快適なパソコンライフを楽しみましょう!