パソコンに複数のハードディスクを接続していて、「これらを1つの大きなドライブとして使えたらいいのに」と思ったことはありませんか?
それを実現する技術がスパンボリューム(Spanned Volume)です。
スパンボリュームは、2台以上の物理ディスクをまたがって(span:またがる)、1つの論理的なボリュームとして扱う仕組みなんですね。例えば、500GBのディスク2台を組み合わせて、1TBの大きなドライブとして認識させることができます。
「便利そう」と思う一方で、「データは大丈夫なの?」「設定は難しくない?」という疑問も湧いてくるでしょう。
この記事では、スパンボリュームの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、設定方法、注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
複数のディスクを効率的に活用する方法を、一緒に学んでいきましょう!
スパンボリュームとは?

スパンボリューム(Spanned Volume)は、2台以上の物理ディスクを連結して、1つの大きな論理ドライブとして扱うディスク管理技術です。
基本的な仕組み
スパンボリュームでは、最初のディスクがいっぱいになったら、自動的に次のディスクにデータが書き込まれていきます。
イメージ図
[ディスク1: 500GB] + [ディスク2: 500GB] = [Eドライブ: 1TB]
↓データがいっぱいになったら
[ディスク3: 500GB]に拡張可能 → [Eドライブ: 1.5TB]ユーザーから見ると、複数のディスクではなく、1つの大きなドライブとして認識されるんですね。
名前の由来
「Span」は英語で「またがる」「広がる」という意味です。
複数のディスクにまたがって1つのボリュームを構成することから、この名前が付けられました。
別名
JBOD(Just a Bunch Of Disks)
「ただのディスクの寄せ集め」という意味で、スパンボリュームと似た概念を指すことがあります。
ただし、JBODは厳密にはより広い意味で使われることもあるため、完全に同じではありません。
スパンボリュームの動作原理
データがどのように保存されるか、詳しく見ていきましょう。
データの書き込み順序
スパンボリュームでは、データは順番に書き込まれます。
手順
- 最初に、ディスク1の空き領域にデータを書き込む
- ディスク1がいっぱいになったら、ディスク2に書き込み開始
- ディスク2もいっぱいになったら、ディスク3に書き込み(拡張している場合)
具体例
- ファイルA(100GB)→ ディスク1に保存
- ファイルB(300GB)→ ディスク1に保存
- ファイルC(200GB)→ ディスク1に100GB、ディスク2に100GB(分割保存)
- ファイルD(400GB)→ ディスク2に保存
1つのファイルが複数のディスクにまたがることもあるんですね。
論理アドレスの管理
オペレーティングシステム(OS)は、物理的なディスクの境界を意識せず、連続した論理アドレスとして管理します。
ユーザーから見た場合
Eドライブ: 1TB の空き容量実際の構成
ディスク1: 500GB(物理ディスク0の一部)
ディスク2: 500GB(物理ディスク1の一部)この抽象化により、使い勝手が向上するわけです。
スパンボリュームのメリット
スパンボリュームを使用する利点を見ていきましょう。
1. 柔軟な容量拡張
既存のボリュームに、後から別のディスクを追加できます。
シナリオ例
最初は500GBのディスクでスタート → 容量不足になったら500GBのディスクを追加 → 1TBのボリュームに拡張
再フォーマットや大量のデータ移行が不要なため、手軽に容量を増やせるんですね。
2. ディスク容量の有効活用
異なるサイズのディスクを組み合わせられます。
例
- 古い300GBのディスク
- 新しい700GBのディスク
- 合わせて1TBのボリュームとして活用
余っている小容量ディスクも無駄なく使えます。
3. シンプルな管理
複数のドライブレター(C:、D:、E:など)を気にせず、1つのドライブとして管理できます。
ファイルの保存場所を意識する必要がなくなるため、管理が楽になるでしょう。
4. コストパフォーマンス
大容量の単一ディスクを買うより、小〜中容量のディスクを複数使う方が安く済む場合があります。
5. 既存環境の活用
新しくディスクを購入する際、手持ちの古いディスクと組み合わせて使えます。
スパンボリュームのデメリット
便利な反面、重大な欠点もあります。
1. 信頼性の低下(最大の欠点)
致命的な問題
構成ディスクのうち、1台でも故障すると、すべてのデータが失われます。
理由
データが複数のディスクに分散して保存されているため、1台が読めなくなると、全体のデータ構造が崩れてしまうんです。
具体例
3台のディスクでスパンボリュームを構成
↓
1台が故障
↓
3TB分のデータすべてが読み取り不能に通常、複数のディスクを使えば冗長性が高まりそうですが、スパンボリュームでは逆に故障リスクが増大します。
2. パフォーマンスの向上なし
複数ディスクを使っていても、同時アクセスによる高速化はありません。
RAID 0(ストライピング)と異なり、1つのディスクに順番にアクセスするため、速度は単一ディスクと変わらないんですね。
3. 復旧が困難
1台でも故障すると、データ復旧は非常に困難です。
専門業者に依頼しても、復旧できない可能性が高いでしょう。
4. 異なるOSでは使えない
Windowsで作成したスパンボリュームは、LinuxやmacOSでは認識できません。
OS固有の機能だからです。
5. 外部接続ディスクには不向き
USB接続の外付けディスクでスパンボリュームを構成すると、接続順序を間違えただけでアクセスできなくなることがあります。
RAID 0(ストライピング)との違い
スパンボリュームとよく比較される「RAID 0」との違いを解説します。
RAID 0(ストライピング)とは?
データを分割(ストライプ)して、複数のディスクに同時に書き込む方式です。
特徴
- データを細かく分割して分散保存
- 複数ディスクに同時アクセスするため高速
- 1台でも故障すると全データ消失(スパンボリュームと同じ)
主な違い
データの保存方法
スパンボリューム
ファイルA → ディスク1
ファイルB → ディスク1
ファイルC → ディスク1がいっぱいになったらディスク2へ順番に使っていく
RAID 0
ファイルA → ディスク1とディスク2に分割して同時書き込み
ファイルB → ディスク1とディスク2に分割して同時書き込み常に分散して書き込む
パフォーマンス
スパンボリューム
- 読み書き速度:単一ディスクと同等
- メリット:なし
RAID 0
- 読み書き速度:ディスク台数に応じて高速化
- メリット:2台なら約2倍の速度
使用するディスク容量
スパンボリューム
- 異なるサイズのディスクを効率よく使える
- 300GB + 700GB = 1TB(無駄なし)
RAID 0
- 最小容量のディスクに合わせられる
- 300GB + 700GB = 600GB(400GBは未使用)
どちらを選ぶべきか?
スパンボリュームが向いている場合
- 速度より容量を重視
- 異なるサイズのディスクを組み合わせたい
- 後から容量を拡張したい
RAID 0が向いている場合
- 容量より速度を重視
- 動画編集など高速アクセスが必要
- 同じサイズのディスクを使う
重要な共通点
どちらも冗長性がなく、1台の故障で全データが失われます。重要なデータには絶対に使わないでください。
他のディスク構成方法との比較
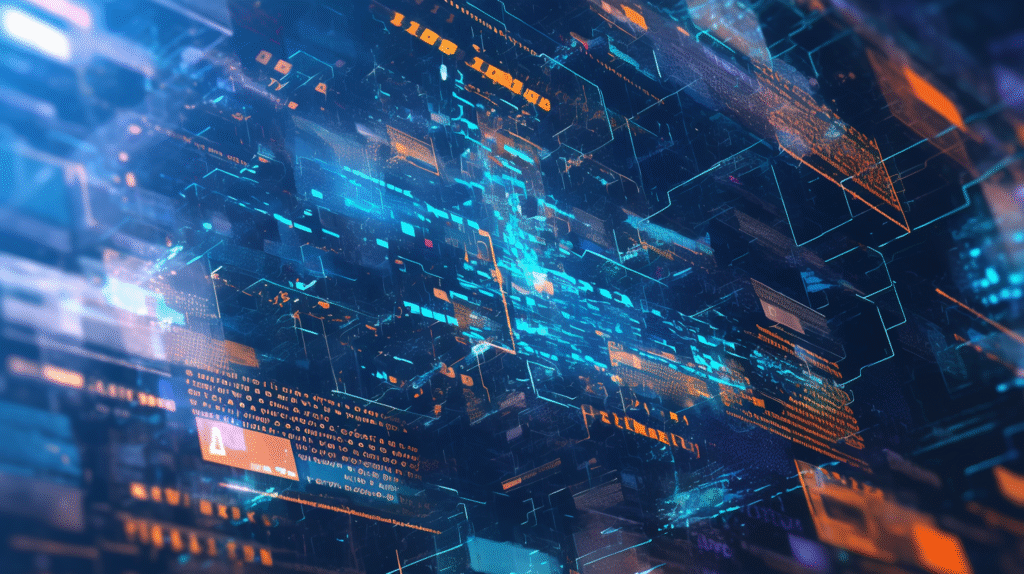
スパンボリューム以外の選択肢も見ておきましょう。
シンプルボリューム(単一ディスク)
特徴
1台のディスクに1つのボリュームを作る、最も基本的な構成です。
メリット
- シンプルで分かりやすい
- 1台が故障しても他のディスクは無事
- 設定が簡単
デメリット
- 容量拡張が困難
- ディスクごとに管理が必要
RAID 1(ミラーリング)
特徴
2台のディスクに同じデータを保存する方式です。
メリット
- 1台が故障してももう1台にデータが残る
- 高い信頼性
デメリット
- 実質容量が半分になる
- コストが高い
RAID 5(パリティ付きストライピング)
特徴
3台以上のディスクでデータとパリティ情報を分散保存します。
メリット
- 1台が故障してもデータ復旧可能
- 容量効率がRAID 1より良い
デメリット
- 最低3台必要
- 設定が複雑
- 書き込み速度がやや遅い
ダイナミックディスク vs ベーシックディスク
ベーシックディスク
Windowsの標準的なディスク管理方式です。
ダイナミックディスク
スパンボリューム、RAID構成など、高度な管理が可能な方式です。
スパンボリュームを作成するには、ディスクをダイナミックディスクに変換する必要があるんですね。
Windowsでスパンボリュームを作成する方法
実際の設定手順を見ていきましょう。
前提条件
必要なもの
- 2台以上の物理ディスク
- 管理者権限
- Windows Pro、Enterprise、Serverエディション(Home版では不可)
注意点
- データはすべてバックアップしておく
- システムドライブ(C:)ではスパンボリュームは作成不可
- ダイナミックディスクへの変換が必要
手順1:ディスクの管理を開く
方法1:ショートカット
Windows + X キーを押す
→「ディスクの管理」を選択方法2:ファイル名を指定して実行
Windows + R キーを押す
→「diskmgmt.msc」と入力してEnter手順2:ダイナミックディスクに変換
操作
- ディスクの管理画面で、使用するディスクを右クリック
- 「ダイナミックディスクに変換」を選択
- 変換するディスクにチェックを入れる
- 「OK」をクリック
- 警告メッセージを確認して「はい」
重要な警告
ダイナミックディスクに変換すると、他のOSから認識できなくなります。デュアルブート環境では注意が必要です。
手順3:スパンボリュームの作成
操作
- 1台目のディスクの未割り当て領域を右クリック
- 「新しいスパンボリューム」を選択
- 新しいスパンボリュームウィザードが起動
- 「次へ」をクリック
ディスクの選択
- 利用可能なディスクの一覧から、追加したいディスクを選択
- 「追加」ボタンをクリック
- 各ディスクの使用する容量を指定
- 「次へ」をクリック
ドライブレターの割り当て
- ドライブレター(例:E:)を選択
- または、フォルダにマウントすることも可能
- 「次へ」をクリック
フォーマット設定
- ファイルシステム:NTFS(推奨)
- アロケーションユニットサイズ:既定値
- ボリュームラベル:任意の名前を入力
- 「クイックフォーマット」にチェック
- 「次へ」をクリック
完了
- 設定内容を確認
- 「完了」をクリック
- フォーマットが実行される
手順4:動作確認
確認方法
- エクスプローラーを開く
- 指定したドライブレターが表示されているか確認
- ファイルを保存してみて、正常に動作するか確認
既存のスパンボリュームに容量を追加する方法
操作
- ディスクの管理を開く
- 拡張したいスパンボリュームを右クリック
- 「ボリュームの拡張」を選択
- 追加するディスクと容量を指定
- ウィザードに従って完了
データを失うことなく、容量を増やせるのがスパンボリュームの利点です。
スパンボリュームの適切な使用例
どんな場面で使うべきか、具体例を見ていきましょう。
適切な使用例
1. 一時的な作業領域
- 動画編集の作業フォルダ
- プログラムのビルド用テンポラリ領域
- 大量のログファイル置き場
いつ消えても問題ないデータなら、スパンボリュームのリスクは許容できます。
2. バックアップの中継地点
- 外部ストレージに転送する前の一時保存場所
- 複数のバックアップソースを集約する場所
最終的に別の場所にコピーするため、ここで失われても影響が少ないんですね。
3. メディアライブラリ(要バックアップ)
- 音楽コレクション
- 動画ライブラリ
- 写真アーカイブ
重要な条件
必ず別の場所にバックアップがあること。スパンボリュームはあくまで作業用です。
4. 開発環境のソースコード置き場
- Git リポジトリのローカルクローン
- テスト用データ
Gitサーバーに最新版があれば、ローカルが消えても復旧できます。
避けるべき使用例
1. 重要な文書やプロジェクトファイル
仕事の成果物、論文、設計図など、失うと困るデータは絶対に保存しないでください。
2. 写真や動画の唯一の保存先
思い出は取り戻せません。RAID 1やクラウドバックアップと併用しましょう。
3. データベースファイル
顧客情報、商品マスタなど、ビジネスに直結するデータは、冗長性のある構成で保管すべきです。
4. システムドライブ
Windowsのシステムファイルは、スパンボリュームに配置できません(仕様上の制限)。
5. 外付けUSBディスク
接続が不安定なため、スパンボリュームには向きません。
トラブルシューティング
スパンボリュームで問題が発生した場合の対処法です。
問題1:スパンボリュームが作成できない
症状
「新しいスパンボリューム」メニューがグレーアウトしている。
原因と解決方法
原因1:Windowsのエディションが対応していない
Windows Home版ではスパンボリュームを作成できません。
解決方法
Pro版またはEnterprise版にアップグレードする。
原因2:ベーシックディスクのまま
ダイナミックディスクに変換していない。
解決方法
ディスクを右クリックして「ダイナミックディスクに変換」を実行。
原因3:GPTとMBRが混在
異なるパーティション形式のディスクは組み合わせられません。
解決方法
すべてのディスクを同じ形式(GPTまたはMBR)に統一する。
問題2:1台のディスクが認識されなくなった
症状
スパンボリューム全体がアクセス不能になった。
原因
構成ディスクの1台が物理的に故障、または接続が外れた。
解決方法
接続確認
- 電源とケーブルを確認
- BIOSでディスクが認識されているか確認
- 別のSATAポートに接続してみる
ディスクが完全に故障している場合
残念ながら、データの復旧は極めて困難です。専門業者に相談するか、バックアップから復元してください。
問題3:ドライブレターが表示されない
症状
スパンボリュームを作成したのに、エクスプローラーに表示されない。
原因
ドライブレターが割り当てられていない。
解決方法
- ディスクの管理を開く
- スパンボリュームを右クリック
- 「ドライブ文字とパスの変更」を選択
- 「追加」をクリック
- 使用していないドライブレターを選択
- 「OK」をクリック
問題4:スパンボリュームを削除したい
操作手順
- 重要:データをバックアップする
- ディスクの管理を開く
- スパンボリュームを右クリック
- 「ボリュームの削除」を選択
- 警告を確認して「はい」
注意点
削除すると、すべてのデータが消えます。必ずバックアップを取ってください。
問題5:ダイナミックディスクをベーシックディスクに戻したい
手順
- スパンボリュームを削除する
- ディスク上のすべてのボリュームを削除する
- ディスクを右クリック
- 「ベーシックディスクに変換」を選択
注意点
すべてのデータが消えます。事前にバックアップ必須です。
スパンボリュームの代替案
より安全で効果的な選択肢を検討しましょう。
1. 外付けストレージの追加
メリット
- 故障しても他のディスクは無事
- 取り外して持ち運べる
- バックアップ先としても使える
2. NAS(Network Attached Storage)
メリット
- ネットワーク経由で複数のPCから共有できる
- RAID 1やRAID 5で冗長性を確保
- 自動バックアップ機能
3. クラウドストレージ
サービス例
- Google Drive
- Microsoft OneDrive
- Dropbox
- Amazon S3
メリット
- 物理的な故障リスクがない
- どこからでもアクセス可能
- 自動同期機能
4. RAID 5またはRAID 6
メリット
- 1台(RAID 5)または2台(RAID 6)の故障に耐えられる
- 容量効率が良い
- 企業用途に適している
デメリット
- 最低3台(RAID 5)または4台(RAID 6)必要
- RAIDカードまたはマザーボード対応が必要
まとめ
スパンボリュームは、複数の物理ディスクを1つの論理ボリュームとして扱う便利な技術です。
しかし、信頼性が低く、1台でも故障すると全データが失われるという重大な欠点があります。
この記事のポイント
- スパンボリュームは複数ディスクを連結して1つのボリュームにする技術
- データは順番に書き込まれ、1台目がいっぱいになったら2台目へ
- 容量の柔軟な拡張が可能で、異なるサイズのディスクも使える
- 1台でも故障すると全データが失われる致命的な欠点がある
- RAID 0と異なり、速度向上のメリットはない
- Windows Pro以上でダイナミックディスクに変換して作成
- 重要なデータには絶対に使用しない
- 一時的な作業領域やバックアップがある場合のみ使用を検討
- より安全な代替案(RAID 1、NAS、クラウド)を優先すべき
最も重要なこと
スパンボリュームは、失っても困らないデータ専用です。重要なデータには、必ずバックアップと冗長性のある保存方法を選択してください。
「容量を増やしたい」という理由だけでスパンボリュームを選ぶのではなく、データの重要度に応じた適切なストレージ構成を検討しましょう。
データは一度失うと取り戻せません。慎重な判断をお願いします!







