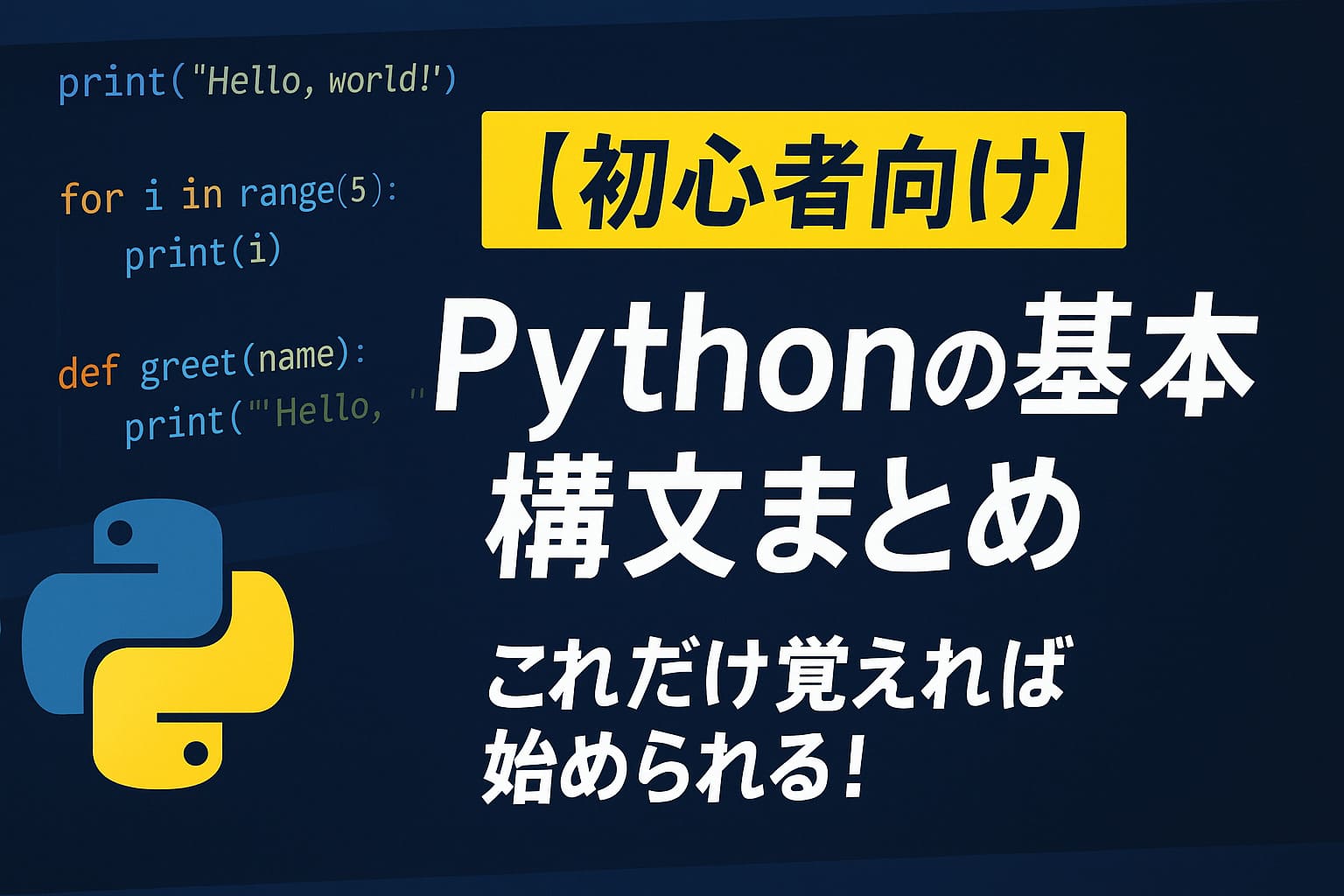「Pythonを始めたいけど、なにから覚えればいいの?」って思いますよね。
実は、Pythonはとってもシンプルな言語なんです。
まるで英語を書くような感じで、読みやすくて初心者にもやさしいのが特徴です。
でも、いざ始めようとすると…
- どんな書き方があるの?
- とりあえず最低限なにを覚えればいい?
- エラーが出ない書き方を知りたい!
そんな疑問が出てきますよね。
この記事では、Pythonを始める人が最初に覚えるべき基本的な書き方をまとめました。
メモを残そう – コメントの書き方
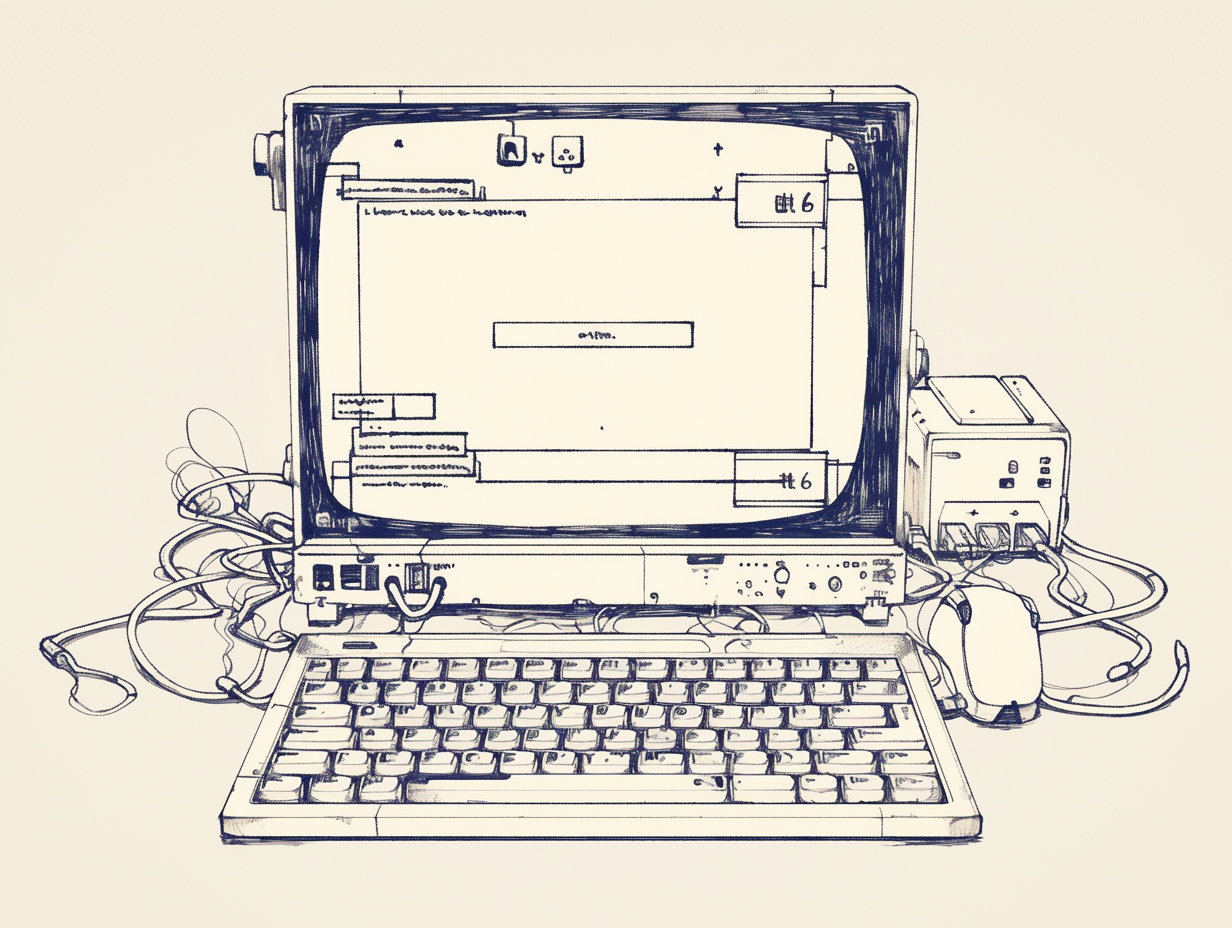
# これはメモです(コメントといいます)
print("こんにちは") # この部分もメモになります行の最初に # を付けると、その部分はメモになります。
プログラムには影響しないので、あとで見返すときの説明に使えて便利です。
値を入れる箱を作ろう – 変数について
#変数 = 値
x = 10
name = "太郎"
変数(へんすう)とは、値を入れておく箱のようなものです。
Pythonでは型を書かなくても、勝手に判断してくれるので楽ちんですね。
章のまとめ:変数は値を保存する便利な箱。
次は、どんな種類の値があるか見てみましょう。
いろんな種類の値 – データの型
age = 25 # 数字(整数)
height = 170.5 # 小数点付きの数字
message = "おはよう" # 文字
is_student = True # 正しいか間違いか(真偽値)
プログラムで扱える値にはいくつか種類があります。
数字、文字、正しいか間違いかを表すものなどです。
章のまとめ:値の種類を覚えたら、次は条件によって処理を変える方法を学びましょう。
条件によって処理を変える – if文
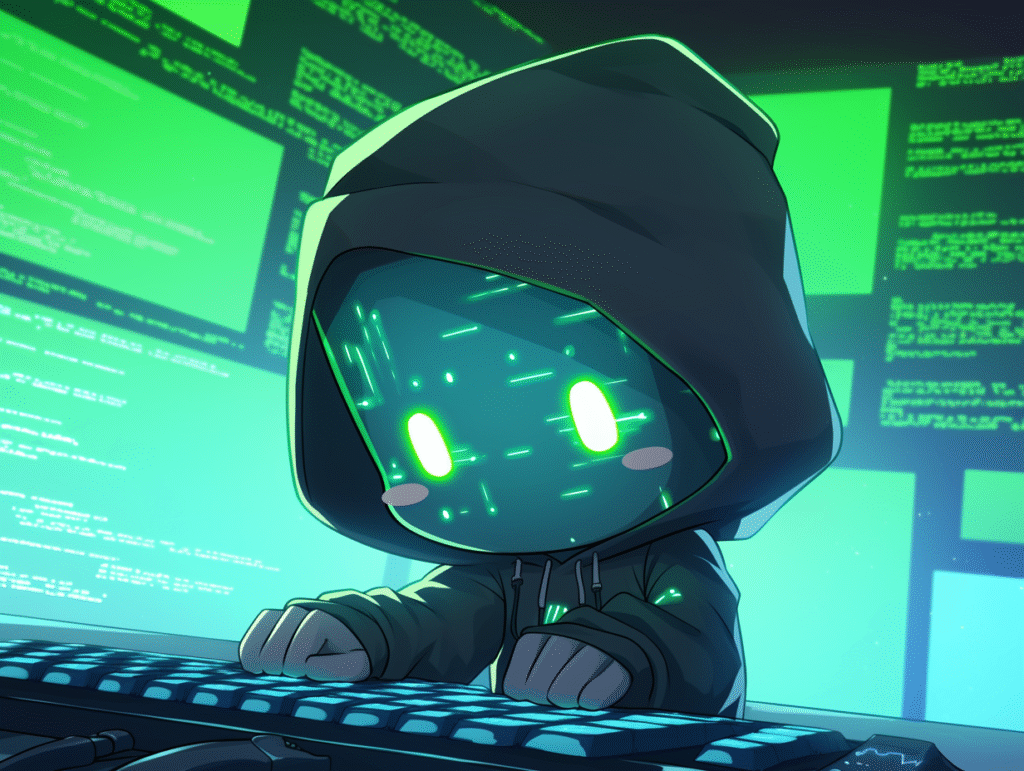
# if 条件1:
# 条件1がtrueの時の処理
# elif 条件2:
# 条件2がtrueの時の処理
# else:
# 条件1と条件2のどちらもfalseの時の処理
score = 80
if score >= 90:
print("すばらしい!")
elif score >= 70:
print("よくできました")
else:
print("がんばりましょう")
if文を使うと、条件によって違う処理ができます。
テストの点数によってメッセージを変えるような場面で使います。
条件分岐ができるようになったら、次は同じ処理を繰り返す方法を覚えましょう。
同じ処理を繰り返そう – ループ処理
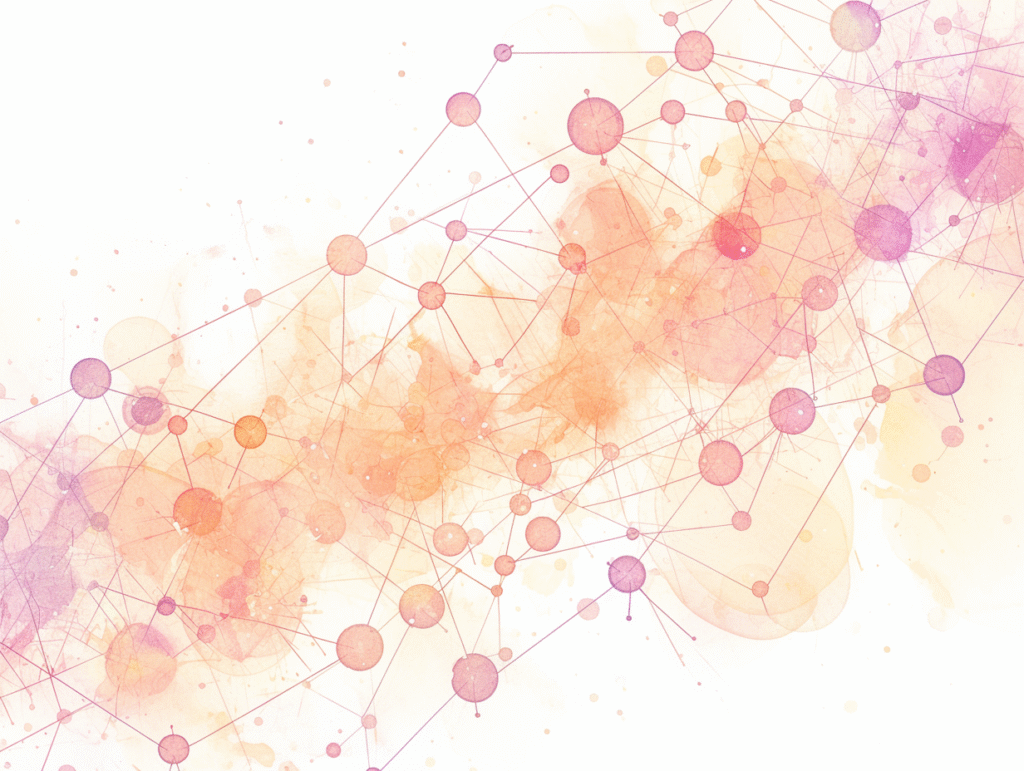
for文(決まった回数繰り返す)
# for i in 範囲:
# 処理(数値はiで取得)
for i in range(3):
print(f"{i + 1}回目です")for文は、決まった回数だけ処理を繰り返したいときに使います。
while文(条件が満たされている間繰り返す)
# while 条件:
# 条件がtrueの時の処理
count = 1
while count <= 3:
print(f"{count}回目です")
count = count + 1
while文は、条件が正しい間ずっと繰り返したいときに使います。
章のまとめ:繰り返し処理を覚えたら、次は処理をまとめる関数について学びましょう。
処理をまとめよう – 関数の作り方
# def 関数名(引数):
# 処理
#
# 呼び出す時は、関数名(引数の値)
def say_hello(name):
return f"こんにちは、{name}さん!"
message = say_hello("花子")
print(message) # こんにちは、花子さん!
関数(かんすう)は、よく使う処理をひとまとめにしたものです。
一度作れば何度でも使えるので、とても便利ですね。
章のまとめ:関数で処理をまとめる方法を覚えたら、次は複数の値を管理するリストを学びましょう。
複数の値をまとめて管理 – リスト

# []内に要素をカンマ区切りで指定
# [要素1, 要素2, 要素3, ・・・]
fruits = ["りんご", "みかん", "バナナ"]
print(fruits[0]) # りんご(最初の要素)
fruits.append("ぶどう") # 新しく追加
print(fruits) # ['りんご', 'みかん', 'バナナ', 'ぶどう']
リストは、複数の値をまとめて管理できる便利な仕組みです。
買い物リストのようなイメージですね。
覚えておこう:リストの番号は0から始まります。最初の要素は1番目ではなく0番目です。
リストで複数の値を管理できるようになったら、次はキーと値のペアで管理する辞書を覚えましょう。
キーと値で管理する – 辞書
# {}内に「キー:値」をカンマ区切りで指定
# {キー1:値1, キー2:値2, キー3:値3, ・・・}
student = {"名前": "田中", "年齢": 20, "学年": 2}
print(student["名前"]) # 田中
student["専攻"] = "情報学部" # 新しく追加
辞書は、キー(鍵)と値をペアで管理する仕組みです。
名前から年齢を調べるような場面で便利ですね。
章のまとめ:辞書でデータを整理できるようになったら、次はエラーが起きたときの対処法を学びましょう。
エラーが起きても大丈夫 – 例外処理
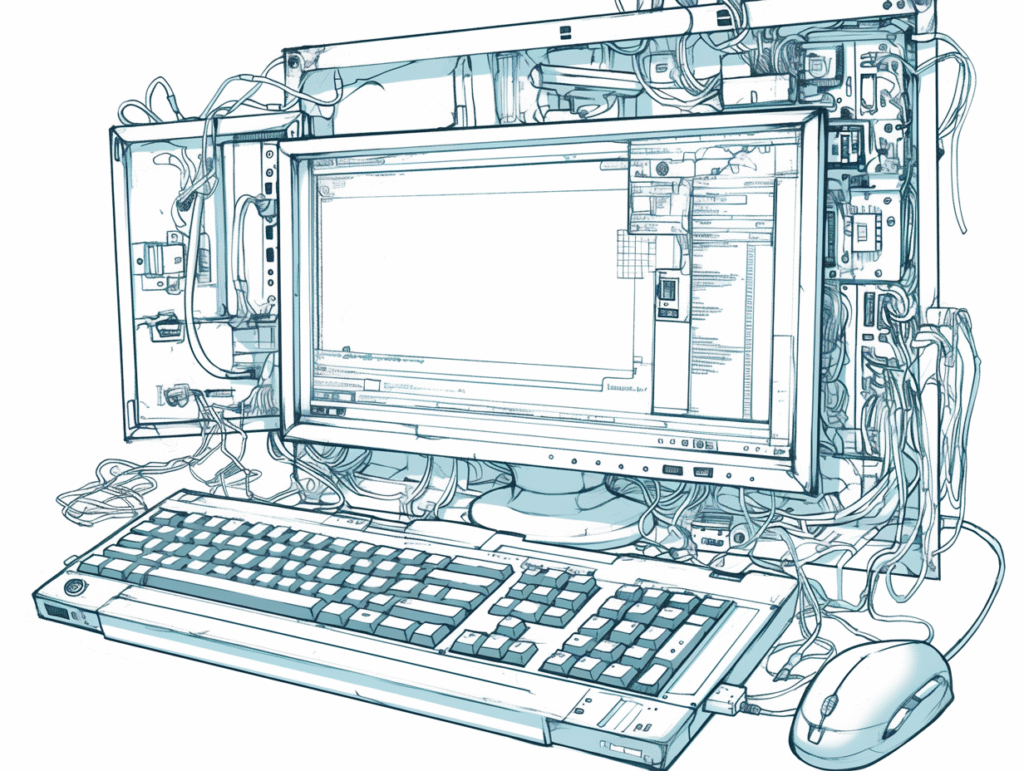
try:
number = int(input("数字を入力してください: "))
result = 10 / number
print(f"結果: {result}")
except ValueError:
print("数字以外が入力されました")
except ZeroDivisionError:
print("0では割れません")
プログラムでは、予想しないエラーが起きることがあります。
try-except文を使うと、エラーが起きても安全に処理を続けることができます。
エラー処理を覚えたら、次は他の人が作った便利な機能を使う方法を学びましょう。
便利な機能を使おう – モジュールの読み込み(import)
# import モジュール名
import math
print(math.sqrt(16)) # 4.0(16の平方根)
import random
print(random.randint(1, 6)) # 1から6までのランダムな数字
モジュールとは、便利な機能をまとめたものです。
数学の計算やランダムな数字を作るなど、様々な機能が用意されています。
モジュールで便利な機能を使えるようになったら、次はファイルの読み書きを覚えましょう。
ファイルを読んだり書いたり – ファイル操作
ファイルに書き込む
#「with open() as 仮の名前」でファイルを開く
#仮の名前.write(書き込む内容)
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
file.write("今日は良い天気です")
ファイルから読み込む
# readでファイルを読み込む
with open("memo.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
content = file.read()
print(content) # 今日は良い天気です
ファイル操作を覚えると、データを保存したり、他のプログラムとやり取りできるようになります。
ファイル操作を覚えたら、次は本格的なプログラミングで使うクラスについて学びましょう。
オブジェクト指向の基本 – クラス
# class クラス名:
# メソッド定義
class Pet:
def __init__(self, name, animal_type):
self.name = name
self.animal_type = animal_type
def introduce(self):
print(f"私の名前は{self.name}、{self.animal_type}です")
my_pet = Pet("ポチ", "犬")
my_pet.introduce() # 私の名前はポチ、犬です
クラスは、関連する変数と関数をまとめたものです。
上記の例だと、ペットの情報と行動をひとまとめにするようなイメージですね。
クラスの基本を覚えたら、最後に便利なテクニックを2つ紹介しましょう。
便利なテクニック
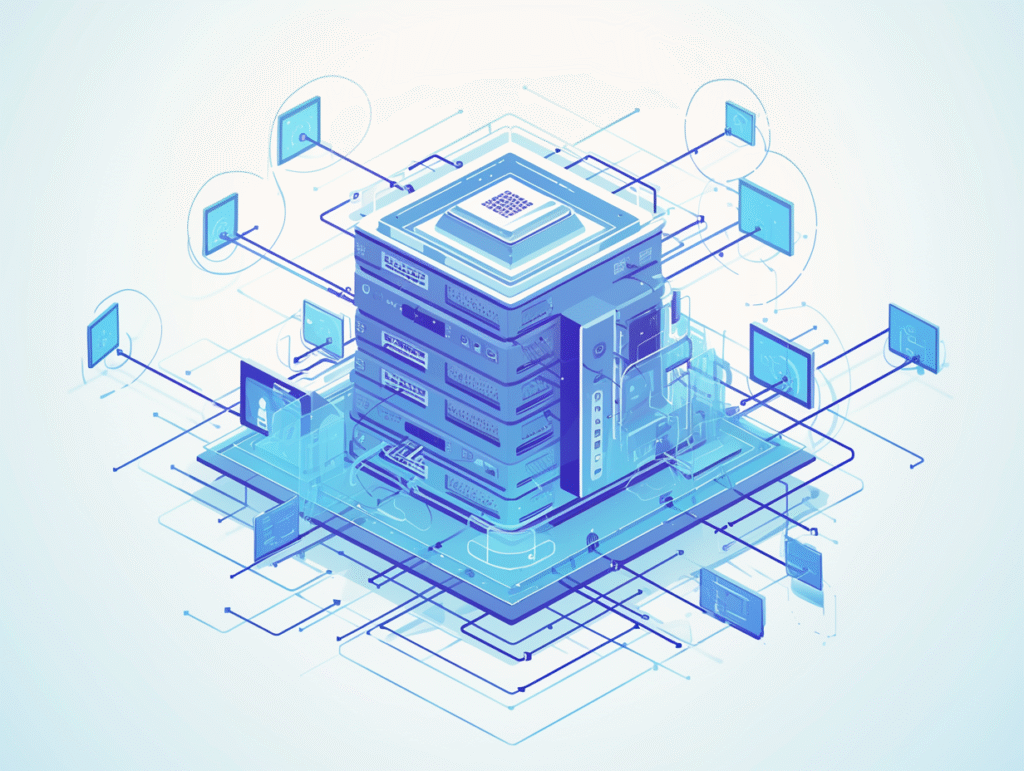
リスト内包表記(短く書ける繰り返し)
# 通常の書き方
squares = []
for x in range(5):
squares.append(x * x)
# 短く書ける方法
# [処理 for 変数 in 範囲]
squares = [x * x for x in range(5)]
print(squares) # [0, 1, 4, 9, 16]
f文字列(文字列に値を入れる)
name = "Python"
version = 3.9
print(f"こんにちは、{name} {version}!")
f文字列を使うと、文字列の中に変数の値を簡単に入れることができます。
まとめ
これでPythonの基本的な構文を紹介しました。
Pythonの良いところは「とりあえず書いてみる」ことができる点です。
ポイントまとめ
- コメント、変数、データ型
- 条件分岐(if文)と繰り返し(for、while)
- 関数、リスト、辞書
- エラー処理、モジュール、ファイル操作
- クラス、便利なテクニック