「パソコンが熱くなってきたら、動きが遅くなった」
「ファンがうるさく回り始めると、作業が進まない」
「夏場になるとパソコンの調子が悪い」
こんな経験はありませんか?
パソコンを使っていると、本体が熱くなることがあります。そして不思議なことに、熱くなると同時に動作が重くなってしまうんです。
実は、これにはちゃんとした理由があります。パソコンには「熱くなりすぎたら性能を落とす」という自己防衛機能が備わっているんです。この記事では、パソコンが熱くなると重くなる仕組みを、初心者の方にも分かりやすく解説します。対処法や予防策も詳しくお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
パソコンが熱くなる基本的な仕組み
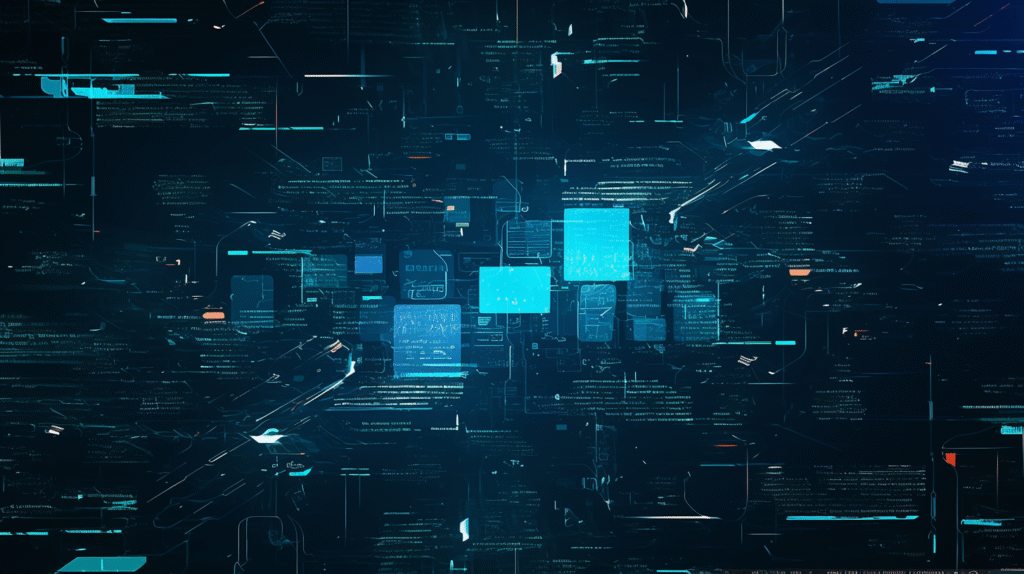
電子部品は動くと熱を発する
まず、なぜパソコンが熱くなるのかを理解しましょう。
熱が発生する理由
パソコンの中には、CPU(中央処理装置)やGPU(画像処理装置)など、たくさんの電子部品が入っています。これらの部品は電気を使って動くため、必ず熱が発生するんです。
例えるなら、人間が運動すると体温が上がるのと同じ。パソコンも「仕事」をすればするほど、熱くなっていきます。
負荷が高いほど熱くなる
パソコンの作業内容によって、発熱量は変わります。
発熱しやすい作業
- 動画編集や3Dゲーム
- 大量のファイルを処理する
- 複数のアプリを同時に起動
- 動画配信やビデオ会議
発熱しにくい作業
- 文書作成
- ウェブ閲覧
- メールのチェック
重い作業をすればするほど、パソコンは熱くなります。
熱はパソコンの大敵
電子部品にとって、熱は天敵です。
高温が引き起こす問題
- 部品の劣化が早まる
- 動作が不安定になる
- 最悪の場合、故障する
そのため、パソコンには熱から身を守る仕組みが備わっています。それが、次に説明する「サーマルスロットリング」なんです。
熱くなると重くなる理由:サーマルスロットリング
サーマルスロットリングとは
パソコンが熱くなると重くなる最大の理由が、この「サーマルスロットリング」という機能です。
サーマルスロットリングの仕組み
パソコンの温度が一定以上になると、CPUやGPUが自動的に動作速度を落とす機能のこと。「Thermal(熱の)」+「Throttling(制限する)」という意味です。
例えるなら、マラソンランナーが体温が上がりすぎないよう、ペースを落とすようなもの。パソコンも自分の身を守るために、意図的に性能を下げるんです。
なぜ性能を落とすのか
「なぜわざわざ遅くするの?」と思うかもしれません。
性能を落とす理由
- さらなる発熱を防ぐ
- 速く動くほど熱が出る
- 遅くすれば発熱が減る
- 部品の破損を防ぐ
- 高温が続くと壊れる
- 性能を落としてでも保護する
- システムダウンを回避
- 突然シャットダウンするより、遅くても動く方がマシ
つまり、重くなるのは故障を防ぐための「安全装置」なんです。
どのくらい性能が落ちるのか
サーマルスロットリングが発動すると、どれくらい遅くなるのでしょうか。
性能低下の目安
- 軽度:10~20%程度の低下
- 中度:30~50%程度の低下
- 重度:50%以上、場合によっては70~80%も低下
温度が高いほど、性能の低下幅も大きくなります。ひどい時は、本来の半分以下の性能になることもあるんです。
温度の閾値(しきいち)
何度になるとサーマルスロットリングが発動するのでしょうか。
一般的な温度の目安
- CPU:70~80℃で徐々に制限開始、90~100℃で大幅制限
- GPU:80~85℃で制限開始、95℃以上で大幅制限
- ノートパソコン:デスクトップより低い温度で制限がかかりやすい
機種や部品によって異なりますが、大体この範囲です。
各パーツと熱の関係
CPUと発熱
CPUは「パソコンの頭脳」と呼ばれる、最も重要な部品です。
CPUの発熱特性
- 最も発熱しやすい部品の一つ
- 小さな面積に大量の熱が集中
- 冷却が不十分だとすぐに高温に
CPUが熱くなると、すべての処理速度が落ちます。アプリの起動、ファイルを開く速度、計算処理など、あらゆる動作が遅くなるんです。
GPUと発熱
GPU(グラフィックス処理装置)も、大きな熱源です。
GPUの特徴
- ゲームや動画編集で大活躍
- CPUと同等かそれ以上に発熱
- 独立したGPU(グラフィックカード)はさらに熱い
GPUが熱くなると、画面の描画が遅くなります。ゲームがカクカクしたり、動画編集のプレビューが重くなったりします。
メモリと発熱
メモリ(RAM)も、実は熱を持ちます。
メモリの発熱
- CPUやGPUほどではないが、それなりに発熱
- 特にゲーミングPCのメモリは熱い
- 高温になると動作が不安定に
メモリが熱くなると、アプリが突然落ちたり、エラーが出やすくなります。
ストレージ(SSDやHDD)と発熱
データを保存するストレージも熱を持ちます。
ストレージの発熱
- SSD(特にNVMe SSD)は結構熱い
- HDDも回転によって発熱
- 高温になると読み書き速度が低下
ファイルの保存や読み込みが遅くなる原因になります。
電源ユニットと発熱
電源ユニットも熱源の一つです。
電源の役割と発熱
- 電気を各部品に供給
- 変換時に熱が発生
- 効率の悪い電源ほど発熱が多い
電源自体が熱くなりすぎると、供給電力が不安定になり、パソコン全体の動作に影響します。
パソコンの冷却システム
空冷ファンの役割
最も一般的な冷却方法が、ファンによる空冷です。
ファンの仕組み
- パソコン内部の熱い空気を外に出す
- 外の冷たい空気を中に入れる
- 空気の流れで部品を冷やす
ファンが正常に動いていないと、すぐに熱がこもってしまいます。
ヒートシンクの役割
ヒートシンクは、熱を効率的に逃がすための金属製の部品です。
ヒートシンクの特徴
- CPUやGPUに取り付けられている
- 金属製(主にアルミや銅)
- 表面積を大きくして放熱を促進
ヒートシンクにホコリが溜まると、冷却効率が大幅に落ちます。
熱伝導グリスの重要性
CPUとヒートシンクの間には、熱伝導グリス(サーマルペースト)が塗られています。
グリスの役割
- 2つの金属の隙間を埋める
- 熱の伝わりを良くする
- 経年劣化で効果が落ちる
古いパソコンの場合、グリスが乾燥して冷却効率が落ちていることがあります。
水冷システム(一部のパソコン)
高性能なパソコンには、水冷システムが使われることもあります。
水冷の特徴
- 空冷より冷却効率が高い
- 静かに冷やせる
- メンテナンスが必要
主にゲーミングPCや高性能ワークステーションで採用されています。
パソコンが熱くなりやすい状況
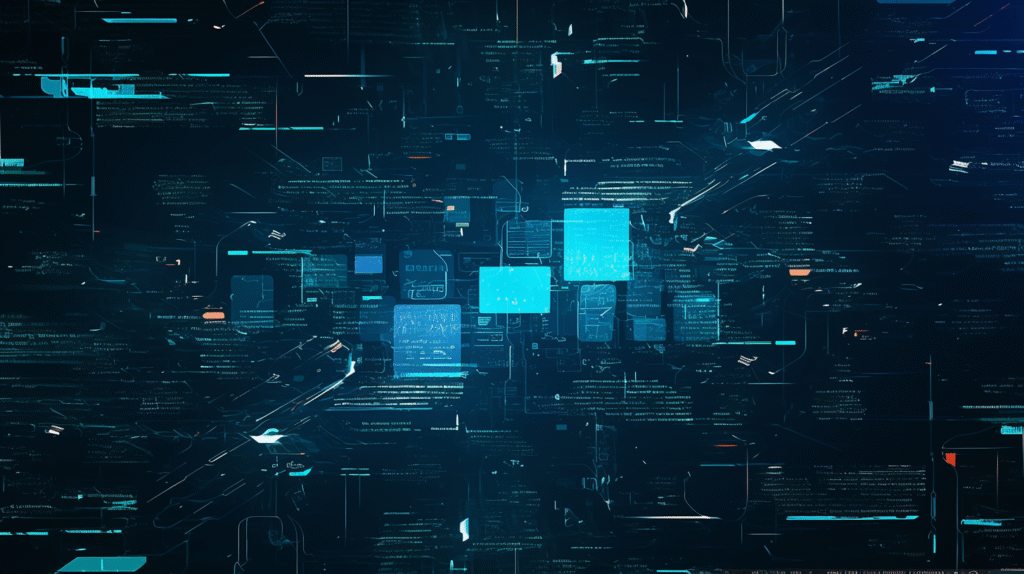
室温が高い
まず、周囲の環境が大きく影響します。
夏場の問題
- 室温が30℃を超えると冷却が追いつかない
- エアコンなしの部屋は特に危険
- 直射日光が当たる場所も要注意
人間も暑い部屋では動きが鈍くなりますよね。パソコンも同じです。
通気口が塞がれている
パソコンの置き場所も重要です。
NGな設置例
- 壁にピッタリくっつけて設置
- カーペットや布団の上に置く
- 本や書類で通気口を塞ぐ
- ノートパソコンを膝の上で長時間使用
通気が悪いと、すぐに熱がこもります。
長時間の連続使用
休みなく使い続けるのも問題です。
連続使用の影響
- 熱が蓄積していく
- 冷却が追いつかなくなる
- 特に負荷の高い作業は要注意
たまには休憩を入れて、パソコンも冷ましてあげましょう。
ホコリの蓄積
内部にホコリが溜まると、冷却効率が大幅に低下します。
ホコリの問題
- ファンの回転を妨げる
- 通気口を塞ぐ
- ヒートシンクの効果を下げる
定期的な掃除が必要です。
経年劣化
古いパソコンは熱くなりやすい傾向があります。
劣化の影響
- 熱伝導グリスが乾燥
- ファンの軸受けが摩耗
- 部品自体の効率が低下
数年使っているパソコンは、メンテナンスが特に重要です。
対処法:すぐにできること
パソコンを涼しい場所に移動
まず、環境を改善しましょう。
設置場所の改善
- エアコンの効いた部屋で使う
- 直射日光を避ける
- 風通しの良い場所に置く
室温を25℃以下に保つのが理想的です。
通気口を確保する
パソコンの周りにスペースを作りましょう。
通気確保のポイント
- 壁から10cm以上離す
- デスクトップPCは床に直置きしない
- ノートPCは冷却台を使う
- 周りに物を置かない
空気の流れを良くすることが大切です。
不要なアプリを終了
パソコンの負荷を減らしましょう。
負荷軽減の方法
- タスクマネージャー(Windowsの場合)を開く
- CPU使用率の高いアプリを確認
- 不要なものを終了する
- バックグラウンドで動いているアプリもチェック
使っていないアプリは、こまめに終了する習慣をつけましょう。
ブラウザのタブを整理
意外と負荷が高いのが、ブラウザです。
ブラウザの最適化
- 開きすぎたタブを閉じる
- 動画サイトのタブは特に負荷が高い
- 拡張機能を見直す
タブは必要な分だけ開くようにしましょう。
パソコンを再起動
シンプルですが効果的な方法です。
再起動のメリット
- メモリがリフレッシュされる
- 不要なプロセスが終了
- 一時ファイルがクリアされる
調子が悪いと感じたら、まず再起動してみましょう。
対処法:少し手間がかかること
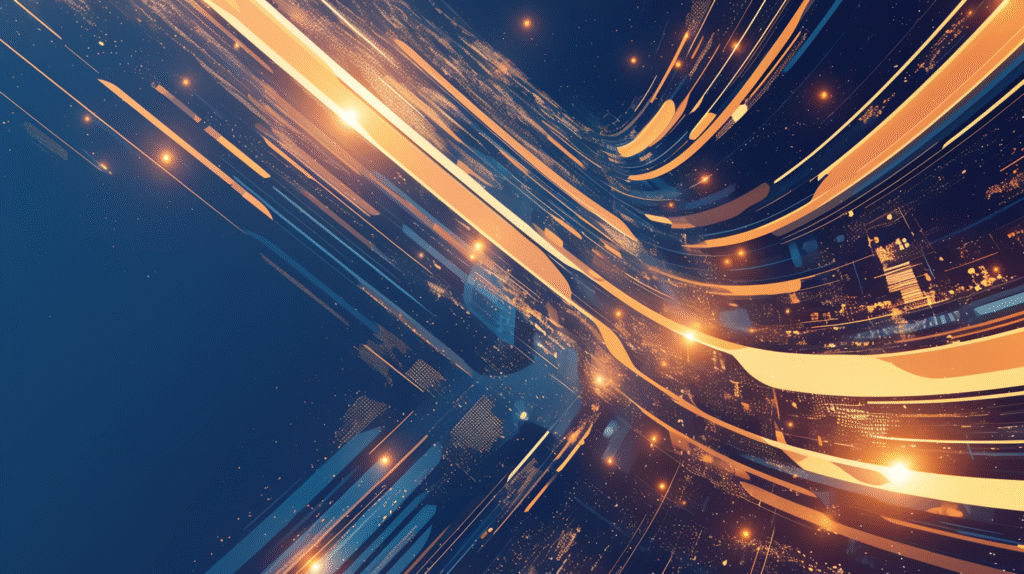
外部から冷却する
市販の冷却グッズを使う方法です。
ノートパソコン用冷却台
- 下から風を送る
- 数千円で購入可能
- かなり効果的
USBファン
- 外付けで追加の冷却
- 安価で手軽
冷却パッド
- 熱を吸収するシート
- ノートPCの下に敷く
パソコン内部の掃除
内部のホコリを取り除きましょう。
掃除の手順(デスクトップPC)
- 電源を切り、コンセントを抜く
- ケースを開ける
- エアダスターでホコリを吹き飛ばす
- ファンやヒートシンクを重点的に
- ケースを閉じる
注意点
- 静電気に注意
- 水は絶対に使わない
- 自信がなければ専門店に依頼
年に1~2回の掃除が理想です。
熱伝導グリスの塗り直し
上級者向けですが、効果は抜群です。
グリス交換の効果
- 冷却効率が大幅に向上
- 古いパソコンには特に有効
- 数年に1度の交換が推奨
注意点
- CPUを取り外す必要がある
- 失敗すると故障のリスク
- 初心者は専門店に依頼推奨
パソコンに詳しくない方は、専門家に任せた方が安全です。
ファンの交換
ファンが劣化している場合は、交換も検討しましょう。
ファン交換のサイン
- 異音がする
- 回転が遅い、または止まっている
- 振動が大きい
新しいファンに交換すると、冷却性能が回復します。
対処法:設定で改善する
電源プランの変更(Windows)
パソコンの動作モードを変更します。
電源プランの変更手順
- コントロールパネルを開く
- 「電源オプション」を選択
- 「省電力」または「バランス」プランを選択
効果
- CPUの最大性能が制限される
- 発熱が抑えられる
- バッテリー持ちも向上(ノートPCの場合)
性能は落ちますが、発熱も抑えられます。
パフォーマンスモードの調整(Mac)
Macにも似た機能があります。
省エネルギー設定
- システム設定を開く
- 「バッテリー」を選択
- 「省エネルギーモード」をオン
グラフィックスを多用しない作業なら、十分快適に使えます。
バックグラウンドアプリの制限
不要なアプリを自動起動させない設定です。
Windows設定
- 設定>アプリ>スタートアップ
- 不要なアプリをオフに
Mac設定
- システム設定>一般>ログイン項目
- 不要なものを削除
起動が早くなり、常時の負荷も減ります。
視覚効果を減らす
見た目の演出を減らして負荷を軽減します。
Windows設定
- コントロールパネル>システム>システムの詳細設定
- パフォーマンスオプションを開く
- 「パフォーマンスを優先する」を選択
Mac設定
- システム設定>アクセシビリティ
- 「ディスプレイ」>「視差効果を減らす」をオン
見た目は地味になりますが、軽快に動くようになります。
予防策:熱くならないための習慣
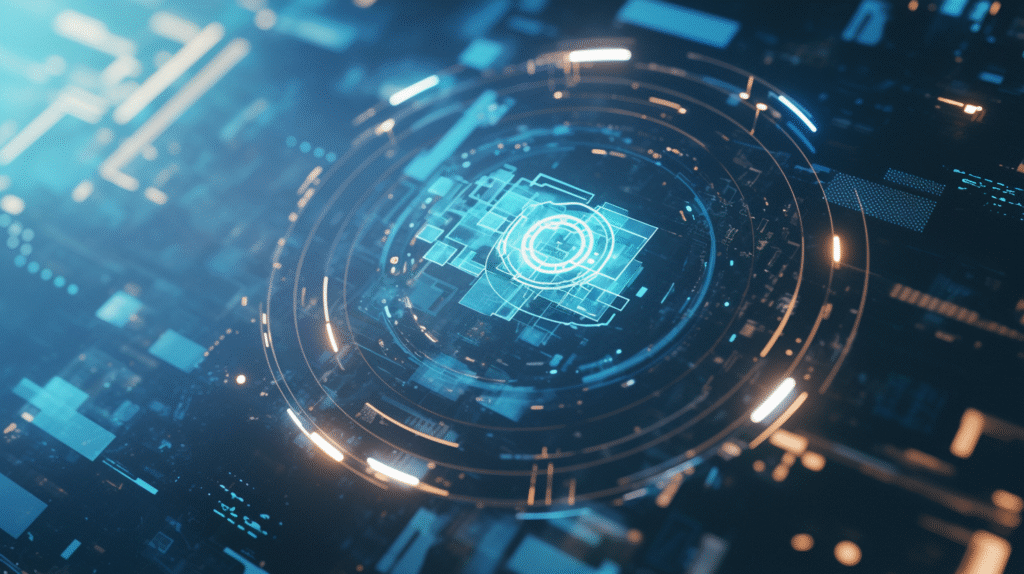
定期的な掃除
ホコリ対策は予防の基本です。
掃除の頻度
- デスクトップPC:3~6ヶ月に1回
- ノートPC:6ヶ月~1年に1回
- ホコリが多い環境ではもっと頻繁に
こまめな掃除が、長持ちの秘訣です。
適切な設置場所
最初から通気の良い場所に置きましょう。
理想的な設置場所
- 風通しが良い
- 直射日光が当たらない
- 室温が安定している
- ホコリが少ない
一度決めたら、なるべく動かさない方が良いです。
重い作業は分散する
一度に負荷をかけすぎないことも大切です。
作業の工夫
- 動画編集とゲームを同時にしない
- 複数の重いアプリは順番に使う
- 長時間の作業は休憩を挟む
計画的に作業すれば、熱の蓄積を防げます。
古いパソコンは買い替えも検討
どうしても改善しない場合は、新しいパソコンも検討しましょう。
買い替えのサイン
- 5年以上使っている
- 常に熱い状態が続く
- 冷却システムが限界
- 修理費が高額
最新のパソコンは省電力で、発熱も少なくなっています。
温度を確認する方法
Windowsでの温度確認
専用ソフトを使って温度を測定できます。
おすすめソフト
- HWMonitor:無料、初心者向け
- Core Temp:CPU温度に特化
- MSI Afterburner:GPU温度の確認
これらのソフトで、各部品の温度をリアルタイムで確認できます。
Macでの温度確認
Macも専用アプリで確認可能です。
おすすめアプリ
- iStat Menus:有料だが高機能
- Macs Fan Control:無料、ファン制御も可能
メニューバーに温度を常時表示できて便利です。
適正温度の目安
何度くらいが正常なのでしょうか。
温度の目安
- アイドル時(何もしていない時)
- CPU:30~50℃
- GPU:30~50℃
- 負荷時(作業中)
- CPU:50~80℃
- GPU:60~85℃
- 危険域
- CPU:90℃以上
- GPU:95℃以上
危険域に達している場合は、すぐに対策が必要です。
よくある質問
常に熱いのは故障?
必ずしも故障とは限りません。
判断のポイント
- 温度が90℃を超えるなら異常
- 何もしていないのに熱いなら要注意
- 突然シャットダウンするなら危険
心配な場合は、専門店で診てもらいましょう。
ノートとデスクトップ、どちらが熱くなりやすい?
一般的に、ノートパソコンの方が熱くなりやすいです。
ノートPCが熱い理由
- 内部スペースが狭い
- 部品が密集している
- 冷却機構が小さい
- 薄型化で放熱が難しい
デスクトップは余裕があるため、冷却しやすいんです。
冷蔵庫で冷やすのはダメ?
絶対にやめましょう。
冷やしすぎの危険性
- 結露で内部が濡れる
- 基板がショートする
- 故障の原因になる
急激な温度変化は、むしろ有害です。
MacBookの底面が熱いのは正常?
MacBookは底面で放熱する設計です。
MacBookの特徴
- アルミ筐体全体がヒートシンク
- 底面が熱くなるのは正常動作
- ただし触れないほど熱いなら異常
「ほんのり温かい」程度なら問題ありません。
ゲーミングPCは常に熱い?
ゲーミングPCは高性能なため、発熱も大きいです。
ゲーミングPCの特徴
- 高性能なCPU・GPUを搭載
- 当然発熱も多い
- その分、冷却機構も強力
適切に冷却されていれば、問題ありません。
まとめ
パソコンが熱くなると重くなる理由について、詳しく解説しました。
この記事のポイント
- 熱くなると「サーマルスロットリング」で性能が制限される
- これは故障を防ぐための安全装置
- 室温、通気、ホコリが主な原因
- 掃除、冷却、設定変更で改善できる
- 定期的なメンテナンスが予防に効果的
パソコンの「熱い」と「重い」は、密接に関係しています。熱対策をすれば、自然と動作も軽快になるはずです。
まずは簡単にできる対策から始めてみましょう。通気を良くして、不要なアプリを閉じるだけでも、効果を実感できるはずですよ!






