パソコンを買う時に「メモリ8GB」「メモリ16GB」といった表記を見かけますよね。でも、メモリって実際何をしているのか、どれくらいあれば足りるのか、よく分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、パソコンのメモリについて、初心者の方でも分かりやすく解説していきます。メモリの役割から選び方まで、すべて詳しくお伝えしますね。
メモリって何?パソコンの「作業台」を理解しよう

メモリの基本的な役割
メモリとは、パソコンが作業をする時に使う「一時的な作業スペース」のことです。机の上で作業をする時を想像してみてください。
広い机があれば、たくさんの資料や道具を同時に広げて効率よく作業できますよね。逆に狭い机だと、必要な物を出したりしまったりで時間がかかってしまいます。
パソコンでも同じで、メモリが多いほど、たくさんのソフトを同時に快適に動かせるんです。
ストレージ(ハードディスク)との違い
よく混同されるのが、メモリとストレージ(ハードディスクなど)の違いです。
メモリ(RAM)
- 一時的な作業スペース
- 電源を切ると中身が消える
- 高速でデータを読み書きできる
ストレージ(HDD/SSD)
- 長期保存の倉庫
- 電源を切っても中身が残る
- メモリより読み書きが遅い
つまり、ストレージは「本棚」で、メモリは「机の上」という関係なんですね。
メモリの種類と規格について
DDR4とDDR5:現在の主流規格
現在のパソコンで使われているメモリには、主に以下の種類があります:
DDR4メモリ
- 2014年から普及している規格
- 安価で安定している
- 多くのパソコンで採用されている
DDR5メモリ
- 2021年から登場した新しい規格
- DDR4より高速で省電力
- まだ価格が高め
どちらも性能面では十分ですが、DDR5の方がより高速な処理が可能です。
メモリの容量:どれくらいあれば十分?
用途別の推奨メモリ容量をご紹介します:
4GB:最低限の使用
- インターネット閲覧
- 簡単な文書作成
- 軽いソフトの使用
8GB:一般的な使用
- 複数のソフトを同時使用
- 動画視聴
- 軽いゲーム
16GB:快適な使用
- 写真や動画の編集
- 重いゲーム
- プログラミング作業
32GB以上:専門的な使用
- 3DCG制作
- 動画編集(4K以上)
- 仮想マシンの運用
現在では、8GBが標準的で、16GBあれば大抵の作業は快適に行えます。
メモリ不足のサインと対処法
こんな症状はメモリ不足かも
以下のような現象が起きたら、メモリ不足の可能性があります:
動作が遅くなる
- ソフトの起動に時間がかかる
- ファイルを開くのが遅い
- 全体的にもっさりした動き
フリーズや強制終了
- ソフトが突然止まる
- 「メモリが不足しています」というエラー
- ブルースクリーンが表示される
メモリ使用量をチェックする方法
Windowsでメモリの使用状況を確認する方法をご紹介します:
タスクマネージャーを使う
- Ctrl + Shift + Escキーを同時に押す
- 「パフォーマンス」タブをクリック
- 「メモリ」を選択して使用率を確認
80%を超えて使用している場合は、メモリ不足の可能性が高いです。
メモリ不足の解決方法
一時的な対処法
- 使わないソフトを終了する
- 不要なタブを閉じる
- パソコンを再起動する
根本的な解決法
- メモリを増設する
- 軽いソフトに変更する
- 仮想メモリの設定を調整する
最も効果的なのは、やはりメモリの増設ですね。
メモリの増設:自分でできる?業者に頼む?
増設前の確認事項
メモリを増設する前に、以下を確認しましょう:
対応メモリの種類
- DDR4かDDR5か
- 最大容量の制限
- 動作周波数の対応範囲
空きスロットの確認
- メモリスロットの数
- 現在使用中のスロット
- 増設可能な容量
パソコンの保証 自分で増設すると、メーカー保証が無効になる場合があります。
自分で増設する場合の手順
必要な道具
- プラスドライバー
- 静電気防止手袋(推奨)
- 作業スペース
基本的な流れ
- 電源を完全に切る
- パソコンのケースを開ける
- メモリスロットを確認
- 新しいメモリを挿入
- ケースを閉じて動作確認
ただし、ノートパソコンの場合は分解が難しいことが多いです。
業者に依頼する場合
メリット
- 安全で確実
- 保証が継続される場合がある
- トラブル時のサポートあり
デメリット
- 費用がかかる
- 時間がかかる場合がある
不安な方は、パソコンショップや修理業者に相談することをおすすめします。
メモリに関するよくある疑問
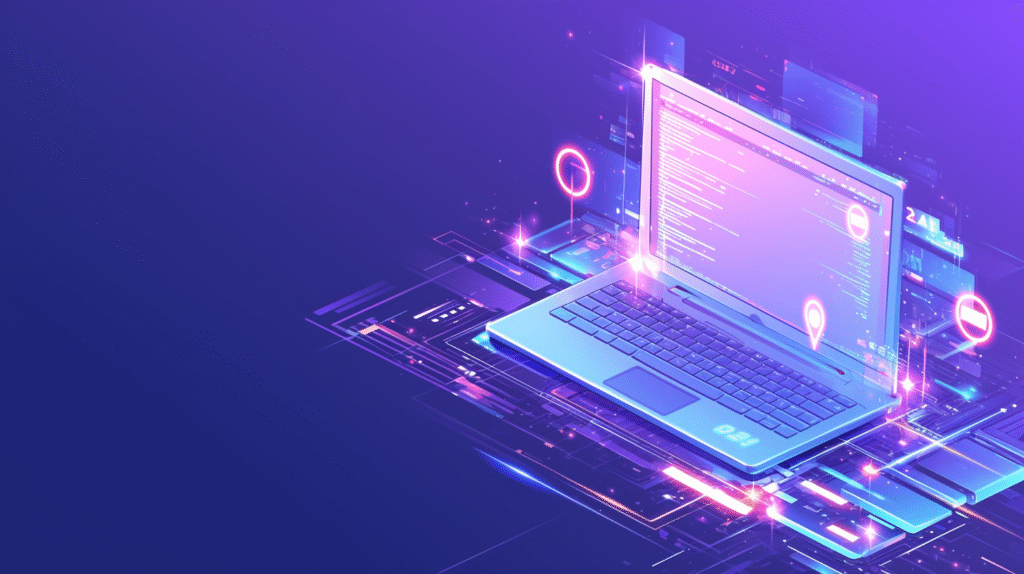
「メモリを増やすと電気代が上がる?」
メモリ自体の消費電力は非常に少ないため、電気代への影響はほとんどありません。むしろ、処理が高速化されることで、全体的な省電力効果が期待できます。
「違うメーカーのメモリを混在させても大丈夫?」
基本的には問題ありませんが、以下の点に注意が必要です:
- 同じ規格(DDR4/DDR5)であること
- 動作周波数が近いこと
- 可能であれば同じ容量にすること
最も安定するのは、同じメーカー・同じ型番のメモリを使うことですね。
「古いパソコンにメモリを増設する意味はある?」
5年以上前のパソコンでも、メモリ増設は効果的です。ただし:
- CPU性能が極端に低い場合は限界がある
- メモリ規格が古い場合は選択肢が少ない
- 費用対効果を検討する必要がある
一般的には、メモリ増設は最もコスパの良いパフォーマンス向上方法とされています。
将来を見据えたメモリ選び
ゲームや動画編集を始める予定がある場合
今は軽い作業しかしなくても、将来的に重い作業をする可能性があるなら、余裕を持って16GB以上を選んでおくと安心です。
長期間使用する予定の場合
パソコンを5年以上使う予定なら、ソフトウェアの進歩に対応するため、多めのメモリを搭載しておくことをおすすめします。
予算とのバランス
メモリは後から増設できることが多いので、最初は予算に合わせて選び、必要に応じて後から追加するのも一つの方法ですね。
まとめ:メモリを理解して快適なパソコンライフを
パソコンのメモリについて、基本から応用まで詳しく解説してきました。
重要なポイントをまとめると:
- メモリはパソコンの「作業台」で、多いほど快適
- 一般用途なら8GB、快適に使いたいなら16GBが目安
- メモリ不足の症状が出たら増設を検討
- 自分で増設できるが、不安なら業者に依頼
メモリは、パソコンの快適さを大きく左右する重要な部品です。適切な容量を選ぶことで、ストレスなくパソコンを使えるようになります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、基本を理解すれば、自分に最適なメモリ構成を選べるようになるでしょう。この知識を活用して、より快適なパソコン環境を整えてくださいね。







