インターネットで動画を見たり、友達とチャットしたり。
そんなとき、実は「モデム」という機器があなたのスマホやパソコンとインターネットの世界を繋いでいます。
家のルーターの近くにある四角い箱を見たことがあるでしょうか?
あれがモデムです。
この記事では、モデムがどうやってインターネットを家に届けているのか、その仕組みと歴史を分かりやすく解説していきます。
モデムの基本:デジタルとアナログの通訳者
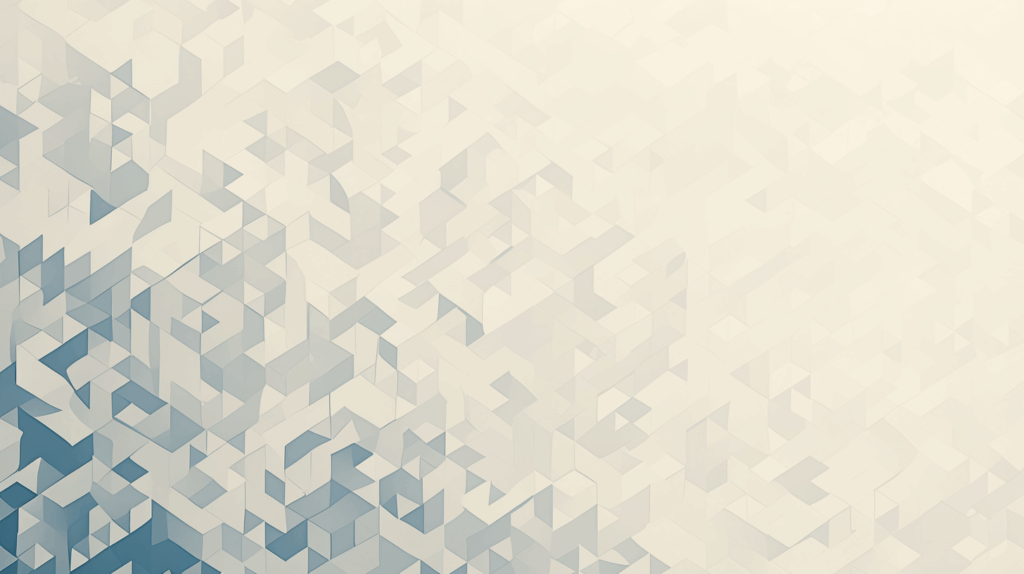
モデムという名前の由来
モデムとは「MOdulator(変調器)」と「DEModulator(復調器)」を組み合わせた言葉です。
1949年にMITリンカーン研究所で初めて開発されました。
簡単に言えば、コンピュータが使うデジタル信号と、電話線やケーブルで送られるアナログ信号を相互に変換する装置なんです。
なぜ信号の変換が必要なのか
コンピュータは0と1のデジタル信号で情報を処理します。
一方、電話線やケーブルは元々音声を伝えるために作られていました。
この音声はアナログ信号と呼ばれる、連続的に変化する信号です。
つまり、コンピュータと通信回線では使う「言語」が違うんですね。
そこで、モデムという「通訳者」が必要になるわけです。
変調と復調って何?
変調とは、デジタル信号(0と1の羅列)を、電話線などで送れるアナログ信号(連続的に変化する波の形)に変換することです。
復調は、その逆のプロセス。
受信したアナログ信号を元のデジタル信号に戻す処理を指します。
モデムはこの両方の機能を持っているため、送信と受信を同時に行える双方向通信が可能なんです。
モデムの動作原理:波に情報を乗せる技術
キャリア信号に情報を載せる
モデムの核心は「キャリア信号(搬送波)」という高周波の波に情報を載せる技術にあります。
キャリア信号には、3つの特性があります。
- 振幅:波の高さ
- 周波数:1秒間に波が繰り返す回数
- 位相:波の開始位置やタイミング
これらを変化させることで、データを伝えていくんです。
アナログ信号とデジタル信号の違い
デジタル信号は、時間と値の両方がとびとび(離散的)です。
0Vなら0、+5Vなら1のように、明確に区別された状態しか持ちません。
コンピュータや携帯電話の内部ではこの形式でデータが処理されています。
アナログ信号は、時間と値の両方が連続的。
理論上は無限の状態を取り得ます。
人間の声や音楽がこの形式で、自然界のほとんどの現象はアナログだと言えます。
なぜ電話線にはアナログ信号が必要だったのか
電話線は元々、人間の声を伝えるために設計されていました。
人間の声は300~3300Hz(ヘルツ)の周波数範囲です。
だから、デジタル信号をそのまま電話線に流すことはできません。
音声の周波数帯域に収まるアナログ信号に変換する必要があったんです。
変調方式の種類:情報を波に乗せる4つの方法
モデムが使う変調方式には、主に4種類あります。
それぞれ特徴が異なり、通信速度やエラーへの強さが変わってきます。
ASK(振幅偏移変調):明るさで信号を送る
ASK(Amplitude Shift Keying)は、波の高さ(振幅)を変えてデータを伝える最もシンプルな方法です。
例えば、波が高い=1、波が低い(またはゼロ)=0という具合に表現します。
懐中電灯で信号を送るのと似ています。
明るく光らせれば1、消せば0。
シンプルで実装しやすいのですが、ノイズ(雑音)の影響を受けやすいという欠点があります。
なぜなら、ノイズも振幅を変化させてしまうからです。
そのため、初期のモデムや光ファイバー通信では使われたものの、電話線のモデムではあまり使われませんでした。
FSK(周波数偏移変調):音の高さで伝える
FSK(Frequency Shift Keying)は、波の周波数(1秒間に繰り返す回数)を変えてデータを伝える方式です。
例えば、1270Hzの高い音=1、1070Hzの低い音=0という風に表現します。
これは音楽の音階に例えられます。
「ド」と「ミ」の音を使い分けて情報を送るようなものです。
ノイズで多少波形が乱れても、周波数の違いは判別できます。
そのため、ASKより信頼性が高いんです。
1960年代の初期のモデム(Bell 103、300bps)では、このFSK方式が使われていました。
ダイヤルアップ接続のときに聞こえた「ピーヒョロロ」という音。
あれは、まさにこのFSKによる通信音だったんです。
PSK(位相偏移変調):波の位置で情報を伝える
PSK(Phase Shift Keying)は、波の位相(波の開始位置やタイミング)を変えてデータを伝える方式です。
基本的なBPSK(Binary PSK)では、0度=1、180度=0のように2つの位相を使います。
さらに進化したQPSK(Quadrature PSK)では、4つの位相を使用。
0度、90度、180度、270度の4つですね。
1つのシンボル(信号の変化)で2ビットのデータを送れます。
時計の針の位置に例えると分かりやすいでしょう。
12時=00、3時=01、6時=10、9時=11という具合です。
PSKはFSKと同じ帯域幅でより多くのデータを送れます。
そのため、1980年代のモデム(V.22、1200bps)から採用されました。
ノイズにもそこそこ強く、効率も良い。
だから、WiFiや衛星通信など現代の通信技術でも広く使われています。
QAM(直交振幅変調):最強の組み合わせ技
QAM(Quadrature Amplitude Modulation)は、振幅と位相の両方を同時に変化させる最も高度な変調方式です。
2次元の信号空間を使うことで、1つのシンボルに大量の情報を詰め込めます。
16-QAMでは、4段階の振幅と4段階の位相を組み合わせます。
これで16通りの状態を作り、1シンボルで4ビットを送信できるんです。
64-QAMなら6ビット、256-QAMなら8ビット。
これは、旗の位置(位相)と明るさ(振幅)の両方を使って信号を送るセマフォ(手旗信号)に似ています。
QAMは1990年代の高速モデムで採用されました。
V.34で28.8kbps、V.90で56kbpsを実現。
現在のケーブルモデムやWiFi、4G/5Gスマートフォンでも使われています。
ただし、複雑な分だけノイズに弱く、高品質な回線が必要になります。
モデムの歴史:300bpsから光の速度まで
黎明期(1940~1970年代):音響カプラの時代
モデムの歴史は1941年まで遡ります。
連合国が開発したSIGSALY暗号化システムが起源です。
商業的なモデムは1958年にAT&TがBell 101(110bps)を発売したのが始まり。
1960年代、興味深い発明が登場しました。
音響カプラです。
当時、AT&Tは電話線への直接接続を独占していました。
他社の機器を繋ぐことが禁止されていたんです。
そこで、1963年にロバート・ワイトブレヒトが開発したのが音響カプラ。
これは電話の受話器をクレードル(台座)に置き、スピーカーとマイクを使って音響的に信号をやり取りする装置でした。
電気的な接続ではなく、音を使う。
まるで糸電話のような原始的な方法です。
でも、これが規制の抜け穴だったんですね。
1968年のカーターフォン判決でFCCが他社機器の接続を認めるまで、音響カプラが重要な役割を果たしました。
Bell 103A標準(300bps)が1962年に確立されます。
これが1980年代まで約20年間、標準速度として君臨しました。
300bpsでは、1MBのファイルをダウンロードするのに7時間以上かかります。
しかし、当時はタイプライター端末での文字通信が主でした。
だから、これでも十分だったわけです。
1980年代:パソコン革命とヘイズの登場
1981年、モデムの歴史を変える革命的な製品が登場します。
Hayes Smartmodem 300です。
ヘイズ社が開発した「ATコマンドセット」は画期的でした。
コンピュータがモデムを制御するための標準的な命令セットで、今でもIoTデバイスや携帯電話のモデムに使われています。
それまでのモデムは手動でダイヤルする必要がありました。
でも、Smartmodemはソフトウェアから自動ダイヤルができたんです。
これにより、BBS(電子掲示板システム)や自動接続が可能になりました。
現代的なネットワーク社会の基礎が築かれたわけですね。
速度も進化していきます。
1200bps(V.22、1980年)、2400bps(V.22bis、1984年)と順調に増加。
1987年頃には2400bpsモデムが200ドル以下で入手できるようになりました。
このスピードアップの鍵は、PSKからQAMへの移行でした。
1つの信号で複数ビットを送る技術により、同じ帯域幅でより多くのデータを伝送できるようになったんです。
1990年代:高速化の黄金時代
1990年代は、モデム技術が爆発的に進化した時代です。
1991年:V.32bis(14.4kbps)
ロックウェル社が399ドルという攻撃的な価格で発売。
年末には250ドルまで下がりました。
これが大衆化のきっかけとなります。
1994年:V.34(28.8kbps)
トレリス符号化変調という高度な技術により、電話回線の理論限界に近づきました。
1996年:V.34bis(33.6kbps)
アナログ電話回線の実質的な限界速度です。
そして1998年、V.90標準(56kbps)が登場します。
これは画期的な技術でした。
従来のモデムは、送信側と受信側の両方でアナログ↔デジタル変換を行っていました。
しかし1990年代後半、電話網はほぼ完全にデジタル化されていたんです。
ISP側が直接デジタル接続を持っていれば、ISPからユーザーへの下りデータは1回の変換(デジタル→アナログ)で済みます。
これにより理論上64kbps(電話網のデジタル音声規格DS0の帯域)まで速度を上げられました。
FCC規制により実際は53.3kbpsに制限されましたが、それでも33.6kbpsの約1.5倍。
ただし上りは従来通りアナログ接続なので33.6kbps(V.92では48kbps)に留まりました。
この非対称性が、56Kモデムの特徴だったんです。
2000年代以降:ブロードバンド時代への移行
1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ダイヤルアップの限界が明らかになりました。
56Kは物理的な限界であり、これ以上速くできません。
常に電話回線を占有するため通話ができない。
接続に30~60秒かかる。
動画や大容量ファイルのダウンロードには遅すぎる。
そこで登場したのがブロードバンド技術です。
ADSLの登場
ADSL(非対称デジタル加入者線)は、1991年にジョン・チオフィが最初のモデムを開発しました。
電話回線を使いながら、音声通話(0~4kHz)とデータ通信(20kHz~1MHz)を周波数分割で分離する技術です。
これにより、電話とインターネットを同時に使える「常時接続」が実現しました。
初期のADSLは最大8Mbps(56Kの約140倍)。
ADSL2+では最大24Mbpsに達しました。
2000年代前半、イギリスで最初の家庭向けブロードバンド(512kbps、月50ポンド)が登場。
しかし、普及には時間がかかりました。
2002年時点でイギリスのブロードバンド接続は約20万件(全世帯の1%未満)。
でも、2009年には約50%の世帯が採用するまでになったんです。
ケーブルモデムの台頭
ケーブルモデムは、既存のCATV(ケーブルテレビ)のインフラを活用しました。
DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification)という標準規格により、2000年代初頭から数十Mbps~数百Mbpsの高速通信が可能になりました。
光ファイバーの時代
光ファイバー(FTTH: Fiber To The Home)は、2010年代から本格的に普及し始めました。
銅線ではなくガラスや樹脂の光ファイバーケーブルを使い、光の点滅でデータを送ります。
初期は数百Mbps、現在では1Gbps~数Gbpsが一般的です。
距離による劣化もほとんどありません。
ダイヤルアップの終焉
ダイヤルアップは急速に衰退しました。
2000年に米国の家庭接続の74%を占めていたダイヤルアップ。
2006年には36%、2017年には0.3%まで減少。
2025年9月、AOLがダイヤルアップサービスを終了し、一つの時代が完全に幕を閉じました。
モデムの種類:用途に合わせた多様な選択肢
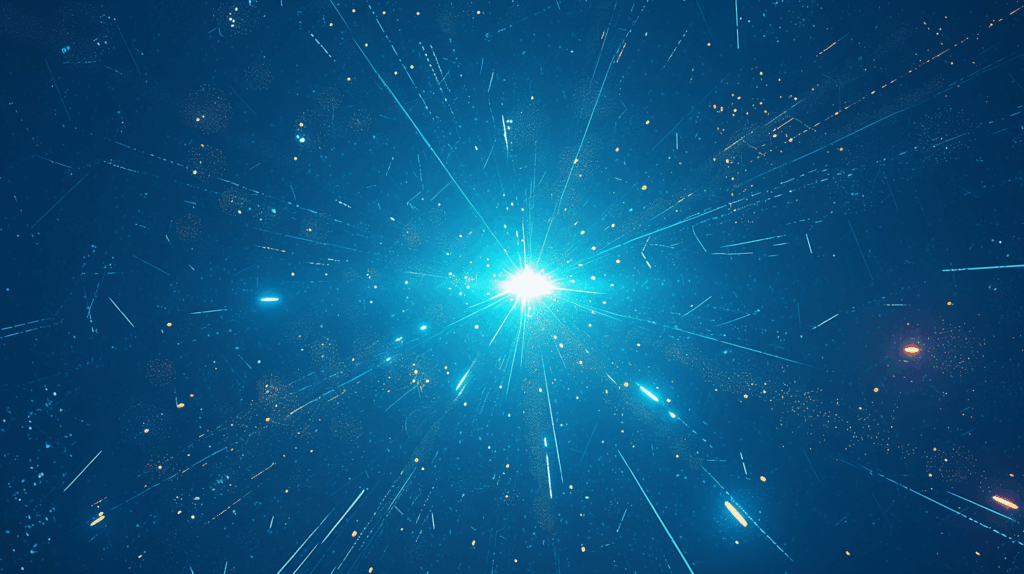
現代では、接続方法に応じて様々な種類のモデムが使われています。
ダイヤルアップモデム:過去の遺産
電話回線(PSTN: Public Switched Telephone Network)を使うアナログモデムです。
最大56kbps(実際は40~50kbps程度)の速度でした。
接続中は電話が使えないという致命的な欠点があり、現在ではほぼ使われていません。
ただし、極端に辺鄙な地域や、クレジットカードのPOS端末では今も現役です。
POS端末がダイヤルアップを使うのは、セキュリティと信頼性を重視しているからなんです。
DSLモデム:電話回線の進化系
ADSL/VDSLは、既存の電話回線(銅線)を使いながら高速通信を実現する技術です。
音声用の低周波数帯(0~4kHz)とデータ用の高周波数帯(20kHz以上)を分離します。
これにより、電話とインターネットの同時使用が可能になりました。
速度の比較
- ADSL:最大24Mbps(ダウンロード)、1.3Mbps(アップロード)
- VDSL2:最大100Mbps(対称)、ただし距離制限が厳しい(約1.4km以内)
- G.fast:最大1Gbps(500m以内)
DSLの最大の利点は、既存の電話インフラをそのまま使える点です。
欠点は、電話局からの距離で速度が大きく低下すること。
5km以上離れると、速度が大幅に落ちてしまいます。
ケーブルモデム:テレビ線でインターネット
ケーブルテレビ用の同軸ケーブルを使ってインターネットに接続するモデムです。
DOCSIS規格に準拠しています。
DOCSISの進化
- DOCSIS 3.0(2013年):最大1Gbps(ダウンロード)、200Mbps(アップロード)
- DOCSIS 3.1(現行標準):最大10Gbps(ダウンロード)、1~2Gbps(アップロード)
- DOCSIS 4.0(2024年から展開開始):最大10Gbps(ダウンロード)、6Gbps(アップロード)
DOCSIS 3.1は、OFDM(直交周波数分割多重)と4096-QAMという高度な変調技術を使います。
一般家庭でも数百Mbps~2Gbps程度の実用速度を実現しています。
DOCSIS 4.0では、上りの速度が大幅に向上。
光ファイバーに匹敵する対称通信が可能になる見込みです。
ケーブルモデムの利点は高速で安定している点。
欠点は近隣住民と帯域を共有するため、夕方など混雑時に速度が低下することがあります。
光モデム(ONU/ONT):最速の選択
光ファイバーを家まで直接引き込むFTTH方式では、ONT(Optical Network Terminal、光回線終端装置)またはONU(Optical Network Unit)と呼ばれる機器が使われます。
厳密にはモデムではなく、光信号と電気信号を変換する装置です。
PON(Passive Optical Network、受動光ネットワーク)というアーキテクチャが一般的。
ISP側のOLT(Optical Line Terminal)と各家庭のONTを光ファイバーで繋ぎます。
途中の分岐器(スプリッタ)は電源不要の受動素子なので、故障が少なく保守コストが低いんです。
PONの種類と速度
- GPON(標準):2.5Gbps(下り)、1.25Gbps(上り)を最大128世帯で共有
- XGS-PON:10Gbps(対称)
- 25G PON(2024年から展開):25Gbps(実効10Gbps)
- 100G PON(研究段階):100Gbps、将来的な展開予定
光ファイバーの利点
- 圧倒的な速度
- 距離による劣化がほぼゼロ
- 対称通信(上りと下りが同じ速度)
- 超低遅延(レイテンシ)
- 電磁干渉に強い
光ファイバーの欠点
- 敷設コストが高い(1軒あたり10~30万円以上)
- 工事に時間がかかる
その他のモデム
セルラーモデム(4G/5G)
携帯電話のネットワークを使ってインターネットに接続します。
固定回線がない場所や、移動中の通信に便利です。
速度の比較
- 4G LTE:5~50Mbps(実用速度)、最大1Gbps(理論値)
- 5G:100~500Mbps(ミッドバンド)、最大3.4Gbps(ミリ波)、遅延10~20ミリ秒
5Gセルラーモデムは、IoT(モノのインターネット)デバイスで急成長しています。
コネクテッドカー(399百万台が2025年までに接続予定)、スマートシティ、産業機器などで使われています。
セルラーIoTモデムの出荷台数は2024年に4.26億台。
売上56億ドルに達し、前年比10%成長しました。
衛星モデム
地上のインフラがない極めて僻地や海上、災害時の緊急通信で使われます。
衛星モデムの種類
- 従来型GEO衛星(高度35,786km):25~150Mbps、遅延約600ミリ秒(往復で地球2.4周分の距離)
- 現代型LEO衛星(Starlinkなど、高度500~2000km):50~250Mbps、遅延25~60ミリ秒
GEO衛星は遅延が大きすぎてオンラインゲームや動画通話には不向きです。
でも、LEO衛星は地上回線に近い使用感を実現しています。
通信速度の進化:指数関数的な成長
モデムの速度は、過去60年間で驚異的な進化を遂げました。
速度の歴史
| 年代 | 標準規格 | 速度 | 主な技術 |
|---|---|---|---|
| 1958-1962 | Bell 101, 103 | 110-300 bps | FSK |
| 1980 | V.21, V.22 | 300-1200 bps | PSK |
| 1984 | V.22bis | 2400 bps | QAM |
| 1988-1991 | V.32, V.32bis | 9600-14,400 bps | QAM、エコーキャンセラー |
| 1994 | V.34 | 28,800 bps | トレリス符号化変調 |
| 1996 | V.34bis | 33,600 bps | 高度なQAM |
| 1998 | V.90 | 56,000 bps | PCM(下りのみ) |
| 2000 | V.92 | 56,000/48,000 bps | PCM(上りも改善) |
| 2000年代~ | ADSL/VDSL | 8~100 Mbps | DMT、ベクタリング |
| 2000年代~ | DOCSIS 3.0/3.1 | 100 Mbps~2 Gbps | QAM、OFDM |
| 2010年代~ | GPON/XGS-PON | 1~10 Gbps | 光通信 |
1958年の110bpsから2025年の10Gbps以上まで。
約100万倍の速度向上が達成されました。
これは、わずか70年弱の間に起きた変化なんです。
速度向上を支えた技術革新
- 変調方式の高度化(FSK→PSK→QAM→高次QAM)
- エコーキャンセレーション(同じ周波数で双方向通信)
- トレリス符号化(誤り訂正と変調の融合)
- デジタル信号処理(DSP)
- 光ファイバーへの移行
ボーレート、ビットレート、誤り訂正:技術的な詳細
ボーレートとビットレートの違い
初心者が混同しやすい概念が、ボーレートとビットレートです。
ボーレート(Baud rate)
1秒間に信号が何回変化するかを示す単位。
「シンボル/秒」とも呼ばれます。
エミール・ボドー(19世紀のフランスの発明家)の名前に由来しています。
ビットレート(Bit rate)
1秒間に実際に送られるデータの量(ビット数)を示す単位。
bps(bits per second)で表されます。
計算式
ビットレート = ボーレート × 1シンボルあたりのビット数
具体例で理解しよう
初期のモデム(FSK)
- ボーレート:300
- 1シンボル:1ビット
- ビットレート:300bps
V.27ter(QPSK)
- ボーレート:2400
- 1シンボル:2ビット
- ビットレート:4800bps
V.32(16-QAM)
- ボーレート:2400
- 1シンボル:4ビット
- ビットレート:9600bps
バスの例えで理解する
- ボーレート:1時間あたりのバスの本数(例:100台/時)
- 1シンボルあたりのビット数:1台のバスが運べる乗客数(例:20人/台)
- ビットレート:1時間あたりの総乗客数(100×20=2000人/時)
なぜ1シンボルに複数ビットを詰め込むのか
電話回線には帯域幅(周波数範囲)の制限があります。
ナイキスト定理により、帯域幅Wヘルツの回線では、最大2Wシンボル/秒しか送れません。
音声電話回線は約3000Hz(300~3300Hz)。
だから、実用上は約3000ボーまでしか使えないんです。
それ以上速くするには、1つのシンボルに複数ビットを詰め込むしかありません。
これがQAMなどの多値変調が発展した理由です。
現代のモデムは、数千ボーで数万~数百万bpsを実現しています。
誤り訂正の技術
通信回線にはノイズ(雑音)が必ず混入します。
だから、誤り訂正技術が不可欠なんです。
誤り検出の方法
パリティチェック
最も単純な方法です。
データに1ビット追加し、1の個数が偶数か奇数かをチェックします。
1ビットエラーは検出できますが、訂正はできません。
チェックサム
データを複数の区画に分け、合計値を計算して付加します。
CRC(巡回冗長検査)
多項式除算を使う高度な検出方式。
バースト誤り(連続した誤り)に強いのが特徴です。
誤り訂正の方法
ARQ(自動再送要求)
エラーを検出したら送信側に再送を要求します。
ダイヤルアップモデムのV.42プロトコルなどで使用されています。
FEC(前方誤り訂正)
冗長ビットを追加し、受信側だけでエラー訂正できるようにします。
FECの代表的な手法
ハミング符号
1ビットエラーを訂正、2ビットエラーを検出できます。
リードソロモン符号
CDやDVD、DSLモデム、デジタルテレビで使用。
複数ビットのバースト誤りに強いのが特徴です。
畳み込み符号
ビットストリームに対してエンコーダーのメモリを使います。
高速モデムのトレリス符号化変調で使用されています。
ターボ符号
3G/4G携帯電話、深宇宙通信で使用。
シャノン限界に迫る高性能を実現しています。
LDPC符号
WiFi(802.11n/ac)、5G、10Gbit Ethernetで使用。
シャノン限界に非常に近い性能です。
モデムでの実装
モデムでは、MNP(Microcom Networking Protocol)やV.42/V.44といった標準プロトコルで誤り訂正が実装されています。
V.42はCRCベースのエラー検出と自動再送を提供。
V.44はデータ圧縮(最大6:1)を提供します。
53.3kbpsのモデムでも圧縮可能なテキストなら実効320kbpsを達成できました。
モデムとルーターの違い:最もよくある誤解
モデムとルーターを混同している人は非常に多い。
実際、この二つは全く異なる役割を持つ装置です。
モデム:インターネットへの入口
モデムは、あなたの家とISP(インターネット・サービス・プロバイダー)を繋ぐ装置です。
ISPのネットワーク(WAN: Wide Area Network、広域ネットワーク)と家庭のネットワーク(LAN: Local Area Network)の間で、信号形式を変換します。
まさに「翻訳者」の役割ですね。
モデムの種類別の役割
- ケーブルモデム:同軸ケーブルのRF信号をイーサネット信号に変換
- DSLモデム:電話線のアナログ信号をイーサネット信号に変換
- ONT/ONU:光ファイバーの光信号を電気信号に変換
モデムには通常、1つの出力ポート(イーサネット)しかありません。
だから、1台のデバイス(普通はルーター)しか直接接続できないんです。
モデムはISPから割り当てられたグローバルIPアドレスを持ちます。
ルーター:家庭内ネットワークの管理者
ルーターは、家庭内に複数のデバイスを繋ぐネットワークを作り、インターネット接続を分配する装置です。
ルーターの主な機能
- 複数のデバイス(パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機など)を同時にインターネットに接続
- 各デバイスにローカルIPアドレスを割り当て(DHCP)
- データを適切な宛先にルーティング(経路選択)
- ファイアウォールでセキュリティを提供
- NAT(Network Address Translation)で、1つのグローバルIPを複数のデバイスで共有
現代のWiFiルーターには、様々な機能が統合されています。
無線アクセスポイント(WiFi電波を発信)、イーサネットスイッチ(有線LAN接続用の複数ポート)、ファイアウォールなどです。
ゲートウェイ:一体型デバイス
最近増えているのが、ゲートウェイ(モデム・ルーター一体型)です。
これは1台の箱にモデムとルーターの機能を両方詰め込んだ装置。
ISPからレンタルされることも多いですね。
ゲートウェイのメリット
- 設定が簡単(1台だけ)
- 配線がシンプル
- コンセント1つで済む
- 初期費用が安い
- ISPのサポートが受けられる
ゲートウェイのデメリット
- 高度な機能が制限されることがある
- 片方だけアップグレードできない
- 故障すると両方の機能が使えなくなる
- ISPのレンタル料(月1000~2000円程度)が永続的にかかる
技術に詳しいユーザーは、別々のモデムとルーターを購入することが多いです。
初期費用は2万~5万円程度かかります。
でも、1~2年でレンタル料の元が取れ、長期的には節約になるんです。
さらに、最新のWiFi 6/WiFi 7ルーターや、ゲーミング向けの高性能ルーターを自由に選べる利点があります。
現代のインターネット接続におけるモデムの役割
2024~2025年現在、モデムは依然としてインターネットインフラの重要な構成要素です。
「光ファイバー時代にモデムは不要になるのでは?」と思うかもしれません。
でも、実際にはそうなっていないんです。
なぜモデムが今も必要なのか
インフラの多様性
全ての家庭に光ファイバーが引かれているわけではありません。
アメリカでは約90%の世帯がケーブルブロードバンドにアクセスできます。
だから、ケーブルモデムが必要なんです。
信号変換の必然性
光ファイバーでも、光信号を電気信号に変換するONT(一種のモデム)が不可欠。
経済的理由
既存の同軸ケーブルや電話線のインフラを活用する方が、全面的に光ファイバーに置き換えるより遥かに安価です。
技術の進化
DOCSIS 4.0やG.fastにより、既存インフラで1Gbps以上を実現できます。
そのため、光ファイバーへの移行圧力が減少しているんです。
モデム市場の現状と将来
モデム市場は堅調に成長しています。
市場規模の予測
- 全体市場:2023年に105.1億ドル、2030年には144.5億ドル(年平均成長率4.6%)と予測
- ビジネス向けモデム:2024年に56.8億ドル、2037年には594.7億ドル(年平均成長率19.8%)と急成長予測
- セルラーIoTモデム:2024年に4.26億台出荷、売上56億ドル(前年比10%増)
この成長の原動力は、IoT(モノのインターネット)の爆発的普及です。
コネクテッドカー(2025年までに3.99億台)、スマートシティ、産業オートメーション、遠隔医療。
あらゆる分野でモデムが必要とされています。
家庭での典型的なセットアップ(2025年)
ケーブルインターネットの場合
- 壁の同軸ケーブル端子
- DOCSIS 3.1ケーブルモデム(購入:14,000~28,000円、またはレンタル:月1,400円)
- WiFi 6/WiFi 7ルーター(12,000~40,000円)
- イーサネットケーブルでモデムとルーターを接続
- 各デバイスをWiFiまたは有線LANで接続
光ファイバーの場合
- 家に引き込まれた光ファイバーケーブル
- ONT/ONU(ISP提供、レンタルまたは無料貸与)
- ルーター(ISP提供または自前)
- ONTとルーターをイーサネットケーブルで接続
- 各デバイスを接続
光ファイバーは対称速度(上りと下りが同じ)、超低遅延、距離による減衰がない、という利点があります。
一方、ケーブルは広く普及しており、DOCSIS 4.0で光に匹敵する速度を実現しつつあります。
まとめ:モデムはインターネットの縁の下の力持ち
モデムは、1949年の発明から75年以上経った今も、インターネット接続に欠かせない装置です。
デジタル信号とアナログ信号、あるいは光信号と電気信号を相互変換。
私たちのデバイスをISPのネットワークに繋いでいます。
この記事で学んだ重要なポイント
モデムの基本
- モデムは「MOdulator-DEModulator(変調器-復調器)」の略
- 信号変換装置として機能する
変調方式の進化
- ASK(振幅)、FSK(周波数)、PSK(位相)、QAM(振幅+位相)
- 技術の進化により高速化を実現
驚異的な速度向上
- 300bpsから56Kbps(約180倍)
- さらにブロードバンドで数万倍へ
多様なモデムの種類
- ダイヤルアップ、DSL、ケーブル、光ファイバー、セルラー、衛星
- 用途に応じて使い分けられている
技術的な理解
- ボーレート(信号変化の回数)とビットレート(実際のデータ量)は異なる
- 1シンボルに複数ビットを詰め込むことで高速化
- 誤り訂正技術(パリティ、CRC、ハミング符号、リードソロモン符号など)により信頼性を確保
モデムとルーターの違い
- モデムはISPとの接続を担当
- ルーターは家庭内ネットワークを管理
最新技術と将来展望
- DOCSIS 4.0、G.fast、25G PONなど最新技術が展開中
- IoT、コネクテッドカー、産業用途でセルラーモデム市場が急成長
最後に
モデムは目立たない存在かもしれません。
でも、私たちの日常生活を支える重要なインフラです。
動画を見るとき、ゲームをするとき、友達とメッセージをやり取りするとき。
その背後ではモデムが黙々と信号を変換し続けています。
技術の進化により、モデムはこれからも形を変えながら、私たちのデジタルライフを支え続けるでしょう。







