コンピュータやネットワーク関連の説明書を読んでいると、「マスター」「スレーブ」という言葉を見かけることがありますよね。
マスター/スレーブとは、コンピュータ技術において、制御する側(マスター)と制御される側(スレーブ)の関係を表す用語です。
簡単に言えば:
- マスター(Master):指示を出す「親分」のような存在
- スレーブ(Slave):指示に従う「子分」のような存在
この関係性は、ハードディスクの接続設定、データベースの構成、通信プロトコルなど、様々な場面で使われてきました。
ただし、この用語は近年、社会的・倫理的な配慮から見直しが進んでおり、代替用語への移行が進んでいます。
この記事では、マスター/スレーブの技術的な意味と使われ方、そして現代における用語の変化まで、分かりやすく解説していきますね。
マスター/スレーブの基本概念
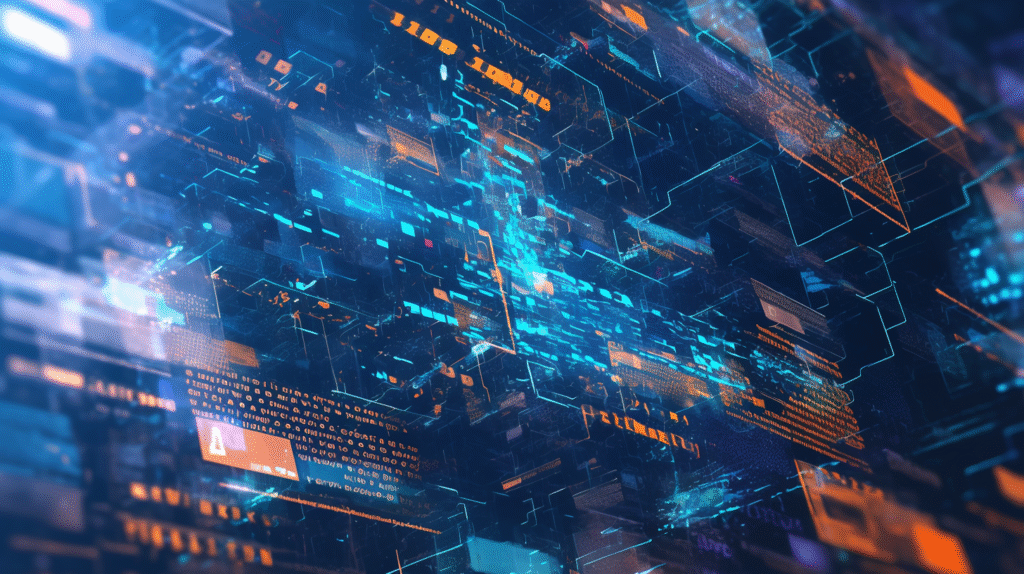
制御関係の仕組み
マスター/スレーブ構成では、明確な役割分担があります。
マスターの役割:
- 全体の制御と指示を担当
- スレーブに命令を送る
- データの流れを管理
- 優先的に動作する
スレーブの役割:
- マスターの指示に従う
- マスターからの命令を待つ
- 指示された通りに動作
- 単独では動作しない(場合が多い)
なぜこの構成が必要なのか
複数のデバイスやシステムが協調して動作する際、誰かが「リーダー」になって全体を管理する必要があります。
具体例:
オーケストラに例えると、指揮者がマスター、演奏者がスレーブのような関係です。
指揮者が全体をコントロールし、演奏者はその指示に従って演奏します。このように役割を分担することで、調和の取れた演奏が実現できるんです。
マスター/スレーブが使われる技術分野
1. ハードディスク接続(IDE/PATA)
最もよく知られているのが、古いタイプのハードディスク接続での使用例です。
IDE/PATA接続の特徴
PATA(旧称IDE)規格では、1本のケーブルに2台のドライブを接続できました。
この2台をどう区別するか?その方法がマスター/スレーブ設定だったんです。
設定方法:
ハードディスクの背面には、小さなピン(ジャンパーピン)があります。
このピンの位置を変えることで、ドライブを「マスター」または「スレーブ」に設定できました。
動作の仕組み:
- マスタードライブ:優先的にアクセスされる
- スレーブドライブ:マスターの後に認識される
- 起動ディスク(OSが入っている)は通常マスターに設定
注意点:
設定を間違えると、どちらか一方、または両方が認識されないトラブルが発生していました。
2. データベースのレプリケーション
大規模なWebサービスでは、データベースのマスター/スレーブ構成がよく使われています。
マスターデータベース:
- データの書き込み(更新・追加・削除)を担当
- 正式なデータの保管場所
- 常に最新の状態を維持
スレーブデータベース:
- マスターのデータをコピー(複製)
- データの読み取り専用として使用
- 負荷分散に貢献
メリット:
大量のユーザーがデータを読み取る際、スレーブを複数用意することで負荷を分散できます。
例えば、1台のマスターと3台のスレーブがあれば、読み取り処理を4台で分担できるんです。
実例:
ショッピングサイトで、商品情報を見るのはスレーブから、注文するのはマスターに書き込む、という使い分けができます。
3. 通信プロトコル
I²C(アイ・スクエアド・シー)やSPI(エスピーアイ)といった通信方式でも、マスター/スレーブの概念が使われています。
I²C通信の例:
- マスター:通信を開始し、クロック信号を生成
- スレーブ:マスターの信号に応答
マイコンボードとセンサーを接続する際、マイコンがマスター、センサーがスレーブとなります。
4. フリップフロップ回路
電子回路の世界でも、マスター/スレーブの概念が使われます。
マスタースレーブ型フリップフロップ:
デジタル回路で使われる記憶素子の一種。
マスター部分で一時的にデータを保持し、スレーブ部分に転送することで、安定した動作を実現します。
5. ハードウェア制御
USB接続
USBでは、パソコン側がホスト(マスター)、接続された機器がデバイス(スレーブ)として動作します。
RAID構成
複数のハードディスクを組み合わせるRAIDシステムでも、コントローラーがマスター的な役割を果たします。
マスター/スレーブの実際の設定方法
IDE/PATAハードディスクの設定
古いパソコンのハードディスク設定を例に、具体的な手順を見てみましょう。
ジャンパーピンの位置
ハードディスクの背面には、次のような設定があります:
- Master(マスター):ジャンパーピンを特定の位置に差す
- Slave(スレーブ):別の位置に差す
- Cable Select(ケーブルセレクト):ケーブルの接続位置で自動判別
設定の基本ルール:
- 1台だけ接続する場合:マスターに設定
- 2台接続する場合:起動ディスクをマスター、もう1台をスレーブに設定
- ケーブルセレクト:対応ケーブルなら自動的に判別
ジャンパーピンの操作:
小さなプラスチック製のキャップ(ジャンパー)を、ピンの正しい位置に差し込みます。
ドライブの表面に印刷された図を見ながら、慎重に設定しましょう。
トラブルシューティング:
設定を間違えると、次のような問題が起こります:
- 両方ともマスターに設定:片方または両方が認識されない
- 両方ともスレーブに設定:どちらも認識されない
- ジャンパーが外れている:予期しない動作
データベースのマスター/スレーブ設定
MySQLなどのデータベースでは、設定ファイルを編集してレプリケーションを構成します。
基本的な流れ:
- マスターサーバーでバイナリログを有効化
- スレーブサーバーでマスターの接続情報を設定
- レプリケーションを開始
これは開発者向けの高度な設定ですが、マスター/スレーブの考え方は同じです。
マスター/スレーブの利点と欠点
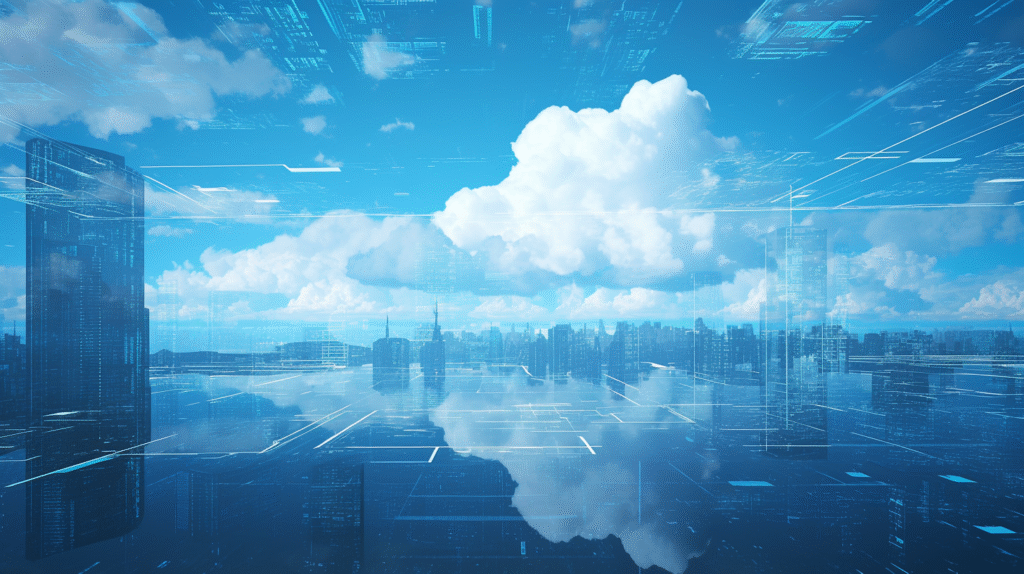
利点
1. 明確な制御構造
どちらが制御する側か、一目瞭然です。
システムの設計や理解が容易になります。
2. シンプルな実装
複雑な調整が不要で、実装しやすい構造です。
3. 効率的なリソース利用
データベースのレプリケーションでは、読み取り処理を複数のスレーブで分散できます。
4. 冗長性の確保
マスターに問題が発生しても、スレーブを昇格させることで継続運用が可能です。
欠点
1. マスターが単一障害点になる
マスターが故障すると、システム全体が停止する可能性があります。
2. マスターの負荷集中
書き込み処理はすべてマスターで行うため、負荷が集中します。
3. データの遅延
マスターからスレーブへのデータ同期に時間がかかることがあります。
4. 設定の複雑さ
古いハードディスクでは、ジャンパーピンの設定ミスがトラブルの原因になりました。
用語の変化:より適切な表現へ
なぜ用語の見直しが必要なのか
「マスター(主人)」と「スレーブ(奴隷)」という言葉は、歴史的に奴隷制度を連想させます。
技術用語として使われてきましたが、近年、社会的・倫理的な配慮から、より中立的な用語への置き換えが進んでいます。
代替用語の例
技術分野ごとに、様々な代替用語が提案・採用されています。
一般的な代替用語:
- Primary / Secondary(プライマリ / セカンダリ):主要 / 副次
- Main / Replica(メイン / レプリカ):本体 / 複製
- Leader / Follower(リーダー / フォロワー):先導 / 追従
- Controller / Peripheral(コントローラー / ペリフェラル):制御装置 / 周辺機器
- Parent / Child(ペアレント / チャイルド):親 / 子
分野別の例:
データベース:
- Primary / Replica
- Source / Replica
- Active / Standby
Git(バージョン管理システム):
- Main / Branch(かつての master から main へ変更)
ハードディスク接続:
- 現在のSATAでは、マスター/スレーブの概念自体が不要
技術業界の動き
主要企業の取り組み:
- GitHub:デフォルトブランチ名を「master」から「main」に変更
- Python:関連用語の置き換えを推奨
- Linux Kernel:代替用語の使用を推進
- MySQL:レプリケーション用語の見直し
国際標準化団体の動き:
IETFやIEEEなどの標準化団体も、用語の見直しを進めています。
過渡期における注意点
現在は移行期間中のため、両方の用語が混在しています。
古い文献や機器:
従来の用語で説明されていることがあります。
新しいシステム:
代替用語が使われていることが増えています。
どちらの用語も理解しておくことで、古い資料と新しい情報の両方に対応できますね。
現代におけるマスター/スレーブ構成の実例
クラウドサービスでの活用
Amazon RDS(データベースサービス)
マスターインスタンスと読み取りレプリカ(スレーブ)の構成が可能です。
ただし、用語は「Primary」と「Read Replica」に変更されつつあります。
負荷分散の実現:
読み取りが多いアプリケーションでは、複数のレプリカを配置して負荷を分散します。
産業用機器
PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラー)
工場の自動化システムでは、マスターPLCが複数のスレーブデバイスを制御します。
通信プロトコル:
Modbus通信などで、マスター/スレーブ方式が使われています。
音楽制作の同期
MIDI Clock
複数の音楽機器を同期させる際、マスタークロックを送信する機器と、それに同期する機器(スレーブ)があります。
用途:
シーケンサー、ドラムマシン、シンセサイザーなどを同時に演奏する際に使用します。
マスター/スレーブに関するよくある疑問
Q1:SATAではマスター/スレーブ設定が不要なのはなぜ?
A:1本のケーブルに1台しか接続しないためです
SATA規格では、各ドライブが独立したケーブルで接続されます。
そのため、マスター/スレーブの区別が不要になりました。
Q2:古いIDEハードディスクを使いたいが、設定が分からない
A:ドライブの表面に印刷された図を確認しましょう
多くの場合、ドライブのラベルにジャンパーピンの設定図が印刷されています。
見つからない場合は、メーカーの公式サイトでマニュアルを探してみてください。
Q3:データベースのスレーブから書き込みはできない?
A:基本的にはできません
読み取り専用レプリカとして設定されている場合、書き込みはエラーになります。
書き込みはマスター(プライマリ)で行う必要があります。
Q4:マスターとスレーブを入れ替えることはできる?
A:フェイルオーバーとして可能です
データベースのレプリケーションでは、マスターに障害が発生した際、スレーブをマスターに昇格させることができます。
これを「フェイルオーバー」と呼びます。
Q5:すべての技術分野でマスター/スレーブという用語は廃止されるの?
A:徐々に移行が進んでいますが、完全な廃止には時間がかかります
既存のシステムや古い機器では従来の用語が残ります。
新しいシステムでは代替用語が採用される傾向にあります。
まとめ:マスター/スレーブは制御関係を表す技術用語
マスター/スレーブは、制御する側と制御される側の関係を表す技術用語です。
この記事のポイント:
✅ 基本概念
マスターが指示を出し、スレーブがそれに従う明確な制御関係
✅ 主な使用分野
IDE/PATA接続、データベースレプリケーション、通信プロトコル、電子回路など
✅ 利点
明確な制御構造、シンプルな実装、効率的なリソース利用
✅ 欠点
マスターが単一障害点、負荷の集中、データ遅延の可能性
✅ 設定方法
IDEではジャンパーピン、データベースでは設定ファイルで管理
✅ 用語の変化
社会的配慮から、Primary/Secondary、Main/Replicaなどの代替用語へ移行中
✅ 現代の状況
古い用語と新しい用語が混在する過渡期
技術用語としてのマスター/スレーブは、長年にわたって使われてきました。
しかし、より包括的で中立的な表現への移行が進んでいます。古い資料や機器を扱う際には従来の用語を理解しつつ、新しいシステムでは代替用語を使うという柔軟な対応が求められています。
また、SATAなど新しい技術では、マスター/スレーブの概念自体が不要になっているケースもあります。
技術の進化とともに、用語も社会の変化に合わせて更新されていくんですね。
これからパソコンの組み立てやデータベースの構築を学ぶ方は、両方の用語を知っておくことで、古い情報と新しい情報の両方を理解できるようになるでしょう。







