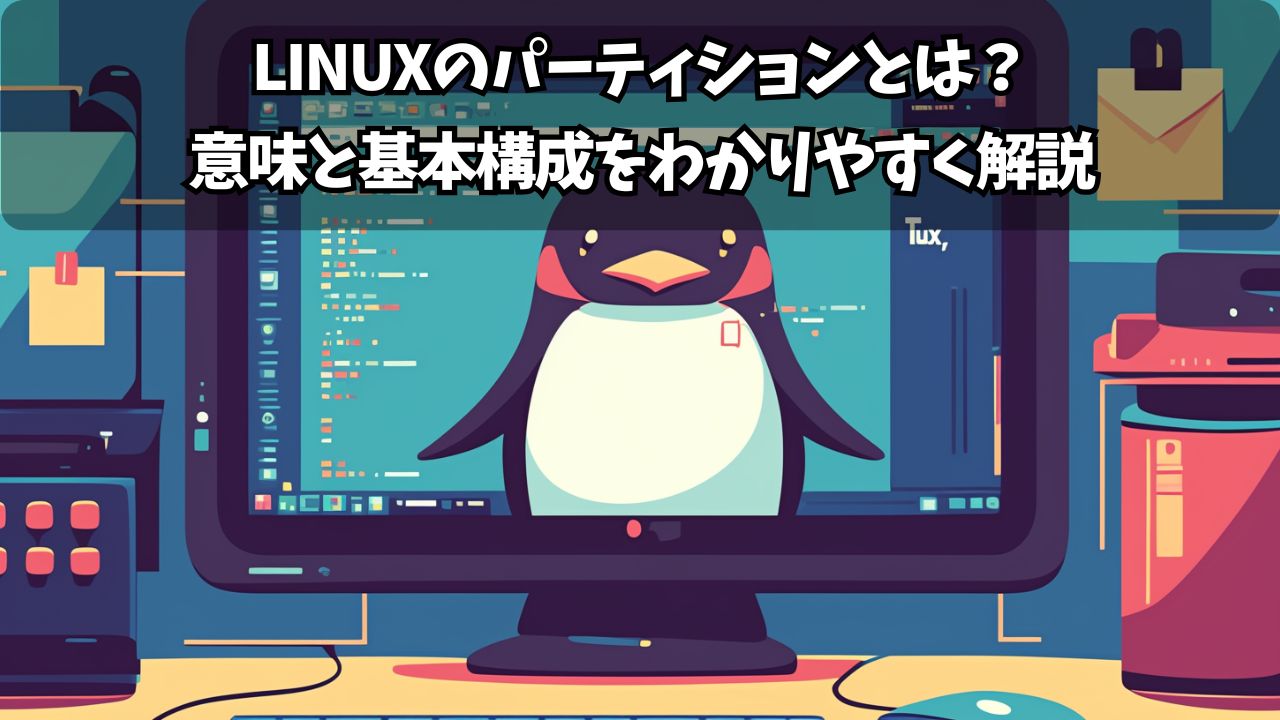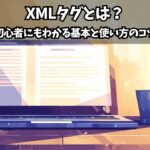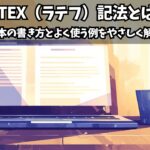「Linuxをインストールしようとしたらパーティションを決める画面が出てきたけど、何をどうすればいいのかわからない」
「/とか/homeとか、なんで日本語じゃないの?」
「swapって何?どれくらい必要なの?」
Linuxを始めようとして、こんなふうに悩んだ経験はありませんか?
Linuxではパーティションの設定がとても重要です。適当に決めると後から困ることも多いため、基本をしっかり理解しておきましょう。
この記事では、初心者の方にもわかるように、パーティションの意味からLinuxならではの考え方、実際の設定方法までやさしく解説します。
パーティションとは?まずは基本から理解しよう

パーティションの基本的な意味
パーティション(Partition)とは、ハードディスクやSSDを「仮想的に分けた領域」のことです。
身近な例で考えてみましょう:
一つの大きな本棚を、用途別に区切って使うイメージです。
┌─────────────────────────────┐
│ 本棚(1TB のハードディスク) │
├─────────────────────────────┤
│ 教科書エリア (300GB) │ ← パーティション1
├─────────────────────────────┤
│ 小説エリア (400GB) │ ← パーティション2
├─────────────────────────────┤
│ 雑誌エリア (300GB) │ ← パーティション3
└─────────────────────────────┘
たとえば1TBのディスクを:
- Cドライブ:500GB
- Dドライブ:500GB
に分けるのも、パーティションを作っているからできることです。
パーティションを分ける理由
なぜわざわざ分けるの?
- データの整理: 用途別に分けることで管理しやすくなる
- トラブル対策: 一部の領域に問題が起きても、他に影響しにくい
- バックアップの効率化: 重要なデータだけ別パーティションにしてバックアップ
- パフォーマンス向上: アクセス頻度に応じて最適化
WindowsとLinuxのパーティション:何が違うの?

Windowsのパーティション構成
Windowsでは一般的に:
| ドライブ | 用途 | 容量例 |
|---|---|---|
| Cドライブ | OSとプログラム | 250GB |
| Dドライブ | ユーザーデータ | 750GB |
このように「ドライブレター」(C:、D:など)で管理します。
Linuxのパーティション構成
Linuxでは:
| マウントポイント | 用途 | 容量例 |
|---|---|---|
/ | システム全体の親ディレクトリ | 20GB |
/home | ユーザーのデータ・設定 | 500GB |
/boot | 起動に必要なファイル | 1GB |
swap | 仮想メモリ | 8GB |
重要な違い:
- Windowsは「ドライブレター」
- Linuxは「ディレクトリ(フォルダ)」単位
マウントポイントって何?
Linuxでは、パーティションを特定のディレクトリに「マウント」(接続)して使用します。
具体例:
/dev/sda1 → /boot (起動ファイル用パーティション)
/dev/sda2 → / (ルートパーティション)
/dev/sda3 → /home (ユーザーデータ用パーティション)
これにより:
/homeにログファイルが溜まっても/に影響しない- ユーザーデータ(
/home)だけ別にバックアップできる - システム更新時も
/homeは保護される
Linuxの基本的なパーティション構成を理解しよう
初心者向け:シンプル構成
個人PCや学習用なら:
| マウントポイント | 容量目安 | 説明 |
|---|---|---|
/ | 20-50GB | システム全体(OSやソフトウェア) |
swap | RAM と同じ | 仮想メモリ(8GB RAMなら8GB) |
この構成なら管理が簡単で、初心者でも迷いません。
中級者向け:分割構成
より安全で管理しやすい構成:
| マウントポイント | 容量目安 | 説明 |
|---|---|---|
/boot | 1GB | 起動ファイル(カーネルなど) |
/ | 20-30GB | システムファイル |
/home | 残り容量の大部分 | ユーザーデータ・設定 |
/var | 10-20GB | ログファイル・一時ファイル |
swap | RAM と同じ | 仮想メモリ |
サーバー向け:本格構成
サーバーや業務用システムでは:
| マウントポイント | 容量目安 | 説明 |
|---|---|---|
/boot | 1GB | 起動ファイル |
/ | 20GB | システムファイル |
/home | 50GB~ | ユーザーデータ |
/var | 20GB~ | ログ・メール・データベース |
/tmp | 5-10GB | 一時ファイル |
/opt | 10-20GB | 追加ソフトウェア |
swap | RAM の 1-2倍 | 仮想メモリ |
分割するメリット:
- ログファイルで
/varが満杯になっても、システム(/)は動作継続 /homeを別にすることで、OS再インストール時もユーザーデータを保護- バックアップ戦略を用途別に最適化
swapパーティションを詳しく解説

swapとは何か?
swap(スワップ)は、物理メモリ(RAM)が足りなくなった時に、一時的にディスクをメモリ代わりに使う領域です。
具体的な動作:
通常時: プログラム → RAM で高速処理
メモリ不足: プログラム → swap(ディスク)で低速処理
swapが使われる場面
- メモリ不足時: 8GB RAMで10GBの処理をする場合
- サスペンド時: スリープ状態の情報を保存
- メモリ最適化: あまり使わないデータをswapに移動
swap容量の決め方
| RAM容量 | swap推奨サイズ | 理由 |
|---|---|---|
| 2GB以下 | RAM の 2倍 | メモリ不足が頻繁 |
| 2-8GB | RAM と同じ | バランス重視 |
| 8GB以上 | 4-8GB | 最低限でOK |
| 16GB以上 | 2-4GB | ほぼ使われない |
現代の考え方:
- SSDが高速化したため、昔ほど大容量は不要
- サーバーでは障害対策で多めに確保
- 仮想環境では最小限に
swapパーティション vs swapファイル
| 方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| swapパーティション | 高速・安定 | 容量変更が困難 |
| swapファイル | 容量変更が簡単 | わずかに低速 |
最近のトレンド: 多くのLinuxディストリビューションは、swapファイルを標準採用しています。
実際にパーティションを確認・管理してみよう
現在のパーティション状況を確認
dfコマンド:使用量をチェック
df -h
出力例:
ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
/dev/sda2 20G 15G 4.2G 79% /
/dev/sda3 200G 50G 140G 27% /home
/dev/sda1 974M 125M 783M 14% /boot
読み方:
/(ルート)は20GBのうち15GB使用(79%)/homeは200GBのうち50GB使用(27%)/bootは1GBのうち125MB使用(14%)
lsblkコマンド:パーティション構造を表示
lsblk
出力例:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 500G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 20G 0 part /
├─sda3 8:3 0 470G 0 part /home
└─sda4 8:4 0 8G 0 part [SWAP]
読み方:
sda:500GBのメインディスクsda1:1GBの/bootパーティションsda2:20GBの/(ルート)パーティションsda3:470GBの/homeパーティションsda4:8GBのswapパーティション
fdiskコマンドでパーティション管理
パーティションテーブルを表示
sudo fdisk -l
対話的にパーティションを編集
sudo fdisk /dev/sda
主なコマンド:
p:パーティション一覧表示n:新しいパーティション作成d:パーティション削除w:変更を保存して終了q:保存せずに終了
注意: fdiskは危険なツールです。必ずバックアップを取ってから使用してください。
パーティション設計のベストプラクティス

用途別の推奨構成
個人用デスクトップ(250GB SSD)
/boot: 1GB (起動ファイル)
/: 30GB (システム)
/home: 210GB (ユーザーデータ)
swap: 8GB (仮想メモリ)
開発者向け(500GB SSD)
/boot: 1GB (起動ファイル)
/: 40GB (システム)
/home: 400GB (プロジェクト・ソースコード)
/var: 50GB (ログ・データベース)
swap: 8GB (仮想メモリ)
サーバー用(1TB HDD)
/boot: 1GB (起動ファイル)
/: 20GB (システム)
/home: 100GB (ユーザー)
/var: 200GB (ログ・データ)
/opt: 50GB (追加ソフト)
/srv: 600GB (Webコンテンツ・データ)
swap: 16GB (仮想メモリ)
パーティション設計のコツ
1. 将来の拡張を考慮
# 余裕を持った容量設計
/ : 実際に必要な容量の 1.5-2倍
/var : ログの増加を想定して多めに
/home : データ量の増加を見込んで
2. バックアップ戦略との連携
# 重要度別にパーティションを分ける
/ : システム(毎日バックアップ)
/home : ユーザーデータ(リアルタイムバックアップ)
/var/log : ログ(定期的にローテーション)
3. パフォーマンス最適化
# アクセス頻度に応じて配置
/ : SSDの高速領域
/home : SSDの大容量領域
/var/log : HDDでもOK(アーカイブ用)
トラブルシューティング:よくある問題と解決法
パーティションが満杯になった場合
1. ディスク使用量の確認
# ディレクトリごとの使用量をチェック
du -sh /* 2>/dev/null | sort -hr
# 大きなファイルを探す
find /var -type f -size +100M -exec ls -lh {} \;
2. 不要ファイルの削除
# ログファイルのクリーンアップ
sudo journalctl --vacuum-time=30d
# パッケージキャッシュの削除
sudo apt clean # Debian/Ubuntu
sudo yum clean all # RHEL/CentOS
3. パーティションの拡張
# GParted(GUI)を使用する場合
sudo apt install gparted
gparted
# コマンドラインの場合(LVM使用時)
sudo lvextend -L +10G /dev/mapper/vg-home
sudo resize2fs /dev/mapper/vg-home
swapが足りない場合
追加のswapファイル作成
# 4GBのswapファイルを作成
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
# 永続的に有効にする
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
パーティション管理のベストツール
GUI ツール
GParted
sudo apt install gparted # Debian/Ubuntu
sudo yum install gparted # RHEL/CentOS
特徴:
- 視覚的でわかりやすい
- パーティションのリサイズが簡単
- ライブUSBから起動可能
KDE Partition Manager
sudo apt install partitionmanager
特徴:
- KDE環境に最適化
- 高度な機能も使いやすい
コマンドラインツール
parted
sudo parted /dev/sda print
sudo parted /dev/sda resizepart 2 100GB
特徴:
- GPTパーティションに対応
- スクリプト化しやすい
gdisk
sudo gdisk /dev/sda
特徴:
- GPT専用
- UEFIシステムに適している
よくある質問と回答
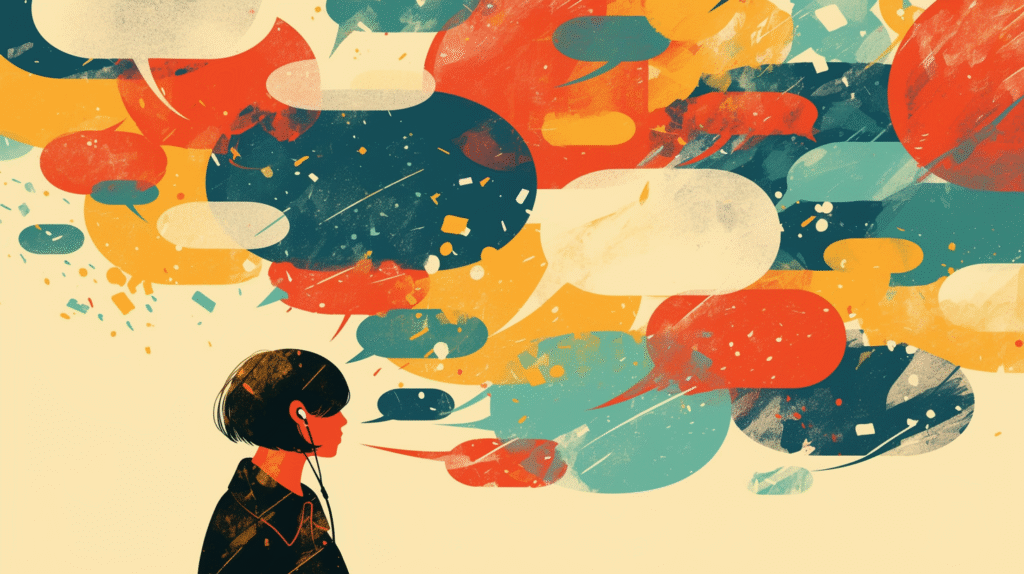
パーティションサイズは後から変更できる?
基本的には可能ですが、条件があります:
- 拡張: 後ろに空き領域があれば比較的安全
- 縮小: データが失われるリスクあり、事前バックアップ必須
- LVM使用: 柔軟な容量変更が可能
GPTとMBRどちらを選ぶべき?
| 項目 | MBR | GPT |
|---|---|---|
| 最大ディスク容量 | 2TB | 9.4ZB |
| 最大パーティション数 | 4個(拡張で増加可) | 128個 |
| UEFIサポート | 限定的 | 完全対応 |
| 推奨環境 | 古いシステム | 現代のシステム |
結論: 特別な理由がなければGPTを選択
LVMって使うべき?
LVM(Logical Volume Manager)のメリット:
- パーティションサイズの動的変更
- 複数ディスクの統合
- スナップショット機能
デメリット:
- 設定が複雑
- トラブル時の復旧が困難
推奨:
- サーバー環境:LVM推奨
- 個人PC:シンプルなパーティションでOK
暗号化パーティションは必要?
推奨する場面:
- ノートPCなど盗難リスクがある環境
- 個人情報や機密データを扱う場合
- セキュリティ要件が厳しい環境
設定例:
# インストール時にLUKS暗号化を選択
# または手動で設定
sudo cryptsetup luksFormat /dev/sda3
sudo cryptsetup open /dev/sda3 encrypted_home
まとめ:Linuxパーティションをマスターしよう
Linuxのパーティションは、最初は複雑に感じるかもしれませんが、基本を理解すれば決して難しくありません。
今回学んだ重要ポイント
- パーティションの役割: データを用途別に分けて管理
- Linuxの特徴: ディレクトリ単位でマウント
- 基本構成:
/、/home、swapが最低限 - 管理コマンド:
df、lsblk、fdisk - 設計のコツ: 用途と将来の拡張を考慮