最近のパソコンでディスク管理を開いたとき、「GPTパーティションスタイル」という表示を見たことはありませんか?
「昔はMBRって書いてあった気がするけど、これって何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実は、GPT(ジーピーティー)は、古いMBR方式に代わる新しいパーティション管理の仕組みなんです。今回は、このGPTについて、初心者の方でも分かりやすく解説していきますよ!
GPTとは?基本を理解しよう
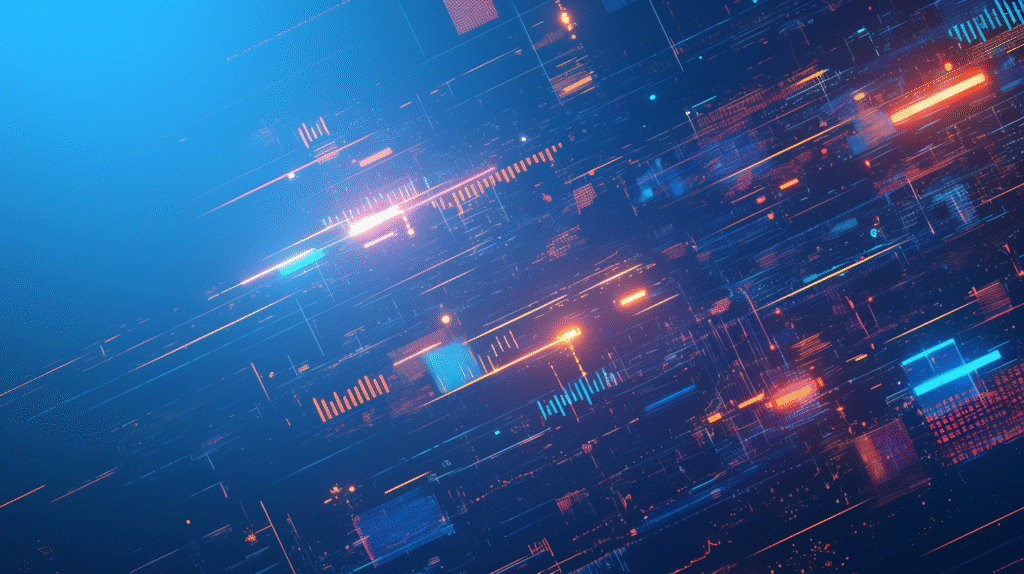
GPTは「GUID Partition Table」の略称です。
GUIDって何?
GUIDは「Globally Unique Identifier」の略で、世界中で一意(ユニーク)な識別子のことです。
128ビットの数値で表され、実質的に重複することがありません。例えば:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000こんな感じの長い文字列で、パーティションを識別するんですね。
パーティションテーブルの役割
パーティションテーブルは、ディスクの「目次」のようなものです。
「この領域は何番目のパーティションで、どこから始まってどこで終わるか」という情報を記録しています。この目次がないと、OSはディスクをどう使えば良いか分からないんですよ。
GPTの登場背景
GPTは、UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)という新しいファームウェアと一緒に登場しました。
2000年代後半から普及し始め、現在ではほとんどの新しいパソコンで標準となっています。
MBRとGPT:何が違うの?
GPTを理解するには、古い方式のMBR(Master Boot Record)との違いを知ることが大切です。
MBRの特徴と制限
MBRは1980年代に開発された、非常に古い技術です。
主な制限:
| 項目 | MBRの制限 |
|---|---|
| 最大ディスク容量 | 2TB |
| パーティション数 | プライマリ4つまで |
| データの冗長性 | なし(壊れたら終わり) |
| 識別方法 | 番号(1,2,3,4…) |
プライマリパーティションの制限が痛い:
4つまでしか作れないので、5つ以上必要な場合は「拡張パーティション」という特殊な仕組みを使う必要がありました。複雑で分かりにくいですよね。
GPTの特徴と利点
GPTは現代のニーズに合わせて設計されています。
主な特徴:
| 項目 | GPTの性能 |
|---|---|
| 最大ディスク容量 | 9.4ZB(ゼタバイト)※実質無制限 |
| パーティション数 | 最大128個(標準)※拡張可能 |
| データの冗長性 | あり(バックアップを持つ) |
| 識別方法 | GUID(ユニークID) |
9.4ZBってどのくらい?
9,400,000,000TB(テラバイト)です。現実的には到達不可能な容量ですね。実質的に容量制限はないと言えます。
GPTの7つのメリット
なぜGPTが推奨されるのか、具体的なメリットを見ていきましょう。
メリット1:大容量ディスクに対応
2TBの壁を突破:
MBRでは2TBまでしか認識できませんでしたが、GPTなら4TB、8TB、10TBのディスクも問題なく使えます。
最近は大容量HDDが安くなっているので、これは大きなメリットですね。
メリット2:パーティション数の制限がほぼない
128個まで作成可能:
実際には128個も使うことは稀ですが、制限を気にせずパーティションを作れるのは便利です。
プライマリと拡張を区別する必要もなくなりました。
メリット3:データの冗長性
パーティションテーブルが2つ:
GPTディスクの先頭と末尾の両方にパーティション情報が保存されます。
先頭が壊れても、末尾のバックアップから復旧できるんですよ。MBRは先頭だけなので、壊れたら完全にアウトでした。
メリット4:CRCによるエラー検出
巡回冗長検査(CRC):
パーティションテーブルにCRC32というチェックサムが付いています。
データの破損を自動的に検出して、可能な場合は修復してくれます。信頼性が大幅に向上していますね。
メリット5:一意な識別子
GUIDで確実に識別:
各パーティションが固有のGUIDを持つため、間違えることがありません。
複数のディスクを扱う環境では特に便利です。
メリット6:UEFI起動に必要
最新のファームウェアに対応:
UEFIモードで起動するには、GPTが必要です。
セキュアブート(Secure Boot)などの新機能も使えるようになります。
メリット7:将来性がある
新しい標準:
すべての新しいパソコンはGPTをサポートしています。
今後もずっと使い続けられる技術なので、今から慣れておいて損はありませんよ。
GPTの内部構造:どうやって動いているの?
GPTディスクがどのような構造になっているか見てみましょう。
GPTディスクのレイアウト
[保護MBR] [GPTヘッダー] [パーティションエントリ配列] [パーティション1] [パーティション2] ... [パーティションエントリ配列(バックアップ)] [GPTヘッダー(バックアップ)]ディスクの先頭から順に、このような構造になっています。
各セクションの役割
LBA 0:保護MBR
MBRとの互換性のために残されています。古いツールが誤ってGPTディスクを操作しないよう保護する役割があります。
「このディスク全体がGPT用です」という情報が書かれているんですね。
LBA 1:プライマリGPTヘッダー
パーティションテーブルの「目次の目次」とも言える重要な情報です。
- ディスクのGUID
- パーティションエントリの位置
- CRCチェックサム
- バックアップヘッダーの位置
これらが記録されています。
LBA 2〜33:パーティションエントリ配列
各パーティションの詳細情報が128個分保存されています。
- パーティションのGUID
- 開始LBA(論理ブロックアドレス)
- 終了LBA
- パーティション名(最大36文字)
- 属性フラグ
データ領域:実際のパーティション
ここにOSやファイルが保存されます。
末尾:バックアップ
パーティションエントリ配列とGPTヘッダーのバックアップがディスクの最後に保存されています。
先頭が破損しても、ここから復旧できる仕組みですね。
UEFI起動とBIOS起動の違い
GPTとMBRは、起動方式とも密接に関連しています。
レガシーBIOS(MBR起動)
古い起動方式:
- MBRディスクを使用
- 最初の512バイトのブートコードを実行
- 16ビットモードで起動
- セキュリティ機能が限定的
UEFI(GPT起動)
新しい起動方式:
- GPTディスクを推奨(MBRも可能だが非推奨)
- EFIシステムパーティション(ESP)から起動
- 32/64ビットモードで起動
- セキュアブート対応
- より高速な起動
EFIシステムパーティション(ESP)とは
UEFIブートでは、ESPという特殊なパーティションが必要です。
ESPの特徴:
- FAT32でフォーマット
- 通常100〜500MB程度
- ブートローダーが保存される
- Windowsでは通常Cドライブの前に配置
Linuxでは/boot/efiにマウントされることが多いですね。
GPTディスクの作成方法
実際にGPTディスクを作成してみましょう。
Windowsでの作成方法
方法1:ディスクの管理(GUI)
Win + Xキーを押して「ディスクの管理」を選択- 新しいディスクを右クリック
- 「ディスクの初期化」を選択
- 「GPTパーティションスタイル」を選択
- OKをクリック
方法2:diskpartコマンド(CLI)
# 管理者権限でコマンドプロンプトを開く
diskpart
# ディスク一覧を表示
list disk
# ディスクを選択(番号は環境によって異なる)
select disk 1
# GPTに変換(データが消えるので注意)
convert gpt
# 終了
exit注意:データがすべて消えます。必ずバックアップを取ってから実行してください。
Linuxでの作成方法
方法1:gdisk(推奨)
# gdiskを起動
sudo gdisk /dev/sdb
# 新しいパーティションテーブルを作成
Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): y
# パーティションを作成
Command (? for help): n
Partition number: 1
First sector: (デフォルトでEnter)
Last sector: +50G (50GBの場合)
# 変更を保存
Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): y方法2:parted
# partedを起動
sudo parted /dev/sdb
# GPTラベルを作成
(parted) mklabel gpt
# パーティションを作成
(parted) mkpart primary ext4 0% 50%
# 確認
(parted) print
# 終了
(parted) quit方法3:GParted(GUI)
- GPartedを起動
- デバイスメニューから「新しいパーティションテーブルを作成」
- 「gpt」を選択
- 適用
視覚的に操作できるので、初心者の方にはこちらがおすすめです。
MBRからGPTへの変換
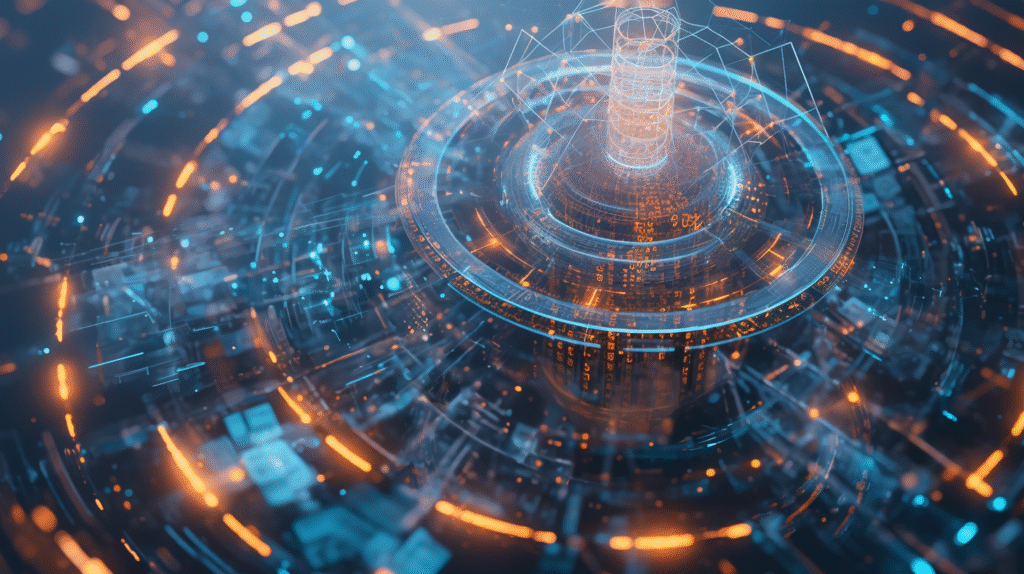
既存のMBRディスクをGPTに変換する方法を紹介します。
Windowsでの変換(Windows 10/11)
方法1:MBR2GPT(データを保持)
Windows 10 バージョン1703以降では、データを保持したまま変換できます。
# 管理者権限でコマンドプロンプトを開く
# 検証モード(実際には変換しない)
mbr2gpt /validate /disk:0
# 実際に変換
mbr2gpt /convert /disk:0
# UEFIモードで起動できるようにする
mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS注意点:
- システムドライブの変換は、BIOSモードをUEFIに変更する必要がある
- BIOS設定で「UEFI」または「UEFI with CSM」に変更
- セキュアブートを有効化する場合もある
方法2:diskpart(データが消える)
diskpart
list disk
select disk 1
clean # すべてのデータを削除
convert gptLinuxでの変換
gdiskで変換(比較的安全)
# gdiskを起動
sudo gdisk /dev/sdb
# MBRからの変換
Command (? for help): w
# 既存のMBRパーティションを読み込んで、GPTに変換してくれるgdiskは賢いので、MBRディスクを開くと自動的にGPTへの変換を提案してくれますよ。
sgdiskコマンド(コマンドライン)
# MBRからGPTに変換
sudo sgdisk -g /dev/sdb
# 確認
sudo sgdisk -p /dev/sdbパーティションタイプGUID
GPTでは、パーティションの種類を示すために特定のGUIDが使われます。
主要なパーティションタイプ
| 用途 | GUID |
|---|---|
| EFIシステムパーティション | C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B |
| Microsoft基本データ | EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 |
| Linux ファイルシステム | 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4 |
| Linux swap | 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F |
| Linux /home | 933AC7E1-2EB4-4F13-B844-0E14E2AEF915 |
| BIOS boot | 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 |
gdiskやpartedでパーティションを作成する際、このGUIDが自動的に設定されます。
パーティションタイプの指定
gdiskでの指定:
Command (? for help): t
Partition number: 1
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8300
# 8300 = Linux filesystem
# ef00 = EFI System Partition
# 8200 = Linux swappartedでの指定:
(parted) set 1 esp on # EFIシステムパーティションに設定
(parted) set 2 msftdata on # Windows用データパーティションGPTディスクのトラブルシューティング
GPTディスクで問題が起きたときの対処法です。
問題1:「GPTパーティションが見つかりません」エラー
症状:
UEFIモードで起動しようとすると、ブートできない。
原因:
- BIOSモードで起動しようとしている
- ESPが正しく設定されていない
対処法:
# Linuxの場合、ESPを確認
sudo parted /dev/sda print
# 「esp」フラグがついているか確認
# ついていなければ設定
sudo parted /dev/sda set 1 esp onBIOS設定で、起動モードを「UEFI」に変更することも忘れずに。
問題2:パーティションテーブルの破損
症状:
「GPTが破損しています」というエラーが表示される。
対処法:
# gdiskでバックアップから復旧
sudo gdisk /dev/sda
# リカバリーモードに入る
Command (? for help): r
# バックアップGPTを使用
Recovery/transformation command (? for help): b
# 変更を保存
Recovery/transformation command (? for help): wGPTは冗長性があるので、たいていの場合は復旧できますよ。
問題3:「保護MBRのみ」と表示される
症状:
古いツールでGPTディスクを見ると、1つの巨大なパーティションとして見える。
原因:
GPTに対応していないツールを使っている。
対処法:
GPT対応のツール(Windows 10以降のディスク管理、gdisk、GPartedなど)を使いましょう。
問題4:WindowsとLinuxのデュアルブートでブートできない
症状:
Windowsをインストール後、Linuxが起動しなくなった。
原因:
WindowsがESPのブートローダーを上書きした。
対処法:
# Live USBで起動して、ブートローダーを再インストール
# ESPをマウント
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
# ルートパーティションをマウント
sudo mount /dev/sda2 /mnt
# chrootで環境に入る
sudo arch-chroot /mnt
# GRUBを再インストール(Ubuntu/Debianの場合)
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
# 設定を更新
sudo update-grubGPTの確認方法
ディスクがGPTかMBRかを確認する方法です。
Windowsでの確認
ディスクの管理から:
Win + X→「ディスクの管理」- ディスクを右クリック→「プロパティ」
- 「ボリューム」タブを見る
- 「パーティションのスタイル」に表示
diskpartコマンド:
diskpart
list disk
# GUIDパーティションテーブル(GPT)欄に*がついていればGPTLinuxでの確認
partedコマンド:
sudo parted -l
# 出力例:
# Partition Table: gpt ← GPT
# または
# Partition Table: msdos ← MBRgdiskコマンド:
sudo gdisk -l /dev/sda
# GPTなら詳細情報が表示される
# MBRなら「MBR partition table detected」と表示fdiskコマンド:
sudo fdisk -l /dev/sda
# 「Disklabel type: gpt」と表示されればGPT実用例:様々なシナリオでの活用
実際の使用場面を見てみましょう。
シナリオ1:4TBの大容量HDDをフルに使う
構成:
MBRでは2TBまでしか認識できませんが、GPTなら4TB全体を使えます。
# GPTディスクを作成
sudo gdisk /dev/sdb
o (新規作成)
n (パーティション作成)
+4000G (全容量)
w (書き込み)
# フォーマット
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1これで4TBのストレージを1つのパーティションとして使えますね。
シナリオ2:複数のOSをインストール
パーティション構成:
- /dev/sda1:ESP(500MB)
- /dev/sda2:Windows(100GB)
- /dev/sda3:Ubuntu(50GB)
- /dev/sda4:Fedora(50GB)
- /dev/sda5:共有/home(300GB)
GPTなら128個までパーティションを作れるので、複数のOSを試すのも簡単です。
シナリオ3:サーバー用ディスク構成
RAID構成での活用:
Disk 1 (8TB GPT): /data1
Disk 2 (8TB GPT): /data2
Disk 3 (8TB GPT): /data3
Disk 4 (8TB GPT): /data4大容量ディスクをRAIDで組んで、信頼性の高いストレージを構築できます。
GPTとMBR:結局どちらを選ぶべき?
判断基準をまとめます。
GPTを選ぶべき場合
以下に該当するならGPT一択:
- 新しいパソコン(2012年以降)
- 2TB以上のディスク
- UEFIモードで起動したい
- 5つ以上のパーティションが必要
- セキュアブートを使いたい
- 将来性を考慮したい
現在では、ほとんどの場合でGPTが適切ですね。
MBRを選ぶべき場合
限定的な状況:
- 非常に古いパソコン(2010年以前)
- 古いOSを使う必要がある(Windows XPなど)
- レガシーBIOSのみ対応のシステム
- 特定の古いソフトウェアの互換性が必要
特別な理由がない限り、新規構築ではGPTを選びましょう。
セキュアブートとGPT
GPTは、セキュアブートという重要なセキュリティ機能とも関連しています。
セキュアブートとは
不正なブートローダーを防ぐ仕組み:
起動時に、ブートローダーがデジタル署名されているかチェックします。
署名がない、または不正な署名の場合は起動を拒否するんですね。
セキュアブートの要件
- UEFIモードでの起動
- GPTディスク
- 署名されたブートローダー
Windowsは標準でサポートしていますが、Linuxでは一部のディストリビューションのみ対応しています。
対応ディストリビューション:
- Ubuntu(18.04以降)
- Fedora
- openSUSE
- Debian(10以降)
これらは、Microsoft署名のshimというブートローダーを使ってセキュアブートに対応していますよ。
よくある質問
Q: MBRディスクをGPTに変換すると、データは消える?
A: Windowsのmbr2gptやLinuxのgdiskを使えば、データを保持したまま変換できます。ただし、念のためバックアップを取ることをおすすめしますよ。
Q: GPTディスクでもレガシーBIOSで起動できる?
A: できますが、非推奨です。GPTディスクにBIOS boot パーティションを作成すれば起動可能ですが、UEFIモードの方が多くのメリットがあります。
Q: 古いWindowsはGPTに対応している?
A: Windows Vista以降(64ビット版)はGPTをサポートしています。ただし、起動ディスクとして使えるのはWindows 7(64ビット)以降でUEFIモードの場合のみです。
Q: GPTディスクは本当に128個までしかパーティションを作れない?
A: 標準では128個ですが、パーティションエントリ配列のサイズを変更すれば、理論上はもっと増やせます。ただし、実用上は128個で十分でしょう。
Q: SSDでもGPTを使うべき?
A: はい。SSDこそGPTを使うべきです。特に最近のNVMe SSDは、UEFIとGPTを前提に設計されています。
まとめ:GPTは現代の標準
GPT(GUID Partition Table)について、重要なポイントをおさらいします。
今日学んだこと:
- GPTは次世代のパーティション管理方式
- MBRの制限(2TB、4パーティション)を克服
- 冗長性があり、データの信頼性が高い
- UEFIモードでの起動に必要
- 大容量ディスクに対応(実質無制限)
- 128個までパーティションを作成可能
- セキュアブートなど最新機能に対応
- 現代のパソコンでは標準となっている
GPTは、もはや「新しい技術」ではなく、「現在の標準」です。
2TB以上のディスクが当たり前になり、UEFIが主流となった今、MBRを使う理由はほとんどありません。新しくパソコンを組む場合や、ディスクを初期化する場合は、迷わずGPTを選びましょう。
多少難しそうに見えますが、実際の操作はMBRとほぼ変わりません。むしろ、パーティション数の制限がなくなって使いやすくなっているんですよ。これからのパソコンライフでは、GPTの知識が必ず役に立つはずです!







