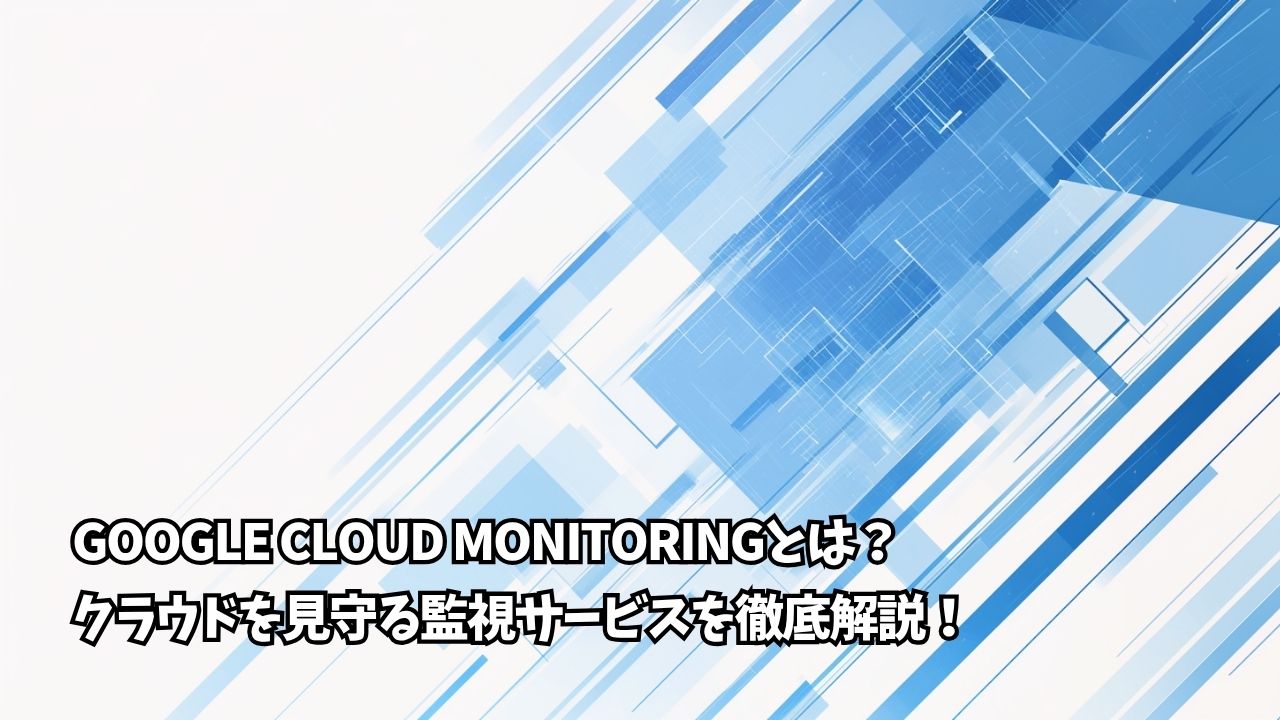「Webサイトが突然落ちた!」「アプリが遅くなっている気がする…」
こんなトラブル、IT業界では日常茶飯事です。
でも、問題が起きてから気づくのでは遅いですよね。理想は、問題が起きる前に気づいて、未然に防ぐことです。
そのために必要なのが、監視(モニタリング)という仕組み。そして、Google Cloudで使える監視サービスが、Google Cloud Monitoringなんです。
「監視って何を見るの?」「どうやって問題を見つけるの?」「初心者には難しそう…」
この記事では、そんな疑問に答えながら、Google Cloud Monitoringについて初心者の方にもわかりやすく解説します。クラウドを使っている人、これから使う予定の人、IT業界を目指す人、ぜひ最後まで読んでみてください。
難しい専門用語は身近な例えで説明していくので、安心してくださいね!
Google Cloud Monitoringとは?
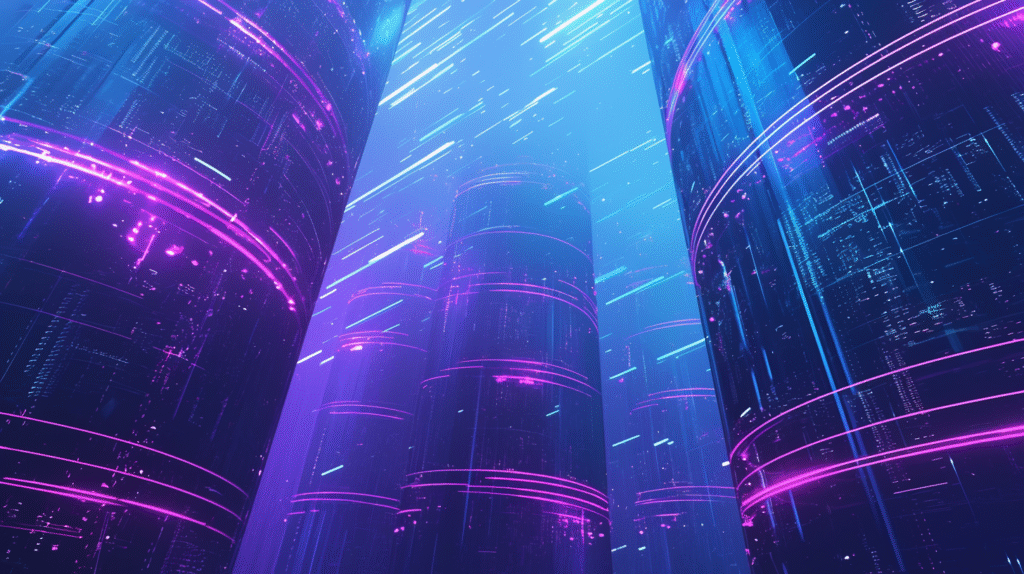
まず、Google Cloud Monitoringの基本から説明しましょう。
Google Cloud Monitoringの正式名称
Google Cloud Monitoring(グーグル・クラウド・モニタリング)は、Googleが提供するクラウド監視サービスです。
以前は「Stackdriver Monitoring(スタックドライバー・モニタリング)」という名前でしたが、2020年にGoogle Cloud Monitoringに改名されました。
監視(モニタリング)とは?
「監視」と聞くと、防犯カメラのようなイメージを持つかもしれませんね。
IT業界の監視も、考え方は似ています。
防犯カメラで例えると
- 防犯カメラ:24時間365日、建物を見張る
- 異常検知:不審者が映ったら警報が鳴る
- 記録:何時に何が起きたか記録される
IT監視も同じ
- 監視ツール:24時間365日、システムを見張る
- 異常検知:エラーが起きたら通知が来る
- 記録:いつ何が起きたかログに残る
つまり、Google Cloud Monitoringは、クラウド上のシステムを見守る番人なんです。
何を監視するの?
Google Cloud Monitoringでは、次のようなものを監視できます。
サーバーの状態
- CPU使用率:頭を使いすぎていないか
- メモリ使用量:記憶容量がいっぱいになっていないか
- ディスク容量:ストレージが足りているか
- ネットワーク通信量:通信が集中していないか
アプリケーションの動作
- 応答速度:ユーザーの操作にすぐ反応しているか
- エラー発生率:正常に動いているか
- リクエスト数:どれくらい使われているか
データベース
- クエリの実行時間:データの取得に時間がかかっていないか
- 接続数:同時にアクセスしている人数
これらの情報を、リアルタイムで監視できるんです。
誰が作ったの?
Google Cloud Monitoringは、Googleが開発・提供しています。
Googleは、検索エンジンやYouTubeなど、世界最大規模のサービスを運営していますよね。
その経験を活かして作られた監視ツールなので、信頼性が高いんです。
どこで使われているの?
Google Cloud(GCP)を使っている企業なら、ほぼすべてがGoogle Cloud Monitoringを活用しています。
使われる場面の例
- Webサービスの運営会社
- スマホアプリの開発会社
- ECサイト(ネットショップ)
- 金融機関のシステム
- ゲーム会社
「サーバーが落ちたら困る」すべてのサービスで、必須のツールなんですね。
なぜ監視が必要なのか?
「監視なんて、本当に必要?」
そう思うかもしれません。でも、監視がないと大変なことになるんです。
理由1:問題が起きてから気づくのでは遅い
監視がないと、ユーザーから苦情が来て初めて問題に気づくことになります。
監視なしのシナリオ
- サーバーのメモリが限界に達する
- アプリが重くなる
- ユーザーが「遅い!」とSNSで拡散
- やっと気づいて対応
- でも時すでに遅し…信頼を失う
監視ありのシナリオ
- メモリ使用率が80%を超える
- アラート(警告)が管理者に届く
- すぐにサーバーを増強
- ユーザーは何も気づかず快適に使える
- トラブル回避!
圧倒的に、監視がある方がいいですよね。
理由2:原因の特定が早くなる
トラブルが起きた時、「何が原因か」を突き止めるのは大変です。
監視なしの調査
- いつから問題が起きているのか不明
- どのサーバーが原因か分からない
- ログを手作業で探す(数時間かかる)
- 推測で対応するしかない
監視ありの調査
- グラフで「◯時◯分に異常発生」と一目瞭然
- 問題のあるサーバーが特定できる
- 関連するログがすぐ見つかる
- データに基づいて対応できる
問題解決のスピードが、全然違うんです。
理由3:コストを最適化できる
監視データを分析すると、無駄なコストを削減できます。
例:使われていないサーバー
グラフを見ると、「このサーバー、夜間は全く使われていない」と分かります。
だったら、夜間は自動で停止させれば、コストが下がりますね。
例:性能過剰なサーバー
「CPU使用率がずっと10%以下」なら、スペックが高すぎます。
安いプランに変更すれば、月々の費用を節約できます。
監視は、節約のヒントも教えてくれるんです。
理由4:将来の計画が立てやすい
長期間のデータを見ると、トレンド(傾向)が分かります。
例:ユーザー数の増加
「毎月10%ずつアクセスが増えている」と分かれば、
「3ヶ月後にはサーバーが足りなくなる」と予測できます。
事前に増強すれば、トラブルを防げますね。
監視データは、未来予測のための資料にもなるんです。
理由5:ビジネスへの影響を最小限に
サービスが止まると、お金を失います。
ECサイトの例
- 売上:1時間あたり100万円
- サーバー停止:3時間
- 損失:300万円
でも、監視があれば:
- 事前に問題を検知
- すぐに対応
- 停止時間:5分
- 損失:約8万円
292万円の差が出るんです。
監視への投資は、十分に元が取れますね。
Google Cloud Monitoringの主な機能
Google Cloud Monitoringには、便利な機能がたくさんあります。
機能1:メトリクスの収集と可視化
メトリクスとは、測定可能な数値データのことです。
収集できるメトリクスの例
- CPU使用率(%)
- メモリ使用量(GB)
- ディスク使用率(%)
- ネットワーク送受信量(Mbps)
- HTTPリクエスト数(回/秒)
- エラー発生数(回)
これらのデータを、自動的に収集してくれます。
そして、グラフで表示してくれるんです。
グラフで見るメリット
- 一目で状況が分かる
- 異常値がすぐ見つかる
- 時系列で変化を追える
数字の羅列より、グラフの方が断然分かりやすいですよね。
機能2:アラート(通知)
設定した条件を満たすと、自動で通知が届きます。
アラートの設定例
- CPU使用率が80%を超えたら通知
- エラー発生率が1%を超えたら通知
- ディスク空き容量が10GB以下になったら通知
通知先
- メール
- SMS(携帯電話のショートメール)
- Slack(チャットツール)
- PagerDuty(専門の通知サービス)
24時間監視していなくても、問題があれば教えてくれるんです。
機能3:ダッシュボード
ダッシュボードは、複数のグラフをまとめて表示する画面です。
車の運転席に例えると分かりやすいですね。
車のダッシュボード
- 速度計
- 燃料計
- 水温計
- タコメーター
Google Cloud Monitoringのダッシュボード
- CPU使用率グラフ
- メモリ使用量グラフ
- エラー発生数グラフ
- リクエスト数グラフ
一画面で、システム全体の状態を把握できます。
機能4:ログ管理(Cloud Loggingとの連携)
Google Cloud Monitoringは、Cloud Logging(ログ管理サービス)と統合されています。
ログとは、システムの行動記録のことです。
ログの例
2025-10-26 10:15:23 INFO ユーザーがログインしました(ID: 12345)
2025-10-26 10:15:25 ERROR データベース接続に失敗しました
2025-10-26 10:15:26 WARNING メモリ使用率が高くなっています(85%)こういった記録を残しておくと、問題の原因を調べる時に役立ちます。
機能5:トレース(Cloud Traceとの連携)
Cloud Traceと連携すると、リクエストの流れを追跡できます。
例:ユーザーがWebページを開く
- ユーザーがリンクをクリック(0秒)
- Webサーバーが処理を開始(0.1秒)
- データベースにクエリを送信(0.2秒)
- データベースが結果を返す(0.5秒)← ここが遅い!
- Webサーバーが画面を生成(0.6秒)
- ユーザーに表示される(0.7秒)
「データベースの処理が遅い」と特定できますね。
これがトレースの力です。
機能6:Uptime Check(死活監視)
定期的にシステムにアクセスして、生きているか確認します。
仕組み
- 5分ごとにWebサイトにアクセス
- 正常に応答があるか確認
- 応答がなければアラート
人間で例えると
定期的に「元気?」と声をかけて、返事がなければ「大丈夫?」と駆けつける感じです。
機能7:SLO(Service Level Objective)管理
SLOとは、「サービスレベル目標」のことです。
例:SLOの設定
- 稼働率:99.9%以上を目指す(月3時間以内の停止)
- 応答速度:95%のリクエストを1秒以内に返す
Google Cloud Monitoringは、SLOの達成状況を追跡してくれます。
目標に対して、今どれくらいできているか一目瞭然です。
メトリクス、ログ、トレースの違い
監視には、3つの柱があります。
それぞれの違いを理解しましょう。
メトリクス(Metrics)
数値データの時系列変化を記録します。
特徴
- 定期的に測定される(例:1分ごと)
- 数値で表現される
- グラフ化しやすい
例
- CPU使用率:10時 → 30%、10時1分 → 35%、10時2分 → 40%
用途
- システムの健全性チェック
- トレンド分析
- 容量計画
人間で例えると
体温計や血圧計のような、定期的な健康チェックです。
ログ(Logs)
イベント(出来事)の記録です。
特徴
- イベント発生時に記録される
- テキスト形式
- 詳細な情報を含む
例
ユーザーAがログインしました
エラー:ファイルが見つかりません
データベースへの接続が切れました用途
- トラブルシューティング(原因調査)
- セキュリティ監査
- デバッグ(バグ修正)
人間で例えると
日記や行動記録のようなものです。
トレース(Trace)
リクエストの流れを追跡します。
特徴
- 1つの処理の全体像を可視化
- 各ステップの所要時間を記録
- ボトルネック(遅い部分)を特定
例
Webページ表示(合計500ms)
├ Webサーバー処理(50ms)
├ データベースクエリ(400ms)← ここが遅い
└ 画面生成(50ms)用途
- パフォーマンス最適化
- 遅い処理の特定
- 複雑なシステムの理解
人間で例えると
宅配便の追跡サービスです。荷物がどこにあるか、各地点での滞在時間が分かります。
3つの関係
この3つは、補完し合う関係です。
トラブル発生時の使い分け
- メトリクス:「いつから遅くなったのか」をグラフで確認
- ログ:「その時間に何が起きたか」を詳細に調査
- トレース:「どの処理が遅いのか」を特定
3つを組み合わせることで、問題を素早く解決できるんです。
アラート設定の基本
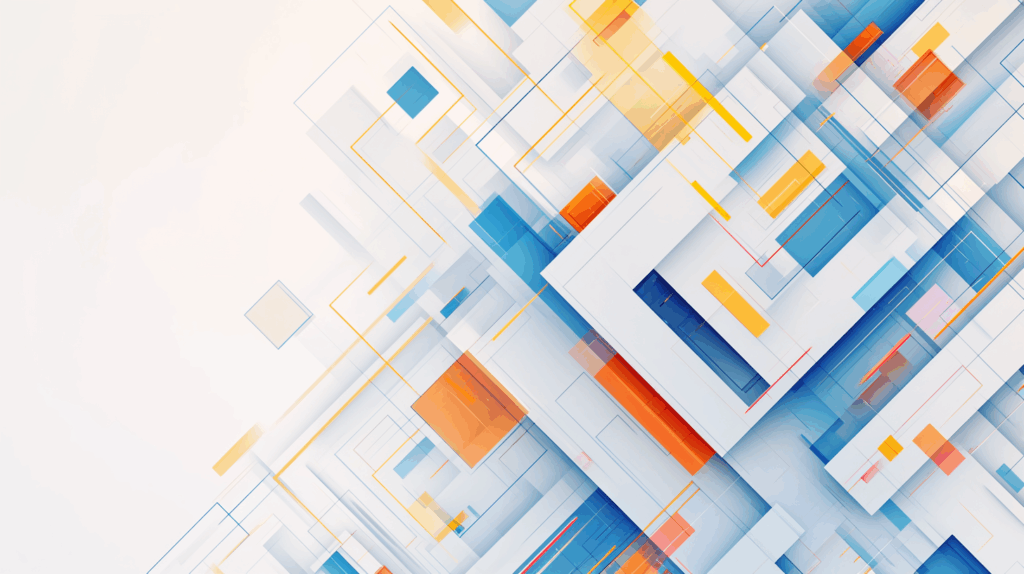
アラート機能は、Google Cloud Monitoringの要です。
アラートポリシーとは?
「◯◯の条件を満たしたら通知する」というルールを、アラートポリシーと呼びます。
アラートの作り方(基本の流れ)
ステップ1:監視対象を選ぶ
何を監視するか決めます。
例:Compute Engine(仮想サーバー)のCPU使用率
ステップ2:条件を設定する
どうなったらアラートを出すか決めます。
例:CPU使用率が80%を超えた状態が5分間続いたら
ステップ3:通知先を設定する
誰にどうやって通知するか決めます。
例:メールで dev-team@example.com に送信
ステップ4:ドキュメントを書く
アラートが来た時、何をすべきか書いておきます。
例:「サーバーの台数を増やす」「不要なプロセスを停止する」
これで、アラートポリシーの完成です!
アラートの種類
閾値アラート(Threshold Alert)
数値が一定の値を超えたら通知します。
例
- CPU使用率 > 80%
- エラー発生率 > 1%
- ディスク空き容量 < 10GB
一番よく使われるタイプです。
変化率アラート(Rate of Change Alert)
急激な変化を検知します。
例
- リクエスト数が急に50%減った
- エラー数が10分で2倍になった
緩やかな変化は見逃すけど、急変はキャッチしたい時に便利です。
欠測アラート(Missing Data Alert)
データが来なくなったら通知します。
例
- サーバーからのメトリクスが5分間届いていない
サーバーがダウンした可能性がありますね。
良いアラート設定のコツ
コツ1:アラートを出しすぎない
些細なことで通知が来ると、重要なアラートを見逃します。
オオカミ少年効果と呼ばれる現象です。
悪い例
- CPU使用率が50%を超えたら通知 → 頻繁に来る
良い例
- CPU使用率が80%を超えた状態が5分間続いたら通知
本当に重要なものだけ通知しましょう。
コツ2:対応可能なアラートだけ設定する
通知が来ても、何もできないアラートは無意味です。
悪い例
- 「ユーザー数が増えています」→ だから何?
良い例
- 「サーバー負荷が高いのでスケールアップしてください」→ 対応できる
アクションに繋がるアラートを設定しましょう。
コツ3:段階的な通知
重要度に応じて、通知方法を変えます。
例
- 警告レベル:Slackに通知
- 危険レベル:メールとSMSで通知
- 緊急レベル:電話で呼び出し
深夜に些細なアラートで起こされるのは避けたいですよね。
ダッシュボードの作り方
ダッシュボードは、監視の司令塔です。
デフォルトダッシュボード
Google Cloudの各サービスには、自動生成されるダッシュボードがあります。
設定不要で、すぐに使えます。
例:Compute Engineのダッシュボード
- CPU使用率
- ディスク使用量
- ネットワーク通信量
基本的な情報は、これで十分です。
カスタムダッシュボード
自分で好きなようにダッシュボードを作ることもできます。
作成手順
ステップ1:新しいダッシュボードを作る
Google Cloud Consoleで「Monitoring」→「Dashboards」→「Create Dashboard」
ステップ2:グラフを追加する
「Add Chart」ボタンをクリック。
ステップ3:メトリクスを選ぶ
何を表示するか選びます。
例:CPU使用率、メモリ使用量など
ステップ4:グラフの種類を選ぶ
- 折れ線グラフ:時系列の変化を見る
- 棒グラフ:複数の値を比較する
- ヒートマップ:分布を見る
- 数値表示:現在の値だけ表示
ステップ5:保存する
名前を付けて保存すれば完成!
ダッシュボードのベストプラクティス
1枚のダッシュボードに詰め込みすぎない
情報過多は、逆に分かりにくくなります。
目的別に複数のダッシュボードを作りましょう。
例
- 概要ダッシュボード:全体の健康状態
- パフォーマンスダッシュボード:応答速度など
- エラーダッシュボード:エラー発生状況
重要な情報を上部に配置
一番見たい情報を、画面の上の方に置きます。
人間の目は、自然と上から見るからです。
色を効果的に使う
- 緑:正常
- 黄色:警告
- 赤:危険
色で状況が分かると、直感的ですね。
定期的に見直す
時間が経つと、必要な情報が変わります。
月に1回程度、ダッシュボードを見直しましょう。
他の監視ツールとの比較
Google Cloud Monitoring以外にも、監視ツールはあります。
AWS CloudWatch(Amazon)
AWSの監視サービスです。
共通点
- メトリクス収集
- ログ管理
- アラート機能
違い
- 対象:CloudWatchはAWS専用、Google Cloud MonitoringはGCP専用
- 料金体系:若干異なる
- インターフェース:見た目や操作感が違う
基本的には、使っているクラウドに合わせて選びます。
Azure Monitor(Microsoft)
Azureの監視サービスです。
共通点
- 基本機能はほぼ同じ
違い
- Microsoftのエコシステムとの統合
- Application Insightsという独自機能
Azureを使っているなら、Azure Monitorが自然な選択です。
Datadog(サードパーティ)
クラウドを問わず使える、独立した監視サービスです。
メリット
- 複数のクラウドを一元管理できる
- AWS、GCP、Azure、オンプレミス全部OK
- 美しいダッシュボード
- 豊富な統合機能
デメリット
- 料金が高い
- 設定が複雑
マルチクラウド環境なら、Datadogが便利です。
Prometheus + Grafana(オープンソース)
無料で使える監視ツールです。
メリット
- 完全無料
- カスタマイズ性が高い
- コミュニティが活発
デメリット
- 自分で構築・管理が必要
- 学習コストが高い
- サポートがない
技術力がある企業や、コスト削減したい場合に選ばれます。
どれを選べばいい?
Google Cloudを使っている → Google Cloud Monitoring
統合が完璧で、設定も簡単。
複数のクラウドを使っている → Datadog
一元管理が便利。
コストを抑えたい → Prometheus + Grafana
技術力があれば、無料で実現できる。
環境と予算に応じて選びましょう。
Google Cloud Monitoringの料金
気になる料金について説明します。
基本は無料枠がある
Google Cloud Monitoringには、無料枠があります。
無料で使える範囲
- メトリクスの収集:1ヶ月あたり一定量まで無料
- ログの保存:50GBまで無料
- APIコール:100万回まで無料
小規模なプロジェクトなら、無料枠内で十分なケースも多いです。
有料になる場合
無料枠を超えると、従量課金が始まります。
料金の例(2025年時点の概算)
- メトリクス:月額$0.258/メトリクス(無料枠超過分)
- ログ:$0.50/GB(50GB超過分)
- API:$0.01/1,000コール(100万回超過分)
詳細は、Google Cloudの公式料金ページで確認してください。
時期によって変わる可能性があります。
コストを抑えるコツ
不要なメトリクスは収集しない
全部のメトリクスを集めると、料金が膨らみます。
本当に必要なものだけ選びましょう。
ログの保存期間を短くする
古いログは、別の安いストレージに移すか削除します。
アラートを最適化する
不要なアラートを減らすと、APIコール数も減ります。
定期的にコストを確認
Google Cloud Consoleで、毎月の使用量をチェックしましょう。
よくある質問
Q1:Google Cloud Monitoringは無料で使える?
一部無料です。
無料枠があるので、小規模なら無料で使えます。
大規模になると、従量課金が発生します。
Q2:監視データはどれくらい保存される?
メトリクスは最大6週間、ログは最大30日間です。
それ以上長期保存したい場合は、別途設定が必要です。
Cloud Storageなどに転送すれば、永久保存も可能です。
Q3:リアルタイムで監視できる?
ほぼリアルタイムです。
メトリクスは通常1分ごとに更新されます。
より頻繁な更新も可能ですが、コストがかかります。
Q4:Google Cloud以外のサービスも監視できる?
できます。
オンプレミス(自社サーバー)やAWSのサーバーも監視できます。
エージェント(監視ソフト)をインストールすれば、データを送信できるんです。
Q5:初心者でも使える?
基本的な機能は使いやすいです。
デフォルトのダッシュボードやアラートテンプレートがあるので、初心者でも始められます。
ただし、高度なカスタマイズには知識が必要です。
Q6:アラートが鳴らなかったらどうなる?
見逃す可能性があります。
だからこそ、アラート設定が重要なんです。
また、Uptime Check(死活監視)を設定しておけば、サーバーダウンは必ず検知できます。
Q7:モバイルアプリはある?
あります。
Google Cloud Consoleのモバイルアプリで、外出先からも監視状況を確認できます。
緊急時の対応にも便利ですね。
まとめ
Google Cloud Monitoringは、クラウドシステムを安全に運用するための必須ツールです。
24時間365日、システムを見守り、問題があれば即座に知らせてくれる頼もしい存在なんですね。
この記事のポイント
✓ Google Cloud Monitoringはクラウドの監視サービス
✓ メトリクス、ログ、トレースで多角的に監視できる
✓ アラート機能で問題を早期発見できる
✓ ダッシュボードで視覚的に状況を把握できる
✓ 無料枠があるので小規模なら無料で使える
✓ 問題発生前に検知して未然に防げる
✓ コスト最適化やキャパシティプランニングにも活用できる
✓ 他のGoogle Cloudサービスとシームレスに統合される
Google Cloudでシステムを運用するなら、Google Cloud Monitoringは必ず使うべきです。
最初は基本的なメトリクス監視とアラート設定から始めて、徐々に高度な機能を使いこなしていきましょう。
監視があれば、安心してサービスを提供できます。ユーザーに快適な体験を届けるためにも、ぜひ活用してくださいね!