ある日突然、SNSのアカウントが乗っ取られたり、銀行口座から見覚えのない送金がされていたり。そんなニュースを見たことはありませんか?これらの多くが「不正アクセス」という犯罪によって引き起こされています。
実は、不正アクセスは特別な人だけが被害に遭うものではありません。スマホやパソコンを使っている人なら、誰でも標的になる可能性があるんです。
2024年には5,358件もの不正アクセスが確認されており、その手口はどんどん巧妙になっています。企業だけでなく、個人も被害に遭う時代になってきました。
この記事では、不正アクセスとは何なのか、どんな手口があるのか、そして自分の身を守るにはどうすればいいのかを、分かりやすく解説します。難しい専門用語は使わないので、安心してくださいね!
不正アクセスってそもそも何?基本を理解しよう
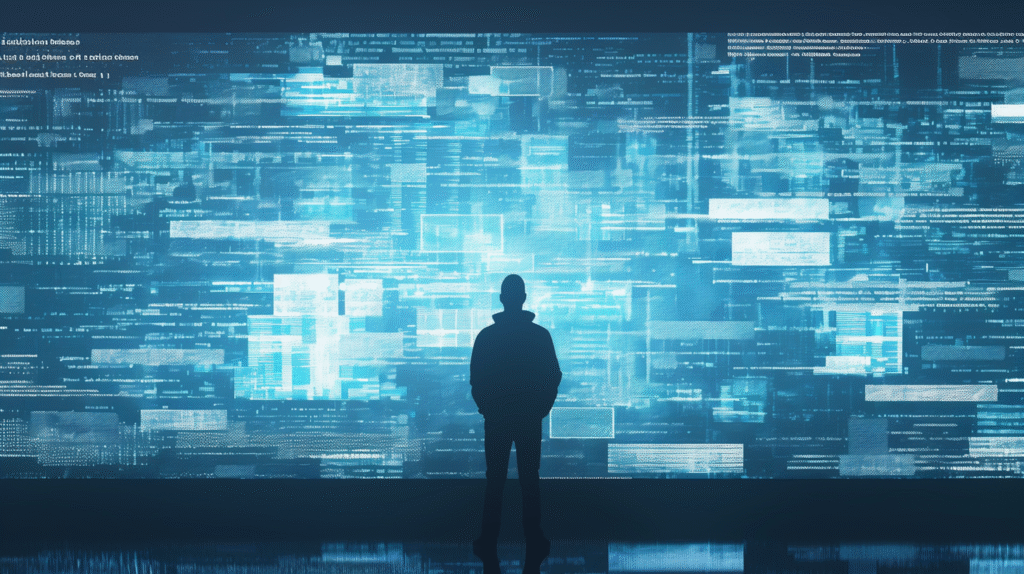
不正アクセスの定義
不正アクセスとは、本来アクセスする権限を持っていない人が、他人のコンピューターやシステムに勝手に侵入する行為のことです。
もっと分かりやすく言うと、あなたの家に勝手に入り込んで、引き出しの中身を見たり、物を盗んだりする泥棒のようなものです。ただし、それがインターネット上で起こっているんですね。
具体的には、以下のような行為が不正アクセスに該当します:
- 他人のIDやパスワードを使って、SNSやメールにログインする
- システムの弱点を突いて、企業のサーバーに侵入する
- ウイルスを使って、パソコンを遠隔操作できる状態にする
- 人を騙してパスワードを聞き出し、それを悪用する
いずれの場合も、「本来の持ち主や管理者以外の人が、許可なく侵入している」というのがポイントです。
不正アクセス禁止法という法律がある
日本では、こうした不正アクセスを防ぐために「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(略して不正アクセス禁止法)という法律が2000年から施行されています。
この法律では、不正アクセスをすることはもちろん、不正アクセスに繋がる行為も禁止しています。たとえば:
- 他人のパスワードを勝手に入手する
- パスワードを第三者に教える
- フィッシング詐欺でパスワードを聞き出そうとする
これらはすべて違法行為です。
罰則も厳しく定められています:
- 不正アクセス行為:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- パスワードの不正取得:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- パスワードの不正提供:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- フィッシング行為:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
「知らなかった」では済まされない、重大な犯罪なんです。
不正アクセスの被害状況を知っておこう
年々増加する不正アクセス
総務省と警察庁が発表したデータによると、2024年に認知された不正アクセスの件数は5,358件でした。前年と比べると少し減少していますが、それでも依然として高い水準で推移しています。
しかも、これは「認知された」件数だけ。実際には、気づかれていない不正アクセスや、報告されていない被害も相当数あると考えられています。
どんな被害が起きているのか
2024年の不正アクセス後に行われた行為を見てみると:
- インターネットバンキングでの不正送金:4,342件
- 最も多い被害がこれです
- 勝手に口座から送金されてしまう
- メールの盗み見などの情報入手:193件
- 重要なメールを読まれる
- 個人情報を盗まれる
- インターネットショッピングでの不正購入:180件
- 勝手に商品を購入される
- クレジットカードを不正利用される
これらの被害は個人だけでなく、企業にも大きな損害を与えています。
実際に起きた被害事例
2024年に実際に起きた代表的な事例をいくつか見てみましょう。
事例1:大手出版社KADOKAWAへの攻撃(2024年6月)
ニコニコ動画を運営するKADOKAWAが大規模なサイバー攻撃を受けました。この攻撃により、ニコニコ動画などの主要サービスが長期間停止。書籍の製造や物流システムにも影響が出て、新刊の発売が遅れる事態になりました。
事例2:JR東日本のシステム障害(2024年5月)
JR東日本がサイバー攻撃を受け、モバイルSuicaやえきねっとが約3時間利用できなくなりました。駅から出られなくなった利用者もいて、大きな混乱が生じました。
事例3:カシオ計算機への攻撃(2024年10月)
カシオ計算機がランサムウェア攻撃を受け、生産システムが停止。クリスマス商戦向けの製品供給が不足し、売上高約130億円、営業利益約40億円という巨額の損失を被りました。
これらは大企業の例ですが、中小企業や個人も標的になっています。「自分には関係ない」と思わず、しっかり対策することが大切です。
不正アクセスの代表的な手口を知ろう
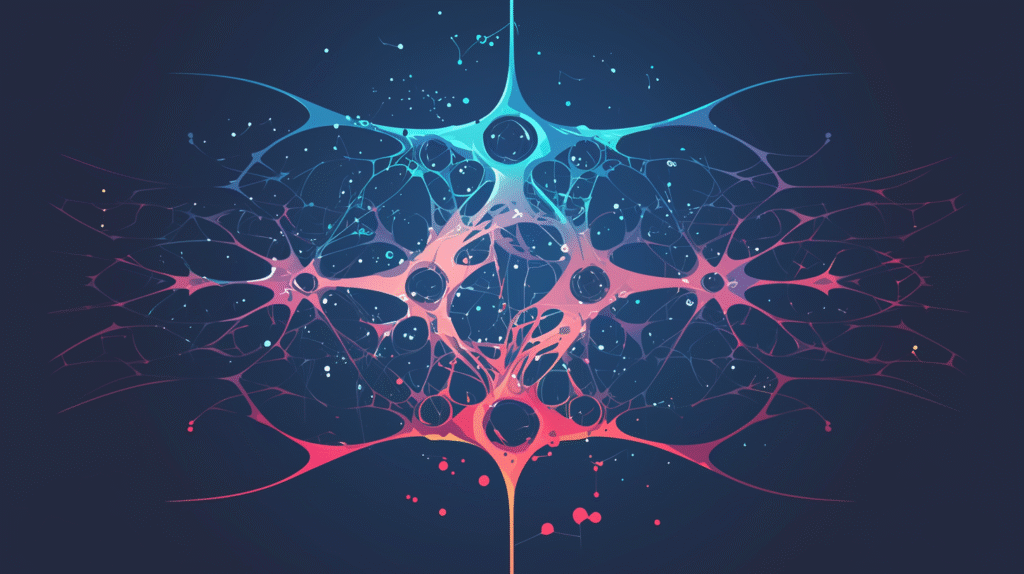
不正アクセスの手口を知っておけば、被害を防ぐヒントになります。代表的な方法を見ていきましょう。
【手口1】パスワードを破る攻撃
ブルートフォースアタック(総当たり攻撃)
考えられるすべてのパスワードの組み合わせを試して、正解を見つけ出す方法です。「総当たり攻撃」とも呼ばれます。
たとえば、「0000」から「9999」まで、すべての4桁の数字を順番に試していくイメージです。パスワードが単純であればあるほど、短時間で破られてしまいます。
辞書攻撃
辞書に載っているような一般的な単語や、よく使われるパスワード(「password」「123456」など)を試す方法です。
多くの人が推測しやすいパスワードを使っているため、この方法でも意外と簡単に侵入できてしまうんです。
パスワードリスト攻撃
他のサイトから流出したID・パスワードのリストを使って、別のサイトでもログインを試みる攻撃です。
同じパスワードを複数のサイトで使い回している人が多いことを利用した手口。一つのサイトから情報が漏れると、芋づる式に他のサイトも被害に遭ってしまいます。
【手口2】フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、本物そっくりの偽サイトに誘導して、IDやパスワードを入力させる詐欺のことです。
よくある流れはこんな感じです:
- 銀行やショッピングサイトを装ったメールが届く
- 「アカウントに問題が発生しました」などと書かれている
- メール内のリンクをクリックすると、本物そっくりの偽サイトに飛ぶ
- そこでIDとパスワードを入力してしまう
- 入力した情報が攻撃者に渡ってしまう
最近のフィッシングサイトは本当に精巧で、見分けるのが難しくなってきています。
【手口3】マルウェア(ウイルス)を使う
マルウェアとは、悪意のあるソフトウェアの総称です。これをパソコンやスマホに感染させることで、様々な情報を盗んだり、遠隔操作したりできるようになります。
感染経路はいろいろありますが、代表的なのは:
- 怪しいメールの添付ファイルを開く
- 不正なウェブサイトにアクセスする
- 偽装されたアプリをインストールする
一度感染すると、キーボードで入力した内容(パスワードなど)が盗まれたり、画面を勝手に撮影されたりします。
【手口4】システムの脆弱性を突く
脆弱性(ぜいじゃくせい)とは、ソフトウェアやシステムに存在するセキュリティ上の弱点のことです。欠陥や不具合とも言えます。
攻撃者はこの弱点を見つけ出し、そこから侵入します。家に例えると、「鍵のかかっていない裏口から侵入する」ようなものですね。
古いバージョンのソフトウェアを使い続けていると、既知の脆弱性を悪用されるリスクが高まります。
【手口5】ソーシャルエンジニアリング
ソーシャルエンジニアリングとは、技術的な手段ではなく、人間の心理的な隙を突いて情報を盗み出す方法です。
具体例を挙げると:
- 社員を装って電話をかけ、パスワードを聞き出す
- IT部門の担当者になりすまして、「確認のため」とパスワードを尋ねる
- ごみ箱に捨てられた書類からパスワードのメモを見つける
- 肩越しにパスワード入力を盗み見る(ショルダーハッキング)
どんなに技術的な対策をしても、人間が騙されてしまえば意味がありません。
不正アクセスされるとどうなる?被害の実態
不正アクセスを受けると、どんな被害が起こるのでしょうか。個人と企業、それぞれの視点で見てみましょう。
個人が受ける被害
金銭的被害
- 銀行口座から勝手に送金される
- クレジットカードを不正利用される
- ポイントやマイルを勝手に使われる
- 仮想通貨が盗まれる
プライバシーの侵害
- メールや写真を勝手に見られる
- SNSアカウントを乗っ取られる
- 個人情報が流出する
- プライベートな情報をネットに晒される
二次被害の危険
- 乗っ取られたアカウントから、友人にウイルスが送られる
- 自分のアカウントが詐欺に利用される
- 流出した情報で新たな犯罪に遭う
企業が受ける被害
情報漏洩による損害
- 顧客情報が流出し、信用を失う
- 機密情報が競合他社に渡る
- 個人情報保護法違反で罰金を科される
- 損害賠償請求を受ける
システム停止による損害
- サービスが使えなくなり、売上が減る
- 業務が停止し、生産性が下がる
- システム復旧に多額の費用がかかる
- 顧客離れが起こる
企業イメージの低下
- 「セキュリティが甘い会社」というレッテルを貼られる
- 株価が下落する
- 取引先からの信頼を失う
- 採用活動にも悪影響が出る
カシオの事例のように、被害額が100億円を超えることもあります。不正アクセスは、企業の存続を脅かすほどの深刻な問題なんです。
不正アクセスから身を守る!効果的な対策
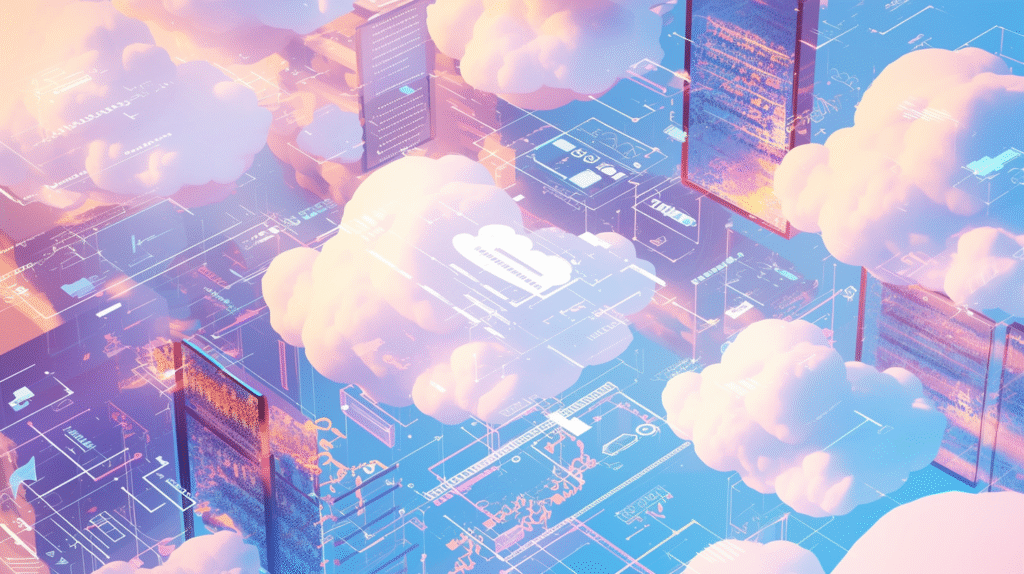
それでは、不正アクセスから身を守るにはどうすればいいのでしょうか。個人でもすぐにできる対策を紹介します。
【対策1】強固なパスワードを設定する
パスワードは不正アクセスを防ぐ最初の砦です。
良いパスワードの条件:
- 12文字以上の長さ
- 大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる
- 辞書に載っている単語をそのまま使わない
- 誕生日や電話番号など、推測されやすい情報を使わない
- サイトごとに異なるパスワードを使う
悪いパスワードの例:
- password123
- 12345678
- 生年月日(19900101など)
- 名前+誕生日(taro0101など)
パスワードの使い回しは絶対にやめましょう。一つ漏れると、すべてのアカウントが危険にさらされます。
【対策2】二段階認証・多要素認証を有効にする
二段階認証(2FA)や多要素認証(MFA)とは、パスワードに加えて、もう一つの認証手段を追加する仕組みです。
たとえば:
- パスワード入力後、スマホに送られてくる確認コードを入力する
- 指紋認証や顔認証を組み合わせる
- 専用アプリで生成されるワンタイムパスワードを使う
これなら、パスワードが漏れても、もう一つの認証をクリアできなければログインできません。セキュリティが格段に向上します。
銀行口座やメールアカウントなど、重要なサービスでは必ず有効にしておきましょう。
【対策3】ソフトウェアを常に最新に保つ
古いバージョンのソフトウェアには、既知の脆弱性があります。攻撃者はこの脆弱性を狙ってきます。
定期的に更新すべきもの:
- パソコンやスマホのOS(WindowsやiOS、Androidなど)
- ウェブブラウザ(Chrome、Safari、Edgeなど)
- アプリケーション全般
- セキュリティソフト
アップデートの通知が来たら、面倒がらずにすぐ実行しましょう。「後でやろう」と放置している間に、攻撃される可能性があります。
【対策4】怪しいメールやリンクをクリックしない
フィッシング詐欺を防ぐには、疑わしいメールに注意することが大切です。
こんなメールは要注意:
- 「アカウントが停止されます」など、不安を煽る内容
- 文章が不自然だったり、誤字脱字が多い
- 送信元のメールアドレスが公式と微妙に違う
- 添付ファイルやリンクをクリックするよう促してくる
安全な対処法:
- メール内のリンクは直接クリックせず、公式サイトに自分でアクセスする
- 公式アプリを使ってログインし、状況を確認する
- 不安な場合は、公式のカスタマーサポートに問い合わせる
「おかしいな」と感じたら、まず疑ってかかることが重要です。
【対策5】セキュリティソフトを導入する
信頼できるセキュリティソフト(ウイルス対策ソフト)をインストールしておくと、マルウェアの感染を防げます。
セキュリティソフトができること:
- ウイルスやマルウェアを検出・削除する
- 危険なウェブサイトへのアクセスをブロックする
- フィッシングサイトを警告する
- ファイアウォールで不正な通信を遮断する
無料のソフトでも基本的な保護は可能ですが、より高度な機能が必要なら有料版の検討もおすすめです。
【対策6】公共Wi-Fiでの利用に注意する
カフェや駅などの公共Wi-Fiは便利ですが、セキュリティが弱いことがあります。
公共Wi-Fiでの注意点:
- 銀行やクレジットカードのサイトにはアクセスしない
- 重要な情報を入力しない
- VPN(仮想プライベートネットワーク)を使って通信を暗号化する
本当に必要な場合以外は、自分のスマホのモバイルデータ通信を使う方が安全です。
【対策7】定期的にアカウントの状況を確認する
不正アクセスに早く気づくことも重要です。
定期的にチェックすること:
- 銀行口座の入出金明細
- クレジットカードの利用履歴
- ログイン履歴(いつ、どこからログインしたか)
- アカウントの設定変更履歴
見覚えのない取引やログインがあったら、すぐにパスワードを変更し、サービス提供元に連絡しましょう。
もし不正アクセスされたら?被害に遭った時の対処法
どんなに対策をしていても、100%防げるわけではありません。万が一、不正アクセスの被害に遭ってしまったら、落ち着いて以下の手順で対応しましょう。
【ステップ1】すぐにパスワードを変更する
まず最優先で、被害に遭ったアカウントのパスワードを変更してください。
もし同じパスワードを他のサイトでも使っていたら、そちらも全部変更しましょう。
【ステップ2】サービス提供元に連絡する
銀行、クレジットカード会社、SNSなど、被害に遭ったサービスの運営元にすぐ連絡します。
状況を説明すれば、適切な対応をしてくれます。場合によっては、不正な取引をキャンセルしてもらえることもあります。
【ステップ3】二段階認証を設定する
まだ設定していなかった場合は、この機会に必ず二段階認証を有効にしましょう。
【ステップ4】被害状況を記録する
いつ、どんな被害に遭ったか、詳細を記録しておきます。
スクリーンショットを撮ったり、メモを残したりしておくと、後で警察に相談する際に役立ちます。
【ステップ5】警察に相談する
金銭的被害が出ている場合や、個人情報が悪用されている場合は、最寄りの警察署に相談しましょう。
サイバー犯罪相談窓口もあります。都道府県警察のサイトで連絡先を確認できます。
【ステップ6】周囲の人に注意喚起する
自分のアカウントから友人に怪しいメッセージが送られている可能性があります。
SNSなどで「アカウントが乗っ取られました。不審なメッセージは開かないでください」と注意喚起しましょう。
企業が取るべき不正アクセス対策

個人だけでなく、企業にも高度なセキュリティ対策が求められています。
技術的な対策
ファイアウォールの導入
不正な通信をブロックするシステムです。外部からの攻撃を防ぐ最初の防波堤になります。
侵入検知システム(IDS)・侵入防止システム(IPS)
不正なアクセスを検知し、自動的にブロックするシステムです。
定期的な脆弱性診断
システムに脆弱性がないか、専門家がチェックします。問題が見つかったら、すぐに修正することが大切です。
データの暗号化
万が一情報が盗まれても、暗号化されていれば内容を読み取られにくくなります。
バックアップの定期実施
ランサムウェア攻撃などでデータが使えなくなっても、バックアップがあれば復旧できます。ただし、バックアップも攻撃されないよう、オフラインで保管するなどの工夫が必要です。
人的な対策
従業員へのセキュリティ教育
どんなに技術的な対策をしても、従業員が騙されてしまえば意味がありません。定期的にセキュリティ研修を実施し、最新の手口を共有しましょう。
アクセス権限の適切な管理
すべての従業員に全ての情報へのアクセス権を与えるのではなく、必要最小限の権限だけを与えます。
インシデント対応計画の策定
不正アクセスが発覚したときに、どう対応するか事前に計画を立てておきます。迅速な対応が被害の拡大を防ぎます。
まとめ:不正アクセス対策は「備えあれば憂いなし」
不正アクセスについて、基本から対策まで詳しく解説してきました。
もう一度、重要なポイントをおさらいしましょう:
不正アクセスとは
- 本来アクセス権限のない人が、他人のシステムに侵入する行為
- 不正アクセス禁止法で厳しく罰せられる犯罪行為
- 個人も企業も被害に遭う可能性がある
主な手口
- パスワードを破る攻撃(ブルートフォース、辞書攻撃、パスワードリスト攻撃)
- フィッシング詐欺
- マルウェア感染
- システムの脆弱性を突く攻撃
- ソーシャルエンジニアリング
今すぐできる対策
- 強固なパスワードを設定し、サイトごとに変える
- 二段階認証を必ず有効にする
- ソフトウェアを常に最新に保つ
- 怪しいメールやリンクをクリックしない
- セキュリティソフトを導入する
- 公共Wi-Fiでの重要な操作を避ける
- 定期的にアカウントの状況を確認する
不正アクセスは他人事ではありません。でも、正しい知識と適切な対策があれば、リスクを大幅に減らすことができます。
「自分は大丈夫」と油断せず、今日からできることから始めてみませんか?この記事で紹介した対策を一つずつ実践していけば、あなたの大切な情報や資産をしっかり守れるはずです。
デジタル社会を安全に楽しむために、セキュリティ意識を高く持ち続けましょう!







