パソコンのモニターを買う時や、ゲーミングPCを組み立てる時に「DisplayPort」という端子を見たことはありませんか?
「HDMIとどう違うの?」「どっちを使えばいいの?」と迷う方も多いはずです。
実はDisplayPortは、特に高解像度や高リフレッシュレートのディスプレイを使う際に威力を発揮する規格なんです。
今回は、DisplayPortの基本から、HDMIとの違い、実際の使い方まで分かりやすく解説していきますね。
DisplayPortとは何か?
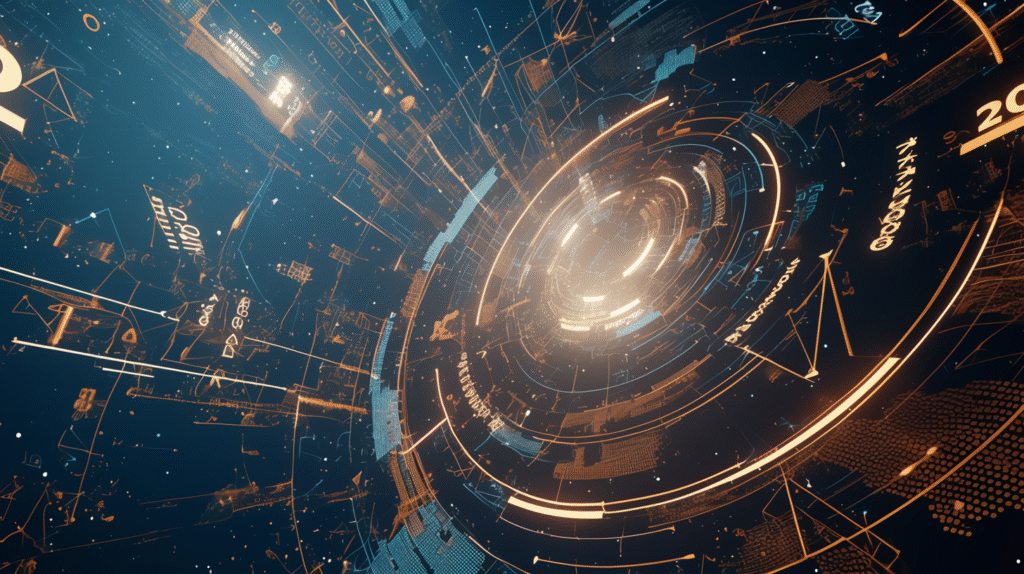
パソコン向けに開発された映像出力規格
DisplayPort(ディスプレイポート)は、パソコンやモニターなどのデジタル映像・音声を伝送するための接続規格です。
2006年に業界団体「VESA(Video Electronics Standards Association)」によって策定されました。
主にパソコンのグラフィックボードとモニターを接続する用途で使われています。
一つのケーブルで映像も音声も伝送
DisplayPortケーブル1本で、以下のものを同時に送ることができます:
- 高解像度の映像信号
- 高品質な音声信号
- データ通信
複数のケーブルを使わなくても、モニターとパソコンをスッキリ接続できるんです。
DisplayPortの主な特徴
高解像度・高リフレッシュレートに対応
DisplayPortの最大の強みは、非常に高いデータ転送速度です。
バージョン別の対応解像度:
DisplayPort 1.2
- 4K(3840×2160)60Hz
- フルHD(1920×1080)144Hz
DisplayPort 1.4
- 4K 120Hz
- 8K(7680×4320)60Hz
- フルHD 240Hz
DisplayPort 2.0(2.1)
- 4K 240Hz
- 8K 120Hz
- 10K(10240×4320)60Hz
特にゲーミングモニターや、プロ向けの制作環境で重宝されています。
デイジーチェーン接続が可能
DisplayPortの独自機能として、デイジーチェーン接続があります。
これは、一つのDisplayPort出力から複数のモニターを数珠つなぎに接続できる機能です。
接続例:
パソコン → モニター1 → モニター2 → モニター3
グラフィックボードの端子が足りない時に便利な機能ですね。
ただし、全てのモニターがMST(Multi-Stream Transport)に対応している必要があります。
可変リフレッシュレートに対応
DisplayPortは、Adaptive-Sync(アダプティブシンク)という技術に標準対応しています。
これは、GPUの描画速度に合わせてモニターのリフレッシュレートを自動調整する機能。
ゲームプレイ時の画面のカクつきやティアリング(画面の分断)を防いでくれます。
この技術は、AMDの「FreeSync」やNVIDIAの「G-SYNC Compatible」として実装されています。
HDMIとの違い
DisplayPortとよく比較されるのがHDMI(High-Definition Multimedia Interface)です。
どちらも映像と音声を伝送できますが、用途や特徴が異なります。
主な違い一覧
開発目的
- DisplayPort:パソコンとモニターの接続用
- HDMI:家電製品(テレビ、ゲーム機など)用
コネクタ形状
- DisplayPort:角張った形状、片側に爪(ロック機構)あり
- HDMI:台形の形状、ロック機構なし
データ転送速度
- DisplayPort 2.0:最大77.4Gbps
- HDMI 2.1:最大48Gbps
マルチモニター対応
- DisplayPort:デイジーチェーン接続可能
- HDMI:各モニターに個別接続が必要
ライセンス料
- DisplayPort:ロイヤリティフリー(無料)
- HDMI:製造時にライセンス料が必要
主な使用機器
- DisplayPort:パソコン、ゲーミングモニター、業務用ディスプレイ
- HDMI:テレビ、ゲーム機、レコーダー、プロジェクター
どちらを選ぶべき?
DisplayPortがおすすめの場合:
- パソコンでゲームをプレイする(144Hz以上のモニター)
- 4K以上の高解像度で作業する
- 複数モニターをデイジーチェーン接続したい
- プロ向けのクリエイティブ作業をする
HDMIがおすすめの場合:
- テレビにパソコンを接続する
- ゲーム機(PlayStation、Xboxなど)を使う
- プロジェクターに接続する
- 一般的な用途(フルHD 60Hz程度)
結論として、パソコンのモニター接続ならDisplayPort、家電との接続ならHDMIが基本です。
DisplayPortのバージョンについて
進化する転送速度と機能
DisplayPortは何度もバージョンアップを重ねており、新しいバージョンほど高性能になっています。
DisplayPort 1.2(2010年)
- 最大帯域幅:21.6Gbps
- 4K 60Hz対応
- MST(マルチストリーム)機能追加
- 現在でも多くの機器で採用
DisplayPort 1.3(2014年)
- 最大帯域幅:32.4Gbps
- 4K 120Hz、5K 60Hz対応
DisplayPort 1.4(2016年)
- 最大帯域幅:32.4Gbps(1.3と同じ)
- Display Stream Compression(DSC)追加
- 8K 60Hz対応(DSC使用時)
- HDR対応強化
DisplayPort 2.0(2019年)
- 最大帯域幅:77.4Gbps
- 8K 60Hz対応(非圧縮)
- 4K 240Hz、10K 60Hz対応
DisplayPort 2.1(2022年)
- 2.0の改良版
- 帯域幅は同じだが、より効率的な伝送
バージョンには下位互換性があるため、新しいケーブルで古い機器も使えます。
確認方法
お使いの機器がどのバージョンに対応しているかは:
- パソコンやモニターの仕様書を確認
- グラフィックボードの製品情報を見る
- デバイスマネージャーで確認する
といった方法で調べられます。
DisplayPortの種類
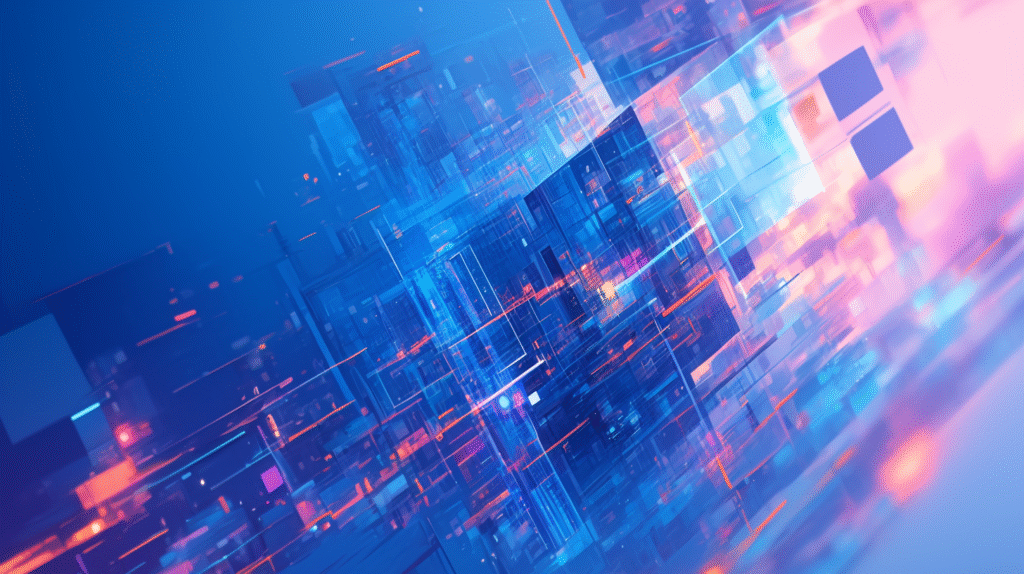
Standard DisplayPort
一般的なサイズのDisplayPort端子です。
デスクトップPCのグラフィックボードや、モニターの入力端子として最も普及しています。
コネクタの片側に小さな爪がついており、抜け落ち防止のロック機構があります。
Mini DisplayPort
Mini DisplayPort(ミニディスプレイポート)は、名前の通り小型化された端子です。
Apple製品(旧MacBook Proなど)や、一部のノートPCに搭載されていました。
現在は、USB Type-Cに置き換わりつつあります。
USB Type-C(Alternate Mode)
最近のノートPCやモバイルモニターでは、USB Type-C端子でDisplayPort信号を伝送できます。
これを「DisplayPort Alternate Mode(Alt Mode)」と呼びます。
USB Type-Cケーブル1本で:
- 映像出力
- 音声出力
- データ転送
- 電力供給(デバイスの充電)
全てができるため、非常に便利です。
ただし、全てのUSB Type-C端子がDisplayPort Alt Modeに対応しているわけではないので注意が必要です。
ケーブルの選び方
長さに注意
DisplayPortケーブルは、長さによって信号の劣化が起こる可能性があります。
推奨される長さ:
- 通常使用:2m以下が理想
- 高解像度・高リフレッシュレート:1m〜1.5m以内
3mを超える場合は、アクティブケーブル(信号増幅機能付き)を選ぶと安心です。
認証マークを確認
VESAによる認証マーク「VESA Certified」がついているケーブルを選びましょう。
認証済みケーブルは、規格に準拠した性能が保証されています。
バージョンに注意
4K 120Hz以上や8Kを使いたい場合は、DisplayPort 1.4以上対応のケーブルが必要です。
古いケーブルを使うと、性能を発揮できないことがあります。
ケーブルのパッケージや製品説明に、対応バージョンが記載されているので確認しましょう。
変換アダプタについて
DisplayPort → HDMI
DisplayPort出力をHDMI入力に変換するアダプタが市販されています。
使用例:
- グラフィックボードのDisplayPortをテレビのHDMI端子に接続
- プロジェクターでプレゼンする
変換時は、HDMI側の性能に制限されます。
HDMI → DisplayPort
逆方向の変換(HDMI出力をDisplayPort入力へ)は、アクティブ変換アダプタが必要です。
信号形式が異なるため、単純な形状変換だけでは動作しません。
価格も高めで、動作が不安定なこともあるため、可能であれば避けたほうが無難です。
DVI・VGA → DisplayPort
古いモニターやプロジェクターと接続する場合も、変換アダプタが使えます。
ただし、古い規格の制限を受けるため、解像度やリフレッシュレートが低くなります。
トラブルシューティング
画面が映らない
原因と対処法:
ケーブルの接続不良
- しっかりと奥まで差し込む
- ロック機構が正しく掛かっているか確認
入力ソースの選択ミス
- モニターの入力切替ボタンでDisplayPortを選択
ケーブルの不良
- 別のケーブルで試してみる
解像度やリフレッシュレートの設定ミス
- パソコン側の設定を下げて試す
音声が出ない
DisplayPort経由でモニターから音を出す場合:
Windows設定を確認
- タスクバーの音量アイコンを右クリック
- 「サウンドの設定を開く」を選択
- 出力デバイスでモニターを選択
モニター側の設定
- モニターにスピーカーが内蔵されているか確認
- モニターの音量設定を確認
画面がチラつく・色が変
考えられる原因:
- ケーブルの品質が低い
- ケーブルが長すぎる
- ケーブルが断線している
- グラフィックドライバが古い
対処法:
- 認証済みの高品質ケーブルに交換
- ケーブルを短いものに変更
- グラフィックドライバを最新版に更新
よくある質問
DisplayPortとThunderboltの違いは?
Thunderboltは、Intelが開発した高速データ転送規格です。
Thunderbolt 3以降はUSB Type-Cコネクタを使用し、DisplayPort信号も伝送できます。
つまり、ThunderboltはDisplayPortの機能を含む、より高機能な規格と言えます。
デイジーチェーンには何台まで繋げる?
理論上は、最大63台までのモニターをデイジーチェーン接続できます。
ただし、実際には帯域幅の制限があるため、4Kモニターなら2〜3台が現実的です。
解像度を下げれば、より多くのモニターを接続できます。
ゲームにはDisplayPortとHDMI、どちらが良い?
PCゲームなら、144Hz以上の高リフレッシュレートに対応しやすいDisplayPortがおすすめです。
家庭用ゲーム機(PS5、Xbox Series Xなど)の場合は、本体がHDMIしか搭載していないため、HDMI一択になります。
まとめ:用途に応じてDisplayPortを活用しよう
DisplayPortは、パソコンとモニターを接続するための高性能な映像出力規格です。
特に高解像度・高リフレッシュレートのゲーミング環境や、クリエイティブな作業環境で真価を発揮します。
この記事のポイント:
- パソコンとモニター接続用に開発された規格
- 高解像度・高リフレッシュレートに強い
- デイジーチェーン接続が可能
- HDMIよりも高いデータ転送速度
- バージョンによって性能が異なる
- USB Type-CでもDisplayPort信号を伝送可能
- ゲーミングPCには特におすすめ
- 変換アダプタで他の規格とも接続可能
一般的な用途(フルHD 60Hz程度)であれば、HDMIでも十分です。
しかし、4K以上の解像度や144Hz以上のリフレッシュレートを活用したい場合は、DisplayPortの選択を検討してみてください。
自分の使用目的に合わせて、最適な接続方法を選びましょう!







