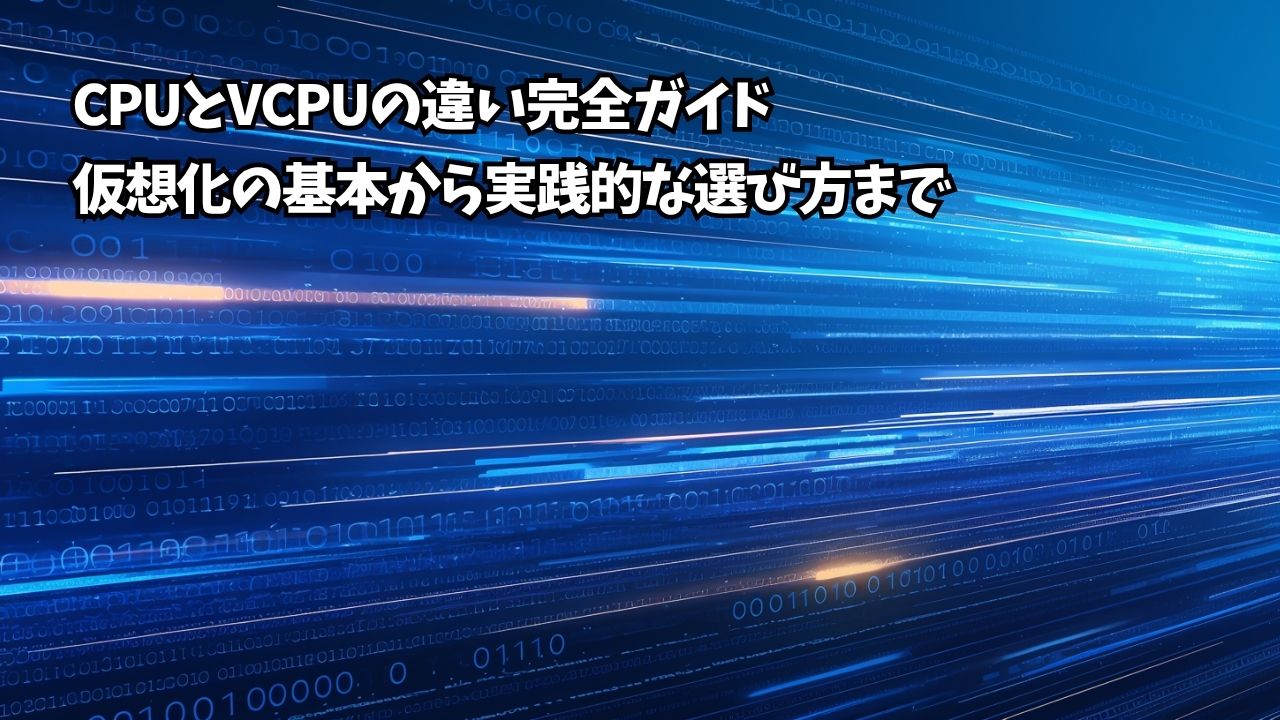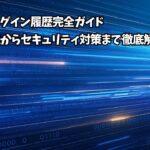クラウドサービスやレンタルサーバーを選ぶ時、「vCPU」という言葉を見かけたことはありませんか?
「CPUとvCPUって何が違うの?」
「vCPU 2コアは、本当に2つのCPUがあるの?」
「性能はどれくらい違うの?」
実は、CPUとvCPUは全く異なる概念です。この違いを理解していないと、期待した性能が出なかったり、無駄にコストをかけてしまったりすることがあるんです。
この記事では、CPUとvCPUの基本から、実際の性能差、選び方のポイントまで、初心者にも分かりやすく解説していきます。
クラウドサービスを賢く選びたい方、仮想化技術を理解したい方は必見ですよ。
CPUとは?基本を理解しよう
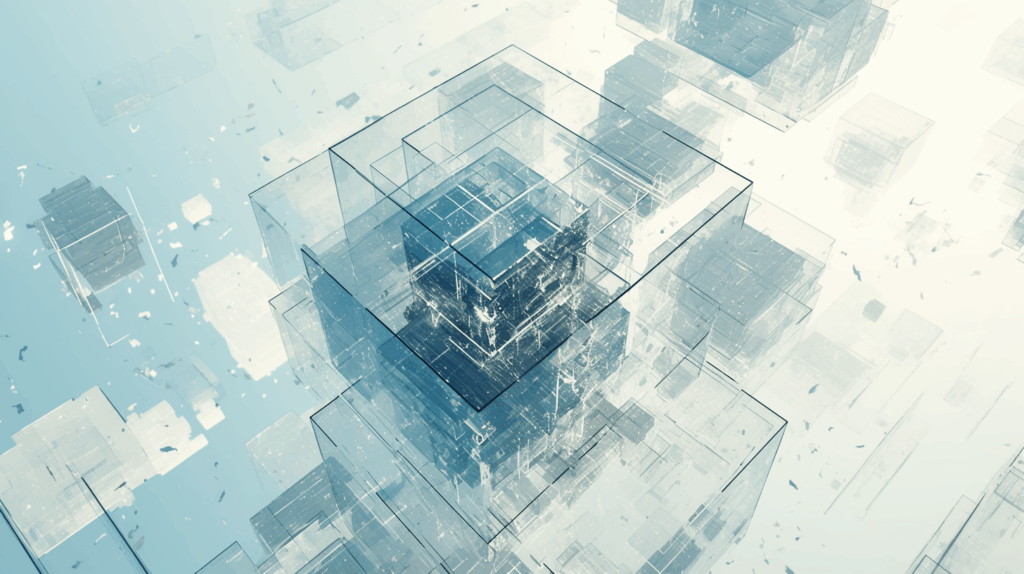
まずは、通常の「CPU」について確認しておきましょう。
CPUの基本
CPU(Central Processing Unit)は、日本語で「中央処理装置」と呼ばれ、コンピュータの頭脳にあたる部品です。
計算や処理を実行する役割を担っています。パソコンやスマホ、サーバーなど、すべてのコンピュータに搭載されている物理的な部品ですね。
主なメーカー:
- Intel(インテル)
- AMD(エーエムディー)
- ARM(アーム)
- Apple(Apple Silicon)
物理CPU・コア・スレッドの違い
CPU関連の用語は混同しやすいので、整理しておきましょう。
物理CPU(プロセッサ):
マザーボードに実際に取り付けられているCPUチップのこと。
1台のサーバーに複数の物理CPUを搭載できます。
コア(Core):
1つのCPUチップの中にある、実際に計算を行う処理ユニットのこと。
現代のCPUは、複数のコアを持つ「マルチコア」が一般的です。
例:
- デュアルコア:2つのコア
- クアッドコア:4つのコア
- オクタコア:8つのコア
スレッド(Thread):
1つのコアが同時に処理できる作業の流れのこと。
インテルの「ハイパースレッディング」やAMDの「SMT」技術により、1つのコアで2つのスレッドを処理できます。
具体例:
物理CPU:1個
コア数:4個
スレッド数:8個(1コアあたり2スレッド)この場合、「4コア8スレッド」と表現されます。
vCPUとは?仮想化の世界
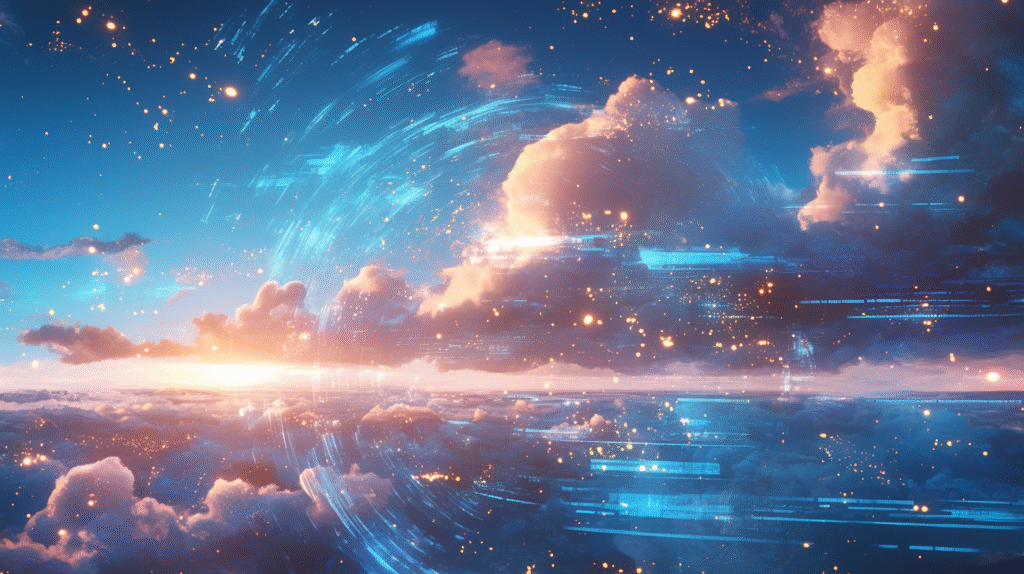
次に、「vCPU」について見ていきましょう。
vCPUの基本
vCPU(Virtual CPU)は、「仮想CPU」のこと。
物理的なCPUチップが存在するわけではなく、ソフトウェアで作られた仮想的なCPUです。
仮想化技術:
1台の物理サーバーを、あたかも複数台のサーバーがあるかのように分割して使う技術を「仮想化」と呼びます。この時、各仮想マシンに割り当てられるCPUリソースがvCPUです。
イメージ:
大きな一軒家(物理サーバー)を、複数の部屋(仮想マシン)に分けて、それぞれの住人(アプリケーション)に貸し出す。
各部屋に割り当てられる電力の一部(vCPU)のようなものですね。
どこで使われる?
vCPUは、以下のような環境で使われています。
クラウドサービス:
- AWS(Amazon Web Services)
- Google Cloud Platform(GCP)
- Microsoft Azure
- さくらのクラウド
仮想化プラットフォーム:
- VMware
- Hyper-V
- KVM
- VirtualBox
コンテナ技術:
- Docker
- Kubernetes
これらのサービスやツールを使う時、「vCPU」という単位でCPUリソースを指定します。
vCPUの割り当て方
物理CPUのリソースを、どうやってvCPUとして分配するのでしょうか?
基本的な仕組み:
- 物理サーバーに搭載されたCPUリソース(コア数×スレッド数)を把握
- ハイパーバイザー(仮想化ソフト)が、このリソースを管理
- 各仮想マシンに、必要な分のvCPUを割り当て
- ハイパーバイザーが、物理CPUの処理時間を各仮想マシンに分配
例:
物理サーバー:8コア16スレッド
仮想マシンA:vCPU 2個
仮想マシンB:vCPU 4個
仮想マシンC:vCPU 2個
合計:vCPU 8個この例では、物理的な16スレッドのうち、8個分のリソースを仮想マシンに割り当てています。
CPUとvCPUの5つの違い
それでは、具体的な違いを見ていきましょう。
違い1:実体の有無
CPU:
物理的に存在するハードウェア。手で触れる実体があります。
vCPU:
ソフトウェアで作られた仮想的な存在。物理的な実体はありません。
違い2:性能の保証
CPU:
専有できるため、性能が保証されています。他の処理の影響を受けません。
vCPU:
物理CPUのリソースを分け合うため、他の仮想マシンの負荷によって性能が変動することがあります。
例:
同じ物理サーバー上の他の仮想マシンが高負荷な処理をしていると、自分のvCPUの性能が低下することがあります。これを「ノイジーネイバー問題」と呼びます。
違い3:リソースの柔軟性
CPU:
物理的な制約があります。コア数を増やすには、CPUを交換するか、追加で購入する必要があります。
vCPU:
設定変更だけで、数分でvCPU数を増減できます。必要に応じてスケールアップ・スケールダウンが容易です。
例:
突然アクセスが増えた時、AWSなどのクラウドサービスでは、数クリックでvCPU数を増やせます。
違い4:コスト
CPU:
物理的なハードウェアを購入する必要があり、初期投資が大きくなります。
vCPU:
従量課金制が一般的。使った分だけ支払えばよく、初期投資が少なくて済みます。
コスト例(AWS EC2):
- t3.micro(vCPU 2個、メモリ1GB):約1,000円/月
- 物理サーバー購入:数十万円〜
違い5:1対1対応ではない
重要なポイント:
vCPU 1個 ≠ 物理コア 1個
vCPUと物理コアは、1対1で対応しているわけではありません。
例:
物理サーバーに8コアのCPUがあっても、16個以上のvCPUを割り当てることができます。これを「オーバーコミットメント」と呼びます。
オーバーコミットメントとは
vCPUの重要な概念、オーバーコミットメントについて詳しく見てみましょう。
基本的な仕組み
オーバーコミットメント(Overcommitment)とは、物理CPUのコア数やスレッド数よりも多くのvCPUを割り当てること。
例:
物理サーバー:4コア8スレッド
割り当て:
仮想マシンA:vCPU 4個
仮想マシンB:vCPU 4個
仮想マシンC:vCPU 4個
合計:vCPU 12個(物理スレッド8個に対して)この場合、オーバーコミット比率は 12 ÷ 8 = 1.5倍 です。
なぜオーバーコミットするのか
理由1:効率的なリソース利用
すべての仮想マシンが常に100%のCPUを使うわけではありません。
多くのアプリケーションは、実際にはCPUをフル活用していない時間が多いんです。その「遊んでいる時間」を他の仮想マシンに回すことで、物理リソースを効率的に使えます。
理由2:コスト削減
物理サーバーの台数を減らせるため、ハードウェアコスト、電気代、スペースなどを節約できます。
オーバーコミットのリスク
性能低下:
複数の仮想マシンが同時に高負荷になると、すべてのパフォーマンスが低下します。
予測不可能な性能:
他の仮想マシンの状況に依存するため、安定したパフォーマンスが得られないことがあります。
適切なオーバーコミット比率
推奨値:
- 通常のワークロード:1.5〜2倍
- 軽い負荷(開発環境など):3〜4倍
- 重い負荷(データベースなど):1〜1.5倍
- ミッションクリティカル:オーバーコミットなし
用途に応じて、適切な比率を選ぶことが重要です。
性能の違いを理解する
実際の性能は、どれくらい違うのでしょうか?
ベンチマーク比較
同じスペックのCPUでも、物理と仮想では性能差があります。
一般的な傾向:
物理CPU:100%
vCPU(オーバーコミットなし):90〜95%
vCPU(2倍オーバーコミット):50〜70%
vCPU(4倍オーバーコミット):25〜40%ただし、これは目安であり、実際の性能は以下の要因で変動します。
性能に影響する要因
1. ハイパーバイザーのオーバーヘッド
仮想化には、ハイパーバイザー(仮想化ソフト)が必要です。このソフトウェアも少しCPUリソースを消費するため、わずかな性能低下が起こります。
通常、5〜10%程度のオーバーヘッドがあります。
2. 他の仮想マシンの負荷
同じ物理サーバー上の他の仮想マシンが高負荷だと、自分のvCPUも影響を受けます。
3. CPU affinity設定
特定の物理コアに固定する設定(CPU affinity)を使うと、性能の安定性が向上します。
4. NUMAアーキテクチャ
複数の物理CPUを搭載したサーバーでは、メモリアクセスの効率が性能に影響します。
体感速度の違い
数字だけでなく、実際の使用感も重要です。
物理CPU:
- 常に安定した高速動作
- 瞬間的な高負荷にも即座に対応
- レスポンスが予測可能
vCPU:
- 通常時は快適だが、時々もたつくことがある
- ピーク時の性能が不安定
- 他の仮想マシンの影響を受ける
用途別の推奨:
- Webサーバー(中程度の負荷):vCPUで十分
- データベースサーバー(高負荷):物理CPU推奨
- 開発環境:vCPUで問題なし
- ゲームサーバー(リアルタイム性重視):物理CPU推奨
クラウドサービスでのvCPU
実際のクラウドサービスでは、どうvCPUが使われているか見てみましょう。
AWS(Amazon Web Services)
AWSでは、EC2インスタンスでvCPUを提供しています。
インスタンスタイプ例:
- t3.micro:vCPU 2個(バースト可能)
- t3.medium:vCPU 2個
- c5.large:vCPU 2個(コンピューティング最適化)
- m5.xlarge:vCPU 4個
バースト可能インスタンス:
T3やT2インスタンスは、通常時は低いCPU利用率で動作し、必要な時だけ高性能を発揮する「バースト」機能があります。
Google Cloud Platform(GCP)
GCPでは、Compute EngineでvCPUを提供しています。
マシンタイプ例:
- e2-micro:vCPU 2個(共有コア)
- n1-standard-1:vCPU 1個
- n2-standard-4:vCPU 4個
共有コアと専有コア:
- 共有コア:物理CPUを他のユーザーと共有(低コスト)
- 専有コア:専有的に使える(高性能、高コスト)
Microsoft Azure
Azureでは、仮想マシンでvCPUを提供しています。
VMサイズ例:
- B1s:vCPU 1個
- D2s_v3:vCPU 2個
- F4s_v2:vCPU 4個(コンピューティング最適化)
各社のvCPU性能比較
クラウドプロバイダーによって、vCPUの性能は異なります。
性能の違いの要因:
- 使用している物理CPUの世代
- オーバーコミット比率
- ハイパーバイザーの種類
- ネットワークやストレージとの統合
一般的には、専有インスタンス > 汎用インスタンス > バースト可能インスタンス の順で性能が高くなります。
適切な選び方のポイント
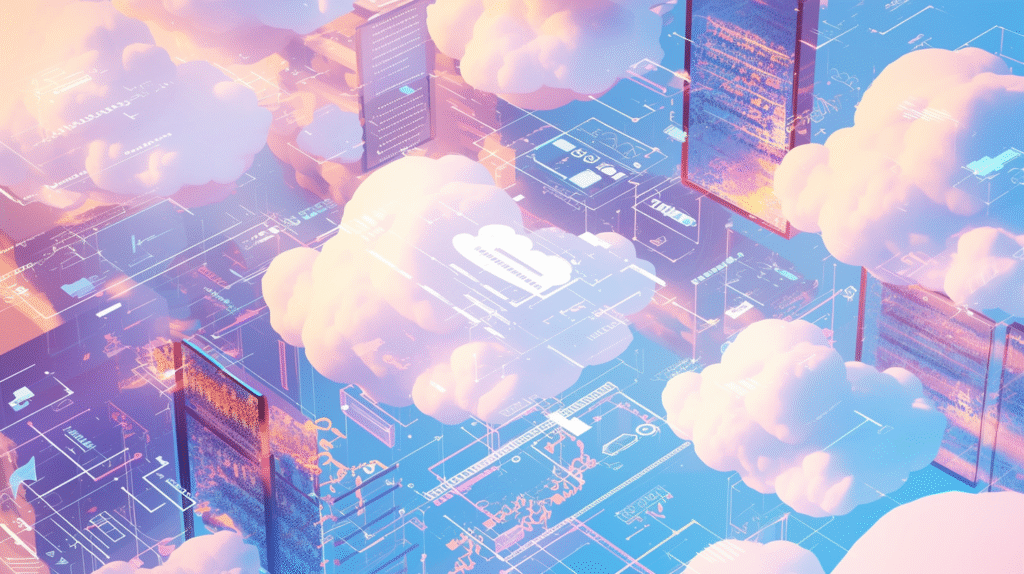
CPUとvCPU、どちらを選ぶべきか判断する基準です。
物理CPUを選ぶべき場合
1. 高い性能が必要
- リアルタイム処理
- 大規模なデータベース
- ゲームサーバー
2. 性能の安定性が重要
- 金融取引システム
- 医療システム
- ミッションクリティカルなアプリケーション
3. 専有リソースが必須
- セキュリティ要件が厳しい
- コンプライアンス上の理由
4. 長期的なコスト
- 常時稼働するサーバー
- 3年以上使う予定
vCPUを選ぶべき場合
1. 柔軟性が必要
- 負荷が変動する
- スケールアップ・ダウンが必要
- テスト環境
2. 初期投資を抑えたい
- スタートアップ
- 小規模プロジェクト
- 短期間のプロジェクト
3. 管理の手間を減らしたい
- 保守やメンテナンスをクラウド事業者に任せたい
- サーバー管理の専門知識がない
4. 中程度の負荷
- Webサーバー
- アプリケーションサーバー
- 開発環境
ハイブリッド構成
物理サーバーとクラウド(vCPU)を組み合わせる構成も有効です。
例:
- データベース:物理サーバー(高性能・安定性)
- Webサーバー:クラウド(柔軟性・スケーラビリティ)
- バッチ処理:クラウド(必要な時だけ使用)
よくある誤解と注意点
CPUとvCPUに関する、よくある勘違いを解消しましょう。
誤解1:vCPU 4個 = 4コアCPU
間違い:
vCPU 4個は、4コアの物理CPUと同じ性能だと思っている。
正解:
vCPUは物理CPUのリソースを分け合うため、性能は大きく異なります。オーバーコミット比率や他の仮想マシンの影響を受けます。
誤解2:vCPUは常に遅い
間違い:
vCPUは物理CPUより必ず遅いと思っている。
正解:
オーバーコミットなし、専有インスタンスの場合、物理CPUに近い性能が出ます。また、クラウド事業者は最新の高性能CPUを使っているため、古い物理サーバーより速いこともあります。
誤解3:vCPU数は多ければ多いほど良い
間違い:
とにかくvCPU数を増やせば性能が上がると思っている。
正解:
アプリケーションが並列処理に対応していない場合、vCPUを増やしても性能は向上しません。シングルスレッド性能が重要な場合もあります。
誤解4:クラウドは必ず安い
間違い:
クラウド(vCPU)は常に物理サーバーより安いと思っている。
正解:
短期間や小規模なら安いですが、大規模で長期間使う場合、物理サーバーの方がコストが低くなることもあります。
実践例:最適な構成の選び方
具体的なシナリオで、最適な選択を考えてみましょう。
シナリオ1:個人ブログ
要件:
- 月間1万PV程度
- WordPressで運用
- 予算は月1,000円程度
推奨構成:
- VPS(vCPU 1〜2個)
- 例:ConoHa VPS(vCPU 2個、メモリ1GB)月額1,000円程度
理由:
低コストで十分な性能。物理サーバーを買う必要はありません。
シナリオ2:中規模Webサービス
要件:
- 月間100万PV
- データベースとWebサーバー
- 可用性が重要
推奨構成:
- クラウド(AWS、GCPなど)
- Webサーバー:vCPU 2〜4個 × 複数台(ロードバランサー配下)
- データベース:vCPU 4〜8個(専有インスタンス推奨)
理由:
スケーラビリティと可用性を確保しつつ、コストを抑えられます。
シナリオ3:大規模データ処理
要件:
- 機械学習の学習処理
- 大量のデータ処理
- 計算速度が重要
推奨構成:
- 物理サーバーまたはベアメタルクラウド
- 高性能CPU(AMD EPYC、Intel Xeonなど)
- 必要に応じてGPUも追加
理由:
計算集約的な処理では、物理CPUの安定した高性能が必要です。
よくある質問と回答
Q1:vCPUは物理CPUより必ず遅い?
必ずしもそうではありません。オーバーコミットがなく、最新の高性能CPUを使ったクラウドインスタンスは、古い物理サーバーより速いこともあります。
Q2:vCPU 1個は、物理コア何個分?
一概には言えません。オーバーコミット比率、他の仮想マシンの負荷、ハイパーバイザーのオーバーヘッドなど、多くの要因に依存します。目安として、0.3〜0.8物理コア分程度と考えるのが妥当です。
Q3:AWSとGCPとAzure、どれが速い?
同じvCPU数でも性能は異なります。ベンチマークでは、インスタンスタイプや用途によって優劣が変わります。実際の用途でテストするのが最も確実です。
Q4:物理サーバーからクラウドに移行すると、どれくらいvCPUが必要?
一般的には、物理コア数の1.5〜2倍のvCPUが目安です。ただし、負荷状況やアプリケーションの特性によって異なるため、実測が重要です。
Q5:vCPUを増やせば、必ず速くなる?
いいえ。アプリケーションが並列処理に対応していない場合、vCPUを増やしても性能は向上しません。ボトルネックがCPUにない場合(メモリやディスクIO)も効果がありません。
Q6:物理CPUのコア数を確認する方法は?
Linuxなら lscpu コマンド、Windowsなら タスクマネージャー→パフォーマンス→CPU で確認できます。
Q7:クラウドのvCPUは共有?専有?
インスタンスタイプによります。通常のインスタンスは共有、「Dedicated」や「Metal」と名前が付くものは専有です。
まとめ:用途に応じて賢く選ぼう
CPUとvCPUは、似ているようで全く異なる概念です。
この記事のポイント:
CPUとvCPUの違い:
- CPU:物理的なハードウェア
- vCPU:ソフトウェアで作られた仮想的なCPU
- vCPU 1個 ≠ 物理コア 1個
オーバーコミットメント:
- 物理リソース以上のvCPUを割り当て可能
- 効率的だが、性能のトレードオフあり
- 推奨比率は用途によって1〜4倍
性能の違い:
- 物理CPU:安定した高性能
- vCPU:柔軟だが性能は変動する可能性
- 専有インスタンスなら物理に近い性能
選び方:
- 高性能・安定性重視:物理CPU
- 柔軟性・コスト重視:vCPU
- 多くの場合、vCPUで十分
覚えておきたいこと:
クラウドやレンタルサーバーを選ぶ時、「vCPU」という表記を見たら、それは物理CPUとは異なることを思い出してください。
性能は用途や設定によって大きく変わります。ベンチマークや試用期間を活用して、実際の性能を確認することが大切です。
初期投資を抑えたい、柔軟にスケールしたいなら、vCPUを使ったクラウドサービスがおすすめ。安定した高性能が必要なら、物理サーバーや専有インスタンスを検討しましょう。
賢く選んで、コストと性能のバランスが取れた環境を構築してくださいね!