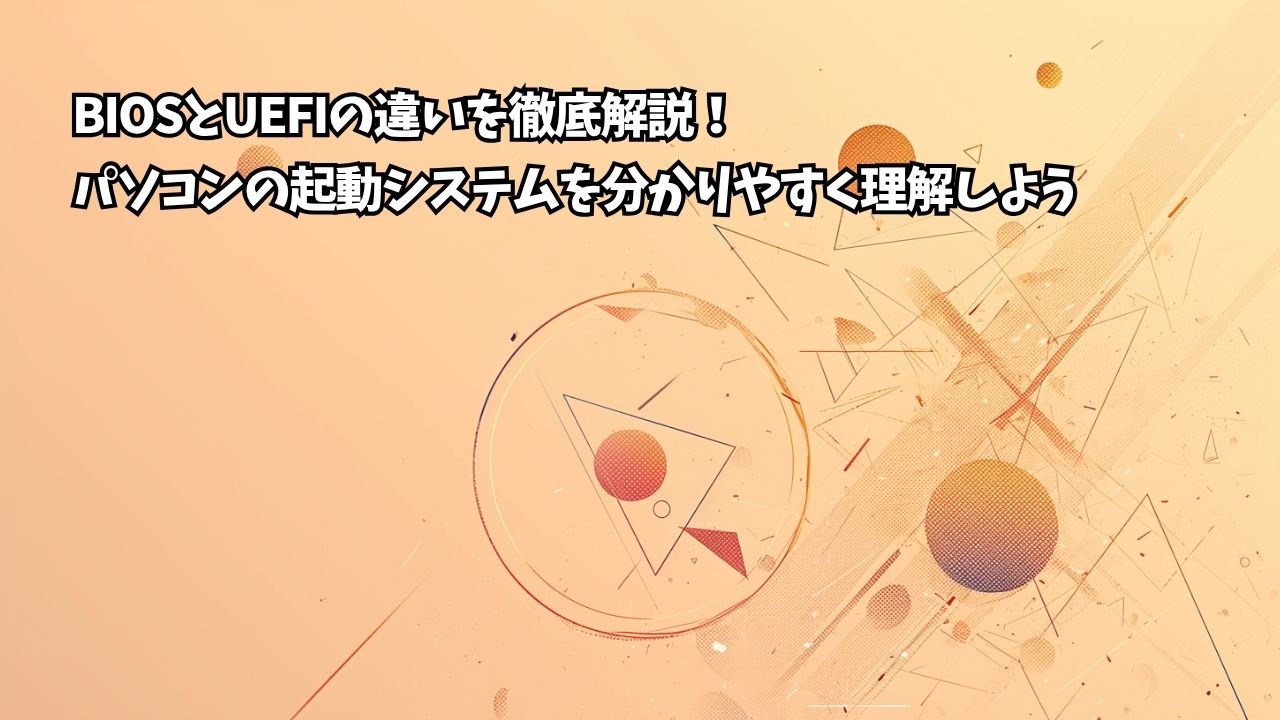パソコンの電源ボタンを押してから、WindowsやMacが起動するまでの間、実は裏側で重要な仕事をしているプログラムがあります。
それがBIOSやUEFIと呼ばれるものです。
「聞いたことはあるけど、よく分からない…」
「自分のパソコンはどっちを使ってるの?」
「何が違うの?」
こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、パソコンの「縁の下の力持ち」であるBIOSとUEFIについて、初心者の方でも理解できるように分かりやすく解説していきます。
BIOSとは?パソコンの「目覚まし時計」的存在
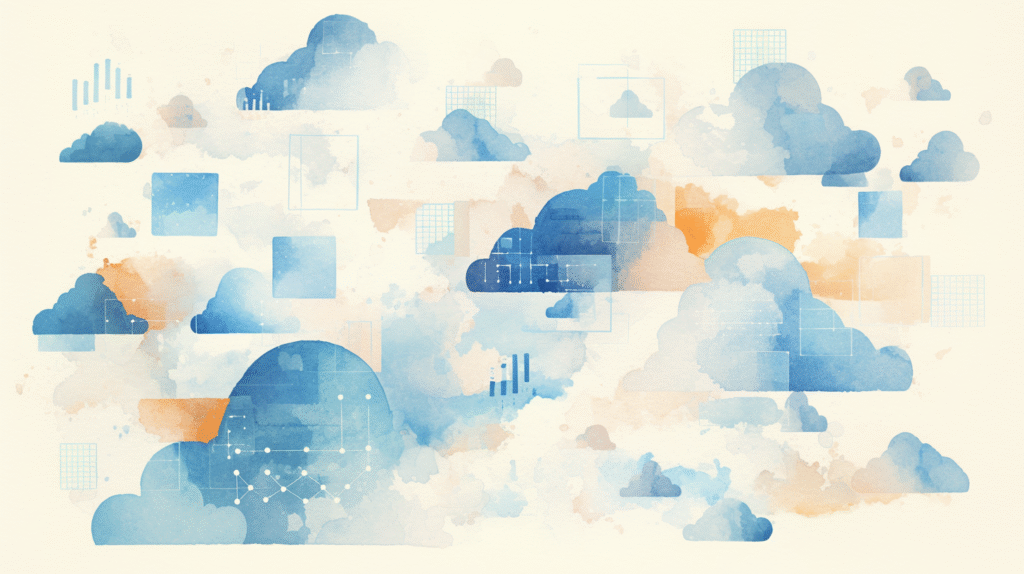
BIOSの基本的な役割
BIOS(バイオス)は「Basic Input/Output System」の略称です。
日本語にすると「基本入出力システム」となりますが、簡単に言えばパソコンが目を覚ますための最初のプログラムだと考えてください。
パソコンの電源を入れた瞬間、BIOSが起動して次のような仕事をします:
- キーボードやマウスが正しく接続されているか確認
- メモリ(RAM)が正常に動作するかチェック
- ハードディスクやSSDなどの記憶装置を認識
- WindowsなどのOSを起動するための準備
BIOSが生まれた背景
BIOSは1970年代に誕生し、長年にわたってパソコンの起動を支えてきました。
マザーボード(パソコンの基盤)に組み込まれた小さなチップに保存されていて、パソコンが起動するたびに最初に実行されるプログラムです。
当時の技術水準に合わせて設計されたため、現代の高性能なパソコンには少し物足りない面もあります。
UEFIとは?進化した新しい起動システム
UEFIの登場
UEFI(ユーイーエフアイ)は「Unified Extensible Firmware Interface」の略称です。
直訳すると「統一された拡張可能なファームウェア・インターフェース」となりますが、要するにBIOSの進化版と考えて問題ありません。
2000年代に入ってから開発が進み、2010年代以降に発売されたパソコンの多くがUEFIを採用しています。
UEFIが解決した問題
古いBIOSには、現代のパソコンを使う上でいくつかの制限がありました。
UEFIはこれらの制限を取り払い、より快適なパソコン環境を実現するために開発されたのです。
BIOSとUEFIの主な違いを比較してみよう
ここからは、両者の具体的な違いを見ていきましょう。
起動速度の違い
BIOSの場合:
電源を入れてからOSが起動するまで、比較的時間がかかります。
UEFIの場合:
起動プロセスが最適化されているため、より素早くパソコンが使える状態になります。
実際に体感できるレベルで速くなっているケースが多いですね。
対応できるハードディスクの容量
BIOSの場合:
最大2TBまでのハードディスクやSSDしか起動ドライブとして認識できません。
これは、BIOSが採用しているMBR(マスター・ブート・レコード)というパーティション方式の制限によるものです。
UEFIの場合:
GPT(GUIDパーティションテーブル)という新しい方式を使うことで、2TBを超える大容量ドライブでも問題なく起動ドライブとして使用できます。
最大で9.4ZB(ゼタバイト)まで対応可能です。
操作画面の使いやすさ
BIOSの場合:
- 青や黒い背景にテキストだけの画面
- キーボードでしか操作できない
- 英語表記がほとんど
UEFIの場合:
- グラフィカルで見やすい画面
- マウスでも操作可能(機種による)
- 日本語表示に対応している製品も多い
初心者の方にとっては、UEFIの方が圧倒的に扱いやすいでしょう。
セキュリティ機能の充実度
BIOSの場合:
基本的なセキュリティ機能しか搭載されていません。
UEFIの場合:
セキュアブートという機能が利用できます。
これは、信頼できるOSやプログラムしか起動できないようにする仕組みで、悪意のあるプログラムからパソコンを守る役割を果たします。
ウイルスやマルウェアがパソコンの起動プロセスに侵入するのを防ぐ、強力なセキュリティ対策です。
自分のパソコンはBIOSとUEFI、どちらを使っている?
「じゃあ、自分のパソコンはどっちなんだろう?」と気になりますよね。
確認方法は簡単です。
Windows 10/11での確認方法
- キーボードの「Windows」キー + 「R」キーを同時に押す
- 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが開く
- 「msinfo32」と入力してEnterキーを押す
- 「システム情報」ウィンドウが表示される
- 「BIOSモード」という項目を探す
ここに表示される内容が答えです:
- 「レガシ」と表示 → BIOS
- 「UEFI」と表示 → UEFI
たったこれだけで、自分のパソコンがどちらの方式を使っているか分かります。
UEFIを使うメリットをもっと詳しく
UEFIには、他にも多くのメリットがあります。
複数のOSをインストールしやすい
WindowsとLinuxを両方使いたい、という方にとって、UEFIは非常に便利です。
パーティション(ハードディスクの区切り)を柔軟に管理できるため、複数のOSを共存させやすくなっています。
ネットワーク機能の搭載
一部のUEFI実装では、OSを起動する前の段階でネットワークに接続できる機能があります。
これにより、ネットワーク経由でのOSインストールやトラブルシューティングが可能になります。
拡張性の高さ
UEFIは名前の通り「拡張可能」な設計になっています。
将来的に新しい機能を追加しやすく、ハードウェアの進化にも柔軟に対応できる構造です。
BIOSからUEFIに変更できる?
既に持っているパソコンをBIOSからUEFIに変更したい、と考える方もいるかもしれません。
結論から言うと、技術的には可能ですが、非常に複雑で危険を伴う作業です。
OSの再インストールやパーティションの変換が必要になり、データが消える可能性もあります。
よほどの理由がない限り、現状のまま使い続けるか、新しいパソコンに買い替える方が無難でしょう。
まとめ:BIOSとUEFIの違いを理解して快適なパソコンライフを
BIOSとUEFIの違いについて、重要なポイントをおさらいしましょう。
BIOS:
- 1970年代から使われてきた伝統的なシステム
- 最大2TBまでの起動ドライブに対応
- シンプルだが機能は限定的
- 古いパソコンで採用されている
UEFI:
- BIOSの進化版として登場した新しいシステム
- 2TB以上の大容量ドライブにも対応
- 起動が速く、セキュリティ機能も充実
- 2010年代以降のパソコンで主流
どちらが使われているかは、パソコンの製造時期やモデルによって決まります。
普段の使用では、どちらを使っていても大きな問題はありません。
ただし、新しいパソコンを購入する際や、大容量のSSDに換装する際には、UEFI対応かどうかを確認しておくと良いでしょう。
パソコンの「最初の一歩」を担うBIOSとUEFI。
その違いを理解することで、パソコンの仕組みがより深く分かるようになりますよ。