「このCPUは3.0GHz(最大5.0GHz)って書いてあるけど、どっちが本当の速度?」
「ベースクロックとブーストクロックって、何が違うの?」
CPUのスペックを見ると、複数のクロック周波数が書かれていて混乱しますよね。
この記事では、ベースクロック(定格クロック)とは何か、ブーストクロックとの違い、そしてあなたのCPUが実際にどう動いているのかを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
難しい技術用語は最小限にして、実例を交えながら説明していきますね。
CPUの性能を正しく理解する第一歩として、ぜひ最後までお読みください!
ベースクロック(定格クロック)とは?
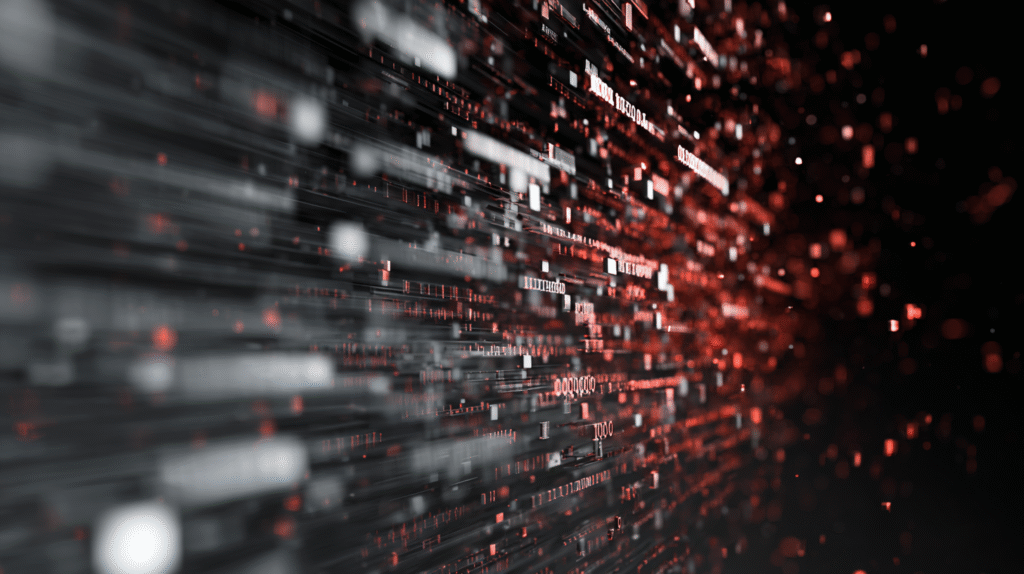
ベースクロックの定義
ベースクロック(Base Clock)とは、CPUが通常の作業時に安定して動作する基本的なクロック周波数のことです。
日本語では定格クロックとも呼ばれます。
「定格」というのは、メーカーが保証している標準的な動作仕様という意味ですね。
例えば:
- Intel Core i7-13700K:ベースクロック 3.4GHz
- AMD Ryzen 7 7700X:ベースクロック 4.5GHz
これが、そのCPUの「基準となる速度」です。
車に例えると分かりやすい
自動車で例えてみましょう。
ベースクロック = 巡航速度
- 高速道路で安定して走り続けられる速度
- 燃費も良く、エンジンに負担が少ない
- 長時間この速度で走っても問題ない
ブーストクロック = 最高速度
- アクセル全開で出せる最高速度
- 燃費は悪く、エンジンに負担がかかる
- 短時間しか維持できない
CPUも同じで、ベースクロックは安定動作の基準値なんです。
なぜベースクロックが重要なのか
ベースクロックは、以下の点で重要です。
1. 消費電力の基準
- TDP(熱設計電力)はベースクロックで計算される
- 冷却設計の基準にもなる
2. 安定性の保証
- この周波数なら確実に動作する
- 長時間の負荷でも問題ない
3. マルチコア動作時の速度
- すべてのコアが同時に動く時の速度
- 実用上、この速度が重要なことも多い
ブーストクロックとの違いを理解しよう
CPUのスペック表には、通常2つ以上の周波数が記載されています。
ブーストクロック(最大クロック)とは
ブーストクロック(Boost Clock / Turbo Clock)とは、短時間だけ動作できる最高クロック周波数のことです。
特徴:
- ベースクロックより高い周波数
- 一時的な性能向上
- 熱や電力に余裕がある時だけ発動
- すべてのコアが同時に最大速度になるわけではない
技術の名称
メーカーによって呼び方が違います。
Intel:
- Turbo Boost(ターボブースト)
- 第11世代以降:Turbo Boost Max 3.0
AMD:
- Precision Boost(プレシジョンブースト)
- Precision Boost Overdrive(PBO)
仕組みは基本的に同じです。
スペック表の読み方
実際のCPUで見てみましょう。
Intel Core i9-13900K の例:
ベースクロック(P-core):3.0GHz
最大ブーストクロック:5.8GHz意味:
- 通常時:3.0GHz前後で動作
- 負荷が高い時:自動的に速度を上げる
- 最大で:5.8GHzまで上昇する
- 条件次第で:実際の速度は変動する
AMD Ryzen 9 7950X の例:
ベースクロック:4.5GHz
最大ブーストクロック:5.7GHz特徴:
- AMDは比較的ベースクロックが高め
- ブーストの上昇幅は少なめ
- 安定した高性能を狙った設計
どちらが実際の速度に近い?
状況によって変わります。
軽い作業(ブラウジング、文書作成):
- ベースクロック以下で動作することも
- 省電力モードで1~2GHz程度
- 性能は十分
中程度の作業(写真編集、軽いゲーム):
- ベースクロックより少し上
- 3.5~4.5GHz程度
重い作業(動画編集、3Dレンダリング、最新ゲーム):
- ブーストクロックに近い速度
- ただし短時間のみ
- すぐに温度上昇で速度低下
ベースクロックの決まり方
CPUのベースクロックは、どうやって決められているのでしょうか?
TDP(熱設計電力)との関係
TDP(Thermal Design Power)が大きく影響します。
TDPとは:
- CPUが発熱する電力の目安
- 冷却システムの設計基準
- 単位はワット(W)
関係:
ベースクロック × すべてのコア = TDP相当の消費電力例:Intel Core i9-13900K
- TDP(PBP):125W
- ベースクロック:3.0GHz
- この条件で全コアが動ける設計
製造プロセスの影響
プロセスルール(製造技術)も関係します。
微細化の進化:
- 14nm → 10nm → 7nm → 5nm → 3nm
- 細かいほど低電力で高速に動作できる
- 同じ電力でより高いクロック周波数が可能
例:
- 古い14nmプロセス:ベース3.0GHz、TDP 95W
- 新しい7nmプロセス:ベース4.0GHz、TDP 105W
アーキテクチャの設計
CPUの内部設計(アーキテクチャ)によっても変わります。
効率重視の設計:
- 1クロックでできる仕事を増やす
- ベースクロックは低めでも高性能
周波数重視の設計:
- とにかく高い周波数を追求
- 消費電力や発熱は増加傾向
市場ポジショニング
製品ラインナップ上の位置づけも影響します。
ハイエンドモデル(i9、Ryzen 9):
- ベースクロックを高めに設定
- 高価格を正当化
ミドルレンジモデル(i5、Ryzen 5):
- バランス重視
- コスパを考慮した設定
省電力モデル(ノートPC用):
- ベースクロックは低め(1.0~2.5GHz程度)
- バッテリー寿命を優先
実際のCPU動作を見てみよう
CPUは状況に応じて、常に周波数を変化させています。
アイドル時(待機中)
状況:
- デスクトップを表示しているだけ
- 特に作業をしていない
動作:
- ベースクロックより大幅に低い
- 0.8~1.5GHz程度
- 多くのコアが停止(スリープ状態)
目的:
- 消費電力を最小化
- 発熱を抑える
- バッテリー寿命を延ばす(ノートPCの場合)
通常作業時
状況:
- Webブラウジング
- 文書作成
- メールチェック
動作:
- ベースクロック前後
- 必要なコアだけが動作
- 2.5~3.5GHz程度
特徴:
- 瞬間的に速度が上下する
- 平均するとベースクロック付近
単一コア高負荷時
状況:
- シングルスレッドのアプリを実行
- 特定のコアだけが忙しい
動作:
- 1つのコアだけブーストクロックまで上昇
- 他のコアは低速または停止
- 最大5.0~5.8GHz(最新CPU)
例:
- ゲームの物理演算
- 一部のプログラミング処理
- 圧縮・解凍作業
全コア高負荷時
状況:
- 動画エンコード
- 3Dレンダリング
- 科学計算
動作:
- すべてのコアが同時に動作
- ベースクロックより高いが、ブーストクロックほどではない
- 3.8~4.5GHz程度(CPUによる)
制限要因:
- 消費電力の上限
- 発熱の問題
- すべてのコアを最大速度にすると冷却が追いつかない
周波数の変化を確認する方法
Windowsの場合:
タスクマネージャー:
- Ctrl + Shift + Esc でタスクマネージャーを開く
- 「パフォーマンス」タブ → CPU
- 右下に「速度」が表示される
- リアルタイムで変化を確認できる
専用ソフト:
- CPU-Z(無料)
- HWMonitor(無料)
- Core Temp(無料)
これらで、各コアの詳細な周波数を見られます。
ベースクロックとマルチプライヤー(倍率)

もう少し技術的な話をしましょう。
CPUのクロック周波数の計算式
実は、CPUのクロック周波数は掛け算で決まります。
計算式:
CPUクロック周波数 = ベースクロック × マルチプライヤー注意:
ここで言う「ベースクロック」は、BCLK(Base Clock)という別の概念です。
先ほど説明した「定格クロック」とは違うので注意してください。
BCLK(ベースクロック信号)とは
BCLKは、マザーボード上の基準クロック発振器から供給される信号です。
一般的な値:
- Intel:100MHz
- AMD(旧世代):100MHz
- AMD(最新世代):100MHz~200MHz
この100MHzが「基準」になります。
マルチプライヤー(倍率)
マルチプライヤー(Multiplier)は、BCLKを何倍にするかの倍率です。
例:Intel Core i7の場合
BCLK:100MHz
マルチプライヤー:35倍
実際のクロック:100MHz × 35 = 3.5GHzブーストクロック時の変化
ブーストクロック時は、マルチプライヤーが自動的に上がります。
通常時:
100MHz × 35 = 3.5GHz(ベースクロック)ブースト時:
100MHz × 52 = 5.2GHz(ブーストクロック)BCLKは変わらず、倍率だけが変わるんですね。
オーバークロックの2つの方法
方法1:マルチプライヤーを上げる
- 最も一般的
- K付きCPU(Intelの場合)で可能
- 100MHz × 40倍 → 100MHz × 45倍
方法2:BCLKを上げる
- より高度な方法
- 他の部品にも影響
- 105MHz × 35倍 = 3.675GHz
ベースクロックと実際の性能
ベースクロックが高ければ性能も高いのでしょうか?
ベースクロックだけでは判断できない
比較例:
CPU A:
- ベースクロック:3.0GHz
- ブーストクロック:5.0GHz
- 新しい世代のアーキテクチャ
CPU B:
- ベースクロック:3.5GHz
- ブーストクロック:4.5GHz
- 古い世代のアーキテクチャ
結果:
多くの場合、CPU Aの方が高性能です。
IPC(1クロックあたりの命令数)
IPC(Instructions Per Cycle)という概念が重要です。
意味:
- 1クロックサイクルで実行できる命令の数
- アーキテクチャの効率性を示す指標
計算:
実際の性能 = クロック周波数 × IPC × コア数例:
- 古いCPU:3.5GHz × IPC 4 = 14の性能
- 新しいCPU:3.0GHz × IPC 5 = 15の性能
新しいCPUの方が、低いクロックでも高性能なんです。
用途による重要度の違い
シングルスレッド性能重視(ゲーム、CADなど):
- ブーストクロックが重要
- 1コアの最大速度が効く
マルチスレッド性能重視(動画編集、レンダリングなど):
- ベースクロックとコア数が重要
- 全コアで長時間動作する速度が効く
省電力重視(ノートPC、サーバーなど):
- ベースクロックが低い方が有利
- 効率性(性能/消費電力)が重要
ノートPCとデスクトップPCの違い
同じCPU名でも、ノートとデスクトップで大きく違います。
デスクトップPC用CPU
特徴:
- ベースクロックが高め(3.0~4.0GHz)
- TDPが高い(65W~125W以上)
- 冷却能力が高い
- 性能重視
例:Intel Core i7-13700K
- ベースクロック:3.4GHz
- 最大ブースト:5.4GHz
- TDP:125W(基本)、253W(最大)
ノートPC用CPU
特徴:
- ベースクロックが低め(1.0~2.5GHz)
- TDPが低い(15W~45W)
- 冷却能力が限られる
- バッテリー寿命重視
例:Intel Core i7-1365U
- ベースクロック:1.8GHz
- 最大ブースト:5.2GHz
- TDP:15W(基本)、55W(最大)
同じ「i7」でも性能は全然違う
誤解されやすい点:
- 「Core i7」という名前は同じ
- でもデスクトップ用とノート用は別物
- ノート用は性能も消費電力も控えめ
型番の見分け方:
- デスクトップ:K、F、無印(例:13700K)
- ノート:H、P、U(例:1365U)
ベースクロックとPBP/MTP
Intelの最近のCPUには、新しい電力表記があります。
PBP(Processor Base Power)
従来のTDPに相当する値です。
意味:
- ベースクロックで動作する時の消費電力
- 冷却システムの設計基準
- 長時間動作時の平均的な消費電力
例:Core i9-13900K
- PBP:125W
- ベースクロック3.0GHzでの消費電力
MTP(Maximum Turbo Power)
ターボブースト時の最大消費電力です。
意味:
- 短時間だけ許容される最大電力
- ブーストクロック到達時の消費電力
- 瞬間的なピーク値
例:Core i9-13900K
- MTP:253W
- ブースト5.8GHz時の消費電力
実際の動作
軽負荷時:30~50W(ベースクロック以下)
↓
中負荷時:100~125W(ベースクロック付近)
↓
高負荷時:180~250W(ブーストクロック)
↓
数秒~数分で温度上昇
↓
温度制限により速度低下(サーマルスロットリング)
↓
ベースクロック付近に落ち着く(125W前後)つまり、長時間の高負荷ではベースクロックが実質的な性能になります。
実際のCPUスペック比較
具体的な製品で比較してみましょう。
ハイエンドデスクトップCPU
Intel Core i9-13900K:
- ベースクロック(P-core):3.0GHz
- 最大ブースト:5.8GHz
- PBP:125W / MTP:253W
- コア数:24コア(8P + 16E)
AMD Ryzen 9 7950X:
- ベースクロック:4.5GHz
- 最大ブースト:5.7GHz
- TDP:170W
- コア数:16コア
比較:
- AMDの方がベースクロックが高い
- Intelの方がブースト時の最大速度が高い
- 用途によって向き不向きがある
ミドルレンジCPU
Intel Core i5-13600K:
- ベースクロック:3.5GHz
- 最大ブースト:5.1GHz
- PBP:125W
- コア数:14コア
AMD Ryzen 5 7600X:
- ベースクロック:4.7GHz
- 最大ブースト:5.3GHz
- TDP:105W
- コア数:6コア
ノートPC用CPU
Intel Core i7-13700H:
- ベースクロック:2.4GHz
- 最大ブースト:5.0GHz
- PBP:45W
- コア数:14コア
AMD Ryzen 7 7840HS:
- ベースクロック:3.8GHz
- 最大ブースト:5.1GHz
- TDP:35~54W
- コア数:8コア
よくある質問と回答
Q. ベースクロックとブーストクロック、どちらを見て選べばいい?
用途によって変わります。
ゲームメイン:
- ブーストクロックを重視
- 短時間の高性能が重要
動画編集・レンダリング:
- ベースクロックとコア数を重視
- 長時間の安定性が重要
普段使い:
- どちらもそれほど気にしなくてOK
- 世代(新しさ)の方が重要
Q. ベースクロックが低いCPUは遅い?
そうとは限りません。
理由:
- アーキテクチャの効率性(IPC)が重要
- ブーストクロックでの動作時間が長い
- 現代のCPUは常に周波数を調整している
例:
- 古い世代:ベース3.5GHz
- 新しい世代:ベース3.0GHz
- 新しい世代の方が実際は速い(IPCが高い)
Q. ベースクロックは常に動作する速度ですか?
いいえ、違います。
実際の動作:
- アイドル時:ベースクロック以下(0.8~1.5GHz)
- 軽作業時:ベースクロック前後
- 高負荷時:ベースクロック以上(ブースト)
ベースクロックは「基準点」であって「常時動作する速度」ではありません。
Q. オーバークロックするとベースクロックも上がる?
はい、上がります。
オーバークロック前:
- ベースクロック:3.5GHz
- ブーストクロック:5.0GHz
オーバークロック後(例):
- ベースクロック:4.0GHz
- ブーストクロック:5.5GHz
マルチプライヤーを上げると、両方が比例して上がります。
Q. ベースクロックが高いほど電気代は高い?
関係はありますが、単純ではありません。
消費電力に影響する要素:
- クロック周波数(高いほど多い)
- 電圧(高いほど多い)
- 動作時間(長いほど多い)
- アーキテクチャの効率性
実際:
- アイドル時間が長ければ電気代は安い
- 常に高負荷なら電気代は高い
- 効率の良い新しいCPUの方が省電力
Q. ノートPCのベースクロックが低いのはなぜ?
バッテリー寿命と発熱対策のためです。
ノートPCの制約:
- 冷却能力が限られる
- バッテリーで動作する必要がある
- 薄型化のため放熱が難しい
解決策:
- ベースクロックを低く設定
- 必要な時だけブースト
- 平均消費電力を抑える
Q. ベースクロックは変更できますか?
オーバークロック可能なCPUでは変更できます。
変更可能なCPU:
- Intel:K付きモデル(例:13900K)
- AMD:全てのRyzenシリーズ(Xモデルは特に)
変更方法:
- BIOSやUEFIの設定
- マルチプライヤーを変更
- BCLKを変更(上級者向け)
注意点:
- 保証が効かなくなる可能性
- 冷却能力が必要
- 電源容量も確認
まとめ:ベースクロックはCPU性能の「基準点」
ベースクロック(定格クロック)について、基本から実用まで解説してきました。
この記事のポイント:
✓ ベースクロックは、CPUが安定して動作する基本周波数
✓ ブーストクロックは、短時間だけ出せる最大周波数
✓ 実際の動作速度は、常に変化している
✓ TDP(PBP)は、ベースクロックでの消費電力を示す
✓ ベースクロックだけで性能は判断できない(IPCも重要)
✓ 用途によって、ベースクロックとブーストクロックの重要度が変わる
✓ ノートPC用CPUはベースクロックが低めだが、これは省電力設計のため
最も大切なこと:
CPUのスペック表を見る時、ベースクロックとブーストクロックの両方を理解することが重要です。
どちらか一方だけを見ても、実際の性能は分かりません。
今日から実践すること:
- タスクマネージャーでCPUの実際の動作周波数を観察してみる
- 軽作業時と重作業時で、どう速度が変わるか確認する
- 自分の使い方では、ベースクロックとブーストクロックのどちらが重要か考える
- CPUを選ぶ時、スペック表の見方を思い出す
ベースクロックとブーストクロックの関係を理解すれば、CPUの本当の性能が見えてきますよ!






