「大切なファイルをバックアップしたいけど、毎回全部コピーするのは時間がかかる…」
「サーバーとパソコンの間でファイルを効率よく同期したい」
そんな悩みを持っているあなたに、ぜひ知ってほしいツールがあります。それがrsync(アールシンク)です。
rsyncは、ファイルやフォルダを賢くコピー・同期してくれる便利なコマンドラインツールなんです。変更された部分だけを転送してくれるので、時間も通信量も大幅に節約できます。
この記事では、rsyncの基本から実践的な使い方まで、初心者の方でも分かるように丁寧に解説していきますね。
rsyncって何?基本を押さえよう
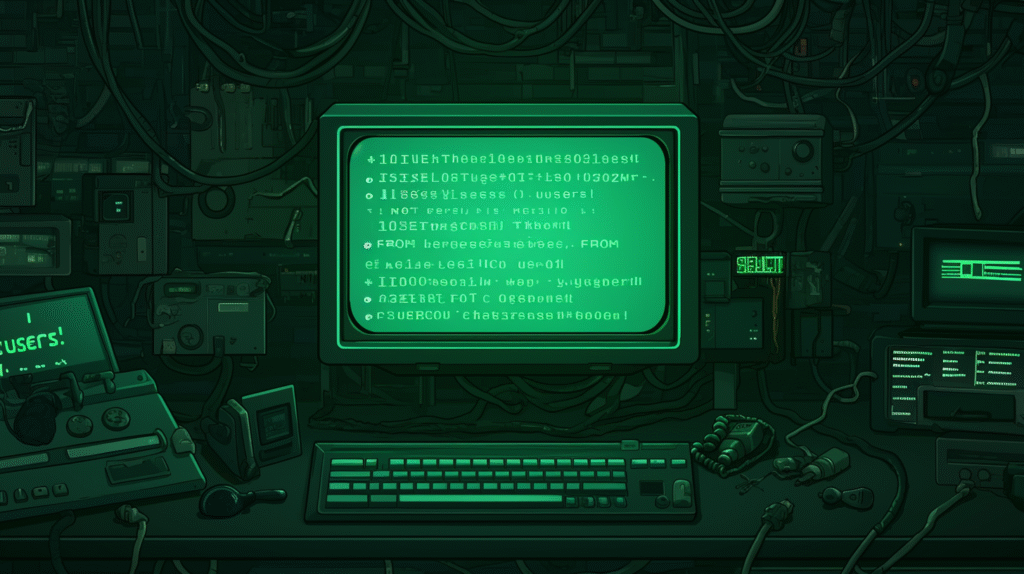
rsyncの正体
rsyncは、「remote sync(リモート シンク)」の略称で、ファイルやディレクトリを同期(シンクロ)するためのツールです。
主にLinuxやMac、UNIXなどのOS(オペレーティングシステム)で使われていて、同じパソコン内でも、ネットワーク越しの別のパソコンやサーバーでも使えます。
普通のコピーとの違いは?
通常の「コピー」や「貼り付け」と何が違うのか、気になりますよね。
普通のコピー
- フォルダ全体を毎回まるごとコピーする
- 変更がない部分も含めて全てを転送
- 時間がかかる&通信量が多い
rsyncの場合
- 差分だけを賢く検出して転送
- 変更されたファイルや新しいファイルのみを処理
- 高速&効率的
例えば、1000個のファイルがあるフォルダのうち、たった3個だけ更新した場合、rsyncならその3個だけを転送してくれるんです。これが最大の魅力ですね。
rsyncの便利な特徴・メリット
rsyncが多くのエンジニアやシステム管理者に愛されている理由を見ていきましょう。
1. 差分転送で超高速
前述の通り、変更された部分だけを転送する仕組みがあります。大容量のバックアップでも2回目以降は驚くほど速く完了します。
2. 圧縮転送に対応
ネットワーク経由で転送する際、データを圧縮してから送ることができます。通信量を減らせるので、回線速度が遅い環境でも助かりますね。
3. SSH接続で安全に転送
SSH(セキュア シェル)という暗号化技術を使って、安全にファイルを転送できます。パスワードや大切なデータを守りながら作業できるわけです。
4. ファイルの属性も保持
ファイルの作成日時、アクセス権限、所有者情報なども、そのまま維持してコピーできます。システムのバックアップには欠かせない機能です。
5. 削除にも対応可能
オプションを使えば、転送元にないファイルを転送先から削除することもできます。完全な「鏡像(ミラー)」を作りたい時に便利です。
rsyncの基本的な使い方
それでは、実際の使い方を見ていきましょう。
基本の書き方
rsyncの基本的なコマンドの形はこうなっています:
rsync [オプション] [転送元] [転送先]とてもシンプルですよね。
ローカルでのコピー例
まずは同じパソコン内でのコピーから試してみましょう。
rsync -av /home/user/documents/ /backup/documents/解説:
-a:アーカイブモード(ファイル属性を保持)-v:詳細表示(処理内容が見える)/home/user/documents/:コピー元/backup/documents/:コピー先
これで「documents」フォルダの内容が「backup」フォルダにコピーされます。
リモートサーバーへの転送例
別のサーバーにファイルを送る場合はこんな感じです:
rsync -avz /home/user/documents/ user@example.com:/backup/documents/解説:
-z:圧縮転送を有効化user@example.com:接続先のユーザー名とサーバー:(コロン):リモートサーバーを指定する記号
SSH経由で安全に転送されます。
よく使う便利なオプション一覧
rsyncには本当にたくさんのオプションがありますが、特によく使われるものをピックアップしました。
必須級のオプション
-a(–archive)
ファイルの属性を全て保持しながらコピー。ほぼ必須のオプションです。
-v(–verbose)
処理の詳細を表示してくれます。何が転送されているか確認できて安心ですね。
-z(–compress)
ネットワーク転送時にデータを圧縮します。リモート転送では基本的に付けましょう。
便利なオプション
-n(–dry-run)
実際には実行せず、「何が起こるか」をシミュレーションしてくれます。本番前の確認に最適です。
-P(–progress)
転送の進行状況をパーセントで表示。大きなファイルの転送時に重宝します。
–delete
転送元にないファイルを転送先から削除します。完全同期したい時に使いますが、注意が必要です。
–exclude=’パターン’
特定のファイルやフォルダを除外できます。例:--exclude='*.tmp'で一時ファイルを除外。
-u(–update)
転送先のファイルの方が新しい場合は上書きしません。安全性重視の時に便利です。
実践的な使用例
実際の現場でよく使われるパターンをご紹介します。
バックアップの自動化
毎日自動でバックアップを取る設定です:
rsync -avz --delete /home/user/important/ /backup/important/これをcron(クロン:定期実行の仕組み)に登録すれば、自動バックアップの完成です。
特定のファイルを除外してバックアップ
キャッシュファイルやログファイルは不要、という場合:
rsync -avz --exclude='*.log' --exclude='cache/' /home/user/project/ /backup/project/リモートからローカルへダウンロード
逆にサーバーからファイルを取得する場合:
rsync -avz user@example.com:/var/www/html/ /home/user/website_backup/転送元と転送先を逆にするだけですね。
進行状況を見ながら転送
大きなファイルを扱う時は進捗が見たいものです:
rsync -avzP /large_folder/ /backup/large_folder/-Pオプションで進行状況がリアルタイムで表示されます。
ドライラン(予行演習)
本番実行の前に、何が起こるか確認しましょう:
rsync -avn --delete /source/ /destination/-nを付けることで、実際には実行されず結果のプレビューだけが表示されます。
使う時の注意点とトラブル回避
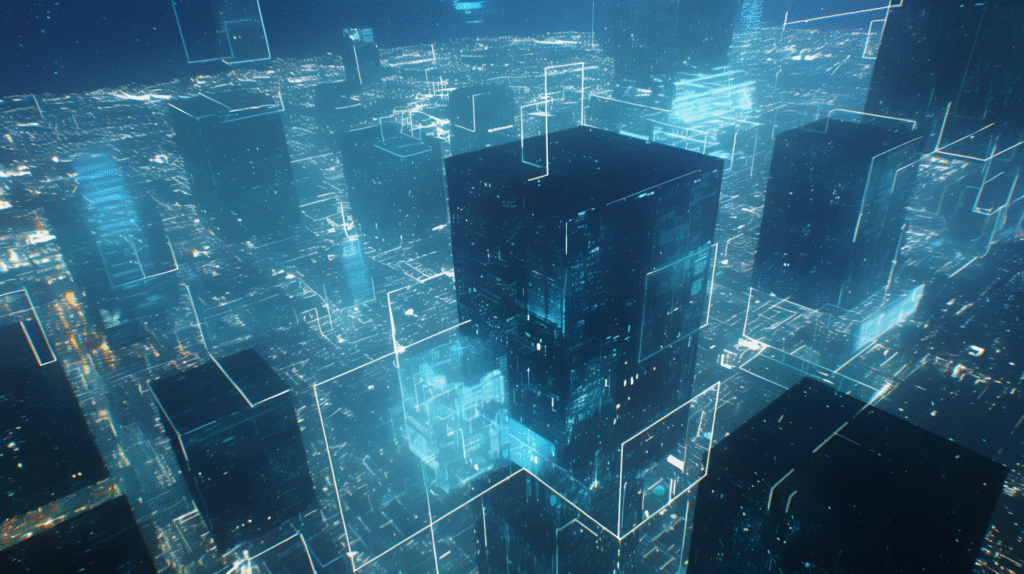
rsyncは便利ですが、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
1. パスの最後のスラッシュに注意
これは初心者が最もハマりやすいポイントです。
rsync -av /source/ /destination/ # sourceの「中身」をコピー
rsync -av /source /destination/ # source「フォルダごと」コピースラッシュ(/)がある・なしで結果が変わるんです。意図しない結果にならないよう、慎重に確認してください。
2. –deleteオプションは慎重に
--deleteは転送先から余計なファイルを削除してくれますが、間違えると大切なデータが消える危険性があります。
必ず事前に-nオプションでドライランして確認しましょう。
3. 権限の問題
他人が所有するファイルをコピーする時、権限エラーが出ることがあります。必要に応じてsudo(管理者権限)を使いましょう。
sudo rsync -av /source/ /destination/4. ネットワーク接続の確認
リモート転送の場合、SSH接続が正しく設定されているか確認してください。事前に以下のコマンドで接続テストができます:
ssh user@example.com5. ディスク容量の確認
バックアップ先に十分な空き容量があるか、事前にチェックしましょう。途中で容量不足になると厄介です。
まとめ:rsyncでファイル管理をスマートに
rsyncは、一度使い始めるともう手放せなくなる便利ツールです。
この記事のポイントをおさらい:
- rsyncは差分転送でファイルを効率的に同期できる
- ローカルでもリモートでも使える万能ツール
- SSH経由で安全にデータを転送可能
-a、-v、-zが基本の三大オプション--deleteや-nを使いこなして安全に運用- パスの最後のスラッシュに要注意
定期的なバックアップ、サーバー間のファイル同期、ウェブサイトのデプロイ(配置)など、様々な場面で活躍してくれます。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえれば誰でも使えるようになりますよ。まずは小さなフォルダで練習してみて、徐々に本格的な用途に使っていくのがおすすめです。
あなたの大切なデータを守るため、そして作業効率を上げるため、ぜひrsyncを活用してみてくださいね!



