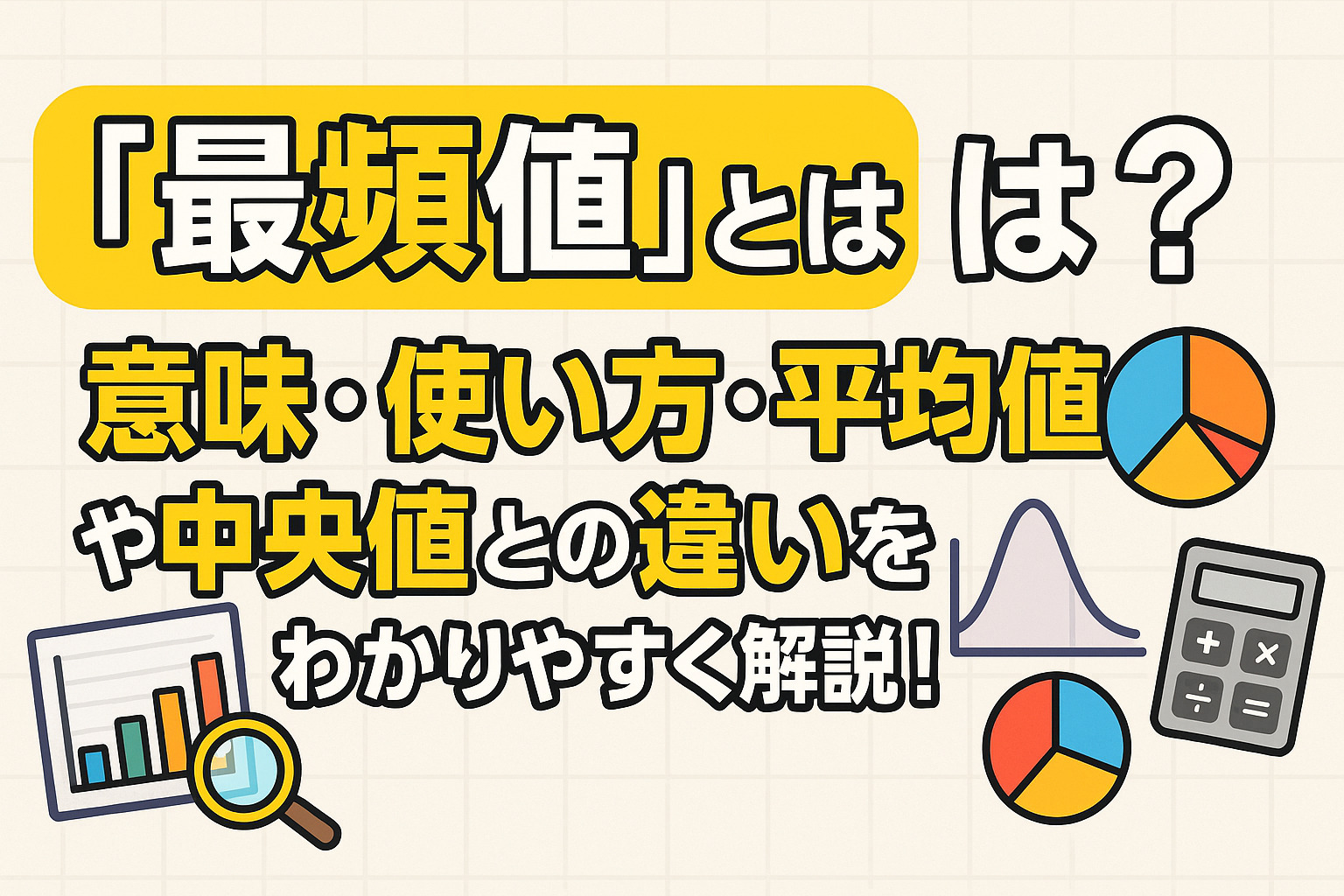データ分析や統計の場面でよく見かける「最頻値」という言葉をご存知ですか?
名前は聞いたことがあるけれど、実際の意味や使い方がよくわからないという方も多いでしょう。
この記事では、最頻値がどんなものなのか、どうやって使うのか、そして平均値や中央値とはどう違うのかを、身近な例を使ってわかりやすく説明します。
データ分析が初めての方でも、きっと理解できるはずです。
最頻値って何?
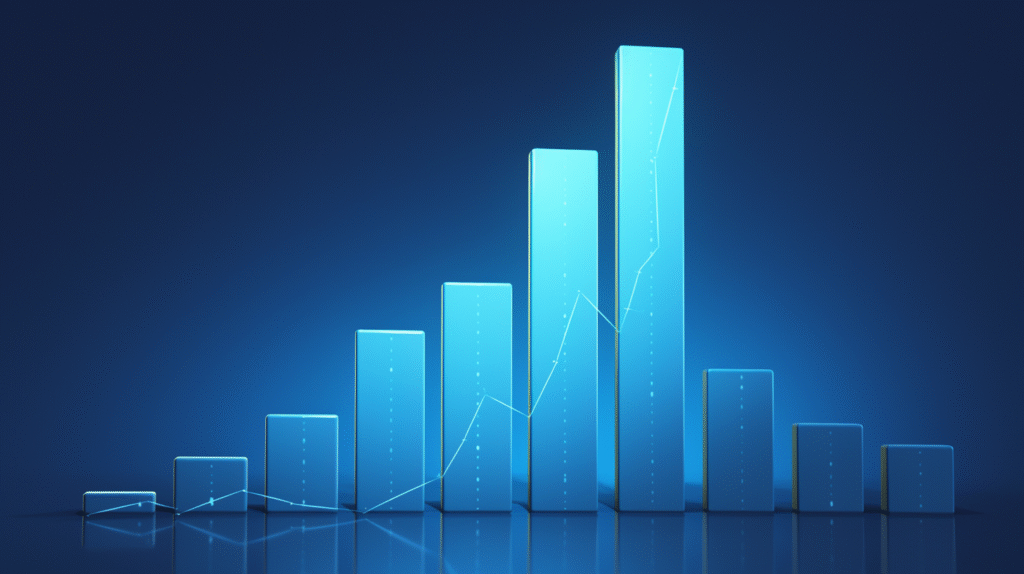
基本の意味
最頻値(さいひんち)とは、あるデータの中で一番多く出てくる値のことです。
英語では「mode(モード)」と呼ばれています。
具体例で理解しよう
たとえば、こんなデータがあったとします:
例1:テストの点数 3点、7点、7点、2点、7点、5点
この中で一番多く出てくるのは「7点」ですね。
3回も出てきています。だから、この場合の最頻値は「7点」になります。
例2:好きな色のアンケート 赤、青、青、緑、青、黄色
この場合、「青」が3回出てくるので、最頻値は「青」です。
最頻値の特徴
複数の最頻値がある場合も
データによっては、同じ回数で最も多く出てくる値が2つ以上ある場合があります。
これを「多峰性(たほうせい)」と呼びます。
例:1、2、2、3、3、4
この場合、「2」と「3」がそれぞれ2回ずつ出てくるので、両方とも最頻値になります。
数字以外でも使える
最頻値は数字だけでなく、色や商品名、アンケートの回答など、カテゴリーデータにも使えます。
これが平均値や中央値との大きな違いの一つです。
平均値・中央値との違い
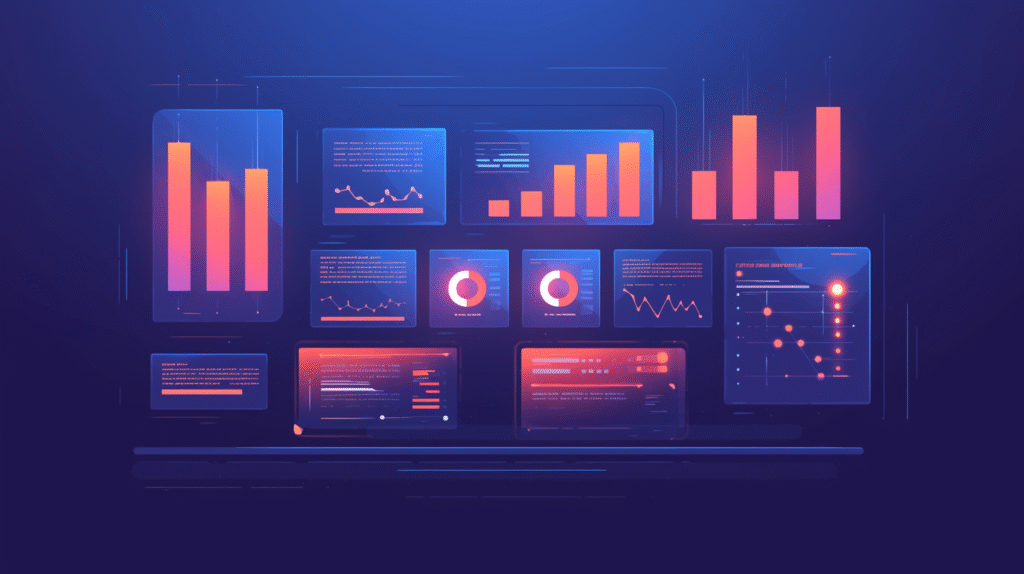
データを代表する値には、最頻値のほかに「平均値」と「中央値」があります。そ
れぞれの特徴を比べてみましょう。
| 種類 | 意味 | 計算方法 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 最頻値 | 一番よく出てくる値 | 出現回数を数える | 人気商品の調査、アンケート結果の分析 |
| 平均値 | データの合計を個数で割った値 | 合計 ÷ 個数 | テストの平均点、売上の平均など |
| 中央値 | データを小さい順に並べたとき真ん中にくる値 | データを並べて真ん中を見つける | 年収の調査、極端な値がある場合 |
具体例で比較
例:ある店での1日の来客数 2人、5人、5人、5人、6人、7人、20人
- 最頻値:5人(3回出現)
- 平均値:(2+5+5+5+6+7+20) ÷ 7 = 約7.1人
- 中央値:5人(7つのデータの真ん中)
この例では、「20人」という極端に多い日があっても、最頻値と中央値は「5人」のままです。
しかし平均値は7.1人になり、実際の傾向とは少し違って見えますね。
実生活での使い方
小売業での活用
洋服店の例
先月売れたTシャツのサイズを調べると: S、M、M、M、L、L、XL
最頻値は「Mサイズ」です。これがわかれば、来月はMサイズを多めに仕入れるという判断ができます。
学校での活用
テストの結果分析
クラス30人のテスト結果で、80点を取った生徒が最も多かった場合、80点が最頻値になります。
これにより、「多くの生徒がこのレベルの理解度にある」ことがわかります。
ウェブサイト分析
アクセス解析
サイトを訪れた人が最もよく見るページや、最もよくクリックするボタンを見つけることで、サイトの改善に役立てられます。
マーケティング調査
顧客の年齢層調査
商品を購入した顧客の年齢で最も多い層(最頻値)がわかれば、その年齢層に向けた広告戦略を立てることができます。
注意すべきポイント
最頻値が意味を持たない場合
すべての値が1回ずつしか出ない場合
例:1、2、3、4、5、6
この場合、どの値も1回ずつしか出ないので、最頻値は存在しません。
データの偏りに注意
最頻値は外れ値(極端に大きいまたは小さい値)の影響は受けにくいのですが、データに偏りがあると誤解を招くことがあります。
例:アンケート調査
100人にアンケートを取ったとき、70人が「とても満足」と答え、残り30人がばらばらの回答をした場合、最頻値は「とても満足」になります。
しかし、これだけを見て「ほとんどの人が満足している」と判断するのは危険かもしれません。
他の代表値と組み合わせる
最頻値だけでなく、平均値や中央値も一緒に見ることで、データの全体像をより正確に把握できます。
まとめ
最頻値は「データの中で最も多く出てくる値」として、私たちの身の回りのさまざまな場面で活用されています。
最頻値の特徴をおさらい
- 出現回数が最も多い値
- 数字以外のデータにも使える
- 複数の最頻値が存在することもある
- 外れ値の影響を受けにくい
効果的な使い方
- 平均値や中央値と組み合わせて分析する
- データの種類や目的に応じて使い分ける
- 結果を解釈するときは、データ全体の傾向も考慮する
データ分析に興味を持った方は、まずは身近なデータで最頻値を探してみることから始めてみましょう。
たとえば、家族の好きな食べ物や、よく使うアプリなど、日常的なデータから最頻値を見つけてみると、データ分析の面白さを実感できるはずです。