平安時代の京都で、若い女性が次々と姿を消す恐ろしい事件が起きていました。
犯人は大江山に住む鬼の大将で、酒を愛し、人の血を酒のように飲み干す恐ろしい存在だったのです。
その名も「酒呑童子」。日本三大妖怪の一つにも数えられる最強の鬼でした。
この記事では、平安時代を震え上がらせた鬼の総大将「酒呑童子」について詳しくご紹介します。
概要
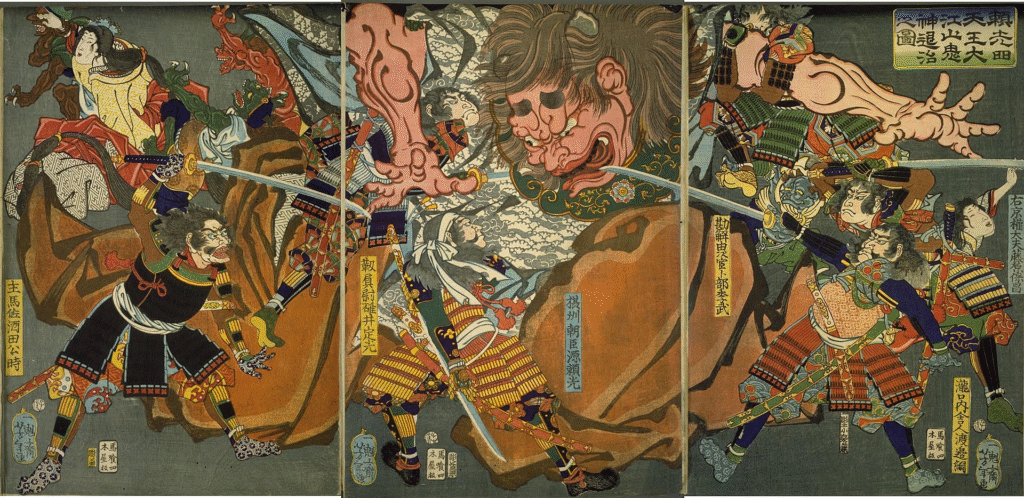
酒呑童子(しゅてんどうじ)は、平安時代に大江山を拠点とした鬼の総大将です。
一条天皇の時代(986~1011年)に京都を恐怖に陥れ、特に若い女性や貴族の姫君をさらっては、その血を酒のように飲み、肉を食べるという残虐な行いで知られていました。
酒呑童子の基本情報
- 日本三大妖怪の一つ
- 大江山(京都府)の鬼の頭領
- 茨木童子など多くの鬼を配下に従える
- 源頼光によって退治された
「酒呑童子」という名前は、酒が大好物で、部下たちからそう呼ばれていたことに由来します。
酒天童子、酒顛童子とも書かれることがありました。
姿・見た目
酒呑童子の姿は、文献によって異なりますが、とにかく巨大で恐ろしい姿だったんです。
『大江山絵詞』による姿
- 身長は5丈(約15メートル)
- 全身が赤い色
- 頭には5本の角
- 15個の眼
- 右足は黒、左足は白
- 右手は黄色、左手は青色
『御伽草子』による姿
- 身長は2丈(約6メートル)
- 赤い髪とぼうぼうの髭
- 手足は熊のよう
- 子供のような髪型だが巨大な体
昼間は美少年や童子の姿に化けることができ、夜になると恐ろしい鬼の正体を現したといわれています。
特徴
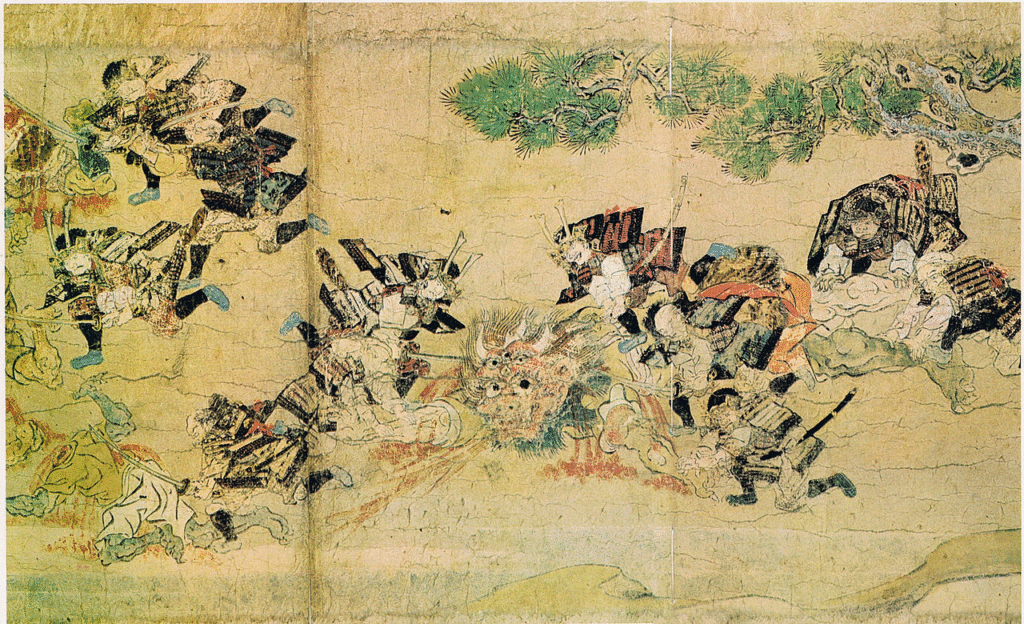
酒呑童子には、他の鬼とは違う特別な能力と習性がありました。
恐ろしい習性
- 人食い:特に若い女性の血肉を好む
- 酒好き:とにかく酒が大好物
- 変身能力:人間の姿に化けられる
- 神通力:超自然的な力を持つ
生活様式
酒呑童子は大江山の鉄の御所と呼ばれる館に住み、さらってきた女性たちを侍女として使いながら、気まぐれに殺して食べていました。
配下には四天王と呼ばれる強力な鬼たちがいました:
- 星熊童子(ほしくまどうじ)
- 熊童子(くまどうじ)
- 虎熊童子(とらくまどうじ)
- 金童子(かねどうじ)
そして最も有名な部下が茨木童子で、後に渡辺綱に腕を切り落とされたことでも知られています。
伝承
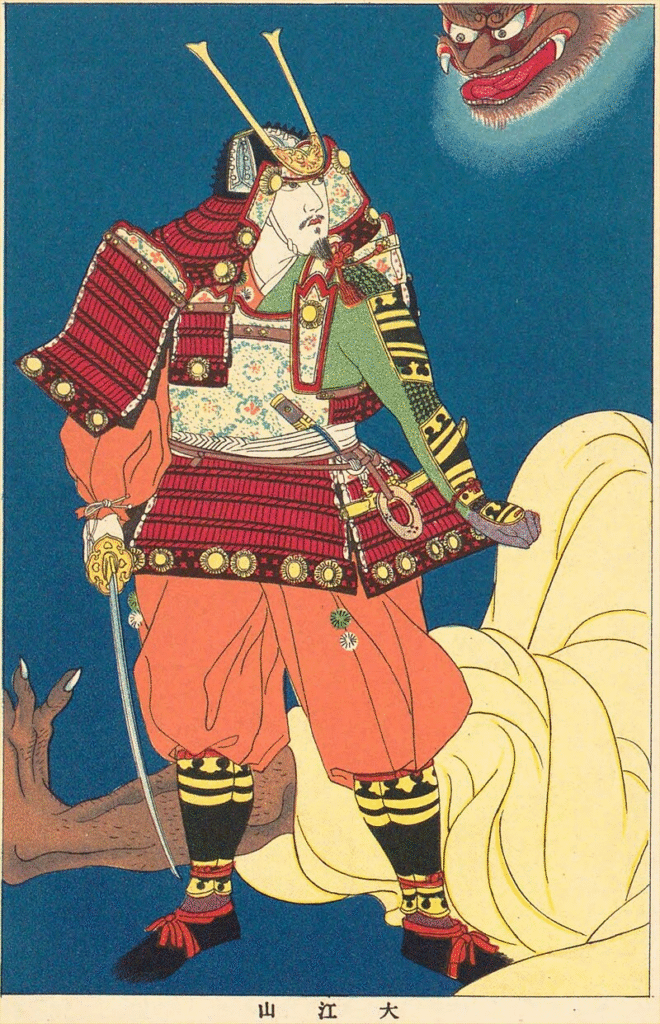
酒呑童子の伝説で最も有名なのが、源頼光による退治物語です。
退治の経緯
都で若い女性の失踪事件が相次ぎ、陰陽師・安倍晴明の占いで大江山の鬼の仕業と判明しました。そこで帝の命令で、源頼光と渡辺綱ら四天王が討伐に向かうことになったんです。
討伐作戦
- 変装作戦:山伏(修行僧)に変装して接近
- 毒酒作戦:神から授かった「神便鬼毒酒」という毒酒を用意
- 宴会で油断させる:酒好きの童子に毒酒を振る舞う
- 寝込みを襲う:酔いつぶれたところを襲撃
酒呑童子の最期
毒酒で体が動かなくなった酒呑童子は、頼光に首を切られます。しかし切られた首はなお生きていて、頼光の兜に噛みつこうとしました。
最期に童子は「鬼に横道なきものを(鬼は嘘をつかないのに、お前たちは騙し討ちをした)」と人間の卑怯さを非難したといいます。
出身地の伝説
酒呑童子の出身地については諸説あります:
- 越後国(新潟県)説:国上寺の美少年の稚児だった
- 伊吹山(滋賀県)説:八岐大蛇の子として生まれた
- 大和国(奈良県)説:白毫寺の稚児だった
まとめ
酒呑童子は、平安時代の都を恐怖に陥れた日本最強の鬼でした。
重要なポイント
- 大江山を拠点に京都を脅かした鬼の総大将
- 身長5丈の巨体と5本の角を持つ恐ろしい姿
- 酒と人の血肉を好む残虐な性格
- 茨木童子など強力な配下を従える
- 源頼光の騙し討ちによって退治された
- 日本三大妖怪の一つ
強大な力を持ちながらも、酒好きという弱点を突かれて倒された酒呑童子。その最期の言葉は、人間の狡猾さへの批判でもありました。彼もまた、朝廷に滅ぼされた者たちの象徴だったのかもしれませんね。



