二次方程式を解くのって、結構大変ですよね。
解の公式を使ったり、因数分解したり…計算ミスも起きやすいし。
でも、ビエタの公式を使えば、解を求めなくても解の和や積が分かるんです!
まるで、プレゼントの箱を開けずに中身が分かるような、そんな「魔法の公式」。
今回は、このビエタの公式について、具体例をたっぷり使って分かりやすく解説します。
読み終わる頃には、「こんな便利な公式があったのか!」と驚くはずです。
ビエタの公式とは:解と係数の美しい関係

基本の定義
ビエタの公式とは、二次方程式の解と係数の関係を表す公式です。
16世紀のフランスの数学者、フランソワ・ビエト(ビエタ)が発見しました。
公式を見てみよう
二次方程式 ax² + bx + c = 0 の2つの解を α(アルファ)、β(ベータ) とすると:
ビエタの公式
解の和:α + β = -b/a
解の積:α × β = c/a
ちょっと難しそう?大丈夫、具体例で見ればすぐ分かります!
もっと簡単なバージョン
x² + px + q = 0 の形(a=1の場合)なら:
解の和:α + β = -p
解の積:α × β = q
これならシンプルですね!
具体例で理解:公式の威力を実感しよう
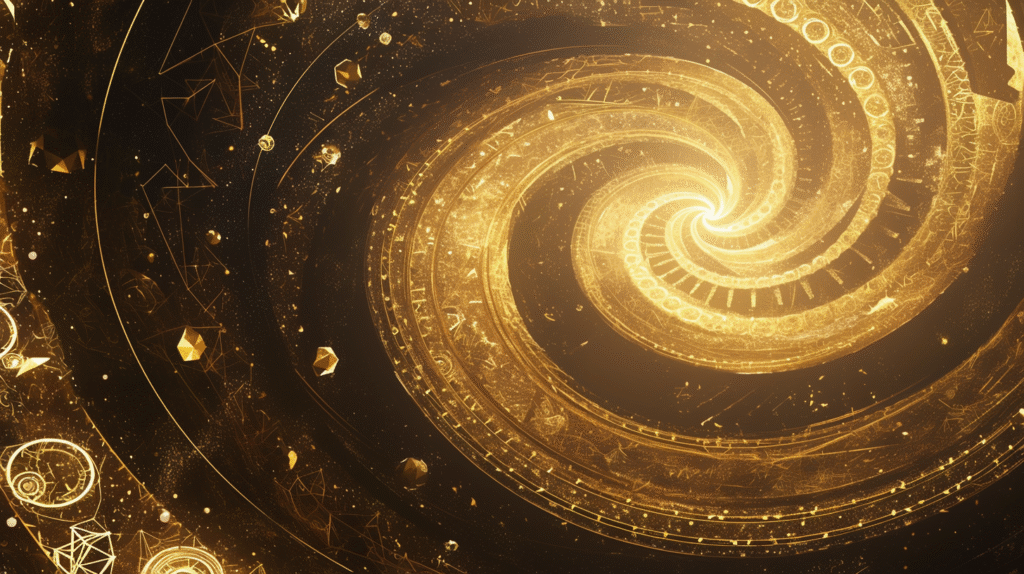
例題1:基本パターン
問題:x² – 5x + 6 = 0 の解の和と積を求めよう
ビエタの公式を使うと…
この方程式は x² + px + q = 0 の形で:
- p = -5
- q = 6
だから:
- 解の和 = -(-5) = 5
- 解の積 = 6 = 6
実際に解いて確認してみよう
因数分解すると:(x – 2)(x – 3) = 0
解は x = 2, 3
- 解の和:2 + 3 = 5 ✓
- 解の積:2 × 3 = 6 ✓
ピッタリ一致しました!
例題2:解を求めずに計算
問題:x² – 7x + 10 = 0 の解をα、βとするとき、α² + β² の値は?
普通の解き方
- 解を求める(x = 2, 5)
- 2² + 5² = 4 + 25 = 29
ビエタの公式を使った解き方
- α + β = 7、α × β = 10(ビエタの公式より)
- α² + β² = (α + β)² – 2αβ
- = 7² – 2×10
- = 49 – 20 = 29
解を求めずに答えが出せました!
例題3:マイナスが入る場合
問題:x² + 3x – 4 = 0 の解の和と積は?
ビエタの公式より:
- 解の和 = -3
- 解の積 = -4
確認 因数分解:(x + 4)(x – 1) = 0 解:x = -4, 1
- 和:-4 + 1 = -3 ✓
- 積:-4 × 1 = -4 ✓
なぜビエタの公式が成り立つ?
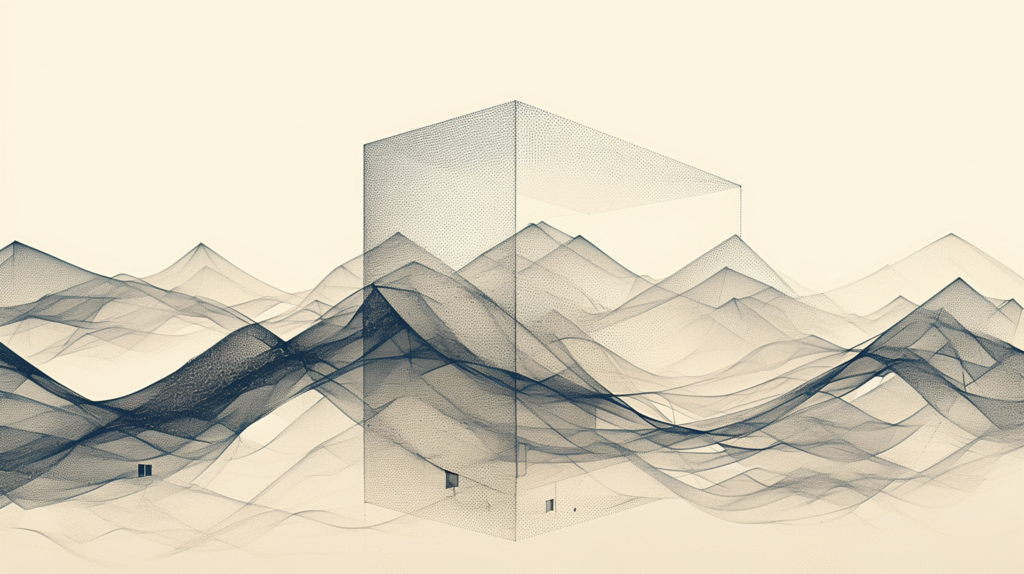
因数分解で考えてみよう
二次方程式 ax² + bx + c = 0 の解が α、β のとき:
ax² + bx + c = a(x - α)(x - β)
右辺を展開すると:
= a(x² - αx - βx + αβ)
= a(x² - (α + β)x + αβ)
= ax² - a(α + β)x + a(αβ)
左辺と係数を比較すると:
- b = -a(α + β) → α + β = -b/a
- c = a(αβ) → αβ = c/a
これがビエタの公式です!
身近な例で理解
お買い物の例
2つの商品を買いました:
- 商品A:α円
- 商品B:β円
レシートには:
- 合計金額(和):α + β円
- 商品を掛け合わせた数(積):α × β円²
この「和」と「積」の情報だけで、元の値段の特徴が分かるのがビエタの公式の考え方です。
ビエタの公式の応用テクニック
テクニック1:逆算で方程式を作る
問題:解が3と4の二次方程式を作れ
ビエタの公式を逆に使う:
- 解の和:3 + 4 = 7
- 解の積:3 × 4 = 12
方程式:x² – (解の和)x + (解の積) = 0
答え:x² – 7x + 12 = 0
テクニック2:対称式の計算
対称式とは?
α と β を入れ替えても変わらない式のこと。
よく出る対称式と変形
- α² + β² = (α + β)² – 2αβ
- α³ + β³ = (α + β)³ – 3αβ(α + β)
- 1/α + 1/β = (α + β)/(αβ)
- α²β + αβ² = αβ(α + β)
テクニック3:判別式との組み合わせ
判別式 D = b² – 4ac と解の関係
- D > 0:異なる2つの実数解
- D = 0:重解(同じ解が2つ)
- D < 0:実数解なし
ビエタの公式と合わせると:
解が両方正 ⇔ 和が正 かつ 積が正 解が異符号 ⇔ 積が負
実践問題で力をつけよう
問題1:基本レベル
x² – 8x + 15 = 0 の解をα、βとするとき:
(1) α + β = ? (2) αβ = ? (3) (α – β)² = ?
解答 (1) α + β = 8 (2) αβ = 15 (3) (α – β)² = (α + β)² – 4αβ = 64 – 60 = 4
問題2:応用レベル
2x² – 6x + 3 = 0 の解をα、βとするとき、α²/β + β²/α の値は?
解答 まず係数を整理:a = 2, b = -6, c = 3
ビエタの公式:
- α + β = 6/2 = 3
- αβ = 3/2
計算:
α²/β + β²/α = (α³ + β³)/(αβ)
= [(α + β)³ - 3αβ(α + β)]/(αβ)
= [27 - 3×(3/2)×3]/(3/2)
= [27 - 13.5]/(3/2)
= 13.5/(3/2)
= 9
問題3:逆問題
解の和が5、解の積が6である二次方程式を作れ
解答
x² – (解の和)x + (解の積) = 0
答え:x² – 5x + 6 = 0
ビエタの公式が役立つ場面
場面1:入試問題
よく出るパターン
- 「解を求めずに〜を計算せよ」
- 「解の条件から係数を求めよ」
- 「対称式の値を求めよ」
これらはビエタの公式の出番!
場面2:グラフの分析
放物線 y = x² + px + q について:
x軸との交点のx座標をα、βとすると:
- 交点の中点:(α + β)/2 = -p/2
- 交点間の距離:|α – β| = √[(α + β)² – 4αβ]
場面3:物理や経済の問題
投げ上げ運動
物体が地面に戻る2つの時刻の和と積から、初速度や最高点を計算できます。
損益分岐点
利益が0になる2つの生産量の和と積から、最適生産量を求められます。
三次以上への拡張
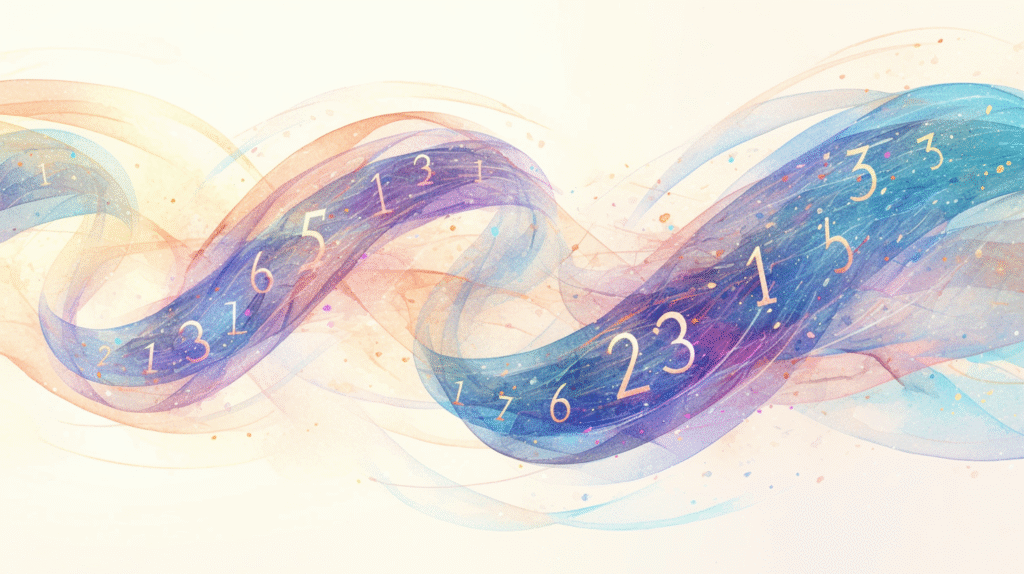
三次方程式のビエタの公式
ax³ + bx² + cx + d = 0 の解をα、β、γとすると:
α + β + γ = -b/a
αβ + βγ + γα = c/a
αβγ = -d/a
パターンが見えてきましたね!
n次方程式の一般形
n個の解の:
- 1個ずつの和
- 2個ずつの積の和
- 3個ずつの積の和
- …
- n個全部の積
これらと係数の関係を表すのが、一般のビエタの公式です。
よくある間違いと注意点
間違い1:符号のミス
要注意!
- 解の和 = -b/a(マイナスがつく)
- 解の積 = c/a(マイナスはつかない)
覚え方:「和にマイナス、積はそのまま」
間違い2:係数の見間違い
2x² – 6x + 3 = 0 の場合
❌ 間違い:b = 6、c = 3 ⭕ 正解:a = 2、b = -6、c = 3
間違い3:x²の係数が1でない場合
3x² – 6x + 2 = 0 なら:
必ず a = 3 で割る!
- 解の和 = 6/3 = 2
- 解の積 = 2/3
よくある質問
Q1. ビエタって誰?
A. フランソワ・ビエト(1540-1603)
フランスの数学者で、代数学の父と呼ばれています。
文字を使った数式の表記法を発展させた人物です。
Q2. 解が虚数でも使える?
A. はい、使えます!
複素数の解でもビエタの公式は成立します。
共役複素数の和は実数になるので便利です。
Q3. いつ使うべき?
A. こんな時に便利:
- 解を求める必要がない問題
- 対称式を計算する問題
- 逆に方程式を作る問題
- 計算を簡略化したい時
まとめ:ビエタの公式は二次方程式の強力な武器!
今回はビエタの公式について詳しく解説しました。
覚えておきたい核心
? ビエタの公式(基本形)
二次方程式 ax² + bx + c = 0 の解をα、βとすると
・解の和:α + β = -b/a
・解の積:α × β = c/a
? 簡単バージョン(a=1)
x² + px + q = 0 の解をα、βとすると
・解の和:α + β = -p
・解の積:α × β = q
? 使いどころ
- 解を求めずに計算したい時
- 対称式の値を求める時
- 方程式を逆算で作る時
- 計算を効率化したい時
? 注意点
- 和の符号にマイナスがつく
- x²の係数で割ることを忘れない
- 対称式の変形パターンを覚える
ビエタの公式は、二次方程式の「裏技」のようなもの。
正面から解くのが大変な問題も、この公式を使えばスマートに解決できます。
最初は慣れないかもしれませんが、使いこなせるようになると、数学の問題を解くスピードが格段に上がります。
ぜひ練習問題で腕を磨いて、ビエタの公式マスターを目指してください!




