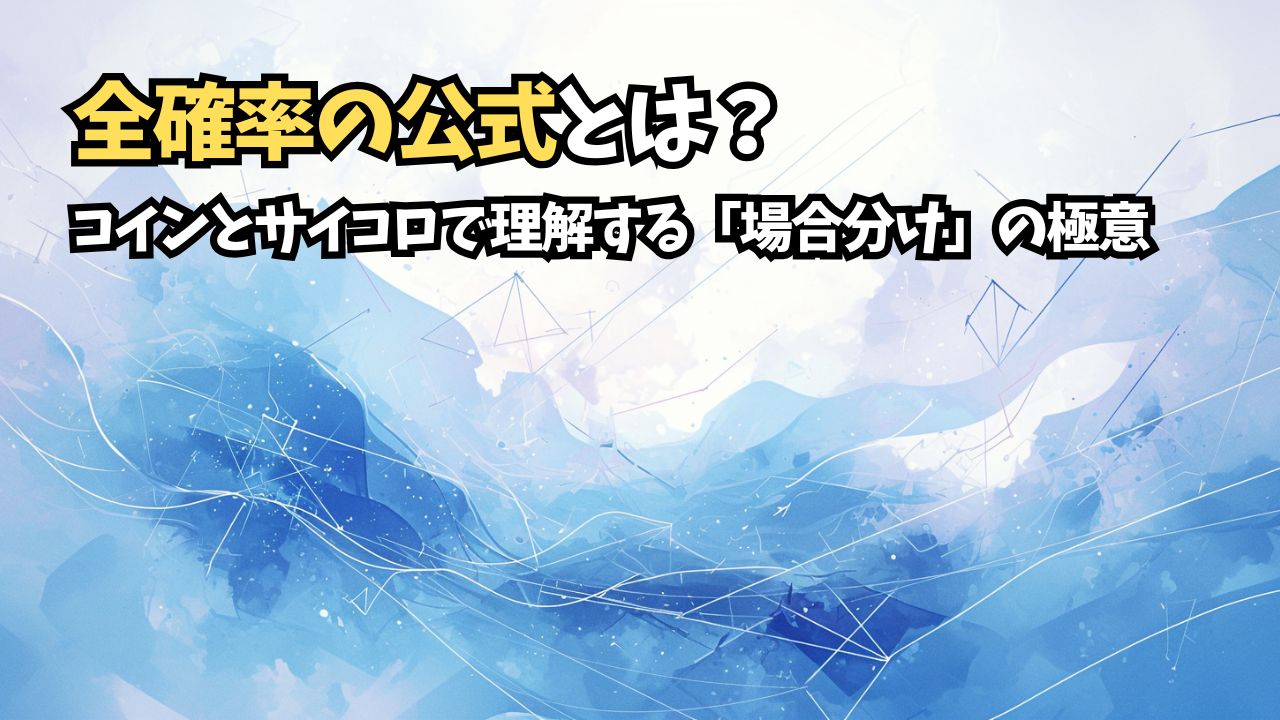「全確率の公式」と聞くと、なんだか難しそうな数学の話に聞こえますよね。
でも実は、私たちが日常生活で無意識に使っている「場合分け」の考え方を、数式にしただけなんです。
たとえば「明日雨が降る確率」を考える時、天気予報では「低気圧が来た場合」と「来なかった場合」に分けて計算していたり。または「電車が遅れる確率」を考える時も、「平日の場合」と「休日の場合」で違いを考慮したり。
この記事では、そんな全確率の公式を、サイコロやコインなどの身近な例を使って、誰でも理解できるように解説していきます。数学が苦手な人も、最後まで読めばきっと「なるほど!」と思えるはずですよ。
全確率の公式とは何か?基本の考え方
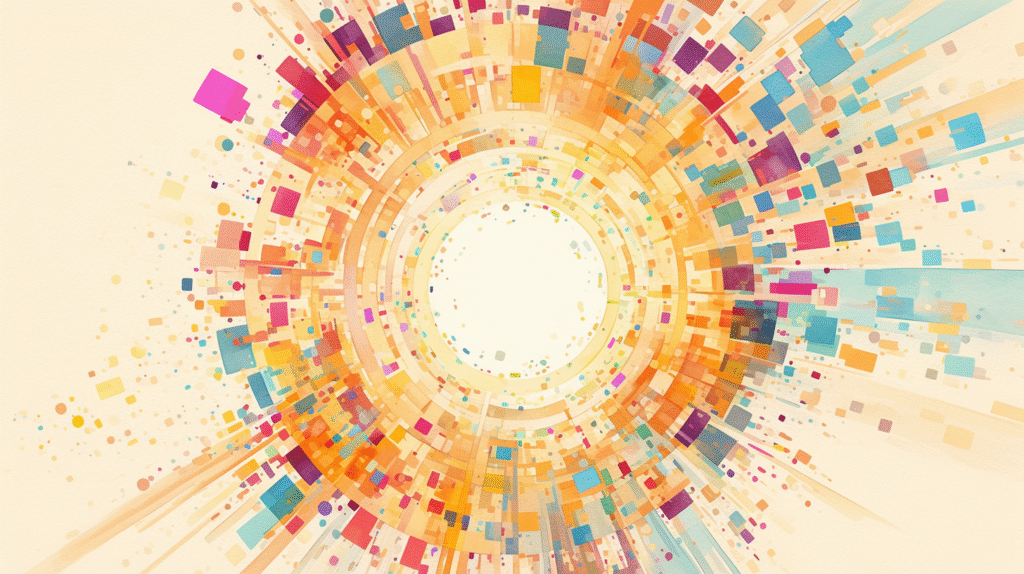
シンプルに言うと「全体を漏れなく場合分けする」こと
全確率の公式は、ある出来事が起こる確率を求めたい時に、すべての可能性を漏れなく場合分けして、それぞれの確率を足し合わせる方法です。
基本の形:
ある出来事の確率 =
(場合1になる確率 × 場合1でその出来事が起こる確率)
+(場合2になる確率 × 場合2でその出来事が起こる確率)
+(場合3になる確率 × 場合3でその出来事が起こる確率)
+...
ちょっと長く見えますが、要は「すべての道筋を考えて、それぞれの確率をかけ算して、最後に全部足す」というだけの話なんです。
具体例1:2つの箱から玉を取り出す問題
問題設定
目の前に2つの箱があるとしましょう。
箱A: 赤玉3個、白玉2個(合計5個)
箱B: 赤玉1個、白玉4個(合計5個)
コインを投げて、表が出たら箱Aから、裏が出たら箱Bから玉を1個取り出します。
このとき、赤玉が出る確率は?
全確率の公式を使った解き方
ステップ1:場合分けをする
- コインが表(箱Aを選ぶ)
- コインが裏(箱Bを選ぶ)
ステップ2:それぞれの確率を計算
- コインが表になる確率:1/2
- コインが裏になる確率:1/2
- 箱Aから赤玉が出る確率:3/5
- 箱Bから赤玉が出る確率:1/5
ステップ3:全確率の公式を適用
赤玉が出る確率 =
(1/2 × 3/5)+(1/2 × 1/5)
= 3/10 + 1/10
= 4/10
= 2/5
答えは2/5(40%)です!
なぜこれで正しいの?
すべての可能性を漏れなくカバーしているからです。
赤玉が出るためには、必ず「箱Aから取る」か「箱Bから取る」のどちらかしかありません。
この2つの道筋をそれぞれ計算して足すことで、全体の確率が求められるんです。
具体例2:天気と遅刻の関係
より身近な例で考えてみよう
太郎くんの遅刻確率を考えてみましょう。
条件:
- 雨の日になる確率:30%(0.3)
- 晴れの日になる確率:70%(0.7)
- 雨の日に遅刻する確率:40%(0.4)
- 晴れの日に遅刻する確率:10%(0.1)
太郎くんが遅刻する確率は?
計算してみよう
場合分け:
- 雨の日に遅刻する
- 晴れの日に遅刻する
全確率の公式を適用:
遅刻する確率 =
(雨の確率 × 雨の日に遅刻する確率)
+(晴れの確率 × 晴れの日に遅刻する確率)
=(0.3 × 0.4)+(0.7 × 0.1)
= 0.12 + 0.07
= 0.19
答えは19%です。つまり、太郎くんは5日に1日くらいの割合で遅刻することになりますね。
全確率の公式が使える条件
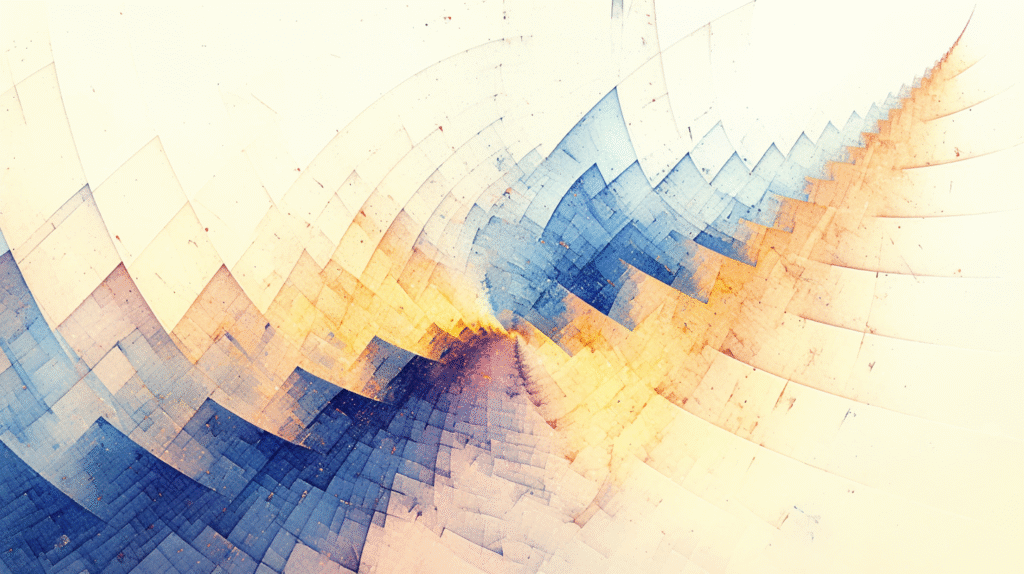
重要な3つのポイント
全確率の公式を使うためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 1. 完全に場合分けできること すべての可能性を漏れなく、重複なくカバーしている必要があります。 例:「晴れ」「曇り」だけだと「雨」が漏れてしまうのでダメ。
- 2. それぞれの場合が同時に起こらないこと 「晴れ」と「雨」が同時に起こることはないので、これはOK。
- 3. 各場合の確率がわかっていること それぞれの場合が起こる確率と、その場合での条件付き確率が必要です。
よくある間違いと注意点
間違い例1:場合分けに漏れがある
悪い例: 「サイコロで偶数が出る確率を、1が出る場合と2が出る場合だけで計算する」
これだと3、4、5、6の場合が漏れています。全確率の公式では、すべての場合を考慮しないと正しい答えが出ません。
間違い例2:確率を単純に足すだけ
悪い例: 「箱Aから赤玉が出る確率3/5と、箱Bから赤玉が出る確率1/5を単純に足して4/5にする」
これは間違い。どちらの箱を選ぶかの確率(1/2ずつ)も考慮する必要があります。
間違い例3:条件付き確率を忘れる
条件付き確率とは「○○の場合に△△が起こる確率」のこと。これを普通の確率と混同しないよう注意しましょう。
全確率の公式の実用的な使い方
ビジネスでの活用例
品質管理: 製品の不良率を計算する時、複数の製造ラインがある場合に全確率の公式を使います。
例:
- ラインA(生産量60%)の不良率:2%
- ラインB(生産量40%)の不良率:3%
- 全体の不良率 = 0.6×0.02 + 0.4×0.03 = 2.4%
日常生活での活用例
通勤ルートの選択: 2つのルートがあって、それぞれ渋滞確率が違う場合の到着時間予測。
保険の計算: 年齢層別の事故率から、全体の事故発生確率を算出。
ベイズの定理との関係
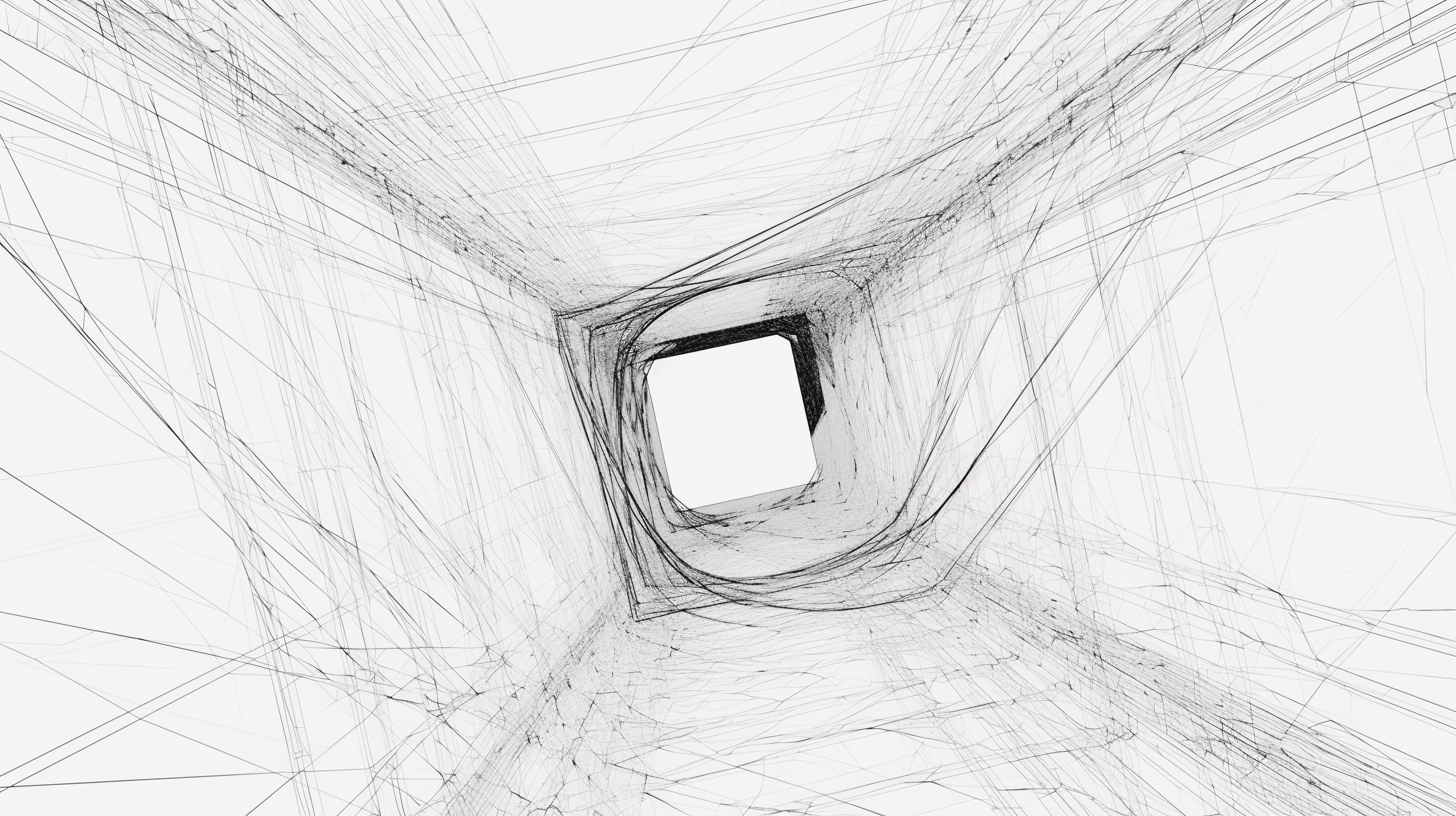
全確率の公式は「原因から結果」、ベイズは「結果から原因」
全確率の公式とよく一緒に出てくるのが「ベイズの定理」です。
違いを簡単に説明すると:
- 全確率の公式:「どの箱を選んだか」から「赤玉が出る確率」を計算
- ベイズの定理:「赤玉が出た」という結果から「どの箱から取った確率」を逆算
実は、ベイズの定理の分母には全確率の公式が使われているんです。つまり、全確率の公式はベイズの定理を理解するための基礎でもあるんですね。
練習問題で理解を深めよう
問題:3枚のコインを使った確率
3枚のコインがあります:
- コインA:両面が表
- コインB:両面が裏
- コインC:片面が表、片面が裏
ランダムに1枚選んで投げたとき、表が出る確率は?
解答
場合分け:
- コインAを選ぶ(確率1/3)→ 表が出る確率1
- コインBを選ぶ(確率1/3)→ 表が出る確率0
- コインCを選ぶ(確率1/3)→ 表が出る確率1/2
全確率の公式:
表が出る確率 =
(1/3 × 1)+(1/3 × 0)+(1/3 × 1/2)
= 1/3 + 0 + 1/6
= 1/2
答えは1/2(50%)です!
まとめ:全確率の公式は「完璧な場合分け」の道具
全確率の公式について、ここまで読んでいただきありがとうございます。
押さえておきたいポイント:
- 基本の考え方 すべての可能性を漏れなく場合分けして、それぞれの確率を計算して足し合わせる
- 使うタイミング 複数の経路や条件があって、最終的な確率を求めたいとき
- 計算の手順
- 完全に場合分けする
- 各場合の確率を求める
- 条件付き確率を掛ける
- すべて足し合わせる
- 注意点
- 場合分けに漏れや重複がないか確認
- 条件付き確率を正しく理解する
全確率の公式は、複雑に見える確率の問題を、シンプルな場合分けで解決する強力な道具です。
最初は式が長く見えて難しそうに感じるかもしれませんが、「すべての道を考えて、それぞれの確率を足す」という基本さえ理解すれば、いろいろな問題に応用できます。
日常生活でも、リスク管理や意思決定の場面で、この考え方はとても役立ちます。ぜひ、身の回りの確率問題を見つけたら、全確率の公式で考えてみてくださいね!