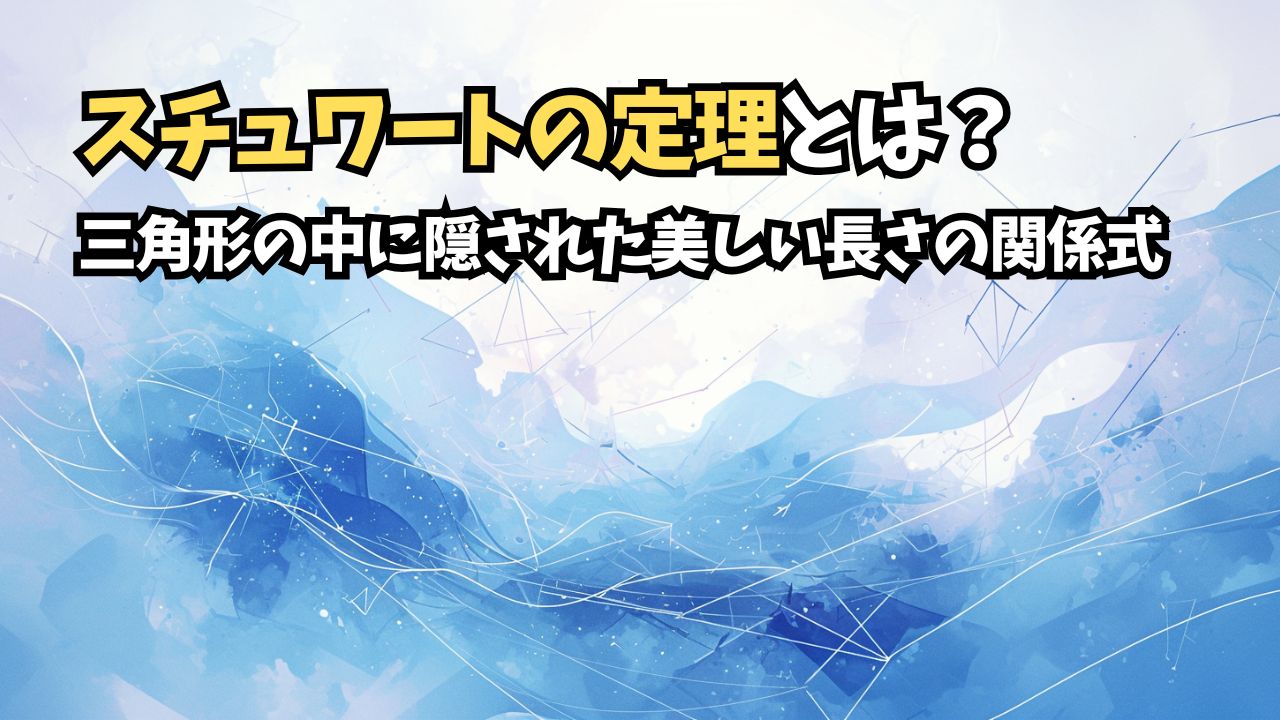三角形を見たとき、あなたは何を思い浮かべますか?
ピラミッド、屋根の形、三角定規…。でも実は、どんな三角形の中にも、目には見えない美しい数学的な関係が隠れています。その一つが「スチュワートの定理」です。
この定理は、1746年にスコットランドの数学者マシュー・スチュワートが発見したもの。三角形の頂点から対辺に線を引いたとき、その線の長さと他の辺の長さの間に成り立つ、不思議な関係式なんです。
「なんだか難しそう…」と思うかもしれません。でも大丈夫。この定理は、実は私たちの日常生活でも使われています。GPSの位置計算、建築物の構造計算、さらには宇宙探査機の軌道計算にも。
この記事では、スチュワートの定理を、図形パズルを解くような感覚で理解していきましょう。数式は最小限にして、「なぜこんな関係が成り立つのか」を中心に解説していきます。
スチュワートの定理を一番簡単に理解する方法
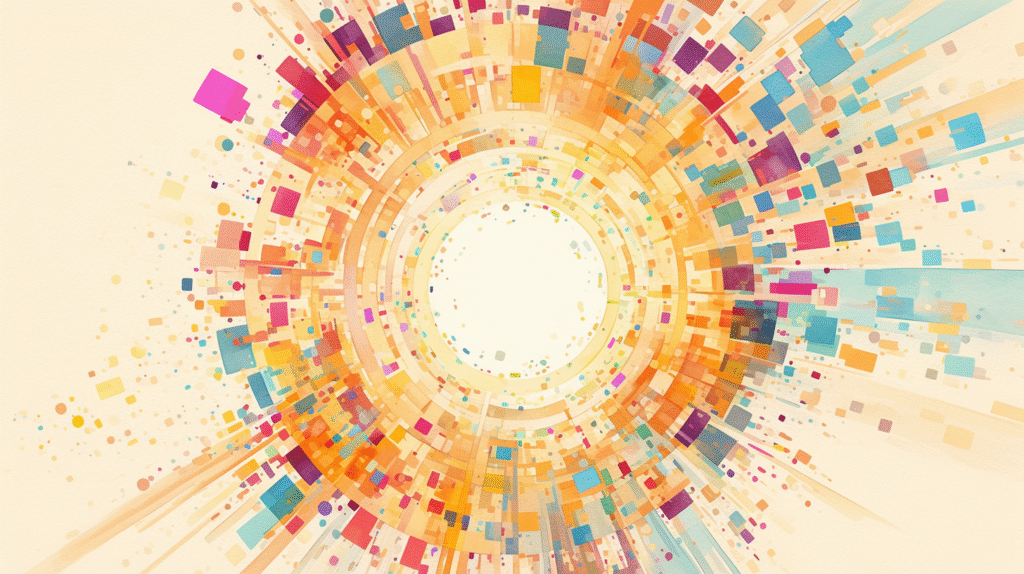
まず、状況を整理しよう
想像してください。あなたの前に三角形ABCがあります。
設定:
- 三角形ABCがある
- 頂点Aから対辺BCに線を引く
- BCとの交点をDとする
- この線ADを「チェビアン」と呼ぶ(頂点と対辺を結ぶ線の特別な名前)
つまり、三角形を1本の線で2つの小さな三角形に分けた状態です。
定理が教えてくれること
スチュワートの定理は、この図形の中の7つの長さの関係を教えてくれます:
関係する長さ:
- 三角形の3辺:AB(c)、AC(b)、BC(a)
- チェビアン:AD(d)
- 分割された底辺:BD(m)、DC(n)
スチュワートの定理の式:
b²m + c²n = a(d² + mn)
左辺と右辺が必ず等しくなる、という美しい関係です。
身近な例で考えてみる
公園のブランコの支柱
公園のブランコを思い浮かべてください。
- A字型の支柱(三角形)
- 補強のための横棒(チェビアン)
この横棒の長さと、支柱の各部分の長さには、スチュワートの定理で表される関係があるんです。設計者はこの関係を使って、最も安定する横棒の位置を計算しています。
なぜこんな関係が成り立つの?直感的な理解
バランスの原理として理解する
スチュワートの定理は、実は「モーメント(回転力)のバランス」として理解できます。
シーソーで考えてみよう:
シーソーがバランスを取るには:
- 軽い人は支点から遠く
- 重い人は支点から近く
これと似た原理が、三角形の中でも働いています。チェビアンADは、両側の三角形のバランスを取る「見えない支点」のような役割を果たしているんです。
エネルギー最小の原理
自然界では、すべてが「最も安定した状態」を求めます。
水滴の例:
- 水滴は球形になる(表面積最小)
- 石けん膜は最小面積を作る
スチュワートの定理も、三角形内の線分が作る「エネルギー的に安定した状態」を表現していると考えることができます。
スチュワートの定理の特殊なケース
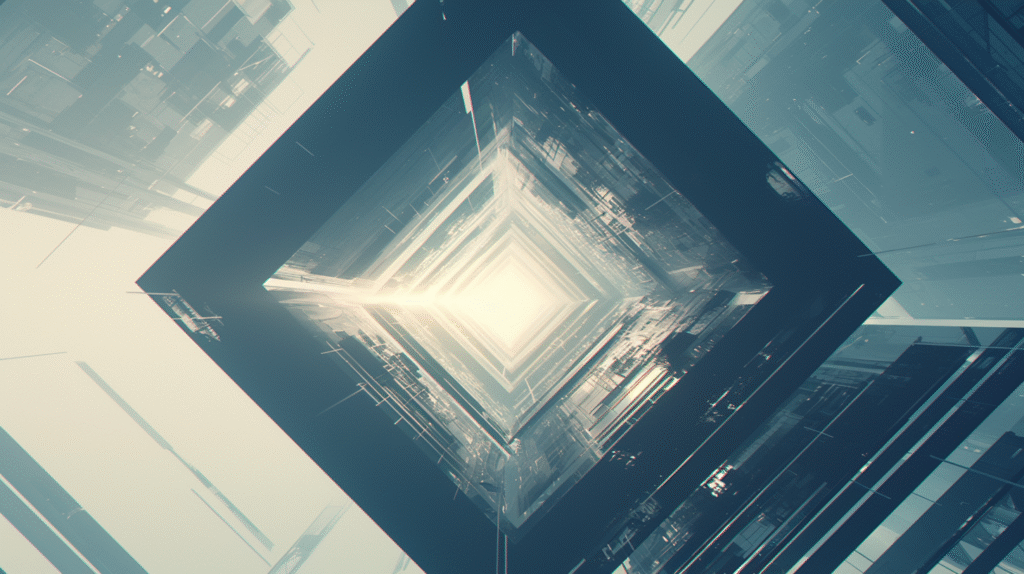
1. 中線の場合(AD が中線)
中線とは、頂点と対辺の中点を結ぶ線です。
このとき、m = n(BDとDCが等しい)なので、定理は簡単になります:
中線の長さの公式:
d² = (2b² + 2c² - a²) / 4
実用例:重心を求める
三角形の3本の中線は1点で交わり、その点が重心になります。物体のバランスを取るときに重要な点です。
2. 角の二等分線の場合
頂点Aの角を二等分する線の場合、また別の美しい関係が現れます。
角の二等分線の性質:
- BD : DC = AB : AC
- つまり、m : n = c : b
この関係を使うと、角の二等分線の長さを計算できます。
3. 高さ(垂線)の場合
頂点から対辺に垂線を下ろした場合も、スチュワートの定理の特殊ケースとして扱えます。
実際の計算例:具体的な数字で確認
例題1:シンプルな三角形
問題:
- 三角形ABC:AB = 5、AC = 4、BC = 6
- Dは BCを 2:3 に内分する点
- ADの長さは?
解き方:
- BD = 6 × (2/5) = 2.4
- DC = 6 × (3/5) = 3.6
- スチュワートの定理を適用:
- 4² × 2.4 + 5² × 3.6 = 6 × (d² + 2.4 × 3.6)
- 38.4 + 90 = 6 × (d² + 8.64)
- 128.4 = 6d² + 51.84
- d² = 12.76
- d = 約3.57
例題2:中線の長さ
問題: 正三角形(すべての辺が6)の中線の長さは?
解き方: 中線の公式を使って:
- d² = (2×6² + 2×6² – 6²) / 4
- d² = (72 + 72 – 36) / 4
- d² = 27
- d = 3√3 ≈ 5.20
正三角形の中線は、辺の長さの(√3/2)倍になることが分かります。
スチュワートの定理の実用的な応用
1. GPS測位システム
三点測位の原理:
GPSは、3つ以上の衛星からの距離を使って位置を特定します。
- 各衛星までの距離が分かる(三角形の辺)
- 地上の位置を求める(チェビアンの足の位置)
スチュワートの定理を応用した計算により、正確な位置が割り出されます。
2. 建築・土木工学
トラス構造の設計:
橋や建物の骨組み(トラス)設計では、スチュワートの定理が活躍します。
- 各部材にかかる力を計算
- 最適な補強材の位置を決定
- 構造の安定性を保証
東京スカイツリーの複雑な鉄骨構造も、こうした幾何学的な計算に基づいています。
3. ロボット工学
ロボットアームの制御:
ロボットアームの関節位置を計算する際に使用されます。
- アームの各部分の長さ(三角形の辺)
- 目標位置(チェビアンの足)
- 必要な関節角度を逆算
工場の組み立てロボットは、この計算を1秒間に何千回も行っています。
4. コンピュータグラフィックス
3Dモデリング:
ポリゴン(多角形)メッシュの処理で活用されます。
- 面の分割
- 頂点の最適配置
- テクスチャマッピング
ゲームのキャラクターの滑らかな動きも、この定理を使った計算の賜物です。
覚え方のコツ:語呂合わせと視覚的記憶
語呂合わせで覚える
スチュワートの定理の式:b²m + c²n = a(d² + mn)
覚え方: 「ビーム(b²m)とシーン(c²n)が、エー(a)でディーツー(d²)とエムエヌ(mn)」
ちょっと強引ですが、リズムで覚えると忘れにくいです。
視覚的に覚える
定理の形を「天秤」として覚える方法:
b²m + c²n
━━━━━━━━━━━
↑
a(d² + mn)
左の皿と右の皿がバランスを取っている、というイメージです。
パターンで覚える
対称性に注目:
- 左辺:「辺の2乗 × 反対側の底辺」の和
- 右辺:底辺全体 × (チェビアンの2乗 + 底辺の部分の積)
この対称性を意識すると、式の構造が見えてきます。
よくある間違いと注意点
間違い1:単位を揃えない
すべての長さの単位を統一することが大切です。
- センチとメートルを混ぜない
- 必ず同じ単位系で計算
間違い2:内分と外分の混同
点Dが辺BC上にある場合(内分)と、BCの延長上にある場合(外分)では、式が少し変わります。
外分の場合: 符号に注意が必要になります。
間違い3:特殊ケースの見落とし
中線や角の二等分線の場合は、もっと簡単な公式があります。わざわざ一般形を使う必要はありません。
他の定理との関係
余弦定理との関係
スチュワートの定理は、実は余弦定理の一般化とも言えます。
余弦定理: c² = a² + b² – 2ab cos C
スチュワートの定理に特別な条件を加えると、余弦定理が導かれます。
ヘロンの公式との関係
三角形の面積を求めるヘロンの公式とも深い関係があります。両方とも、辺の長さだけから他の量を求める点で共通しています。
メネラウスの定理・チェバの定理
これらも三角形の中の線分に関する定理ですが、スチュワートの定理は「長さ」に、メネラウス・チェバは「比」に注目している点が違います。
発展:高次元への拡張
四面体への拡張
スチュワートの定理は、3次元の四面体にも拡張できます。
四面体版:
- 頂点から対面への垂線
- 各辺の長さとの関係式
宇宙ステーションの構造設計などで使われています。
n次元への一般化
数学的には、任意の次元の単体(シンプレックス)に対して、同様の関係式が成り立ちます。
応用分野:
- 機械学習の特徴空間
- データ解析の次元削減
- 量子力学の状態空間
歴史的背景:スチュワートとその時代

マシュー・スチュワート(1717-1785)
スコットランドの数学者で、エディンバラ大学の教授でした。
時代背景:
- 産業革命の黎明期
- ニュートン力学が確立した後
- 測量技術が発展した時代
この定理は、当時の測量や航海術の発展に貢献しました。
実は古代から知られていた?
似た関係式は、実は古代ギリシャのアルキメデスも知っていたという説があります。しかし、一般的な形で定式化したのはスチュワートが最初です。
練習問題で理解を深める
基本問題
問題1: 三角形ABC(AB=7、AC=5、BC=8)で、ADが角Aの二等分線のとき、ADの長さを求めよ。
ヒント: 角の二等分線の性質を使って、まずBDとDCの長さを求めましょう。
応用問題
問題2: 正六角形の中心から各頂点への距離と、各辺の中点への距離の関係を、スチュワートの定理を使って説明せよ。
ヒント: 正六角形を6つの正三角形に分けて考えます。
まとめ:美しい幾何学の世界への入り口
スチュワートの定理は、一見複雑に見える図形の中に、シンプルで美しい関係が隠れていることを教えてくれます。
覚えておきたいポイント:
- 基本の形を理解する
- 三角形 + チェビアン = 7つの長さの関係
- b²m + c²n = a(d² + mn)
- 特殊ケースを知る
- 中線:簡単な公式がある
- 角の二等分線:比の性質を使う
- 高さ:ピタゴラスの定理と組み合わせる
- 実用的な応用
- GPS、建築、ロボット工学
- 見えないところで大活躍
- 他の定理との関係
- 余弦定理の一般化
- メネラウス・チェバとの違い
- 問題解決のコツ
- 単位を揃える
- 図を正確に描く
- 特殊ケースを見逃さない
最後に:数学の美しさを感じる
スチュワートの定理は、数学が持つ「予想外のつながり」の美しさを示す好例です。バラバラに見える長さが、実は一つの式でつながっている。
この定理を知ることで、身の回りの三角形を見る目が変わるかもしれません。屋根の梁、自転車のフレーム、クレーンのアーム…。すべての中に、スチュワートの定理が隠れています。
数学は、世界を理解するための言語。スチュワートの定理は、その言語の美しい一文なのです。