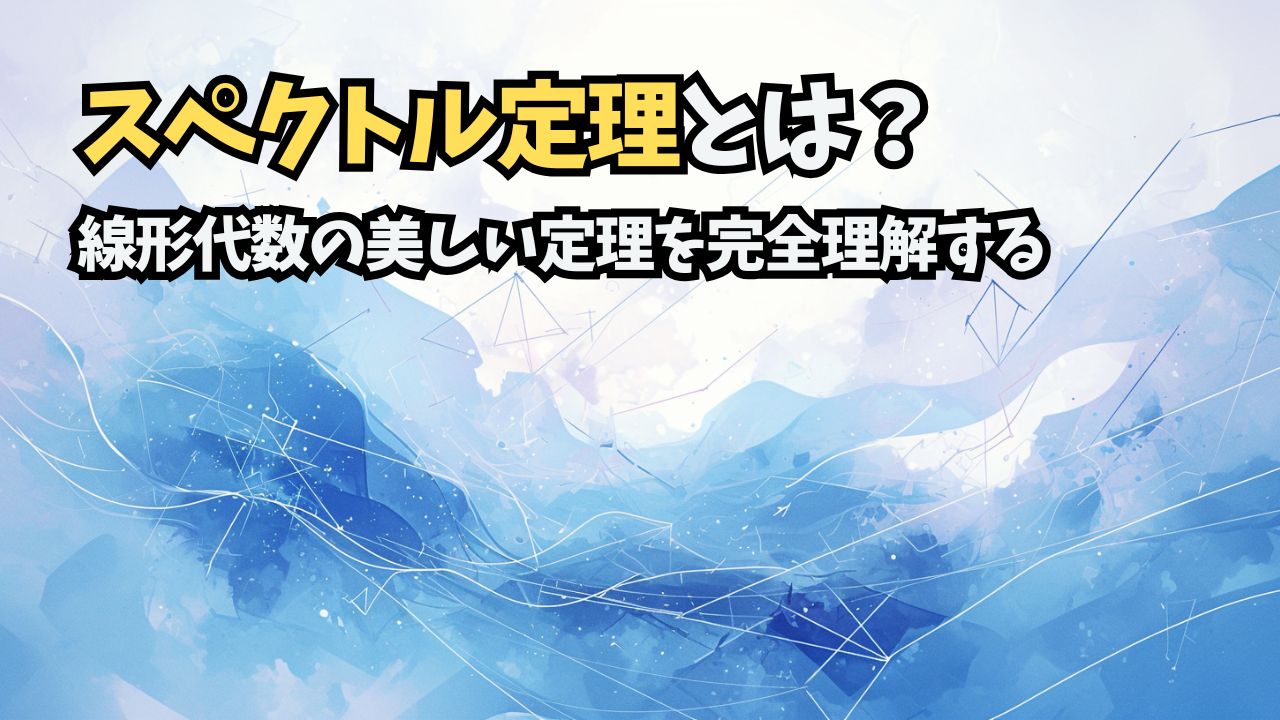数学の世界には、複雑に見えるものを単純で美しい形に変換できる「魔法のような定理」がいくつか存在します。
スペクトル定理は、まさにそんな定理の一つです。
この定理は、対称行列や正規行列といった「性質の良い行列」を、対角行列という最もシンプルな形に変換できることを保証してくれます。まるで、絡まった糸を一本一本きれいにほどいて並べ直すような、そんな働きをしてくれるのです。
物理学の量子力学、工学の振動解析、データサイエンスの主成分分析など、現実世界の様々な問題を解く鍵となるこの定理。今回は、その本質を分かりやすく解説していきます。
スペクトル定理の基本:行列を「分解」するという発想
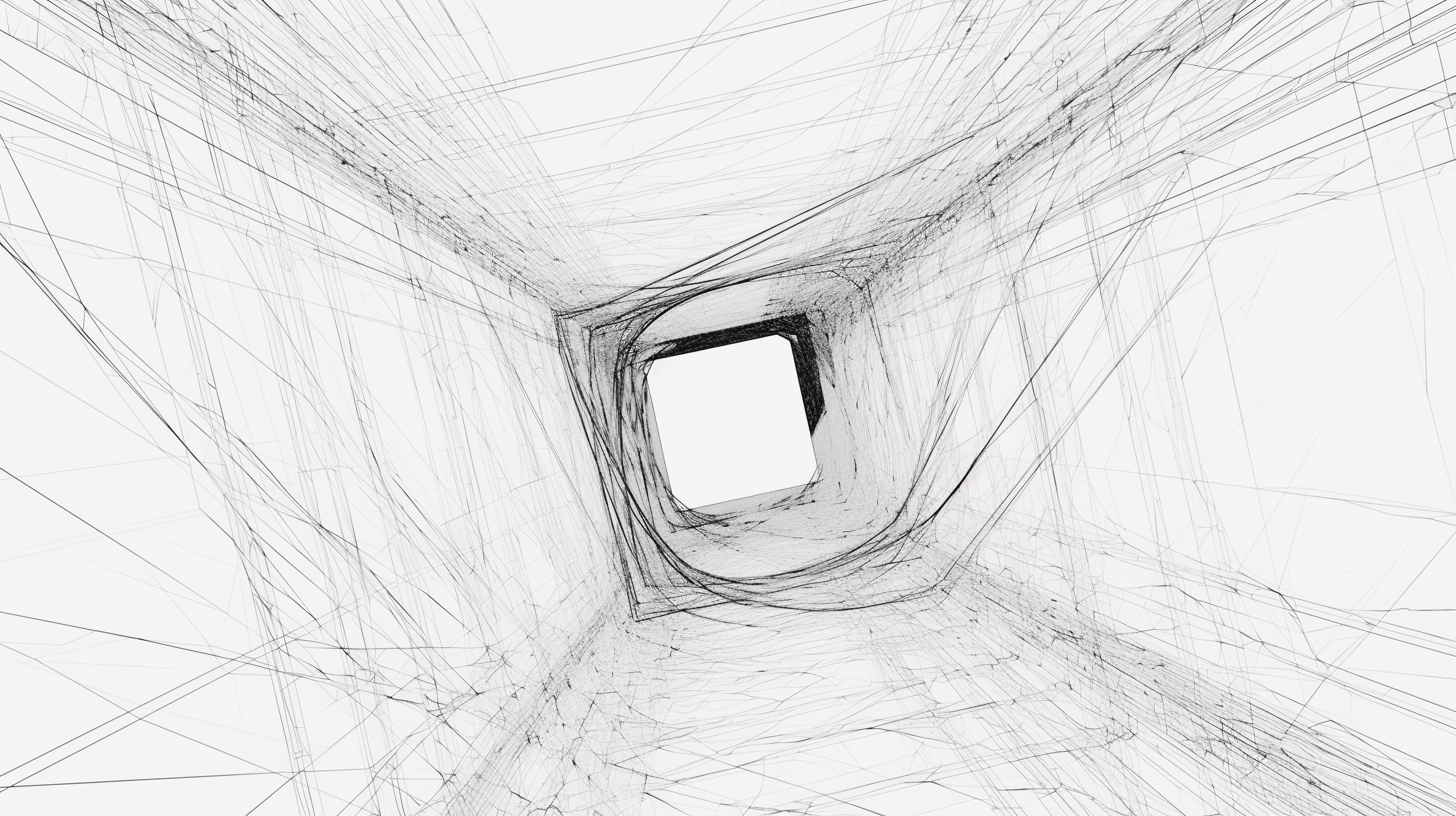
そもそもスペクトル定理って何?
スペクトル定理を一言で表現すると:
「対称行列(またはより一般に正規行列)は、直交行列を使って対角化できる」
という定理です。
これだけ聞いても「?」となるかもしれません。料理に例えると、こんな感じです:
複雑な料理(対称行列)を
↓
基本的な材料(固有値)と
調理法(固有ベクトル)に
↓
分解して理解できる
なぜ「スペクトル」という名前?
スペクトル(spectrum)は、もともと光を分解したときに現れる虹色の帯を指す言葉でした。
白い光 → プリズム → 虹色のスペクトル
これと同じように、行列を「固有値」という基本的な成分に分解することから、この名前が付けられています。
行列 → スペクトル分解 → 固有値の集まり
必要な基礎知識:これだけは押さえておこう
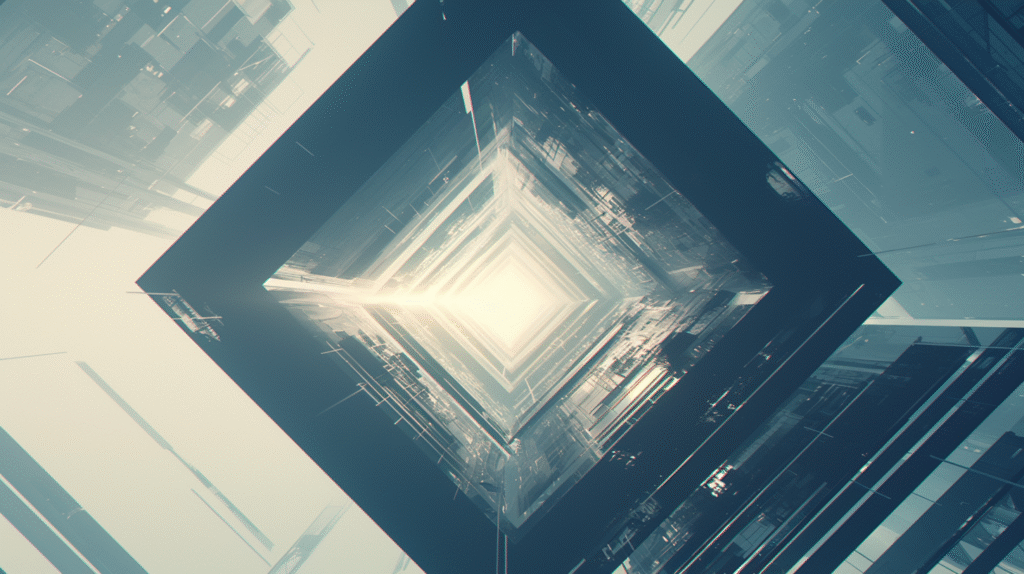
1. 対称行列とは
対称行列は、転置しても変わらない行列です。
A = [2 1] A^T = [2 1]
[1 3] [1 3]
A = A^T なので対称行列
特徴:
- 対角線を軸に左右対称
- 実数の固有値を持つ
- 固有ベクトルが直交する
2. 固有値と固有ベクトル
行列Aに対して、以下を満たすベクトルvとスカラーλ:
Av = λv
- λ:固有値(eigenvalue)
- v:固有ベクトル(eigenvector)
直感的な意味: 「行列Aをかけても、方向が変わらず大きさだけがλ倍になるベクトル」
3. 直交行列
直交行列Qは、以下を満たす行列:
Q^T Q = QQ^T = I(Iは単位行列)
特徴:
- 列ベクトルが互いに直交
- 各列ベクトルの長さが1
- 回転や反射を表す
4. 対角行列
対角成分以外がすべて0の行列:
D = [λ₁ 0 0 ]
[0 λ₂ 0 ]
[0 0 λ₃]
計算が非常に簡単になるため、行列を対角化できると嬉しい!
スペクトル定理の内容:3つの重要なバージョン
バージョン1:実対称行列の場合
定理の内容: 「n×nの実対称行列Aは、直交行列Qによって対角化可能」
A = QDQ^T
ここで:
- Q:固有ベクトルを並べた直交行列
- D:固有値を並べた対角行列
具体例:
A = [3 1]
[1 3]
固有値:λ₁ = 4, λ₂ = 2
固有ベクトル:v₁ = [1/√2, 1/√2]^T, v₂ = [1/√2, -1/√2]^T
Q = [1/√2 1/√2] D = [4 0]
[1/√2 -1/√2] [0 2]
A = QDQ^T が成立!
バージョン2:エルミート行列の場合
複素数を含む場合の拡張です。
エルミート行列:A = A*(*は複素共役転置)
定理: 「エルミート行列は、ユニタリ行列Uによって対角化可能」
A = UDU*
バージョン3:正規行列の場合
最も一般的なバージョンです。
正規行列:AA* = A*A を満たす行列
定理: 「正規行列は、ユニタリ行列によって対角化可能」
これには対称行列、歪対称行列、直交行列、ユニタリ行列などがすべて含まれます。
直感的な理解:幾何学的な意味

スペクトル分解の幾何学的解釈
対称行列による変換を、3つのステップに分解できます:
元のベクトル x ↓ ① 回転(Q^T) 固有ベクトル方向に座標軸を回転 ↓ ② 拡大縮小(D) 各軸方向に固有値倍 ↓ ③ 逆回転(Q) 元の座標系に戻す 変換後のベクトル Ax
2次元の例で見てみよう
楕円の方程式:x^T A x = 1
A = [3 1]
[1 3]
スペクトル分解により:
・主軸の方向 = 固有ベクトル
・主軸の長さ = 1/√固有値
つまり、傾いた楕円を
まっすぐな楕円として理解できる!
実際の応用例:スペクトル定理が活躍する場面
1. 主成分分析(PCA):データサイエンスの基本技術
問題: 高次元データの次元を削減したい
スペクトル定理の活用:
# 共分散行列(対称行列)のスペクトル分解
共分散行列 C = X^T X / n
C = QDQ^T
↓
主成分 = 固有ベクトル(Q の列)
寄与率 = 固有値の比率
結果:
- データの主要な変動方向を発見
- ノイズを除去
- 可視化が可能に
2. 量子力学:物理現象の理解
ハミルトニアン演算子(エルミート演算子)
Ĥ|ψ⟩ = E|ψ⟩
Ĥ:ハミルトニアン(エネルギー演算子)
E:エネルギー固有値
|ψ⟩:固有状態
スペクトル定理により:
- エネルギー準位(固有値)は実数
- 固有状態は直交
- 任意の状態を固有状態の重ね合わせで表現可能
3. 振動解析:建築・機械工学
問題: 建物や橋の振動モードを解析
運動方程式:
M ẍ + K x = 0
M:質量行列(対称)
K:剛性行列(対称)
固有値問題:
K v = λ M v
固有値 λ = ω²(固有振動数の2乗)
固有ベクトル v = 振動モード
4. グラフ理論:ネットワーク解析
ラプラシアン行列(対称行列)のスペクトル分解により:
- グラフの連結性を判定
- コミュニティ検出
- グラフの類似度計算
- ページランクの計算
5. 画像圧縮:JPEG圧縮の基礎
画像ブロック(8×8)
↓
離散コサイン変換(DCT)
(一種のスペクトル分解)
↓
主要成分だけ保存
↓
データ量削減
証明のアイデア:なぜ成り立つのか
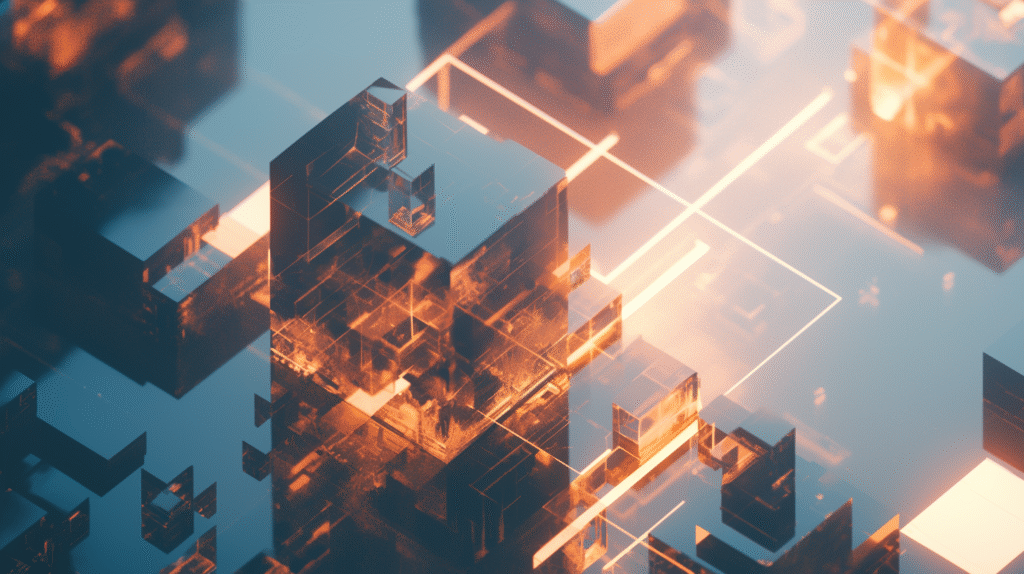
実対称行列の場合の証明スケッチ
ステップ1:固有値は実数
Av = λv
v*Av = λv*v
(v*Av)* = λ*(v*v)*
v*Av = λ*v*v
対称性より左辺は実数
→ λ = λ* → λは実数
ステップ2:異なる固有値の固有ベクトルは直交
Av₁ = λ₁v₁, Av₂ = λ₂v₂
λ₁ ≠ λ₂ のとき
λ₁(v₁·v₂) = (Av₁)·v₂ = v₁·(Av₂) = λ₂(v₁·v₂)
(λ₁-λ₂)(v₁·v₂) = 0
→ v₁·v₂ = 0(直交)
ステップ3:固有ベクトルで正規直交基底を作る
- グラム・シュミットの直交化法を使用
- 正規化して長さを1に
結果: Q = [v₁ v₂ … vₙ] とすると、A = QDQ^T
計算方法:実際に対角化してみよう
2×2行列の例
問題:
A = [5 2]
[2 2]
を対角化せよ
ステップ1:固有値を求める
det(A - λI) = 0
det([5-λ 2 ]) = 0
([2 2-λ])
(5-λ)(2-λ) - 4 = 0
λ² - 7λ + 6 = 0
λ = 6, 1
ステップ2:固有ベクトルを求める
λ₁ = 6のとき:
(A - 6I)v = 0
[-1 2][v₁] = [0]
[2 -4][v₂] [0]
v₁ = [2, 1]^T → 正規化 → [2/√5, 1/√5]^T
λ₂ = 1のとき:
v₂ = [1, -2]^T → 正規化 → [1/√5, -2/√5]^T
ステップ3:行列を構成
Q = [2/√5 1/√5] D = [6 0]
[1/√5 -2/√5] [0 1]
確認:A = QDQ^T ✓
よくある誤解と注意点
誤解1:すべての行列が対角化可能
間違い! 対角化可能なのは特別な行列だけです。
反例:
A = [0 1]
[0 0]
この行列は対角化不可能(ジョルダン標準形になる)
誤解2:固有ベクトルは一意
間違い! 固有ベクトルの向きと長さは任意性があります。
Av = λv なら
A(cv) = λ(cv) も成立(cは0でない定数)
誤解3:計算は常に簡単
間違い! 大きな行列では数値計算が必要で、誤差の蓄積に注意が必要です。
実用的なアルゴリズム:
- QR法
- ヤコビ法
- ハウスホルダー変換
- 特異値分解(SVD)
発展的な話題:さらに深く学ぶために
1. 関数解析への拡張
無限次元空間でのスペクトル定理:
- コンパクト自己共役作用素
- 非有界自己共役作用素
- スペクトル測度
2. スペクトル定理の一般化
特異値分解(SVD): 任意の行列を分解
A = UΣV^T
極分解:
A = UP(Uは直交/ユニタリ、Pは半正定値)
3. 数値計算での応用
- 反復法の収束性解析
- 条件数の評価
- 前処理行列の設計
4. 機械学習での応用
- カーネル法
- グラフニューラルネットワーク
- スペクトルクラスタリング
まとめ:スペクトル定理の美しさと実用性
スペクトル定理は、複雑な行列を最もシンプルな形(対角行列)に変換できることを保証する、線形代数の中心的な定理です。
重要なポイント:
✅ 対称行列は必ず対角化可能
- 実固有値を持つ
- 固有ベクトルが直交基底を作る
✅ 幾何学的な意味が明確
- 回転 → 拡大縮小 → 逆回転
- 主軸変換として理解可能
✅ 応用範囲が広い
- データ解析(PCA)
- 物理学(量子力学)
- 工学(振動解析)
- コンピュータサイエンス(グラフ理論)
この定理の美しさは、「複雑なものを単純な要素に分解できる」という点にあります。まるで、複雑な音楽を個々の音符に分解するように、行列の本質を明らかにしてくれるのです。
数学の抽象的な理論が、これほど多くの実用的な問題を解決する鍵となっている。それがスペクトル定理の魅力であり、線形代数を学ぶ意義でもあるのです。