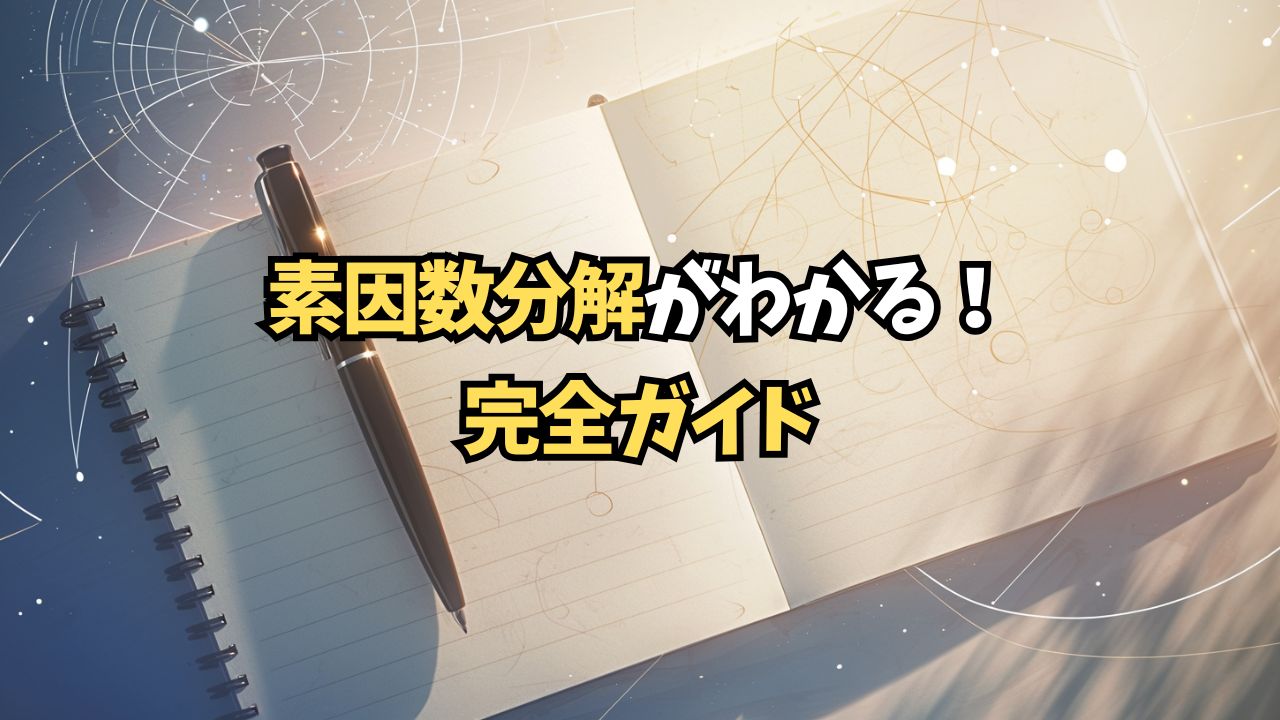「素因数分解」と聞くと、難しそうに感じるかもしれません。
でも大丈夫!素因数分解は、数を「素数」という基本的な数のかけ算で表すだけです。
たとえば、12という数を「2×2×3」と表すことが素因数分解です。
実は、素因数分解はインターネットの暗号化やゲームのプログラミングなど、私たちの身の回りでたくさん使われています。
今日は、この素因数分解を一緒にマスターしていきましょう。
素数の基本を理解しよう
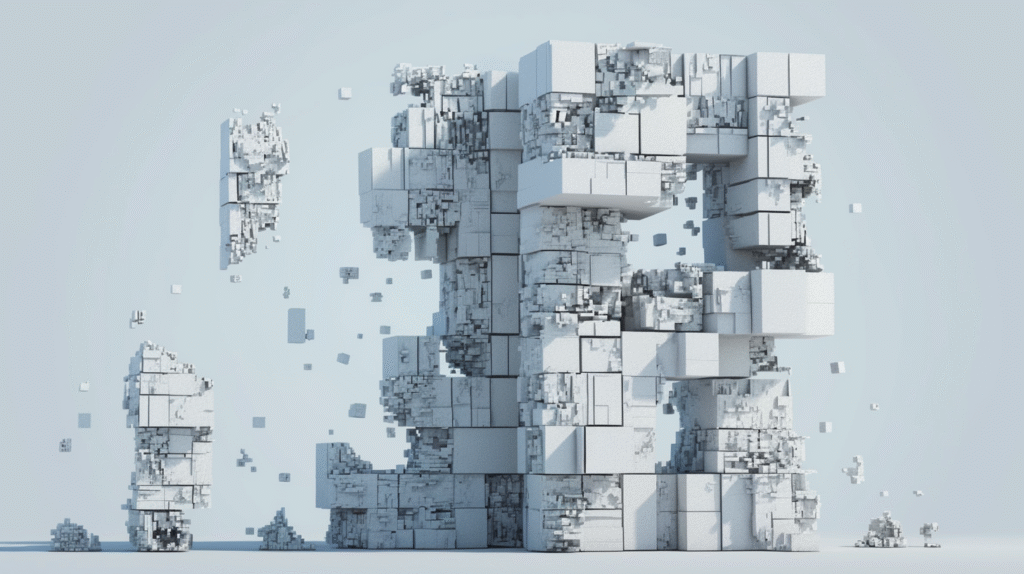
素数とは何か
素数とは「1とその数自身でしか割り切れない、2以上の自然数」のことです。
例:
- 7は1と7でしか割り切れない → 素数
- 6は1、2、3、6で割り切れる → 素数ではない(合成数)
重要な注意点: 1は素数ではありません。なぜなら、約数が1つしかないから。素数の定義は「約数がちょうど2つ」なのです。
100までの素数
まずは20までの素数を確実に覚えましょう。
20までの素数:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
語呂合わせで覚える:
- 「兄さん(2、3)、ご飯(5、7)、いい(11)」
- 「父さん(13)、いいな(17)、行く(19)」
100までには全部で25個の素数があります。大きめの素数も少しずつ覚えていきましょう。
エラトステネスのふるい
古代ギリシャの数学者エラトステネスが考えた素数の見つけ方:
- 1から100までの数を書き出す
- 1を消す(素数ではない)
- 2を残して、2の倍数を全部消す
- 3を残して、3の倍数を全部消す
- 5を残して、5の倍数を全部消す
- 7を残して、7の倍数を全部消す
- 残った数が素数!
実際にノートに書いてやってみると、パターンが見えてきて楽しいですよ。
素因数分解のやり方
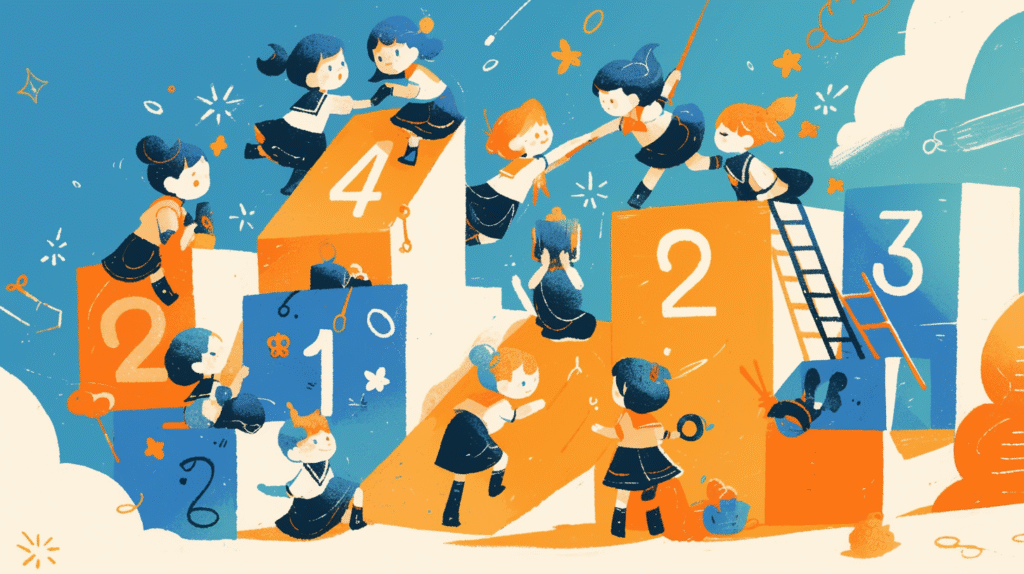
基本の5ステップ
素因数分解は次の手順で行います:
- 分解したい数を書く
- 一番小さい素数(2)から順に割っていく
- 割り切れたら、その商でまた同じことを繰り返す
- 商が素数になったら終了
- 同じ素数は指数でまとめる
実例:84の素因数分解
84 ÷ 2 = 42 (2で割れた!)
42 ÷ 2 = 21 (まだ2で割れる!)
21 ÷ 3 = 7 (3で割れた!)
7は素数なので終了
答え:84 = 2² × 3 × 7
ポイントは「小さい素数から順番に試す」ことです。
割り切れるかどうかの判定法
| 倍数 | 判定方法 | 例 |
|---|---|---|
| 2の倍数 | 一の位が0、2、4、6、8 | 126 → 一の位が6 → 2の倍数 |
| 3の倍数 | 各位の数字の和が3の倍数 | 126 → 1+2+6=9 → 3の倍数 |
| 5の倍数 | 一の位が0か5 | 125 → 一の位が5 → 5の倍数 |
これを知っていると、素因数分解がぐっと速くなります。
すだれ算(連除法)
すだれ算とは
すだれ算は、日本の学校でよく教えられる素因数分解の方法です。計算の形が「すだれ」(ブラインドカーテン)に似ているからこの名前がつきました。
すだれ算の実例
30を素因数分解:
2) 30
3) 15
5
縦に読むと:30 = 2 × 3 × 5
視覚的でわかりやすく、ミスも少なくなります。
最大公約数と最小公倍数を同時に求める
12と18の場合:
2) 12 18
3) 6 9
2 3
- 最大公約数(GCD):左側の数をかける → 2 × 3 = 6
- 最小公倍数(LCM):全部かける → 2 × 3 × 2 × 3 = 36
一度に両方求められて便利!
練習問題
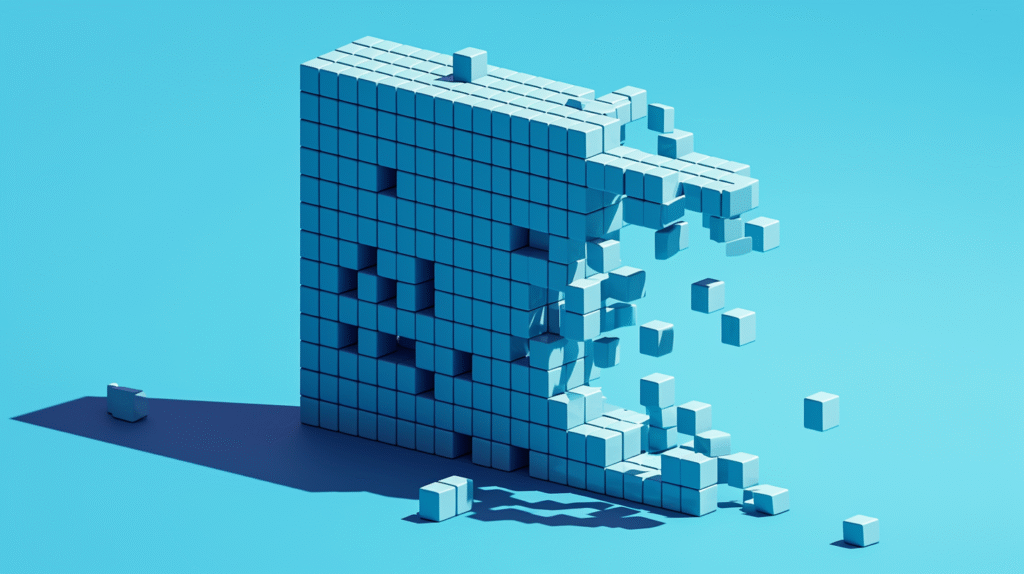
レベル1:基本問題
次の数を素因数分解してみましょう。
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 20 = ? | 20 = 2² × 5 |
| 36 = ? | 36 = 2² × 3² |
| 45 = ? | 45 = 3² × 5 |
レベル2:大きな数
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 120 = ? | 120 = 2³ × 3 × 5 |
| 180 = ? | 180 = 2² × 3² × 5 |
レベル3:応用問題
問題: 126を素因数分解して、その素因数をすべて足すといくつ?
解答:
- 126 = 2 × 3² × 7
- 素因数は2、3、7
- 2 + 3 + 7 = 12
最大公約数と最小公倍数
素因数分解を使った求め方
例:36と48の場合
まず素因数分解:
- 36 = 2² × 3²
- 48 = 2⁴ × 3
最大公約数(GCD): 共通する素因数の小さい方の指数を選ぶ → GCD = 2² × 3¹ = 12
最小公倍数(LCM): すべての素因数の大きい方の指数を選ぶ → LCM = 2⁴ × 3² = 144
互いに素
2つの数の最大公約数が1のとき、「互いに素」といいます。
例:7と10は互いに素(共通の約数が1しかない)
豆知識: 隣り合う2つの整数は必ず互いに素になります。
実生活での活用
インターネットの暗号化
ネットショッピングで使われる「RSA暗号」の基礎が素因数分解です。
大きな数(300桁以上!)を素因数分解するのはスーパーコンピュータでも何年もかかります。この「素因数分解の困難さ」が、私たちの情報を守っているのです。
音楽のリズム
異なるリズムが同時にそろうタイミングは最小公倍数で計算できます。
例:3拍子と4拍子が同時に始まったら、12拍目で再びそろう(LCM(3,4) = 12)
歯車の設計
機械の歯車では、歯の数を互いに素にすることで、すべての歯が均等に摩耗するように設計されています。
よくある間違いと対策
間違いやすいポイント
| 間違い | 正しい理解 | 対策 |
|---|---|---|
| 1は素数と思う | 1は素数ではない | 約数が2つという定義を覚える |
| 素数でない数で割る | 必ず素数で割る | 2、3、5、7…の順番を守る |
| 最後の商を書き忘れる | 商も素因数に含める | 最後が素数か確認 |
| 指数表記を忘れる | 同じ素数は指数でまとめる | 2×2×2 → 2³ |
検算の習慣
素因数分解が終わったら、必ず掛け算をして元の数に戻るか確認しましょう。これで計算ミスを防げます。
素数の覚え方と判定のコツ
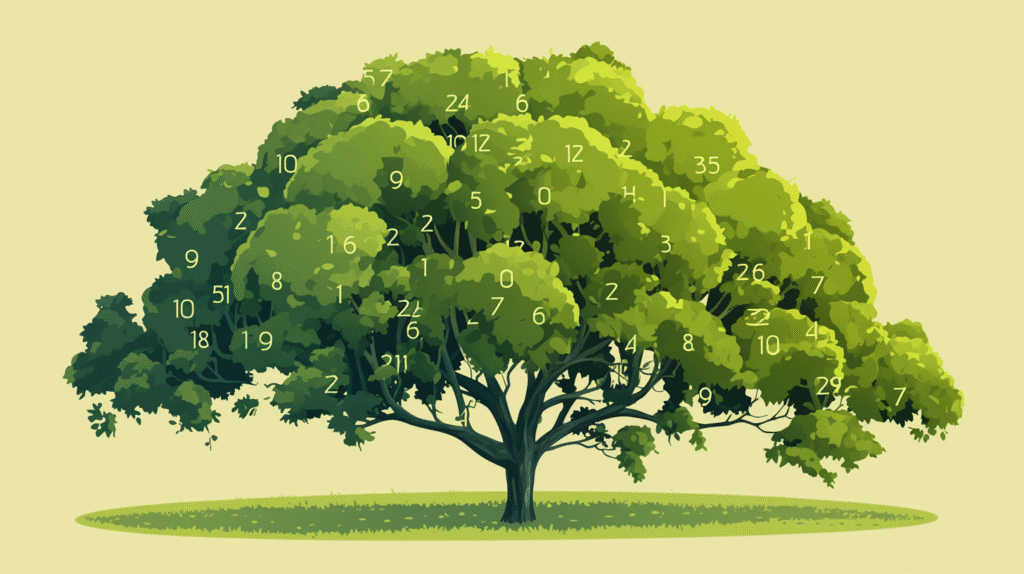
効率的な暗記法
絶対に覚える20までの素数:
- 一桁:2、3、5、7
- 二桁:11、13、17、19
覚えるコツ:
- 偶数は2だけが素数
- 5の倍数で素数は5だけ
- 11から19の間には4つの素数
素数判定の裏技
ある数が素数かどうか調べるには、その数の平方根までの素数で割り切れるかチェックすれば十分。
例:97は素数?
- √97 ≈ 9.8
- 2、3、5、7で割り切れるかチェック
- どれでも割り切れない → 97は素数!
まとめ:素因数分解マスターへの道
素因数分解は、数学の基礎でありながら、現代社会を支える重要な技術でもあります。
今日学んだ5つのポイント
- 素数は数の基本単位 – まずは20までの素数を完璧に
- 小さい素数から順番に – 2→3→5→7…の順で割る
- すだれ算は便利な方法 – 視覚的でミスが少ない
- GCD・LCMの計算に活用 – 素因数分解ができれば簡単
- 実生活でも大活躍 – 暗号化から音楽まで幅広く使用
最初は時間がかかるかもしれませんが、練習すれば必ず速くなります。素因数分解は高校入試でも必ず出題される重要な単元です。
素因数分解ができるようになると:
- 約数や倍数の問題がスラスラ解ける
- 高校で学ぶ平方根の計算に役立つ
- 数学的思考力が身につく
一つずつ確実に身につけていけば、きっと数学が楽しくなるはずです。がんばってください!