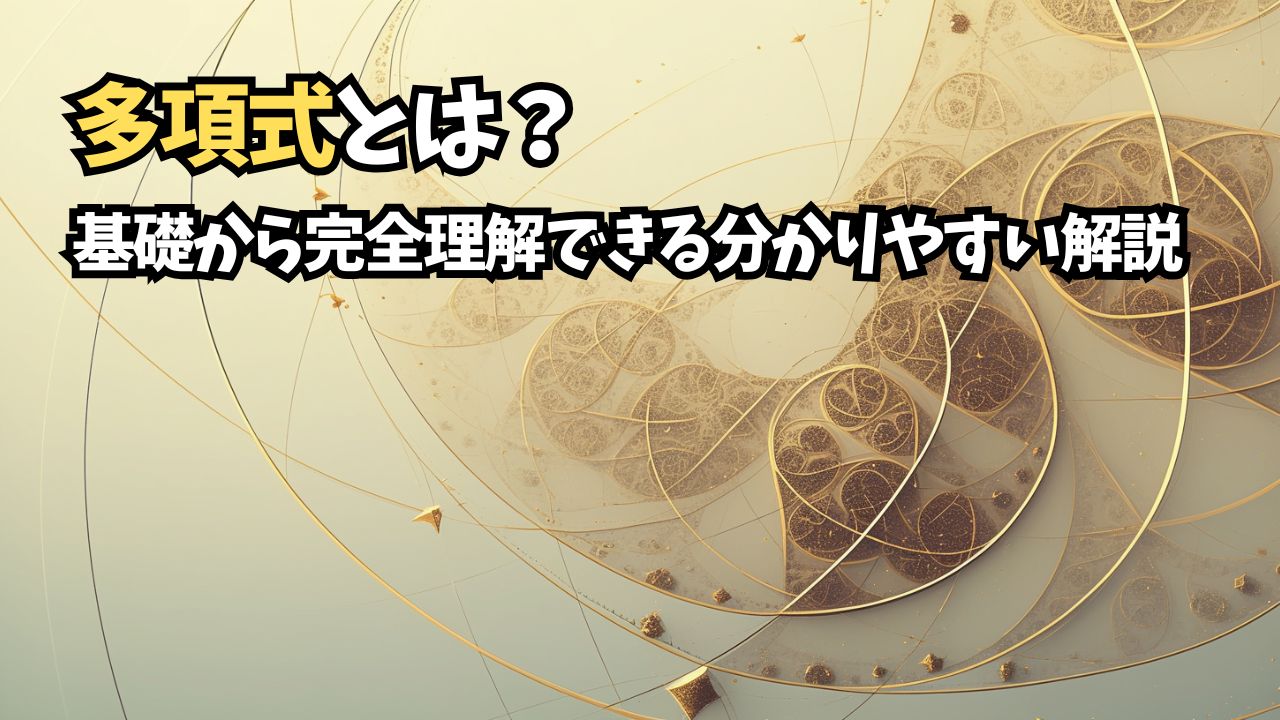「多項式」という言葉を聞いて、難しそう…と感じましたか?
でも実は、あなたはすでに多項式を使いこなしているんです。
2x + 3 とか、x² + 5x – 6 みたいな式、見たことありますよね? これらがまさに多項式なんです。
多項式は、中学・高校数学の土台となる超重要な概念。 方程式を解くときも、関数を学ぶときも、必ず多項式が登場します。
今回は、多項式について基礎の基礎から丁寧に解説していきます。 この記事を読み終わる頃には、「なんだ、多項式ってこういうことか!」とスッキリ理解できているはずですよ。
多項式って何?まずは基本から理解しよう
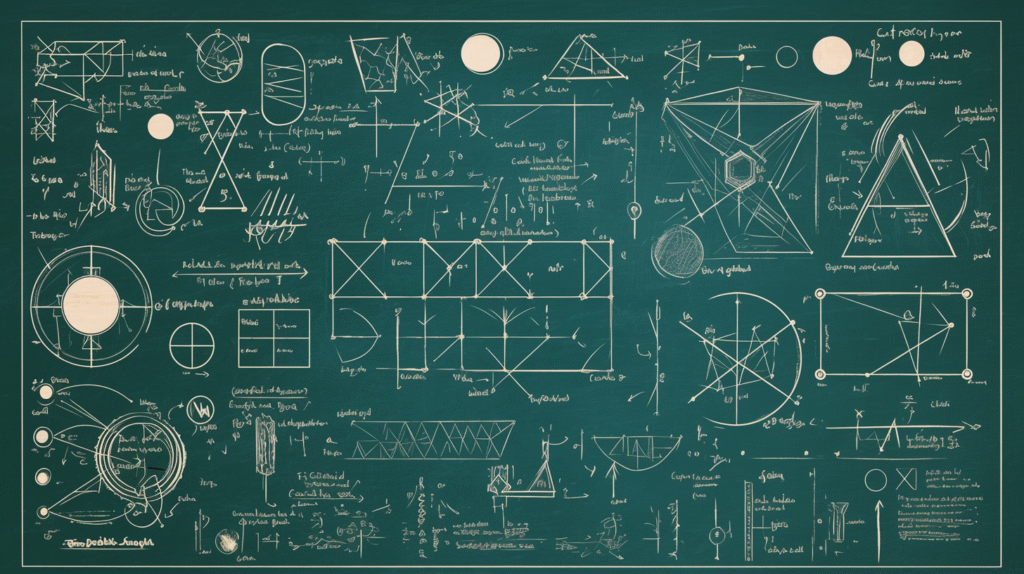
多項式の正体を明らかにする
多項式とは、簡単に言うと「いくつかの項を足したり引いたりしてできた式」のことです。
例えば:
- 3x + 5(2つの項を足している)
- x² – 2x + 1(3つの項を足したり引いたりしている)
- 4x³ + 2x² – 7x + 3(4つの項の組み合わせ)
これらはすべて多項式です。
「多」は「たくさん」、「項」は「式の部品」、「式」は「数式」という意味。
つまり、複数の部品(項)でできた式ということですね。
単項式と多項式の違い
まず、単項式(たんこうしき)から説明しましょう。
単項式とは:
- 3x(数字と文字の掛け算だけ)
- -5x²(1つの項だけ)
- 7(数字だけでもOK)
これらは「1つの項だけ」でできているので単項式といいます。
一方、多項式は:
- 3x + 2(2つの項)
- x² – 5x(2つの項)
- 2x³ + x² – 3x + 1(4つの項)
複数の単項式を足したり引いたりしたものが多項式です。
覚え方のコツ: 単項式 = シングル(1つ) 多項式 = マルチ(複数)
項、係数、次数という大切な言葉
多項式を理解するには、3つの用語を知っておく必要があります。
項(こう): 式を構成する1つ1つの部品のこと。 例:3x² + 5x – 2 の場合
- 3x²が第1項
- 5xが第2項
- -2が第3項
係数(けいすう): 文字についている数字のこと。
例:5x の係数は5、-3x² の係数は-3
次数(じすう): 文字についている指数(右上の小さい数字)のこと。
例:x³ の次数は3、x² の次数は2、x の次数は1
これらの用語は、今後ずっと使うので覚えておきましょう!
多項式の種類を整理しよう
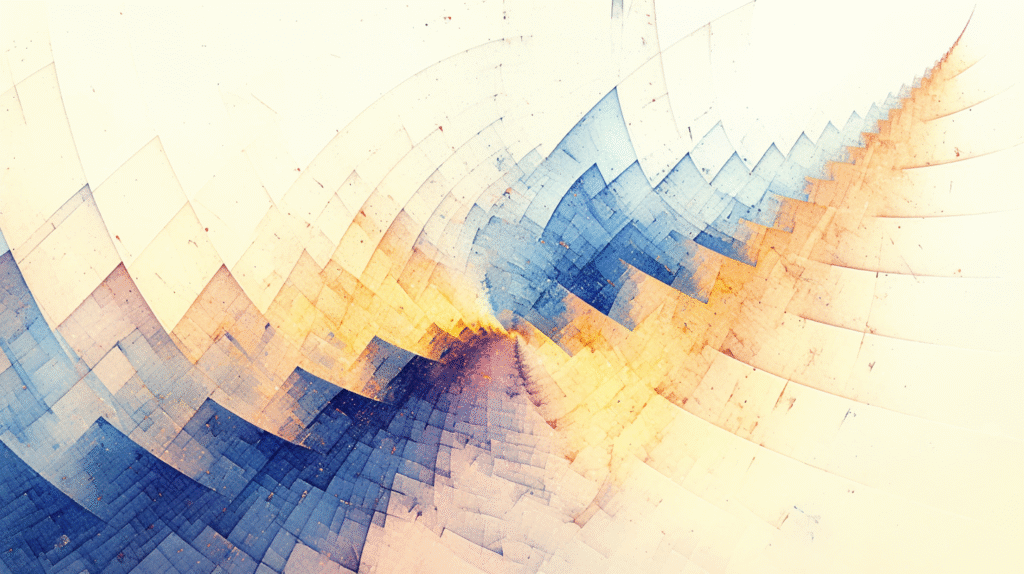
次数による分類
多項式は、最も大きい次数によって名前が変わります。
1次式: 最高次数が1の多項式 例:2x + 3、-5x + 7、3x – 1
2次式: 最高次数が2の多項式 例:x² + 3x + 2、2x² – 5、-x² + 4x – 3
3次式: 最高次数が3の多項式 例:x³ + 2x² – x + 1、2x³ – 5x、x³ + 1
n次式: 最高次数がnの多項式 例:5次式なら x⁵ + 3x³ – 2x + 1
次数が高くなるほど、グラフの形が複雑になっていきます。
項の数による分類
項がいくつあるかでも、特別な名前があります。
単項式(1項): 3x²、-5x、7
二項式(2項): x + 2、3x² – 5、2x – 1
三項式(3項): x² + 3x + 2、2x² – 5x + 1
4項以上は特別な名前はなく、単に「多項式」と呼びます。
定数項って何?
文字を含まない項を「定数項(ていすうこう)」といいます。
例:3x² + 5x + 7 この式の定数項は 7 です。
例:2x³ – 4x² + x – 9 この式の定数項は -9 です。
定数項がない場合もあります: x² + 3x(定数項は0と考える)
多項式の計算をマスターしよう
同類項をまとめる(整理)
同類項(どうるいこう)とは、文字の部分が全く同じ項のことです。
- 例:3x と 5x は同類項(両方とも x だけ)
- 例:2x² と -7x² は同類項(両方とも x²)
- 例:3x と 3x² は同類項ではない(次数が違う)
同類項はまとめることができます:
3x + 5x = 8x 2x² – 7x² = -5x²
実際の計算例:
(2x² + 3x + 1) + (x² – 5x + 4) = 2x² + x² + 3x – 5x + 1 + 4 = 3x² – 2x + 5
項目ごとに整理すると間違えにくいですよ。
多項式の足し算・引き算
足し算の手順:
- カッコを外す
- 同類項を集める
- 計算してまとめる
例:(3x + 2) + (2x – 5) = 3x + 2 + 2x – 5 = 3x + 2x + 2 – 5 = 5x – 3
引き算の手順:
- 引く方の符号を全部逆にする
- あとは足し算と同じ
例:(3x + 2) – (2x – 5) = 3x + 2 – 2x + 5(マイナスを配る) = 3x – 2x + 2 + 5 = x + 7
ポイントは、引き算のときにマイナスの符号を忘れないこと!
多項式の掛け算(展開)
多項式の掛け算は「分配法則」を使います。
単項式 × 多項式の場合: 2x(3x + 5) = 2x × 3x + 2x × 5 = 6x² + 10x
多項式 × 多項式の場合: (x + 2)(x + 3) = x × x + x × 3 + 2 × x + 2 × 3 = x² + 3x + 2x + 6 = x² + 5x + 6
覚えておくと便利な公式:
- (x + a)(x + b) = x² + (a+b)x + ab
- (x + a)² = x² + 2ax + a²
- (x – a)² = x² – 2ax + a²
- (x + a)(x – a) = x² – a²
これらの公式を使えば、計算がグッと速くなります!
多項式の見分け方と注意点
これは多項式?多項式じゃない?
多項式になるもの:
多項式にならないもの:
多項式は「整式(せいしき)」とも呼ばれ、きれいに整った式のことなんです。
よくある間違いパターン
間違い1:次数の数え方
x²y の次数は? 間違い:2 正解:3(xが1次、yが1次で、合計3次)
間違い2:定数項の扱い
5 の次数は? 間違い:1 正解:0(定数の次数は0)
間違い3:係数の符号
-3x の係数は? 間違い:3 正解:-3(マイナスも含める)
実生活で使われる多項式
身近な例1:お買い物
りんごをx個、みかんをy個買うとき: 合計金額 = 150x + 80y
これも立派な多項式です!
身近な例2:図形の面積
正方形の一辺を x cm 伸ばしたときの面積: 元の一辺が 5cm なら 面積 = (5 + x)² = 25 + 10x + x²
身近な例3:物理の運動
ボールを投げ上げたときの高さ: h = -5t² + 20t + 2 (tは時間、hは高さ)
このように、多項式は現実世界の様々な現象を表現するのに使われています。
多項式を使った問題を解いてみよう
基本問題
問題1:次の式を整理せよ 3x + 2x – 5 + x + 3
解答: = 3x + 2x + x – 5 + 3 = 6x – 2
問題2:次の計算をせよ (2x² + 3x – 1) – (x² – 2x + 4)
解答: = 2x² + 3x – 1 – x² + 2x – 4 = x² + 5x – 5
応用問題
問題3:次の式を展開せよ (2x + 3)(x – 4)
解答: = 2x × x + 2x × (-4) + 3 × x + 3 × (-4) = 2x² – 8x + 3x – 12 = 2x² – 5x – 12
問題4:x = 2 のとき、3x² – 2x + 1 の値を求めよ
解答: = 3 × 2² – 2 × 2 + 1 = 3 × 4 – 4 + 1 = 12 – 4 + 1 = 9
多項式の学習を深めるために

次に学ぶべきこと
多項式を理解したら、次はこれらを学びましょう:
- 因数分解:多項式を積の形に変形する
- 方程式:多項式 = 0 を解く
- 関数:多項式をグラフで表現する
- 微分・積分:多項式の変化を調べる(高校数学)
多項式は、これらすべての基礎になっています。
練習問題のコツ
多項式の問題を解くときのコツ:
- まず項を整理する(同類項をまとめる)
- 次数の高い順に並べる(降べきの順)
- 計算ミスを防ぐため、途中式を丁寧に書く
- 最後に検算する(代入して確認)
暗記より理解を
公式を丸暗記するより、なぜそうなるのか理解することが大切です。
例えば (x + 2)² = x² + 4x + 4 を覚えるより、 (x + 2)(x + 2) を展開できることの方が重要。
理解していれば、忘れても自分で導き出せますからね。
まとめ:多項式は数学の基本中の基本
多項式について、基礎から丁寧に解説してきました。
押さえるべきポイント:
- 多項式 = 複数の項を足したり引いたりした式
- 項、係数、次数という用語を理解する
- 同類項はまとめることができる
- 計算は順序立てて丁寧に
多項式は、今後学ぶすべての数学の土台です。 ここでしっかり理解しておけば、方程式も関数も怖くありません。
最初は難しく感じるかもしれませんが、問題を解いていくうちに必ず慣れてきます。 一歩ずつ、着実に理解を深めていきましょう。
数学の世界への第一歩、多項式から始めてみませんか?