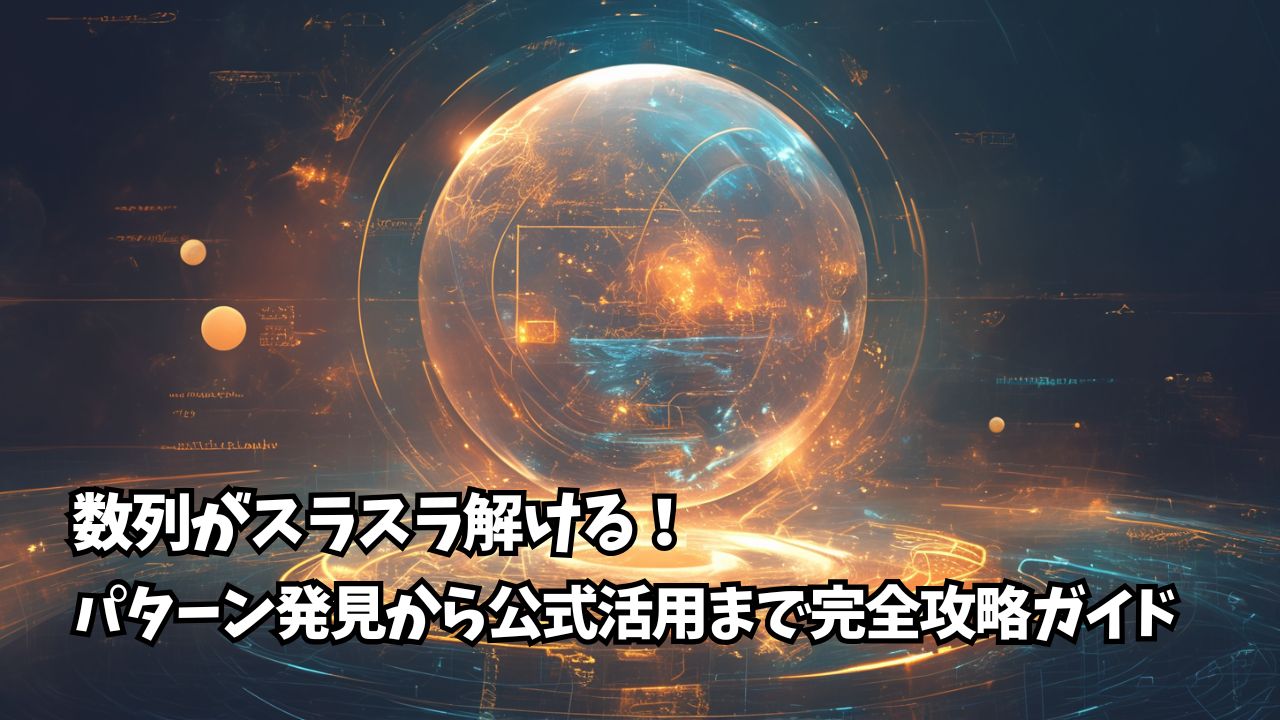「1, 3, 5, 7, 9… 次は何?」 「100段の階段、全部で何段登る?」 「複利で増える貯金、10年後はいくら?」
これ、全部数列の問題なんです!
数列って聞くと「難しそう…」と思うかもしれません。 でも実は、私たちの生活の中にたくさん隠れているんですよ。
この記事を読めば、数列の規則性を見抜く目が養われ、複雑に見える問題もサクサク解けるようになります! さらに、実生活での活用例もたっぷりご紹介します。
そもそも数列って何?5秒で分かる基本
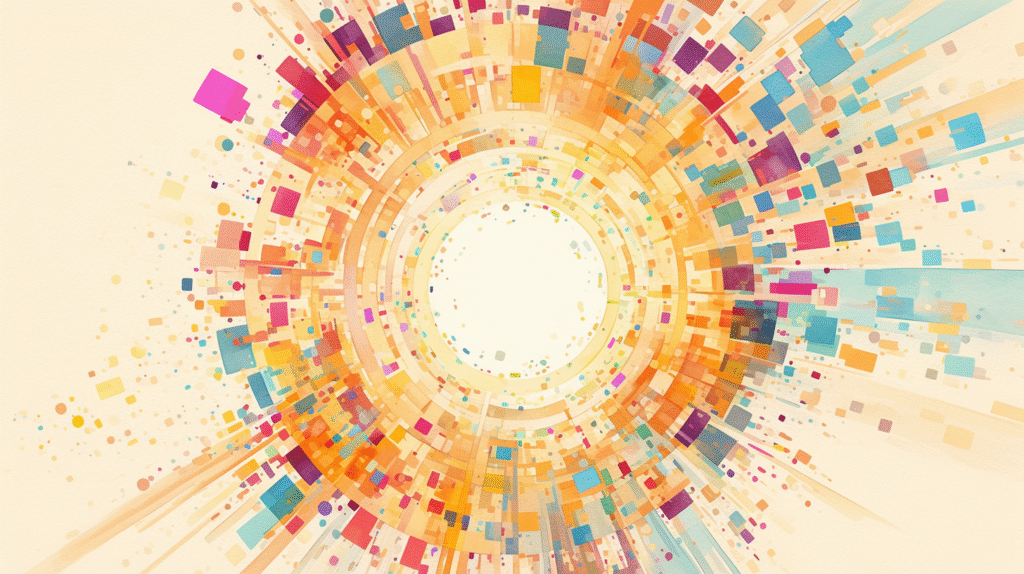
数列 = 数字の並び
めちゃくちゃシンプルに言うと、**数列は「規則的に並んだ数字の列」**です。
身近な例:
偶数の列:2, 4, 6, 8, 10, 12...
3の倍数:3, 6, 9, 12, 15, 18...
正方形の数:1, 4, 9, 16, 25, 36...
この「規則」を見つけるのが、数列の醍醐味なんです!
数列の基本用語(これだけ覚えよう)
数列:1, 3, 5, 7, 9...
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
第1項 第2項 第3項...(項=各数字のこと)
初項(a₁):最初の数 = 1
末項:最後の数
項数(n):全部で何個あるか
記号で書くと:
- a₁ = 第1項
- a₂ = 第2項
- aₙ = 第n項(n番目の数)
これで準備完了!
3大基本数列:これさえ分かれば8割解ける
1. 等差数列(とうさすうれつ)- 一定の差で増える
特徴:隣同士の差が同じ!
例:3, 7, 11, 15, 19...
+4 +4 +4 +4 → 公差(d)= 4
公式(超重要!):
第n項を求める:
aₙ = a₁ + (n-1)d
a₁:初項
d:公差(こうさ)
n:項数
例題:初項3、公差4の等差数列の第10項は?
a₁₀ = 3 + (10-1)×4
= 3 + 9×4
= 3 + 36
= 39
和の公式:
Sₙ = n(a₁ + aₙ)/2
または
Sₙ = n{2a₁ + (n-1)d}/2
実例:1から100までの和
S₁₀₀ = 100×(1+100)/2
= 100×101/2
= 5050
ガウスが小学生の時に瞬時に解いた有名な問題です!
2. 等比数列(とうひすうれつ)- 一定の比で増える
特徴:隣同士の比が同じ!
例:2, 6, 18, 54, 162...
×3 ×3 ×3 ×3 → 公比(r)= 3
公式:
第n項を求める:
aₙ = a₁ × r^(n-1)
a₁:初項
r:公比(こうひ)
n:項数
例題:初項2、公比3の等比数列の第5項は?
a₅ = 2 × 3^(5-1)
= 2 × 3⁴
= 2 × 81
= 162
和の公式(r ≠ 1):
Sₙ = a₁(r^n - 1)/(r - 1)
または
Sₙ = a₁(1 - r^n)/(1 - r)
3. 階差数列(かいさすうれつ)- 差に規則がある
特徴:差自体が数列を作る!
元の数列:1, 3, 6, 10, 15...
階差: 2, 3, 4, 5... ← これも数列!
解き方のコツ:
- まず階差を出す
- 階差の規則を見つける
- 元の数列を復元
例:フィボナッチ数列
数列:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
規則:前の2つを足す
aₙ = aₙ₋₁ + aₙ₋₂
パターン発見のコツ:規則性を見抜く7つの視点
1. まず差を見る(等差数列チェック)
5, 8, 11, 14, 17...
+3 +3 +3 +3 → 等差数列!公差3
2. 次に比を見る(等比数列チェック)
3, 12, 48, 192...
×4 ×4 ×4 → 等比数列!公比4
3. 階差を取る(2回差を取ることも)
1, 4, 10, 19, 31...
+3 +6 +9 +12 ← 第1階差(公差3の等差数列)
+3 +3 +3 ← 第2階差(一定)
4. 奇数項・偶数項で分ける
1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20...
奇数項:1, 2, 3, 4...(+1ずつ)
偶数項:5, 10, 15, 20...(+5ずつ)
5. 平方数・立方数をチェック
1, 4, 9, 16, 25...
= 1², 2², 3², 4², 5²... → n²
6. 分数にして考える
2, 3, 5, 8, 13...
= 2/1, 3/1, 5/2, 8/3, 13/5...
→ フィボナッチ数列の隣接項の比!
7. 素数や約数を疑う
2, 3, 5, 7, 11, 13...
→ 素数列
実生活での数列活用例:こんなところに数列が!
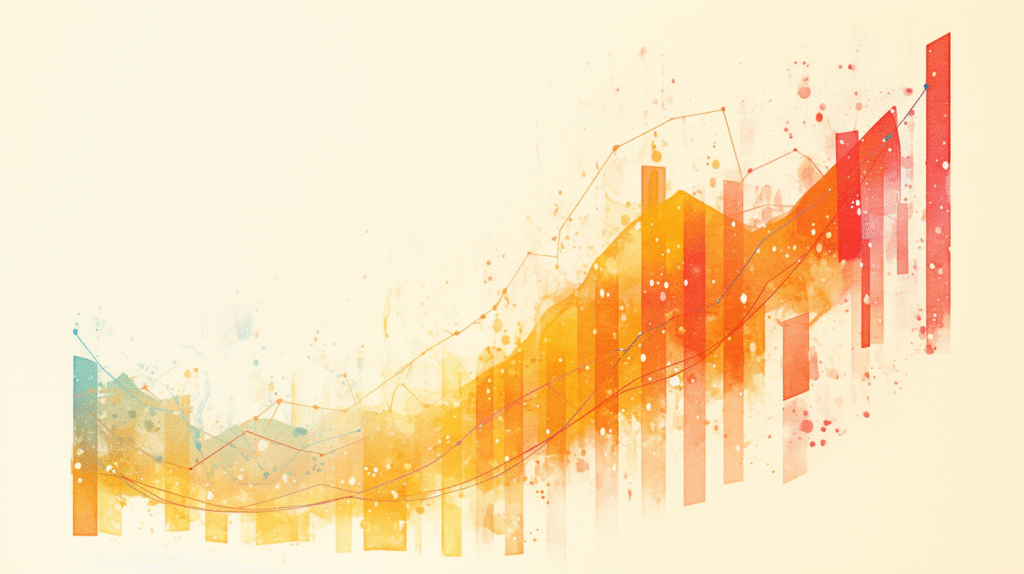
1. お金の計算
複利計算(等比数列):
年利5%で100万円を預けると...
1年後:100万 × 1.05 = 105万
2年後:105万 × 1.05 = 110.25万
3年後:110.25万 × 1.05 = 115.76万
公式:n年後 = 100万 × (1.05)^n
住宅ローン返済(等差数列的):
元金均等返済の場合:
毎月の元金返済額は一定
利息は残高に応じて減少
2. 階段やピラミッド
階段の段数問題:
1段目:1個
2段目:2個
3段目:3個
...
n段目:n個
合計:1+2+3+...+n = n(n+1)/2
ピラミッド型の積み上げ:
みかんをピラミッド状に積む
底辺5個×5個なら:
5² + 4² + 3² + 2² + 1² = 55個必要
3. 自然界の数列
ひまわりの種の配列:
フィボナッチ数列:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...
らせん状に21本、34本、55本...と並ぶ
ウサギの繁殖モデル:
1ヶ月目:1組
2ヶ月目:1組
3ヶ月目:2組
4ヶ月目:3組
5ヶ月目:5組
→ フィボナッチ数列!
4. コンピューター・プログラミング
データ量の増加:
ビット数:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...
= 2⁰, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷...
アルゴリズムの計算量:
バブルソート:n²回の比較
二分探索:log₂n回の比較
頻出問題パターンと解法テクニック
パターン1:穴埋め問題
問題:「2, 5, 10, 17, ?, 37」の?を求めよ
解法:
階差を取る:
5-2=3, 10-5=5, 17-10=7
→ 階差が3, 5, 7...(公差2の等差数列)
次の階差は9
よって ? = 17 + 9 = 26
パターン2:一般項を求める
問題:「3, 7, 11, 15…」の一般項を求めよ
解法:
公差d = 7-3 = 4
初項a₁ = 3
一般項:aₙ = 3 + (n-1)×4
= 3 + 4n - 4
= 4n - 1
パターン3:和を求める
**問題:**1+3+5+7+…+99の和を求めよ
解法:
これは奇数の和
初項a₁=1, 末項aₙ=99
項数n:99 = 2n-1 より n=50
和 = 50×(1+99)/2 = 50×100/2 = 2500
別解:1から99までの奇数の和 = 50² = 2500
パターン4:条件から数列を特定
**問題:**第5項が16、第8項が25の等差数列の初項は?
解法:
a₅ = a₁ + 4d = 16 ... ①
a₈ = a₁ + 7d = 25 ... ②
②-①:3d = 9
よって d = 3
①に代入:a₁ + 12 = 16
よって a₁ = 4
数列の応用:シグマ(Σ)記号をマスター
Σ(シグマ)= 「合計」の記号
n
Σ k = 1 + 2 + 3 + ... + n
k=1
読み方:「k=1からnまでのkの和」
重要な公式集
1. 自然数の和:
n
Σ k = n(n+1)/2
k=1
2. 平方数の和:
n
Σ k² = n(n+1)(2n+1)/6
k=1
3. 立方数の和:
n
Σ k³ = {n(n+1)/2}²
k=1
覚え方のコツ:
- 1乗の和:分母に2
- 2乗の和:分母に6(=2×3)
- 3乗の和:1乗の和の2乗
実践例:Σを使った計算
**例題:**1² + 2² + 3² + … + 10²を求めよ
10
Σ k² = 10×11×21/6
k=1
= 2310/6
= 385
間違えやすいポイントと対策
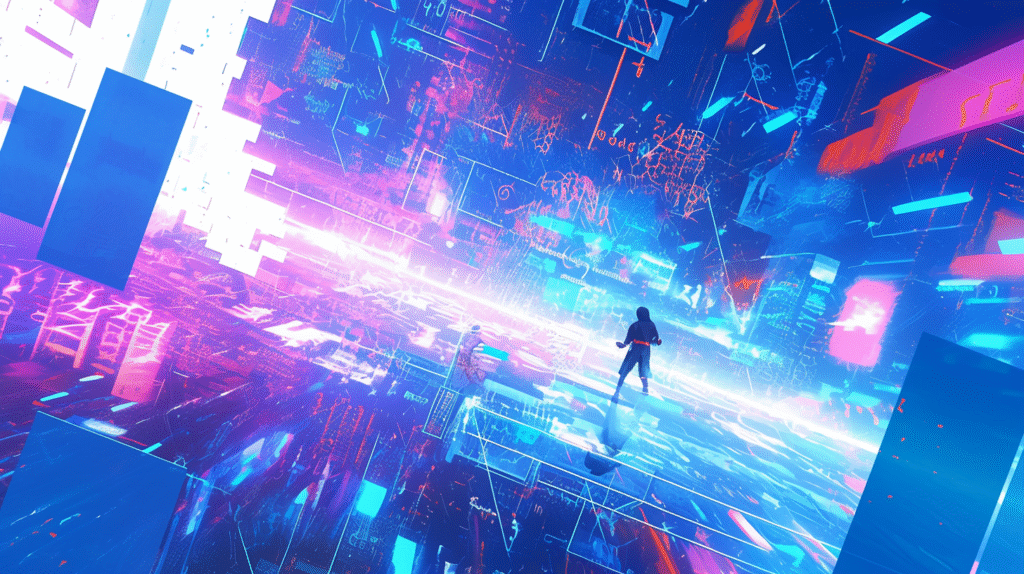
落とし穴1:項数の数え間違い
間違い例: 「1から100までの偶数は100個」→ ✗
正解:
2, 4, 6, ..., 100
最後の項 = 2n = 100
よって n = 50個
落とし穴2:初項を0と勘違い
間違い例: 「0, 3, 6, 9…の第5項は12」→ ✗
正解:
第1項=0, 第2項=3, 第3項=6, 第4項=9, 第5項=12 → ✓
(0も第1項として数える)
落とし穴3:公比が負の数
2, -6, 18, -54...
公比r = -3(符号も含めて考える)
落とし穴4:等比数列の和で r=1 の場合
r=1の時は公式が使えない!
Sₙ = na₁(単純にn個足すだけ)
受験でよく出る数列の特殊パターン
1. 群数列
(1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), ...
第1群 第2群 第3群 第4群
第n群:n個の数を含む
第n群の最初の数:1+2+...+(n-1)+1
2. 分数数列
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ...
一般項:n/(n+1)
3. 漸化式で定義される数列
aₙ₊₁ = 2aₙ + 1, a₁ = 1
a₁ = 1
a₂ = 2×1 + 1 = 3
a₃ = 2×3 + 1 = 7
a₄ = 2×7 + 1 = 15
4. 調和数列
1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ...
逆数が等差数列
プログラミングで数列を生成(Python例)
等差数列の生成
# 初項3、公差4、項数10の等差数列
def arithmetic_sequence(a1, d, n):
return [a1 + i*d for i in range(n)]
result = arithmetic_sequence(3, 4, 10)
print(result) # [3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39]
等比数列の生成
# 初項2、公比3、項数8の等比数列
def geometric_sequence(a1, r, n):
return [a1 * r**i for i in range(n)]
result = geometric_sequence(2, 3, 8)
print(result) # [2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374]
フィボナッチ数列
def fibonacci(n):
if n <= 0:
return []
elif n == 1:
return [1]
elif n == 2:
return [1, 1]
fib = [1, 1]
for i in range(2, n):
fib.append(fib[i-1] + fib[i-2])
return fib
print(fibonacci(10)) # [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
数列を使った面白い問題
問題1:ハノイの塔
n枚の円盤を移動する最小手数:
1枚:1回
2枚:3回
3枚:7回
4枚:15回
規則:2ⁿ - 1 回
問題2:コラッツ予想
任意の自然数から始めて
・偶数なら2で割る
・奇数なら3倍して1を足す
例:7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13
→ 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1
必ず1に到達する(未証明)
問題3:誕生日のパラドックス
n人いるとき、誕生日が重なる確率:
23人:約50%
50人:約97%
70人:約99.9%
これも数列の応用!
数列マスターへの練習問題
基礎レベル
- 等差数列: 5, 12, 19, 26, □, 40
- 等比数列: 3, 6, 12, □, 48
- 階差数列: 1, 3, 6, 10, □, 21
中級レベル
- 一般項: 2, 5, 10, 17, 26… の一般項は?
- 和の計算: 2+4+6+…+100 = ?
- 項数: 7, 11, 15, …, 83 は全部で何項?
上級レベル
- 漸化式: aₙ₊₁ = 3aₙ – 2, a₁ = 2 のとき、a₅は?
- 群数列: 第10群の最初の数は?
- 応用: 1×2 + 2×3 + 3×4 + … + 10×11 = ?
解答:
- 33(公差7)
- 24(公比2)
- 15(階差が1,2,3,4,5…)
- aₙ = n² + 1
- 2550
- 20項
- 142
- 46
- 440
まとめ:数列は「パターン発見ゲーム」だ!
数列をマスターするポイントは3つ!
1. 基本の3パターンを確実に:
- 等差数列(差が一定)
- 等比数列(比が一定)
- 階差数列(差が数列)
2. パターン発見の視点を持つ:
- まず差を見る
- 次に比を見る
- ダメなら階差を取る
3. 公式は理解して使う:
- 丸暗記より仕組みを理解
- 実際に手を動かして計算
数列の面白さ:
- 規則性を見つけた時の快感
- 複雑に見えて実はシンプル
- 実生活にも応用できる
数列は、数学の中でも特に「発見する楽しさ」が味わえる分野です。 パズルを解くような感覚で、楽しみながら学んでくださいね!
次は、数列の知識を使って微分積分や確率統計にも挑戦してみましょう!