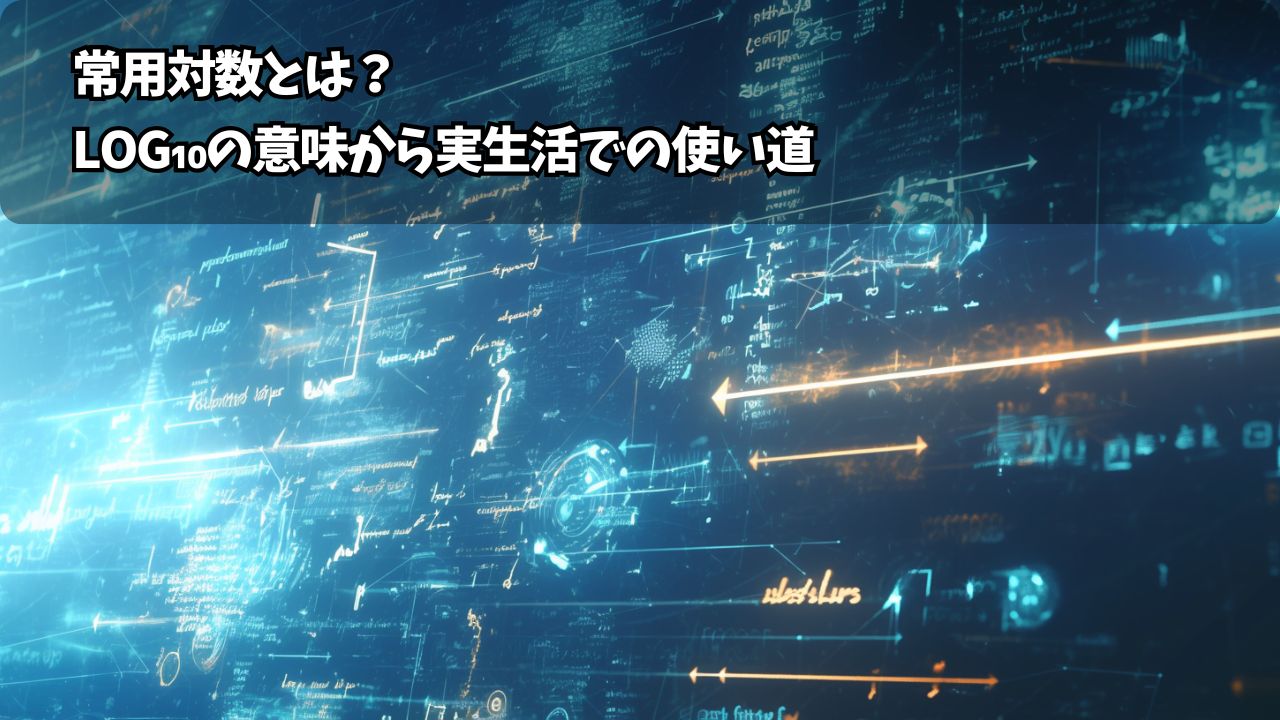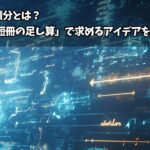「1億は10の何乗?」
「地震のマグニチュード6と7って、実際どれくらい違うの?」
「pH(ペーハー)って、なんで対数を使うの?」
こんな疑問に答えてくれるのが、常用対数(じょうようたいすう)です。
高校で習う「log₁₀」という記号。 見た瞬間に拒否反応を起こす人も多いですよね。
でも実は、常用対数は「大きな数を扱いやすくする」ための便利な道具なんです。 地震の強さ、音の大きさ、酸性・アルカリ性の強さ… 私たちの身の回りで、知らないうちに大活躍しています。
この記事では、常用対数が何なのか、なぜ必要なのか、どう使うのかを、数学が苦手な人でも分かるように解説していきます。
一緒に、数の「桁数」を操る技術を身につけましょう!
常用対数の基本:10の何乗かを表す数

そもそも常用対数って何?
常用対数を一言で説明すると、こうなります。
常用対数とは: 「10を何乗したら、その数になるか」を表す数
記号で書くと:
- log₁₀ 100 = 2(10を2乗すると100)
- log₁₀ 1000 = 3(10を3乗すると1000)
- log₁₀ 10000 = 4(10を4乗すると10000)
つまり: 「10の〇乗」の「〇」の部分を求めるのが常用対数です。
なぜ「常用」というの?
「常用」には「日常的によく使う」という意味があります。
常用対数が「常用」な理由:
- 私たちは10進法を使っている
- 桁数と直接関係がある
- 計算が比較的簡単
- 実用的な場面で頻繁に登場
他の対数との違い:
- 常用対数:底が10(log₁₀)
- 自然対数:底がe(約2.718…)(ln または logₑ)
- 二進対数:底が2(log₂)
底が10だから「常用」なんです。
基本的な値を覚えよう
よく使う常用対数の値です。
覚えておくべき値:
- log₁₀ 1 = 0(10⁰ = 1)
- log₁₀ 10 = 1(10¹ = 10)
- log₁₀ 100 = 2(10² = 100)
- log₁₀ 1000 = 3(10³ = 1000)
- log₁₀ 10000 = 4(10⁴ = 10000)
規則性:
- 0が1個増えるごとに、log値が1増える
- つまり、桁数 – 1 ≈ log値(整数部分)
小数の場合:
- log₁₀ 0.1 = -1(10⁻¹ = 0.1)
- log₁₀ 0.01 = -2(10⁻² = 0.01)
この章のポイント:常用対数は「10の何乗か」を表す。底が10だから「常用」。桁数と密接な関係がある。
常用対数の性質と計算方法
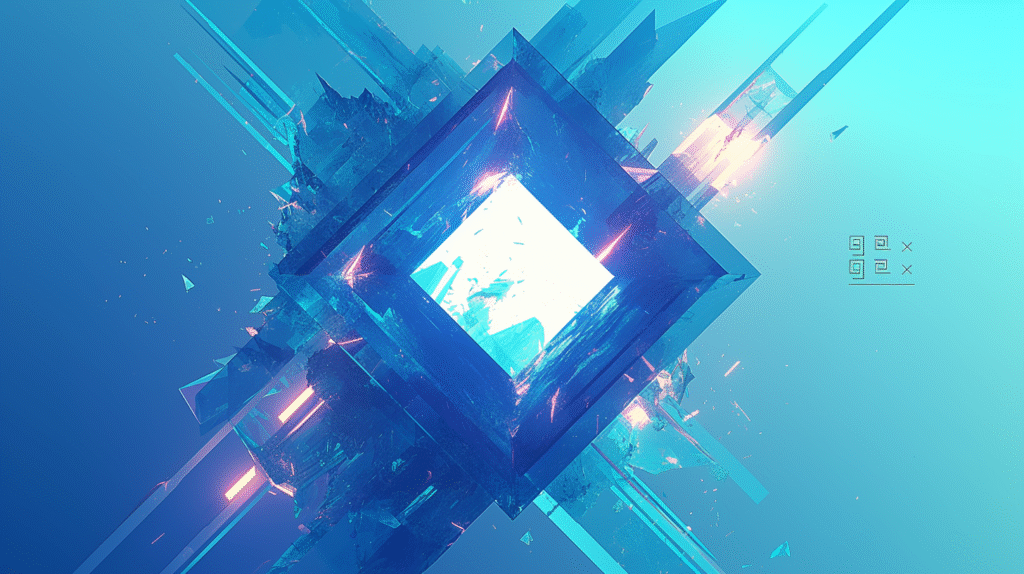
3つの重要な性質
常用対数には、計算を楽にする性質があります。
性質1:積の対数は和になる log₁₀(A × B) = log₁₀ A + log₁₀ B
例:
- log₁₀(100 × 1000) = log₁₀ 100 + log₁₀ 1000
- = 2 + 3 = 5
- 確認:100 × 1000 = 100000 = 10⁵
性質2:商の対数は差になる log₁₀(A ÷ B) = log₁₀ A – log₁₀ B
例:
- log₁₀(1000 ÷ 10) = log₁₀ 1000 – log₁₀ 10
- = 3 – 1 = 2
- 確認:1000 ÷ 10 = 100 = 10²
性質3:累乗の対数は積になる log₁₀(A^n) = n × log₁₀ A
例:
- log₁₀(100³) = 3 × log₁₀ 100
- = 3 × 2 = 6
- 確認:100³ = 1000000 = 10⁶
よく使う常用対数の近似値
テストや実用でよく使う値です。
暗記推奨の値:
- log₁₀ 2 ≈ 0.301(0.3010)
- log₁₀ 3 ≈ 0.477(0.4771)
- log₁₀ 5 ≈ 0.699(0.6990)
- log₁₀ 7 ≈ 0.845(0.8451)
覚え方のコツ:
- log₁₀ 2 ≈ 0.3「2は3割」
- log₁₀ 3 ≈ 0.48「3は48(しは)」
- log₁₀ 5 = log₁₀(10/2) = 1 – 0.3 = 0.7
これらから導ける値:
- log₁₀ 4 = log₁₀ 2² = 2 × 0.301 = 0.602
- log₁₀ 6 = log₁₀ 2 + log₁₀ 3 = 0.301 + 0.477 = 0.778
- log₁₀ 8 = log₁₀ 2³ = 3 × 0.301 = 0.903
桁数を求める方法
常用対数の最も実用的な使い方です。
桁数の求め方: 「N桁の数」⇔「log₁₀の値が N-1 以上 N 未満」
例:2³⁰の桁数は?
- log₁₀ 2³⁰ = 30 × log₁₀ 2
- = 30 × 0.301 = 9.03
- 9 < 9.03 < 10
- よって10桁
実用例:
- 複利計算の結果
- 細菌の増殖数
- コンピュータの計算量
この章のポイント:積は和に、商は差に、累乗は積に変換できる。
log₁₀ 2 ≈ 0.3を覚えれば多くの値が計算可能。桁数は整数部分+1。
実生活での常用対数:身近な活用例
pH(水素イオン濃度)
理科で習うpHも常用対数です。
pHの定義: pH = -log₁₀[H⁺] ([H⁺]は水素イオン濃度)
具体例:
- 純水:[H⁺] = 10⁻⁷ → pH = 7(中性)
- レモン汁:[H⁺] = 10⁻² → pH = 2(酸性)
- 石鹸水:[H⁺] = 10⁻¹¹ → pH = 11(アルカリ性)
なぜ対数を使う?
- 濃度の幅が大きすぎる(10⁻¹⁴〜10⁰)
- 対数で1〜14の扱いやすい数に変換
- pH1の違い = 濃度10倍の違い
地震のマグニチュード
地震の強さも対数スケールです。
マグニチュードの性質:
- M(マグニチュード)が1増える → エネルギー約32倍
- Mが2増える → エネルギー約1000倍
計算式(簡略版): log₁₀ E = 1.5M + 4.8 (Eはエネルギー)
実例:
- M6とM7の違い:エネルギー32倍
- M6とM8の違い:エネルギー1000倍
- だから、M8は桁違いに破壊的
デシベル(音の大きさ)
音の大きさも対数で表します。
デシベル(dB)の定義: dB = 10 × log₁₀(音の強さ/基準値)
身近な音のレベル:
- 0 dB:聞こえる限界
- 30 dB:ささやき声
- 60 dB:普通の会話
- 90 dB:地下鉄の車内
- 120 dB:飛行機のエンジン音
10 dB増える = 音の強さ10倍 20 dB増える = 音の強さ100倍
星の等級
夜空の星の明るさも対数です。
等級の性質:
- 1等級の差 = 明るさ約2.5倍の差
- 5等級の差 = 明るさ100倍の差
計算式: 等級差 = -2.5 × log₁₀(明るさの比)
実例:
- 1等星と6等星:明るさ100倍の差
- 満月:約-13等級
- 太陽:約-27等級
この章のポイント:pH、マグニチュード、デシベル、等級…すべて常用対数。
巨大な範囲を扱いやすい数値に変換している。
常用対数表の使い方と電卓での計算
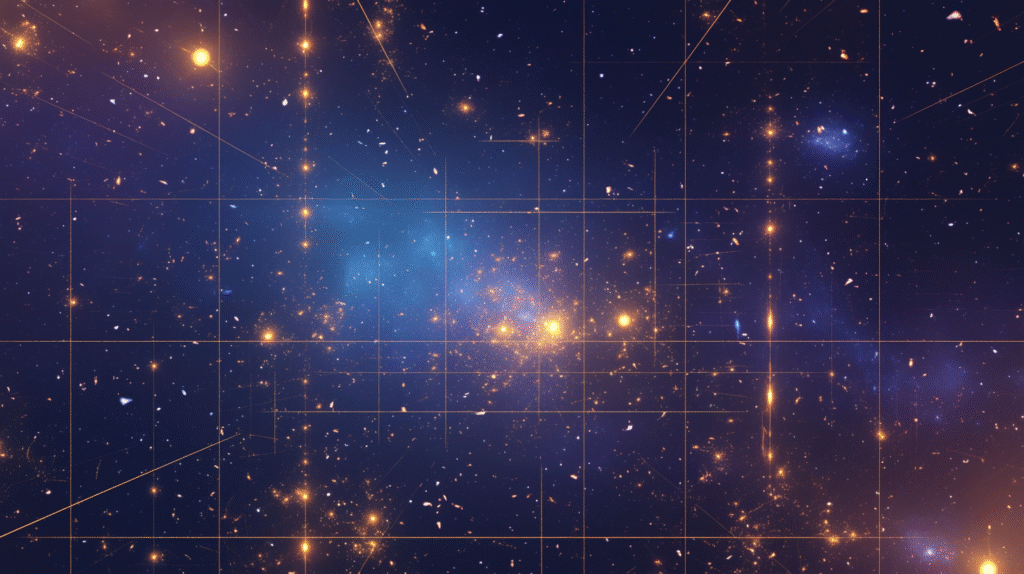
常用対数表の読み方
電卓がない時代の必需品でした。
対数表の構造:
- 縦軸:数値の上2桁
- 横軸:3桁目
- 交点:log値の小数部分
使用例:log₁₀ 2.34を求める
- 縦軸で「23」を探す
- 横軸で「4」を探す
- 交点の値「3692」を読む
- log₁₀ 2.34 = 0.3692
現代での意味:
- 仕組みを理解する教材
- 電卓がない環境での備え
- 概算の訓練
電卓での計算方法
現代の便利な方法です。
一般的な電卓:
- 数値を入力(例:100)
- 「log」ボタンを押す
- 答えが表示(2)
関数電卓の場合:
- 「log」は常用対数(底10)
- 「ln」は自然対数(底e)
- 間違えないよう注意
スマホの電卓:
- iPhoneは横向きで関数電卓に
- Androidも科学計算モード有り
逆算(真数を求める)
log値から元の数を求める方法です。
10のべき乗で計算: log₁₀ x = 2.3 のとき、x = ? → x = 10^2.3 = 10² × 10^0.3 → = 100 × 2 = 200(概算)
電卓での計算:
- 「10」を入力
- 「x^y」または「^」ボタン
- 「2.3」を入力
- 「=」で答え(約199.5)
よく使う変換:
- 10^0.3 ≈ 2
- 10^0.5 ≈ 3.16
- 10^0.7 ≈ 5
この章のポイント:対数表は歴史的道具だが原理は重要。
電卓なら「log」ボタン一発。逆算は10のべき乗で。
よくある間違いと学習のコツ
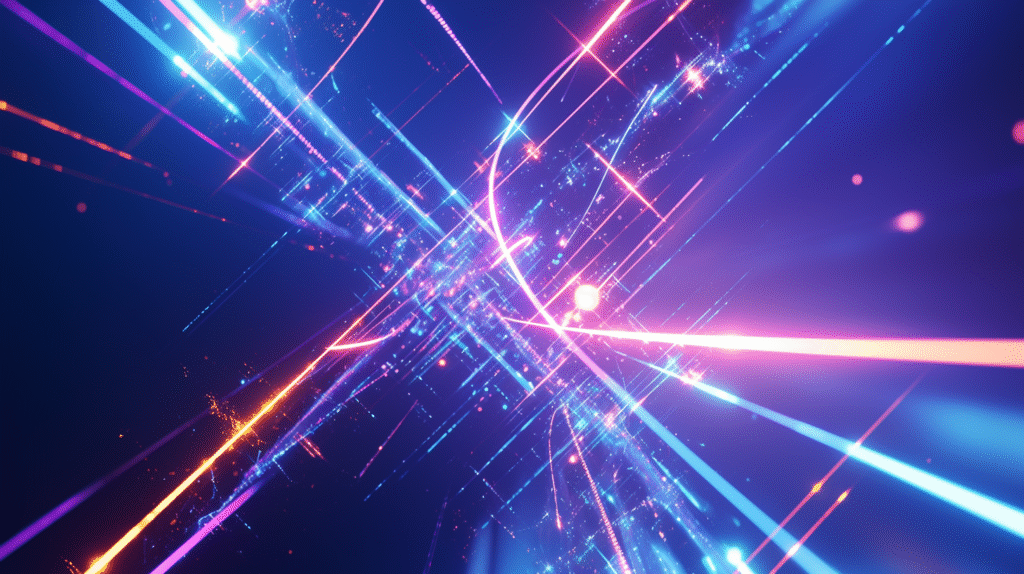
間違い1:底を忘れる・混同する
「logとlnを間違えた!」
区別のポイント:
- log = log₁₀(常用対数、底は10)
- ln = logₑ(自然対数、底はe)
- 問題文をよく読む
変換公式: ln x = log x / log e ≈ log x / 0.434
使い分け:
- 実用計算:常用対数(log)
- 微分積分:自然対数(ln)
間違い2:対数の性質を誤用
よくあるミス:
- log(A + B) ≠ log A + log B(これは間違い!)
- log(A – B) ≠ log A – log B(これも間違い!)
正しいのは:
- log(A × B) = log A + log B(積のみ)
- log(A ÷ B) = log A – log B(商のみ)
覚え方: 「掛け算が足し算に、割り算が引き算になる」
間違い3:マイナスの対数
「log₁₀(-5)は?」
重要な制限:
- 真数(logの中身)は正の数のみ
- log₁₀ 0 は定義されない(-∞)
- log₁₀(負の数) は実数では存在しない
ただし:
- log値自体はマイナスになれる
- log₁₀ 0.1 = -1(OK)
- log₁₀ 0.01 = -2(OK)
学習のコツ
常用対数をマスターする方法:
- まず10のべき乗を完璧に
- 10⁰ = 1, 10¹ = 10, 10² = 100…
- 10⁻¹ = 0.1, 10⁻² = 0.01…
- 基本値を暗記
- log 2 ≈ 0.3
- log 3 ≈ 0.48
- log 5 ≈ 0.7
- 実例と結びつける
- pH値で酸性・アルカリ性
- 地震のマグニチュード
- 音のデシベル
- グラフでイメージ
- y = log₁₀ x のグラフを描く
- 増加は緩やか
- x = 1で0を通る
この章のポイント:底の区別は重要。対数は積と商でのみ分解可能。真数は正の数のみ。実例と結びつけて理解しよう。
まとめ:常用対数は「桁数」を操る道具
ここまで、常用対数について詳しく見てきました。
重要ポイントの整理:
基本概念:
- 常用対数は「10の何乗か」を表す
- 底が10だから「常用」
- log₁₀ 1000 = 3(10³ = 1000)
- 桁数 – 1 ≈ log値の整数部分
- 真数は正の数のみ
重要な性質:
- log(A×B) = log A + log B
- log(A÷B) = log A – log B
- log(A^n) = n × log A
- 掛け算を足し算に変換
- 巨大な数を扱いやすく
実生活での活用:
- pH:水素イオン濃度(0〜14)
- マグニチュード:地震の強さ
- デシベル:音の大きさ
- 等級:星の明るさ
- すべて対数スケール
覚えるべき値:
- log 2 ≈ 0.301
- log 3 ≈ 0.477
- log 5 ≈ 0.699
- これだけで多くの値が計算可能
学習のアドバイス:
- 10のべき乗から理解
- 実例と結びつける
- グラフでイメージ
- 電卓を活用
- 底の違いに注意
常用対数は、最初は難しく感じるかもしれません。 「なんでこんなもの必要なの?」と思うこともあるでしょう。
でも、実は私たちの生活に深く関わっています。 地震のニュースを聞くとき、 pHを測るとき、 音の大きさを考えるとき。
常用対数は、途方もなく大きな数や小さな数を、扱いやすい数に変換する「魔法の道具」です。
10億(10⁹)も、10億分の1(10⁻⁹)も、 対数を使えば「9」と「-9」。 シンプルに表現できるんです。
この「桁数を操る技術」を身につけて、大きな数の世界を自在に扱えるようになってください!