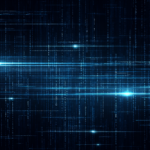「ほんの一部が分かれば全部分かる」
こんなことが本当にあるのでしょうか?実は、複素解析の世界では、これが当たり前なんです。
この不思議な現象を保証してくれるのが「一致の定理」です。今回は、正則関数の驚くべき性質を明らかにするこの定理について、詳しく見ていきましょう。
一致の定理とは
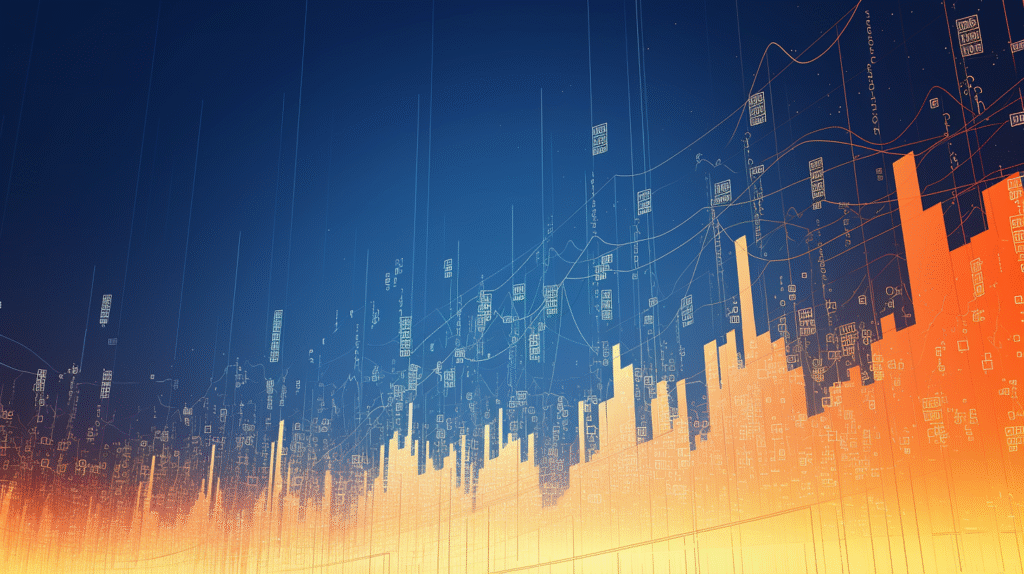
一致の定理(Identity Theorem)は、複素解析における基本的な定理の一つです。
定理の基本的な内容
一致の定理を簡単に言うと、こうなります。
「ある領域で正則な2つの関数が、その領域の一部で一致していれば、領域全体で一致する」
もっと具体的に言うと、次のようなことが言えます。
領域 $D$ で正則な関数 $f(z)$ と $g(z)$ があるとき、
- $D$ 内のある線分や曲線上で $f = g$ ならば、$D$ 全体で $f = g$
- $D$ 内のある小さな領域で $f = g$ ならば、$D$ 全体で $f = g$
- $D$ 内で $f = g$ となる点の列があって、その列が $D$ 内のある点に収束するならば、$D$ 全体で $f = g$
たったこれだけの情報から、領域全体での一致が言えてしまうんです。
零点に関する表現
一致の定理には、もう一つの表現方法があります。
関数 $f(z)$ が領域 $D$ で正則で、$f(z) = 0$ となる点(零点)が $D$ 内で集積点を持つならば、$f(z)$ は $D$ 全体で恒等的に0です。
「集積点」とは、その近くに零点が無限に詰まっている点のことです。
なぜこれが驚きなのか
一致の定理の何が驚きなのか、実数の関数と比較してみましょう。
実数の関数では成り立たない
実数の世界では、このような性質は一般には成り立ちません。
たとえば、次のような関数を考えてみてください。
$$f(x) = \begin{cases}
0 & (x \leq 0) \
e^{-1/x^2} & (x > 0)
\end{cases}$$
この関数は、$x = 0$ で無限回微分可能です。さらに、$x = 0$ におけるすべての導関数の値は0です。
でも、$x > 0$ では $f(x) \neq 0$ ですよね。
つまり、ある点とその近傍で0なのに、全体では0ではない関数が実数の世界には存在するんです。
複素関数は「硬い」
一方、複素平面上の正則関数は、実数の関数と比べて遥かに「硬い」(制約が厳しい)性質を持っています。
一度でも微分可能なら無限回微分可能で、さらにはテイラー展開も可能です。
そして、一致の定理が示すように、わずかな情報から関数全体の形が完全に決まってしまいます。
定理の証明の概要
一致の定理の証明を、大まかに見ていきましょう。
ステップ1:零点の近くで関数は0
まず、関数 $h(z) = f(z) – g(z)$ を考えます。
$h(z)$ の零点が集積点 $z_0$ を持つとします。
$h(z)$ は正則なので、$z_0$ の周りでテイラー展開できます。
$$h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$$
もし $h(z)$ が $z_0$ の近くで0でないなら、最初の0でない項があるはずです。
その最小の次数を $n$ とすると、
$$h(z) = (z-z_0)^n \cdot g(z)$$
となり、$g(z_0) \neq 0$ です。
しかし、これは $z_0$ が零点の集積点であることに矛盾します。なぜなら、$z_0$ の十分小さい近傍では $h(z) \neq 0$($z \neq z_0$ のとき)となってしまうからです。
したがって、$z_0$ の近傍では $h(z) = 0$ でなければなりません。
ステップ2:領域全体に広げる
次に、$h(z) = 0$ となる領域を徐々に広げていきます。
$h(z) = 0$ となる点全体の集合を $E$ とします。
ステップ1から、$E$ は開集合です(各点の周りに小さな円板が含まれる)。
また、$h(z)$ が連続であることから、$E$ は閉集合でもあります。
領域 $D$ は連結(一つにつながっている)なので、開かつ閉である部分集合は $D$ 全体か空集合のどちらかです。
$E$ は空でないので(集積点を含む)、$E = D$ となります。
つまり、$h(z) = 0$ が $D$ 全体で成り立ちます。
一致の定理の応用
一致の定理は、様々な場面で活用されます。
三角関数の加法定理
実数の範囲で成り立つ三角関数の加法定理、例えば
$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$
これが複素数の範囲でも成り立つことを、一致の定理を使って簡単に示せます。
証明の流れ:
まず、$y$ を固定して、$f(z) = \sin(z + y)$ と $g(z) = \sin z \cos y + \cos z \sin y$ を考えます。
$z$ が実数のとき、$f(z) = g(z)$ です(実数の加法定理)。
$f$ と $g$ はどちらも複素平面全体で正則です。
実軸は集積点を持つので、一致の定理より、すべての複素数 $z$ で $f(z) = g(z)$ です。
次に、$z$ を固定して、$y$ についても同様の議論をすれば完了です。
ガンマ関数の等式
ガンマ関数の重要な等式
$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$
も、実数の範囲で証明してから、一致の定理を使って複素数に拡張できます。
関数の一意性
ある級数が限られた範囲でしか収束しないとき、その関数を広い範囲に拡張する「解析接続」という操作があります。
一致の定理は、この解析接続が一意に決まることを保証してくれます。
つまり、拡張の仕方は本質的に一通りしかないんです。
零点の孤立性
一致の定理から、重要な結果が導かれます。
正則関数の零点は孤立する
領域 $D$ で正則な関数 $f(z)$ が恒等的に0でないなら、$f(z)$ の零点は孤立しています。
つまり、各零点の周りには、その零点以外に零点がない小さな領域が存在します。
なぜそうなるの?
もし零点が孤立していなければ、零点が集積点を持つことになります。
すると一致の定理より、$f(z)$ は $D$ 全体で0となり、「恒等的に0でない」という仮定に矛盾します。
コンパクト集合上の零点は有限個
領域 $D$ で正則な関数が恒等的に0でないとき、$D$ 内の任意のコンパクト集合(有界で閉じた集合)上の零点は高々有限個です。
これは、ボルツァノ・ワイエルシュトラスの定理を使えば簡単に示せます。
もし無限個の零点があれば、集積点が存在してしまい、一致の定理に矛盾するからです。
実際の使い方
一致の定理を実際に使う場面を見てみましょう。
複素関数の等式の証明
複素関数 $f(z)$ と $g(z)$ が複素平面全体で正則で、実軸上で $f(x) = g(x)$ が成り立つとします。
このとき、一致の定理より、複素平面全体で $f(z) = g(z)$ です。
つまり、実数での等式を確認すれば、複素数での等式が自動的に従います。
簡単な例
$f(z) = e^{2z}$ と $g(z) = (e^z)^2$ を考えます。
実数 $x$ に対して、$e^{2x} = (e^x)^2$ は明らかです。
どちらも複素平面全体で正則なので、一致の定理より、すべての複素数 $z$ で $e^{2z} = (e^z)^2$ が成り立ちます。
一致の定理の歴史
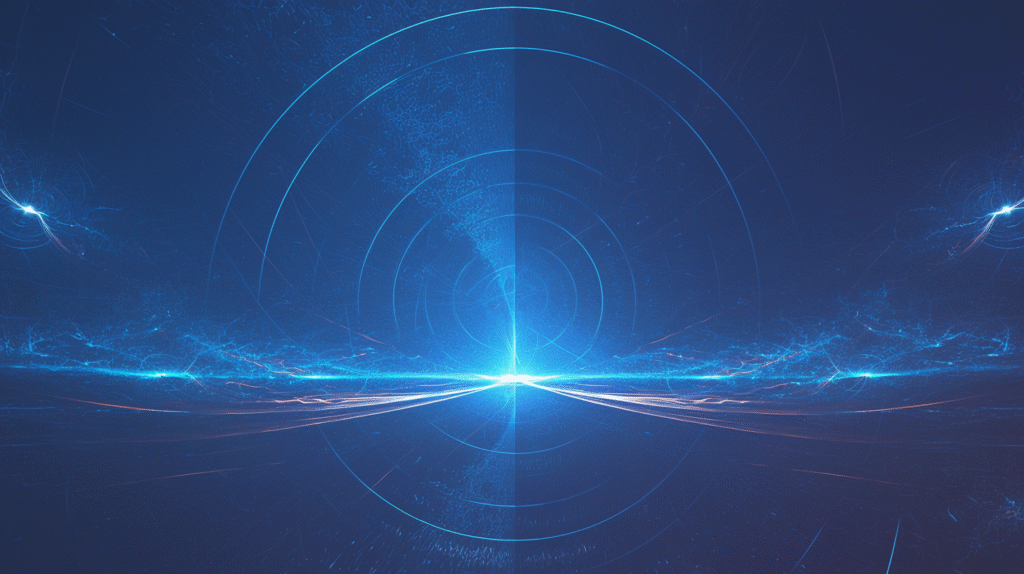
一致の定理には特定の命名者はいませんが、その発展には重要な歴史があります。
リウヴィルの貢献
1844年頃、ジョゼフ・リウヴィルが楕円関数の研究において、この定理の特殊な形を初めて適用しました。
コーシーによる一般化
その直後、オーギュスタン=ルイ・コーシーが、自身が開発していた複素解析の枠組みの中でこの定理を一般化しました。
現在の一致の定理の形は、このコーシーの仕事に基づいています。
重要な注意点
一致の定理を使うときの注意点を確認しておきましょう。
連結性が必要
領域が連結(一つにつながっている)ことが重要です。
もし領域が2つ以上の飛び地から成っているなら、一致の定理は成り立ちません。
例えば、$D = {z : 0 < |z| < 1} \cup {z : 2 < |z| < 3}$ のような領域では、各部分で別々の関数を定義できます。
正則性が必須
一致の定理が成り立つのは正則関数だけです。
単に連続な関数や、実数の意味で微分可能な関数では成り立ちません。
集積点が必要
一致する点の集合が集積点を持つことが重要です。
有限個の点で一致しているだけでは、全体での一致は言えません。
一致の定理と解析接続
一致の定理は、解析接続という重要な概念と密接に関係しています。
解析接続とは
ある関数が限られた領域でしか定義されていないとき、その定義域を自然に広げる操作を解析接続と言います。
例えば、べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ は $|z| < 1$ でしか収束しませんが、これは実は $\frac{1}{1-z}$ という、もっと広い範囲で定義できる関数です。
一意性の保証
もし2つの異なる方法で解析接続ができたとしたら、どちらが正しいのでしょうか?
一致の定理が答えを教えてくれます。
元の領域で一致している2つの正則関数は、広げた領域でも一致します。
つまり、解析接続は本質的に一意なんです。
一致の定理の変種
一致の定理には、いくつかの同値な表現があります。
導関数による表現
領域 $D$ で正則な関数 $f(z)$ について、次は同値です。
- $D$ 全体で $f(z) = 0$
- ある点 $z_0 \in D$ で、すべての階数の導関数が0:$f^{(n)}(z_0) = 0$ ($n = 0, 1, 2, \ldots$)
- ある点 $z_0$ の近傍で $f(z) = 0$
つまり、一点での無限個の条件から、全体の情報が分かるんです。
実用的な形
実際によく使われるのは、次の形です。
2つの正則関数 $f$ と $g$ が、ある開集合上で一致するなら、領域全体で一致する
この形は、関数の等式を証明するときに非常に便利です。
まとめ
一致の定理は、複素解析における驚くべき定理です。
その要点をまとめると、以下のようになります。
- 内容:正則関数の一部での一致から、全体での一致が従う
- 特徴:正則関数の「硬直性」を示す重要な性質
- 応用:三角関数の公式、ガンマ関数の等式、解析接続の一意性など
- 証明:テイラー展開と領域の連結性を利用
- 歴史:リウヴィルとコーシーによって確立
実数の関数では考えられないこの性質は、複素関数ならではの美しさを示しています。
「部分が全体を決定する」という一致の定理は、正則関数がいかに強い制約を受けているかを教えてくれます。
そして、この強い制約こそが、複素解析を豊かで応用範囲の広い学問にしているのです。
一致の定理を理解することで、複素解析の奥深さをより実感できるはずです。