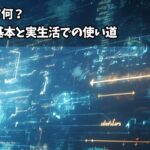「図形の問題って、いろんな定理があって覚えきれない…」
「何をどう使えばいいか分からない」
そんな悩みを持っていませんか?
数学の図形問題では、定理を知っているだけで解ける問題がぐっと増えます。
逆に知らないと、どこから手を付けていいか分からなくなりがちです。
この記事では、中学〜高校でよく使う図形の定理を一覧で紹介します。
あわせて簡単な使い方やポイントもまとめたので、ぜひ理解を深めてみてください。
三角形に関する重要な定理

三角形は図形問題の基本です。ここで紹介する定理は、高校入試や大学入試でもよく出題されます。
正弦定理(サイン定理)
定理の内容
任意の三角形ABCにおいて、
a/sin A = b/sin B = c/sin C = 2R
(Rは外接円の半径)
使うタイミング
- 角度と辺の長さが混在している問題
- 外接円の半径を求める問題
- 角度がわかっていて、対応する辺を求めたい場合
覚え方のコツ
「辺の長さ ÷ 向かい合う角のサイン = 一定」と覚えましょう。
余弦定理(コサイン定理)
定理の内容
c² = a² + b² - 2ab cos C
使うタイミング
- 三辺の長さがすべてわかっている場合
- 二辺とその間の角がわかっている場合
- 角度が鋭角か鈍角かを調べたい場合
ピタゴラスの定理との関係
角Cが90度のとき、cos C = 0になるので、c² = a² + b² となります。つまり、ピタゴラスの定理は余弦定理の特別な場合なんです。
三角形の面積公式
定理の内容
面積 = (1/2) × a × b × sin C
使うタイミング
- 高さがわからないとき
- 二辺とその間の角がわかっている場合
- 座標平面上での三角形の面積を求める場合
従来の公式との違い
「底辺 × 高さ ÷ 2」では高さを求める必要がありますが、この公式なら直接計算できます。
円に関する重要な定理
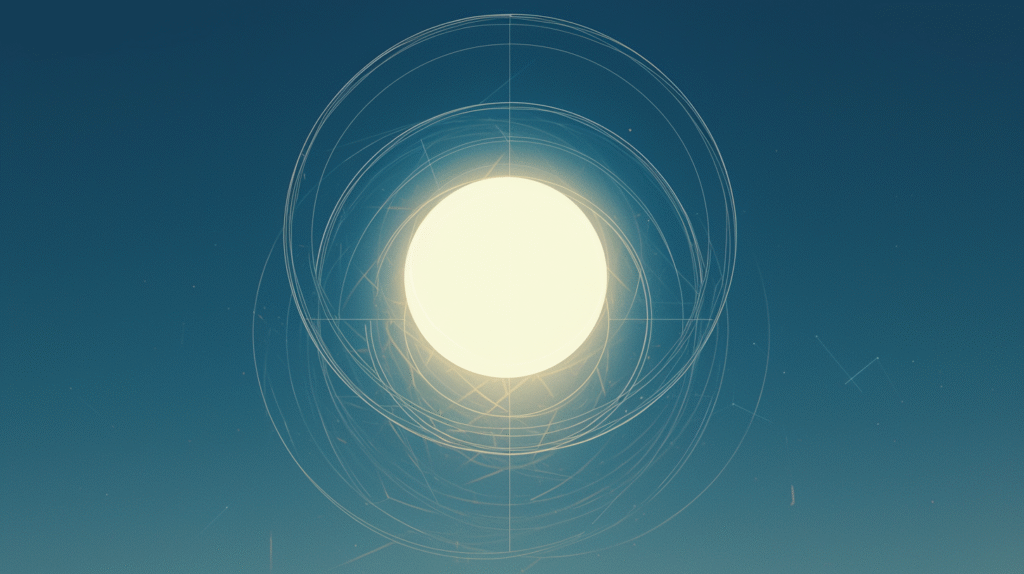
円の問題は図形問題の中でも特に重要です。パターンを覚えておくと、確実に得点できる分野でもあります。
円周角の定理
定理の内容
円の同じ弧に対する円周角は、どこから見ても等しい角度になります。また、円周角は中心角の半分になります。
使うタイミング
- 円の問題で角度を求める場合
- 四角形が円に内接することを証明する場合
- 角度の等しさを示したい場合
よくあるパターン
- 半円に内接する角は必ず90度
- 同じ弧を見る円周角はすべて等しい
接弦定理
定理の内容
接線と弦が作る角は、その弦に対する円周角に等しくなります。
使うタイミング
- 問題文に「接線」という言葉が出てきた場合
- 円の外部の点から引いた接線に関する問題
- 角度の関係を調べる問題
見分け方
図に接線が描かれていたら、この定理を疑ってみましょう。
方べきの定理
定理の内容
円の外部(または内部)の一点から円に引いた二本の直線について、交点までの距離の積は一定になります。
PA × PB = PC × PD
使うタイミング
- 円と直線の交点に関する問題
- 線分の長さの関係を調べる問題
- 比例関係を見つける問題
応用例
この定理を使うと、一つの長さがわからなくても、他の三つがわかれば計算で求められます。
四角形と多角形に関する定理
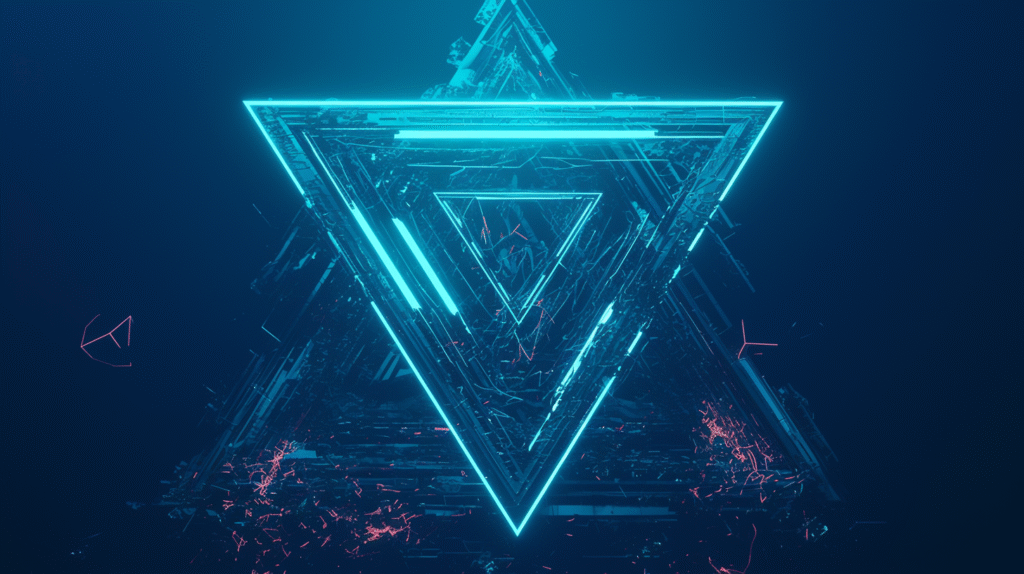
四角形や多角形の問題では、内角の性質や特別な条件を使った問題がよく出題されます。
多角形の内角の和
定理の内容
n角形の内角の和は 180° × (n - 2) で計算できます。
- 三角形(3角形):180° × (3-2) = 180°
- 四角形:180° × (4-2) = 360°
- 五角形:180° × (5-2) = 540°
- 六角形:180° × (6-2) = 720°
覚え方のコツ
「角の数から2を引いて、180をかける」と覚えましょう。
円に内接する四角形の条件
定理の内容
四角形が円に内接するための条件は、向かい合う角(対角)の和が180°になることです。
使うタイミング
- 四角形が円に内接することを証明する問題
- 円に内接する四角形の角度を求める問題
- 逆に、対角の和から円に内接するかどうかを判定する問題
実用例
対角の和が180°でない四角形は、円に内接できません。
知っておくと便利なその他の定理
基本的な定理以外にも、覚えておくと役立つ定理があります。
ヘロンの公式
定理の内容
三角形の三辺の長さ a、b、c がわかっているときの面積を求める公式です。
S = √[s(s-a)(s-b)(s-c)]
ここで、s = (a+b+c)/2(半周の長さ)
使うタイミング
- 三辺の長さだけがわかっている場合
- 角度が全くわからない三角形の面積を求める場合
- 座標が与えられていない図形問題
計算のコツ
sを先に計算してから、(s-a)、(s-b)、(s-c)を順番に計算すると間違いにくいです。
ピタゴラスの定理
定理の内容
直角三角形において、斜辺の二乗は他の二辺の二乗の和に等しくなります。
c² = a² + b²
使うタイミング
- 直角三角形の一辺を求める場合
- 三辺の長さから直角三角形かどうかを判定する場合
- 座標平面上での距離を求める場合
逆の使い方
三辺がピタゴラスの定理を満たすなら、その三角形は直角三角形です。これは「ピタゴラスの定理の逆」と呼ばれます。
まとめ
図形問題は「どの定理を使うか」がわかれば一気に楽になります。今回紹介したように、
分野別の重要定理
- 三角形 → 正弦定理・余弦定理・面積公式
- 円 → 円周角の定理、接弦定理、方べきの定理
- 四角形 → 内角の和、円に内接する条件
- その他 → ヘロンの公式、ピタゴラスの定理
定理を覚えるコツ
- 公式の意味を理解する:丸暗記ではなく、なぜその式になるのかを考える
- 問題パターンと対応させる:「この問題なら〇〇定理」という対応を覚える
- 実際に使ってみる:練習問題を解いて、使い方に慣れる