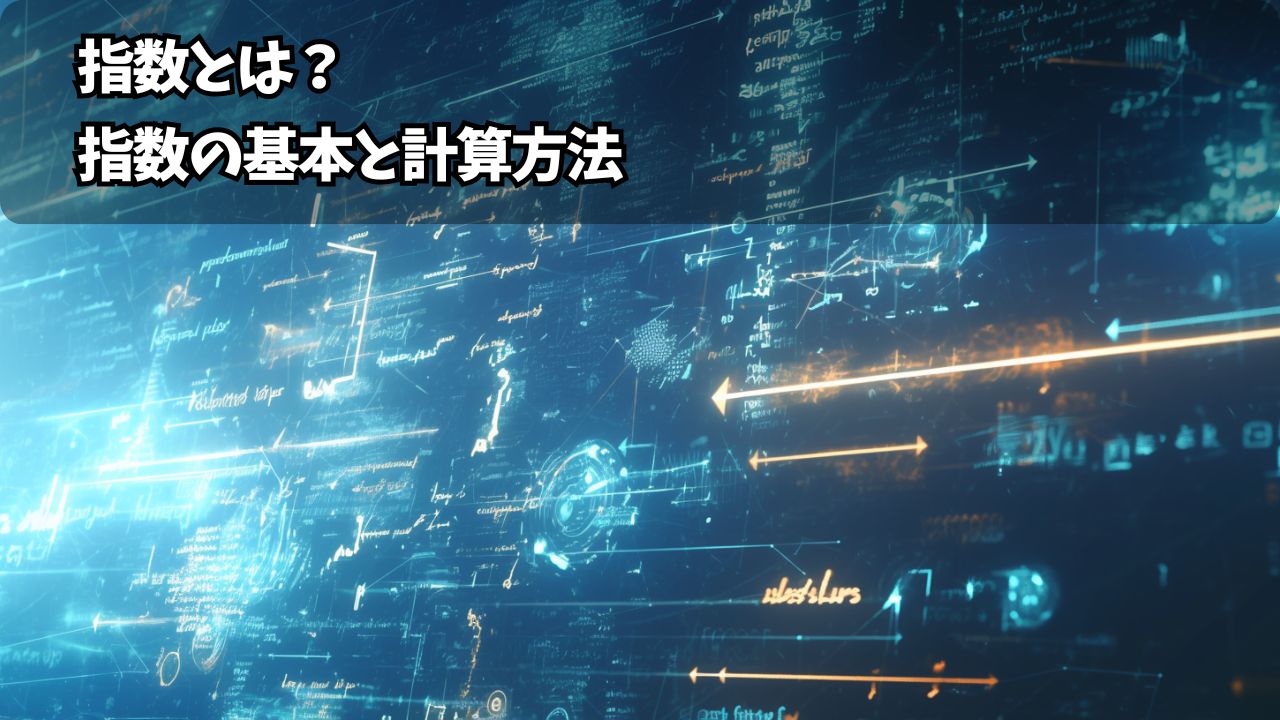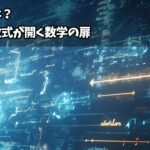「2の3乗」って聞いたことありますか? これを数式で書くと 2³ となりますが、この小さな「3」のことを指数(しすう)といいます。
指数は、同じ数を何回かけるかを表す便利な記号です。 たとえば、2×2×2 と書くのは面倒ですよね。 これを 2³ と書けば、とてもシンプルになります。
この記事では、指数の基本から計算方法まで、身近な例を使いながら分かりやすく解説していきます。 数学が苦手な人でも大丈夫。 一緒に指数の世界を探検してみましょう!
指数って何?基本から理解しよう
指数の正体
指数とは、ある数(基数または底と呼びます)を何回かけ合わせるかを示す数のことです。
たとえば:
- 5² → 5を2回かける → 5×5 = 25
- 3⁴ → 3を4回かける → 3×3×3×3 = 81
この時、5² の「5」を基数(底)、「2」を指数と呼びます。 全体を「5の2乗」や「5の2べき」と読みます。
なぜ指数を使うの?
指数を使う理由は主に3つあります。
- 表記が簡単になる 10×10×10×10×10 と書くより 10⁵ の方がスッキリしていますよね。
- 計算が楽になる 指数の法則を使えば、複雑な計算も簡単にできます。
- 大きな数や小さな数を表現しやすい 1,000,000 は 10⁶ と書けますし、0.001 は 10⁻³ と表せます。
この章では、指数の基本的な意味と、なぜ使うのかを学びました。 次は、実際にどう書いて、どう読むのかを詳しく見ていきましょう。
指数の書き方と読み方をマスターしよう
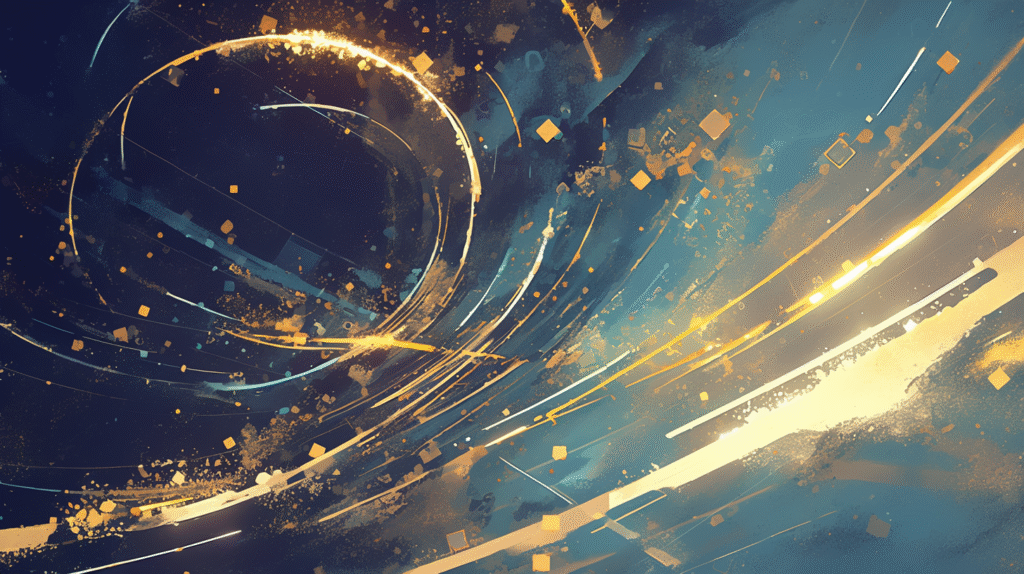
基本的な書き方
指数は、基数の右上に小さく書きます。
〈書き方の例〉
- 2の3乗 → 2³
- 7の5乗 → 7⁵
- 10の4乗 → 10⁴
読み方のルール
指数の読み方には、いくつかのパターンがあります。
〈一般的な読み方〉
- 2² → にの にじょう
- 3³ → さんの さんじょう
- 5⁴ → ごの よんじょう
〈特別な読み方〉
- 指数が2の場合:「平方(へいほう)」とも読む 例:3² → 3の平方
- 指数が3の場合:「立方(りっぽう)」とも読む 例:4³ → 4の立方
よく使う指数の値
覚えておくと便利な値があります。
〈2の累乗〉
- 2¹ = 2
- 2² = 4
- 2³ = 8
- 2⁴ = 16
- 2⁵ = 32
〈10の累乗〉
- 10¹ = 10
- 10² = 100
- 10³ = 1,000
- 10⁴ = 10,000
- 10⁵ = 100,000
指数の書き方と読み方を理解したところで、次はいよいよ計算方法を学んでいきます。 最初は難しく感じるかもしれませんが、ルールさえ覚えれば簡単ですよ。
指数計算の基本ルール(指数法則)
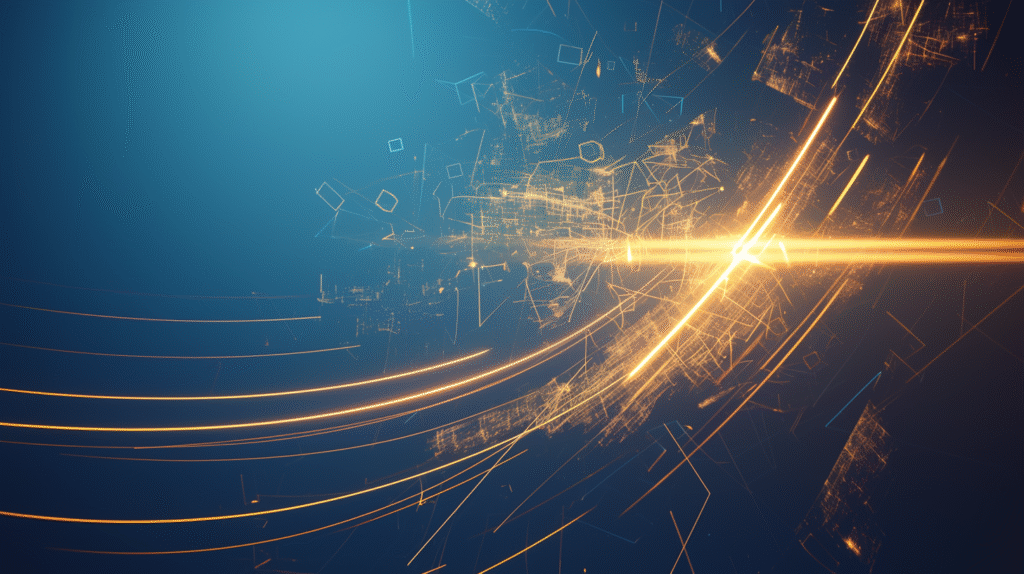
ルール1:同じ基数の掛け算
同じ基数の累乗をかけるときは、指数を足します。
〈計算例〉
- 2³ × 2² = 2³⁺² = 2⁵ = 32
- 5² × 5⁴ = 5²⁺⁴ = 5⁶
なぜこうなるの? 2³ × 2² = (2×2×2) × (2×2) = 2×2×2×2×2 = 2⁵ このように、実際に展開してみると指数が足し算になることが分かります。
ルール2:同じ基数の割り算
同じ基数の累乗を割るときは、指数を引きます。
〈計算例〉
- 3⁵ ÷ 3² = 3⁵⁻² = 3³ = 27
- 7⁸ ÷ 7³ = 7⁸⁻³ = 7⁵
ルール3:累乗の累乗
累乗をさらに累乗するときは、指数をかけます。
〈計算例〉
- (2³)² = 2³ˣ² = 2⁶ = 64
- (5²)³ = 5²ˣ³ = 5⁶
ルール4:0乗と1乗
どんな数でも:
- 0乗は1になる(0以外の数) 例:5⁰ = 1、100⁰ = 1
- 1乗はその数自身になる 例:7¹ = 7、15¹ = 15
ルール5:マイナスの指数
マイナスの指数は「分数」を表します。
〈計算例〉
- 2⁻¹ = 1/2 = 0.5
- 3⁻² = 1/3² = 1/9
- 10⁻³ = 1/1000 = 0.001
これらの基本ルールを覚えれば、複雑な指数計算もできるようになります。 次は、身の回りにある指数の例を見て、より理解を深めていきましょう。
身近な例で理解する指数

コンピューターの世界
パソコンやスマホのデータ容量で指数が活躍しています。
〈データの単位〉
- 1KB(キロバイト)= 2¹⁰ バイト = 1,024バイト
- 1MB(メガバイト)= 2²⁰ バイト = 約100万バイト
- 1GB(ギガバイト)= 2³⁰ バイト = 約10億バイト
なぜ2の累乗なの? コンピューターは0と1の2進数で動いているため、2の累乗が基本単位になっているんです。
細菌の増殖
細菌は分裂して増えていきます。 1個の細菌が30分ごとに2個に分裂する場合:
- 0時間後:1個 = 2⁰個
- 30分後:2個 = 2¹個
- 1時間後:4個 = 2²個
- 1.5時間後:8個 = 2³個
- 2時間後:16個 = 2⁴個
このように、時間とともに指数的に増加します。
お金の複利計算
銀行の利息計算でも指数が使われています。
年利5%で100万円を預けた場合:
- 1年後:100万円 × 1.05¹ = 105万円
- 2年後:100万円 × 1.05² = 110.25万円
- 3年後:100万円 × 1.05³ = 115.76万円
利息にも利息がつく複利の仕組みは、指数で表現できるんです。
紙を折る回数
1枚の紙(厚さ0.1mm)を折り続けるとどうなるでしょう?
- 1回折る:0.1mm × 2¹ = 0.2mm
- 5回折る:0.1mm × 2⁵ = 3.2mm
- 10回折る:0.1mm × 2¹⁰ = 102.4mm(約10cm)
- 20回折る:0.1mm × 2²⁰ = 104,857mm(約105m)
たった20回折るだけで、ビルの高さくらいになってしまいます!
身近な例を通じて、指数がいかに強力な概念かが分かったと思います。 次は、よくある間違いと注意点を確認して、正確に指数を使えるようになりましょう。
5. よくある間違いと注意点
間違い1:指数の足し算と掛け算の混同
〈よくある間違い〉 2³ + 2² = 2⁵ ? → これは間違い!
〈正しい計算〉 2³ + 2² = 8 + 4 = 12
足し算のときは、それぞれ計算してから足します。 指数を足すのは、同じ基数の掛け算のときだけです。
間違い2:基数が違う場合の計算
〈よくある間違い〉 2³ × 3² = 6⁵ ? → これは間違い!
〈正しい計算〉 2³ × 3² = 8 × 9 = 72
基数が違うときは、それぞれ計算してからかけます。
間違い3:マイナスの基数
〈注意が必要な例〉
- (-2)² = (-2) × (-2) = 4
- -2² = -(2²) = -4
カッコがあるかないかで意味が変わります! カッコがないときは、指数計算を先にしてからマイナスをつけます。
間違い4:0の0乗
0⁰ は定義されていません。 数学では「不定」として扱われることが多いです。
〈覚えておくべきこと〉
- 0以外の数の0乗 = 1
- 0の正の数乗 = 0
- 0⁰ = 定義なし
間違い5:分数の指数
分数の指数は累乗根を表します。
〈例〉
- 4^(1/2) = √4 = 2
- 8^(1/3) = ³√8 = 2
これは高校で詳しく学びますが、知っておくと便利です。
これらの注意点を押さえておけば、指数の計算で間違えることが少なくなります。 最後に、今日学んだことをまとめてみましょう。
まとめ
今日学んだこと
指数について、基本から応用まで幅広く学びました。
〈重要ポイント〉
- 指数は同じ数を何回かけるかを表す
- 基数の右上に小さく書く
- 指数法則を使えば計算が簡単になる
- 身の回りにも指数がたくさん使われている
- 間違えやすいポイントに注意する