「統計学の期待値って、なんだか難しそう…」
「数学の授業で出てきたけど、いったい何に使うの?」
統計学や確率論で非常に重要な「期待値」という概念。
高校の数学や大学の授業で習ったものの、「結局何のことかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、期待値の意味と基本的な求め方を、数学が苦手な方でも理解できるように丁寧に解説します。
身近な例を使いながら、「なぜ期待値が大切なのか」「どんなときに使うのか」も一緒に学んでいきましょう。
期待値とは何か?
簡単な言葉で説明すると
期待値とは、「長い間やり続けたら、だいたいこのくらいの値になるよ」という平均的な結果のことです。
たとえば、宝くじを何回も何回も買い続けたとき、「平均的にはどのくらい当たるのか」を計算したものが期待値です。
正確な定義
統計学的には、期待値は確率変数の平均的な値や「長期的に期待される結果の平均」を表します。
もう少し詳しく言うと:
- 「確率的にどのくらいの値が出るかの平均値」
- 「それぞれの結果に、その結果が出る確率をかけて足し合わせた値」
- 「理論上の平均値」
なぜ「期待値」という名前なの?
「期待」という言葉がついているので、「希望する値」と思いがちですが、実際は違います。
「期待値」の「期待」は、「予想される」「見込まれる」という意味です。
つまり、「この値が出ることが予想される」という意味で「期待値」と呼ばれています。
身近な例で理解しよう

例① コイン投げゲーム
まずは簡単な例から見てみましょう。
ゲームのルール
- コインを投げて表が出たら100円もらえる
- 裏が出たら0円
- 参加費は無料
このゲームを何回もやったら、平均でいくらもらえるでしょうか?
計算方法
- 表が出る確率:2分の1(0.5)
- 裏が出る確率:2分の1(0.5)
- 表が出たときのもらえる金額:100円
- 裏が出たときのもらえる金額:0円
期待値 = 100円 × 0.5 + 0円 × 0.5 = 50円
つまり、このゲームを長期間やり続けると、平均して1回につき50円もらえるということになります。
例② くじ引きの期待値
もう少し複雑な例を見てみましょう。
くじの内容
- 1等(1000円):10分の1の確率
- 2等(500円):10分の2の確率
- 3等(100円):10分の3の確率
- はずれ(0円):10分の4の確率
計算
期待値 = 1000円 × 0.1 + 500円 × 0.2 + 100円 × 0.3 + 0円 × 0.4 = 100円 + 100円 + 30円 + 0円 = 230円
このくじを引き続けると、平均して1回につき230円の価値があるということです。
もしこのくじ1枚の値段が300円だったら?
230円 – 300円 = -70円となり、平均して70円の損になることがわかります。
期待値の求め方(計算方法)
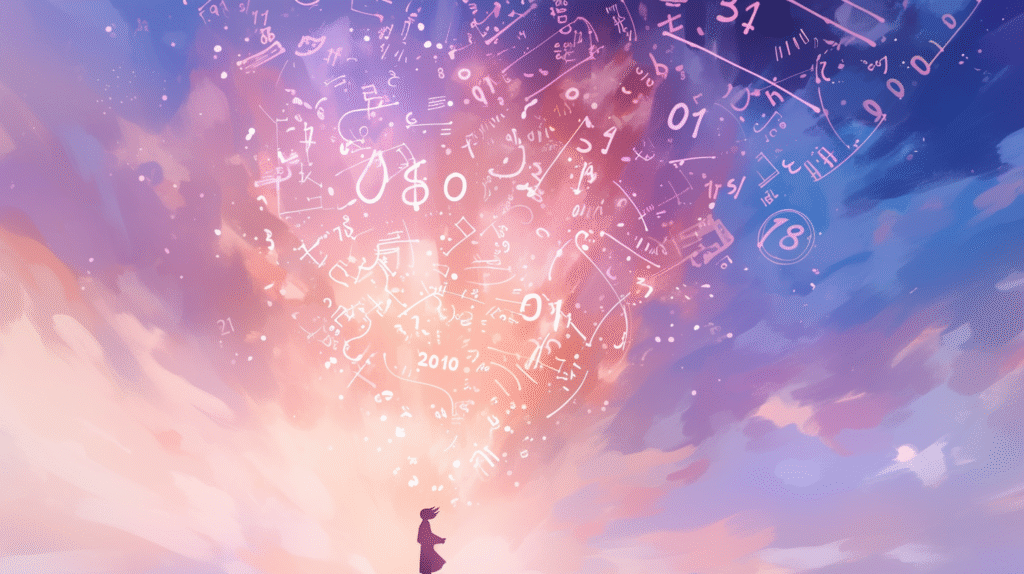
離散型確率変数の場合
「離散型」とは、取りうる値が決まっている場合のことです(サイコロの目、くじの等級など)。
公式
E(X) = Σ(xi × pi)
説明
- E(X):期待値
- xi:i番目の値
- pi:xi が起こる確率
- Σ:すべての i について足し合わせる
具体的な手順
- 起こりうるすべての結果を列挙する
- それぞれの結果の確率を求める
- 「結果の値 × その確率」を計算する
- すべての結果について計算したものを足し合わせる
一言で言えば、それぞれの値と確率を掛け算した積の合計値を求めるんです。
実践例:サイコロの期待値
普通の6面サイコロを振ったときの出る目の期待値を計算してみましょう。
情報整理
- 出る目:1, 2, 3, 4, 5, 6
- それぞれの確率:6分の1ずつ(約0.167)
計算過程
E(X) = 1 × (1/6) + 2 × (1/6) + 3 × (1/6) + 4 × (1/6) + 5 × (1/6) + 6 × (1/6)
= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) × (1/6)
= 21 × (1/6)
= 3.5
結果の意味
サイコロを振り続けると、平均して3.5の目が出ることになります。
実際には3.5という目は存在しませんが、これが理論上の平均値です。
連続型確率変数の場合
「連続型」とは、取りうる値が連続している場合のことです(身長、体重、時間など)。
公式
E(X) = ∫ x × f(x) dx
説明
- f(x):確率密度関数
- ∫:積分記号(連続型では積分を使う)
この計算は高校数学の積分の知識が必要になるため、詳細は大学レベルの統計学で学習します。
基本的な考え方は離散型と同じで、「値 × その値が起こる確率」を全範囲にわたって足し合わせる(積分する)ことです。
期待値の重要な性質
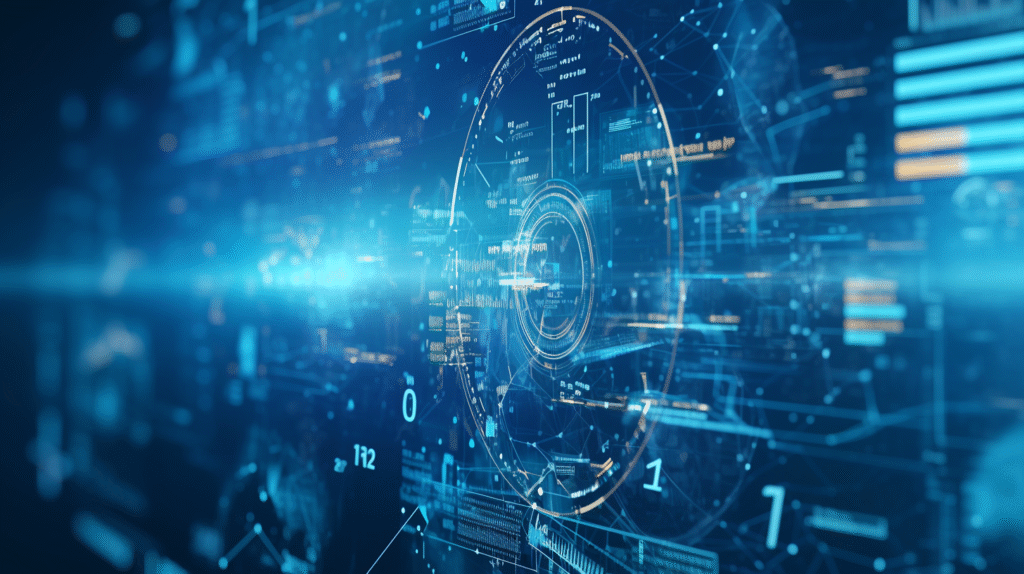
線形性(足し算と掛け算のルール)
期待値には便利な性質があります。
定数倍の性質 E(aX) = a × E(X)
例:サイコロの目を2倍したゲームの期待値 サイコロの期待値が3.5なので、2倍すると3.5 × 2 = 7
足し算の性質 E(X + Y) = E(X) + E(Y)
例:2つのサイコロを振って合計する場合 それぞれの期待値が3.5なので、合計の期待値は3.5 + 3.5 = 7
定数を足す場合 E(X + c) = E(X) + c
例:サイコロの目に10を足すゲームの場合 期待値は3.5 + 10 = 13.5
期待値と実際の結果の違い
大切なことは、期待値は「平均的な値」であって、「必ず出る値」ではないということです。
サイコロの例で考えると
- 期待値は3.5
- でも実際に3.5の目が出ることはない
- 1回だけ振ったら、1から6のどれかが出る
- 何百回、何千回と振り続けると、平均が3.5に近づいていく
この性質を「大数の法則」といいます。
期待値の使い道と応用例
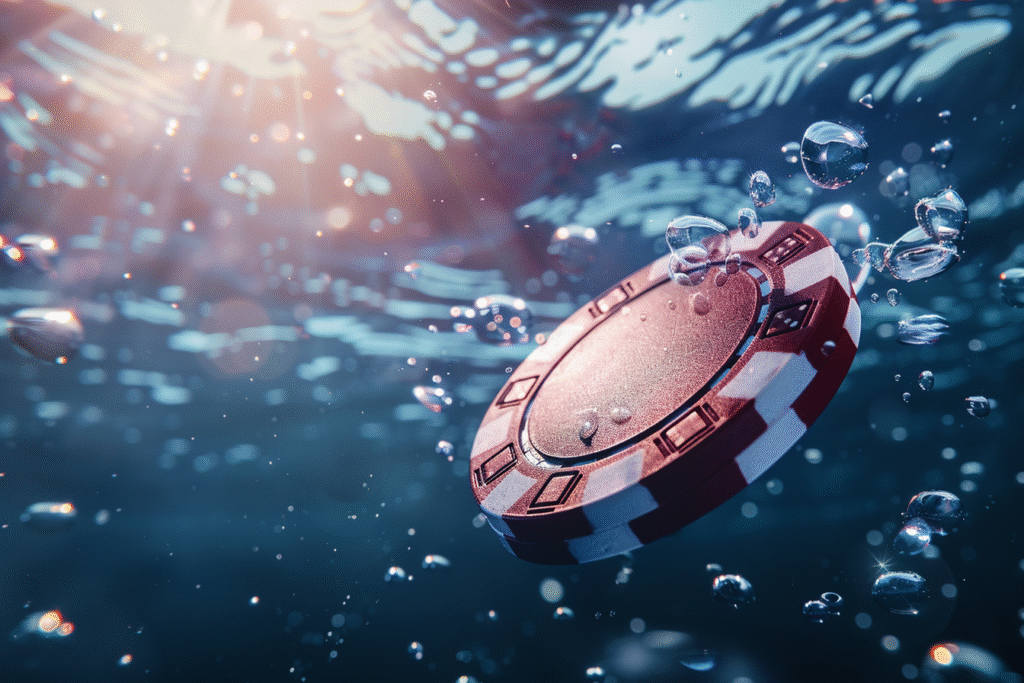
ゲームや賭け事の分析
パチンコ・スロットの期待値
- お店側は期待値をマイナスに設定している
- プレイヤーは長期的には損をする仕組み
- 「勝てるかどうか」を数学的に判断できる
宝くじの期待値
- 多くの宝くじは期待値が購入価格を下回る
- 例:300円の宝くじの期待値が150円など
- エンターテイメントとして楽しむもの
ビジネスでの活用
投資の期待収益率
- 株式投資や債券投資の期待リターンを計算
- リスクとリターンのバランスを判断
- ポートフォリオ最適化に使用
保険業界
- 保険金の支払い期待値を計算
- 保険料の設定に使用
- リスク管理の基本ツール
マーケティング
- キャンペーンの期待効果を計算
- 広告費用対効果の予測
- 新商品の売上予測
日常生活での判断
交通手段の選択
- 電車とバスの到着時間の期待値を比較
- 遅延リスクを含めた判断
買い物の判断
- セール期間を待つかどうか
- まとめ買いの期待メリット
進路選択
- 大学や専攻の期待収入
- 資格取得の期待メリット
よくある間違いと注意点

間違い① 期待値=必ず起こる結果
間違った考え方 「サイコロの期待値が3.5だから、平均的に3.5の目が出る」
正しい考え方 「たくさん振ったときの平均値が3.5に近づく」
間違い② 期待値が高い=必ず得
間違った考え方 「期待値がプラスのゲームは必ず勝てる」
正しい考え方 「長期的には利益が期待できるが、短期的には損する可能性もある」
間違い③ 確率の理解不足
よくある間違い
- 確率の合計が1にならない
- 条件付き確率を考慮していない
- 独立性を間違って仮定している
注意点:分散とリスク
期待値だけでは、結果のばらつき(リスク)がわかりません。
例:2つの投資商品
- 商品A:期待収益率5%、リスクが小さい
- 商品B:期待収益率5%、リスクが大きい
期待値は同じでも、商品Bの方が大きく損する可能性があります。
このようなばらつき(リスク)を表すのが「分散」や「標準偏差」です。
練習問題で理解を深めよう
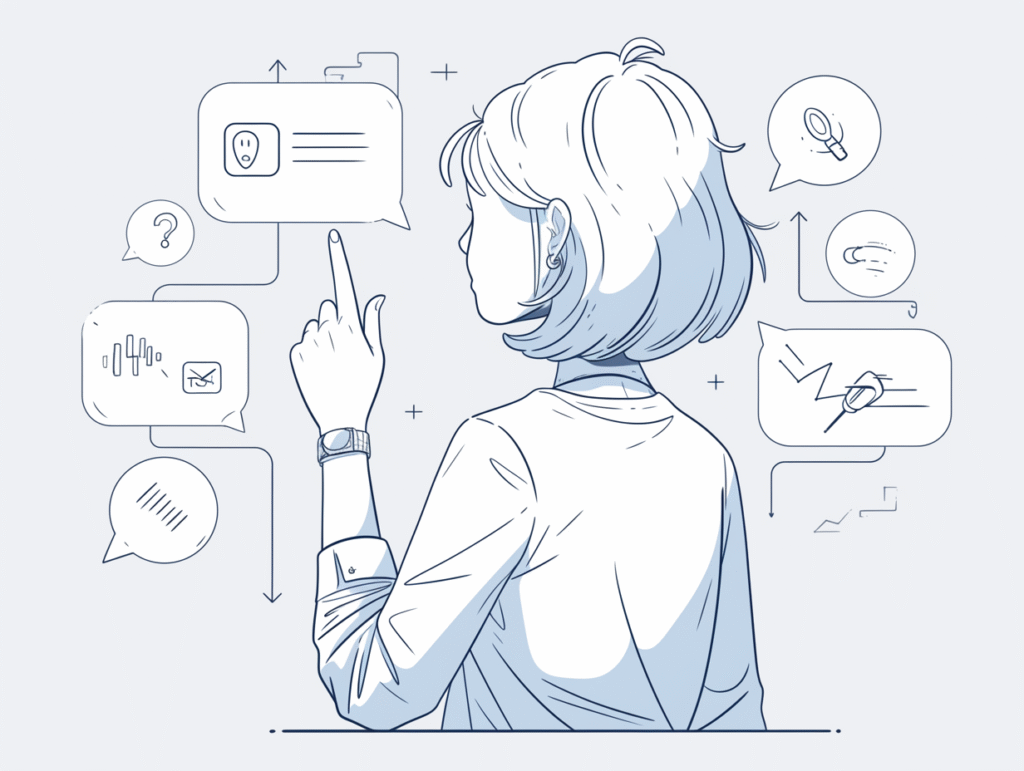
問題① 簡単なくじ引き
以下のくじの期待値を計算してください。
- 当たり(500円):確率20分の1
- はずれ(0円):確率20分の19
期待値 = 500円 × (1/20) + 0円 × (19/20) = 25円
問題② ゲームの損益分析
参加費100円のゲームがあります。
- 1等(1000円):確率100分の1
- 2等(200円):確率100分の9
- はずれ(0円):確率100分の90
このゲームの期待値は?参加した方がいい?
解答 期待値 = 1000円 × 0.01 + 200円 × 0.09 + 0円 × 0.90 = 10円 + 18円 + 0円 = 28円
参加費100円に対して期待値28円なので、期待損失は72円。長期的には損をするゲームです。
問題③ 実生活での応用
傘を持参するかどうかの判断:
- 雨が降る確率:30%
- 傘を忘れて雨に濡れたときの損失:1000円相当
- 傘を持参するコスト:50円相当(重さ、荷物)
傘を持参すべき?
解答
傘を持参しない場合の期待損失 = 1000円 × 0.3 = 300円
傘を持参するコスト = 50円
300円 > 50円なので、傘を持参した方が合理的です。
まとめ
期待値について覚えておくべきポイント
基本概念
- 期待値は「長期的な平均値」を表す
- 「値 × 確率」をすべて足し合わせて計算
- 短期的な結果とは異なる場合がある
計算方法
- 離散型:E(X) = Σ(xi × pi)
- 連続型:積分を使用(大学レベル)
- 線形性の性質を活用できる
実用性
- ゲームや投資の判断に役立つ
- ビジネスでのリスク管理に使用
- 日常生活の合理的判断にも応用可能
期待値を理解することの意義
期待値を理解することで、感情に左右されない合理的な判断ができるようになります。
例えば
- 宝くじを「夢を買う」として楽しむのか、「投資」として考えるのかを区別できる
- ギャンブルの仕組みを数学的に理解できる
- ビジネスや投資での意思決定に活用できる







