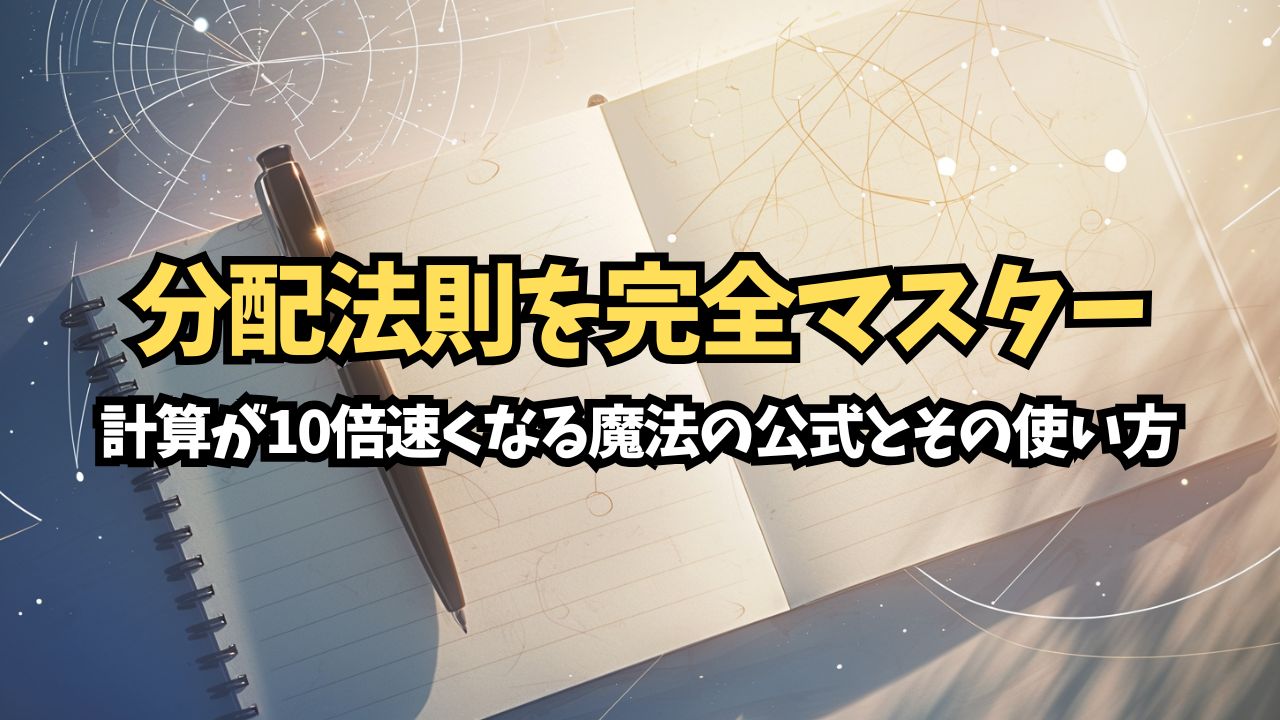「分配法則って聞いたことあるけど、いまいちピンとこない」 「テストで出てくるけど、なんで必要なのか分からない」 「もっと計算を速くしたい」
そんなあなたに朗報です。
分配法則は、ただの数学のルールじゃありません。買い物の計算から、テストの時短テクニック、さらには将来のプログラミングまで、いろんな場面で役立つ「計算の近道」なんです。
この記事を読み終わる頃には、複雑に見える計算も頭の中でサッと解けるようになります。一緒に分配法則の世界を探検していきましょう。
分配法則とは?基本からしっかり理解
そもそも分配法則って何?
分配法則を一言で説明すると、「かけ算を分けて配る法則」です。
基本の形: a × (b + c) = a × b + a × c
具体例で考えてみましょう: 3 × (4 + 5) = 3 × 4 + 3 × 5
左側:3 × 9 = 27 右側:12 + 15 = 27
ほら、同じ答えになりました!
なぜ「分配」って言うの?
イメージしやすい例で説明します。
お菓子を配る場面を想像してください:
- 3人の子供がいます
- 1人にチョコ4個とアメ5個をあげます
計算方法は2つ:
- 先に合計する:(4 + 5) × 3 = 9 × 3 = 27個
- 別々に計算:4 × 3 + 5 × 3 = 12 + 15 = 27個
どちらでも同じ。これが分配法則の本質です。
引き算でも使える分配法則
実は引き算でも同じように使えます:
a × (b – c) = a × b – a × c
例:5 × (8 – 3) = 5 × 8 – 5 × 3
- 左側:5 × 5 = 25
- 右側:40 – 15 = 25
これも便利に使えるんです。
小学生でも分かる!身近な例で理解する
お買い物で使う分配法則
スーパーでの計算例:
問題:198円のお菓子を3個買うといくら?
普通の計算:198 × 3 = 594円(暗算は大変…)
分配法則を使うと:
- 198 = 200 – 2 と考える
- 3 × (200 – 2) = 3 × 200 – 3 × 2
- = 600 – 6 = 594円
200円で計算して、あとで引く。これなら暗算でできますね!
時間の計算で使う
問題:45分の授業が4回あると合計何分?
分配法則で解く:
- 45 = 40 + 5 と考える
- 4 × (40 + 5) = 4 × 40 + 4 × 5
- = 160 + 20 = 180分 = 3時間
40分と5分に分けると、計算が楽になります。
お小遣いの計算
問題:毎週550円のお小遣いを4週間もらうと?
分配法則を使って:
- 550 = 500 + 50
- 4 × (500 + 50) = 4 × 500 + 4 × 50
- = 2000 + 200 = 2200円
キリのいい数字に分けると、暗算が簡単!
中学生向け:文字式での分配法則

文字を使った分配法則
中学になると、数字の代わりに文字(x、yなど)を使います。
基本形: a(b + c) = ab + ac
具体例: 2(x + 3) = 2x + 6
かっこを外す練習
よく出る問題パターン:
- 3(x + 4) = 3x + 12
- 5(2x – 1) = 10x – 5
- -2(x + 3) = -2x – 6(マイナスに注意!)
- x(x + 2) = x² + 2x
式の展開で大活躍
複雑な式も分配法則で解決:
(x + 2)(x + 3) を展開
手順:
- x + 2 の x を (x + 3) に分配:x × x + x × 3 = x² + 3x
- x + 2 の 2 を (x + 3) に分配:2 × x + 2 × 3 = 2x + 6
- 合わせる:x² + 3x + 2x + 6 = x² + 5x + 6
これが展開の基本です。
高校生向け:発展的な分配法則
因数分解での逆利用
分配法則を逆に使うと因数分解になります:
ab + ac = a(b + c)
例:
- 2x + 6 = 2(x + 3)
- 3x² + 6x = 3x(x + 2)
- xy + xz = x(y + z)
共通因数をくくり出す、これも分配法則の応用です。
複雑な計算での活用
問題:999² を計算
分配法則を使った解法:
- 999² = (1000 – 1)²
- = (1000 – 1)(1000 – 1)
- = 1000² – 1000 × 1 – 1 × 1000 + 1²
- = 1,000,000 – 1,000 – 1,000 + 1
- = 998,001
電卓なしでも解けました!
三項以上での分配法則
a(b + c + d) = ab + ac + ad
例:2(x + y + 3) = 2x + 2y + 6
項がいくつあっても、すべてに分配します。
計算スピードを上げる実践テクニック
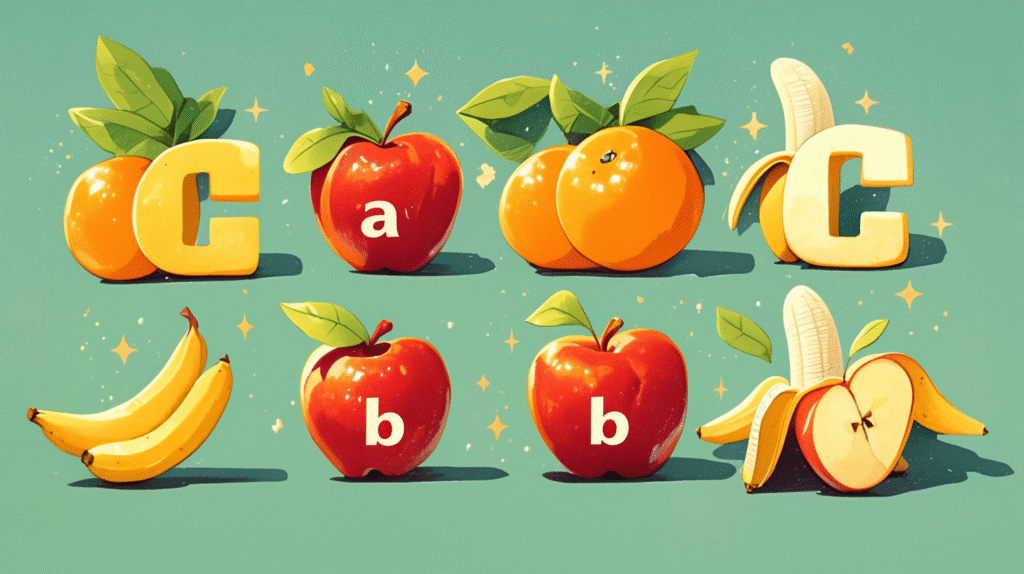
暗算が速くなる分解術
大きい数の計算を簡単にする方法:
97 × 8 の計算:
- 97 = 100 – 3
- 8 × (100 – 3) = 800 – 24 = 776
15 × 16 の計算:
- 15 × 16 = 15 × (10 + 6)
- = 150 + 90 = 240
11の倍数の裏技
11をかける計算:
34 × 11:
- 34 × (10 + 1) = 340 + 34 = 374
123 × 11:
- 123 × (10 + 1) = 1230 + 123 = 1353
10倍して元の数を足すだけ!
25の倍数の裏技
25 = 100 ÷ 4 を利用:
36 × 25:
- = 36 × (100 ÷ 4)
- = 3600 ÷ 4 = 900
または:
- 36 × 25 = 9 × 4 × 25 = 9 × 100 = 900
よくある間違いと注意点
マイナスの分配でミスしやすいポイント
要注意パターン:
-3(x – 2) の展開:
- 間違い:-3x – 6
- 正解:-3x + 6
マイナス×マイナス=プラスを忘れずに!
かっこの前の符号に注意
-(2x + 3) の展開:
- これは -1 × (2x + 3) と同じ
- = -2x – 3
見えない「-1」があることを意識しましょう。
分配し忘れに注意
2(3x + 4) = 6x + 4 ←間違い! 2(3x + 4) = 6x + 8 ←正解
すべての項に分配することを忘れずに。
日常生活での活用例
消費税の計算
商品価格に1.1をかける計算:
2,500円の10%税込み価格:
- 2,500 × 1.1 = 2,500 × (1 + 0.1)
- = 2,500 + 250 = 2,750円
割引計算
20%引きの計算:
3,000円の20%引き:
- 3,000 × 0.8 = 3,000 × (1 – 0.2)
- = 3,000 – 600 = 2,400円
面積の計算
長方形の面積:
縦3m、横(5+2)mの面積:
- 3 × (5 + 2) = 3 × 5 + 3 × 2
- = 15 + 6 = 21㎡
部屋を分けて考えると分かりやすい!
練習問題で実力チェック
基本レベル(小学生〜)
- 4 × (6 + 3) = ? 答え:4 × 9 = 36 または 24 + 12 = 36
- 7 × 98 = ?(98 = 100 – 2として) 答え:700 – 14 = 686
- 12 × 15 = ?(15 = 10 + 5として) 答え:120 + 60 = 180
標準レベル(中学生〜)
- 3(x + 5) = ? 答え:3x + 15
- -2(3x – 4) = ? 答え:-6x + 8
- (x + 3)(x + 2) = ? 答え:x² + 5x + 6
応用レベル(高校生〜)
- 6x + 9 を因数分解 答え:3(2x + 3)
- 101² を計算 答え:(100 + 1)² = 10,000 + 200 + 1 = 10,201
- 2x² + 8x を因数分解 答え:2x(x + 4)
分配法則をマスターするコツ
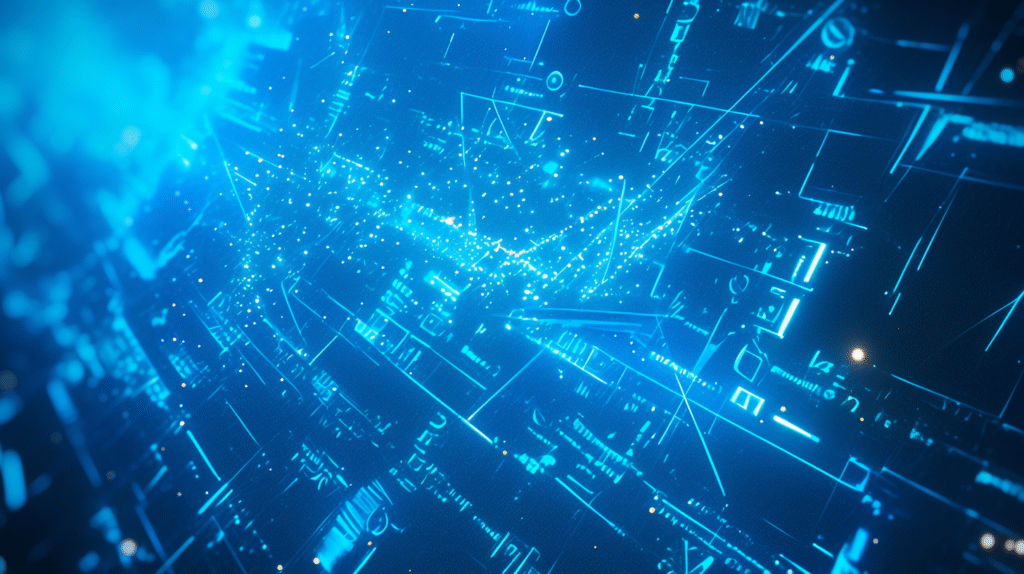
視覚的にイメージする
長方形の面積で考える習慣をつけましょう。
- 縦 a、横 (b + c) の長方形
- 2つの長方形に分けて考える
- それぞれ ab と ac の面積
日常で練習する
買い物中に練習:
- レジに並んでいる間に暗算
- 199円 × 3 = (200 – 1) × 3 = 597円
間違いを恐れない
最初は時間がかかってもOK。慣れれば必ず速くなります。
- まず正確に
- 次に速く
- 最後に応用
プログラミングでの分配法則
効率的なコード作成
プログラミングでも分配法則の考え方は重要:
// 非効率
result = a * b + a * c + a * d
// 効率的(分配法則の逆)
result = a * (b + c + d)
計算回数が減って、処理が速くなります。
アルゴリズムの最適化
大量のデータ処理でも:
- 共通部分をまとめる
- 計算の重複を避ける
- メモリ使用量も削減
将来プログラマーを目指す人には必須の考え方です。
まとめ:分配法則は一生使える財産
分配法則をマスターすれば、こんなメリットが:
すぐに実感できる効果:
- 暗算が速くなる
- テストの時間に余裕ができる
- 買い物の計算が楽になる
- 数学への苦手意識が減る
- 論理的思考力が身につく
これから使える場面:
- 高校・大学の数学
- 資格試験の計算問題
- 仕事での見積もり計算
- プログラミング
- 日常のあらゆる計算
分配法則は、ただの公式じゃありません。「複雑なものを簡単にする」という、問題解決の基本的な考え方なんです。
今日から、身の回りの計算で分配法則を使ってみてください。最初は意識的に、そのうち自然に使えるようになります。
気づいたら、あなたも計算マスターの仲間入り。数学が少し楽しくなるはずです。