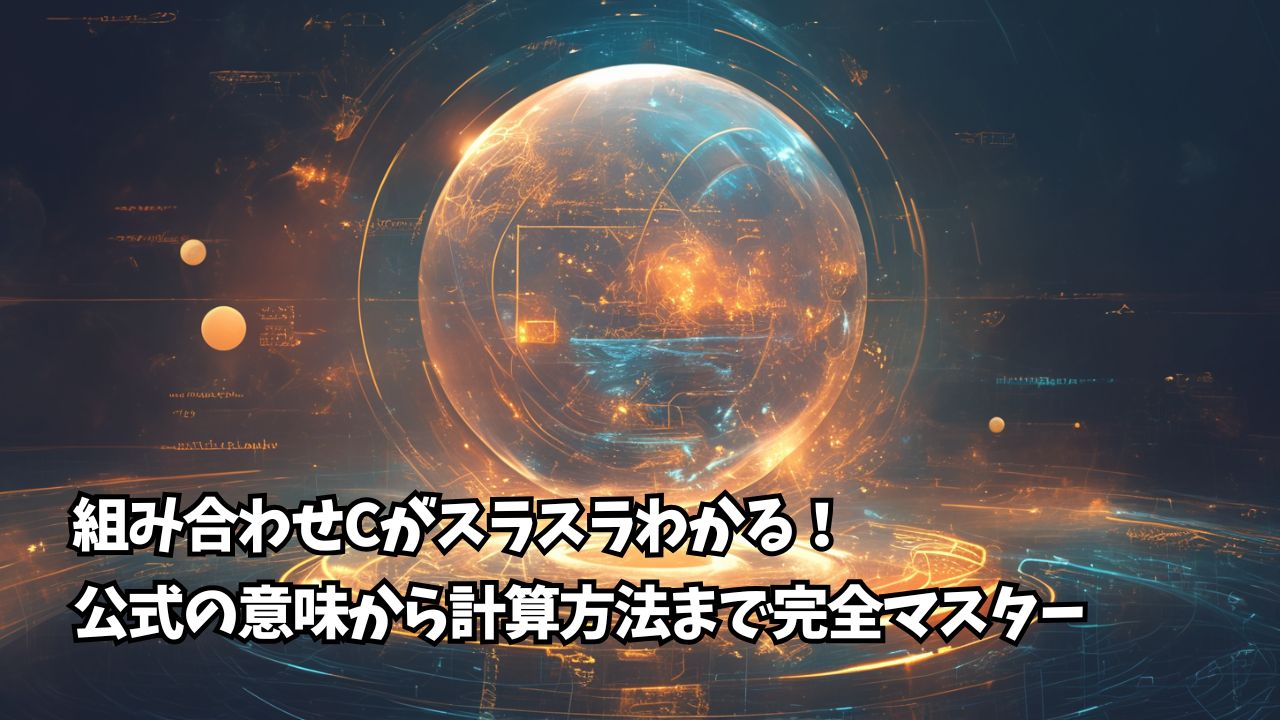「組み合わせのCって、Pとどう違うの?」 「₅C₃の計算方法がいつも混乱する…」 「なんで階乗(!)が出てくるの?」 「実生活でいつ使うの?宝くじの当選確率?」
数学の授業で突然現れるC(コンビネーション)。 見た目も計算も複雑そうで、多くの人が苦手意識を持っていますよね。
でも実は、組み合わせCは**「選ぶ」という日常的な行為を数式にしただけ**なんです。 5人から3人を選ぶ、10個のお菓子から3個選ぶ…これがまさに組み合わせ!
この記事では、小学生でも理解できる例え話から始めて、大学入試レベルまで段階的に解説。 さらに、電卓での計算方法やエクセルでの求め方まで、実用的な内容も満載です。
読み終わる頃には、「なんだ、組み合わせCってこんなに簡単だったのか!」と思えるはずです。
組み合わせCとは?3分でわかる基本概念

一言で説明すると…
組み合わせC(Combination)は、「順番を考えずに選ぶ場合の数」を表す記号です。
身近な例で理解しよう
例1:友達とランチに行く
5人の友達(A、B、C、D、E)から3人を選んでランチに行く場合:
- A、B、C を選ぶ
- A、C、B を選ぶ
この2つは同じ組み合わせとして数えます。 誰が先に選ばれたかは関係ないからです。
これが ₅C₃(5人から3人を選ぶ組み合わせ)です!
順列Pとの決定的な違い
| 項目 | 組み合わせ(C) | 順列(P) |
|---|---|---|
| 順番 | 考えない | 考える |
| 例 | チーム選び | 並び順 |
| ABC と BAC | 同じ(1通り) | 違う(2通り) |
| 使用場面 | 選ぶ、組を作る | 並べる、順位を決める |
| 計算 | 順列÷並べ替え | n!/(n-r)! |
覚え方:
- Combination = Choose(選ぶ)
- Permutation = Place(配置する)
組み合わせCの記号と読み方
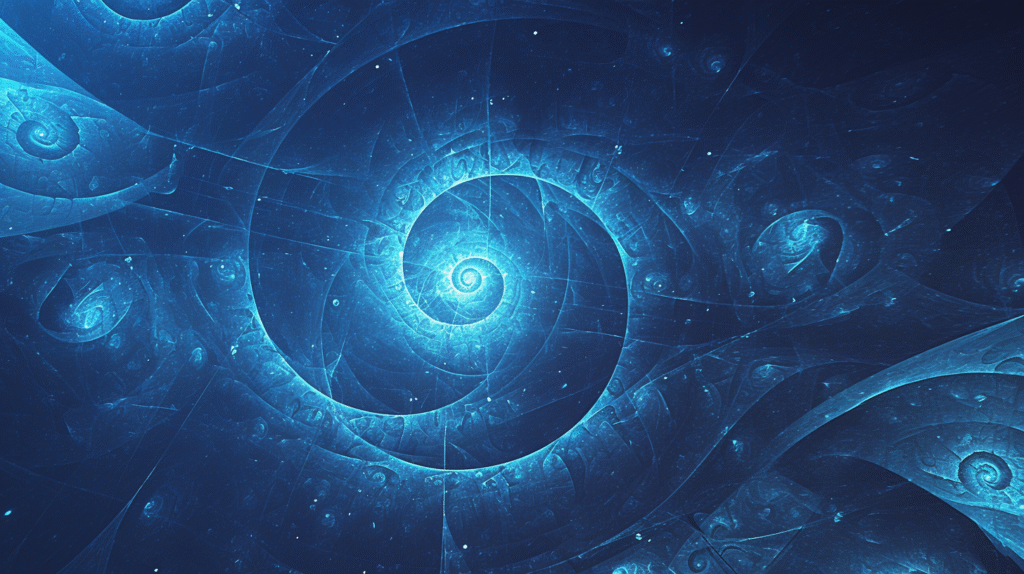
正しい表記方法
組み合わせは以下のように書きます:
1. 標準的な表記
nCr
- n:全体の数
- r:選ぶ数
- C:Combinationの頭文字
2. 実際の使用例
- ₅C₃ = 5個から3個選ぶ組み合わせ
- ₁₀C₄ = 10個から4個選ぶ組み合わせ
- ₙCᵣ = n個からr個選ぶ組み合わせ
読み方のバリエーション
₅C₃ の読み方:
- 「ごシーさん」(最も一般的)
- 「5コンビネーション3」
- 「5個から3個選ぶ組み合わせ」
他の表記方法
数学の分野によって異なる表記も:
C(n,r) (関数表記)
(n r) (二項係数表記)
C_n^r (上付き表記)
どれも同じ意味ですが、日本では nCr が主流です。
組み合わせCの公式と計算方法
基本公式:これだけ覚えればOK!
nCr = n! / (r! × (n-r)!)
階乗(!)って何?
階乗は、その数から1まで順番に掛け算することです。
- 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
- 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24
- 3! = 3 × 2 × 1 = 6
- 0! = 1(定義)
実際に計算してみよう:₅C₃の場合
方法1:公式をそのまま使う
₅C₃ = 5! / (3! × 2!)
= 120 / (6 × 2)
= 120 / 12
= 10
方法2:約分を使った簡単計算
₅C₃ = (5 × 4 × 3!) / (3! × 2 × 1)
= (5 × 4) / (2 × 1) ← 3!が約分で消える
= 20 / 2
= 10
💡 計算のコツ: 分子と分母で同じ階乗があれば、先に約分すると楽!
よく出る組み合わせの値(暗記推奨)
| 式 | 値 | 覚え方 |
|---|---|---|
| ₃C₁ | 3 | 3つから1つ選ぶ |
| ₄C₂ | 6 | トランプのペア |
| ₅C₂ | 10 | 5人で握手する回数 |
| ₅C₃ | 10 | ₅C₂と同じ |
| ₆C₃ | 20 | |
| ₇C₂ | 21 | |
| ₁₀C₂ | 45 |
なぜこの公式になるの?直感的な理解
ステップで考える組み合わせ
₅C₃を例に、なぜ10通りになるか理解しましょう。
Step1:まず順列で考える
5人から3人を順番付きで選ぶと:
- 1人目:5通り
- 2人目:4通り
- 3人目:3通り
- 合計:5 × 4 × 3 = 60通り
Step2:重複を除く
でも組み合わせでは順番は関係ない! ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA は全部同じ。
3人の並べ替えは 3! = 6通り
Step3:割り算で求める
組み合わせ = 順列 ÷ 並べ替え
₅C₃ = 60 ÷ 6 = 10
これが公式 n!/(r! × (n-r)!) の意味です!
図解で理解する
5人から3人選ぶ全パターン:
{A,B,C} {A,B,D} {A,B,E}
{A,C,D} {A,C,E} {A,D,E}
{B,C,D} {B,C,E} {B,D,E}
{C,D,E}
合計10通り!
実践!いろいろな組み合わせ問題
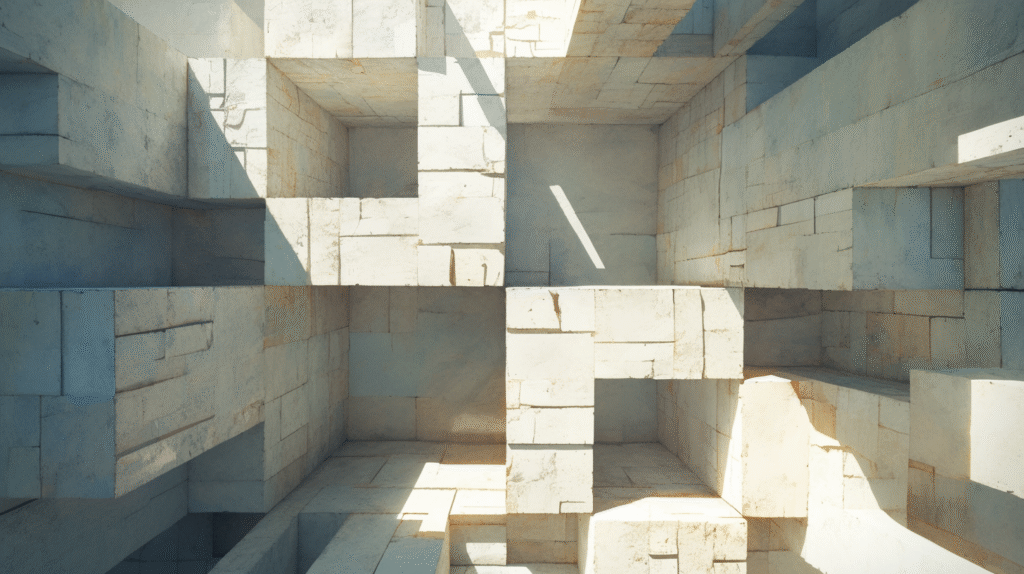
基本問題:クラスから委員を選ぶ
**問題:**30人のクラスから学級委員3人を選ぶ方法は何通り?
解答:
₃₀C₃ = 30! / (3! × 27!)
= (30 × 29 × 28) / (3 × 2 × 1)
= 24360 / 6
= 4060通り
応用問題1:男女混合で選ぶ
**問題:**男子5人、女子4人から3人選ぶ。ただし男女とも最低1人は含む。
解き方:
- 全体から3人選ぶ:₉C₃
- 男子だけ3人:₅C₃
- 女子だけ3人:₄C₃(実際は不可能)
**答え:**₉C₃ – ₅C₃ = 84 – 10 = 74通り
応用問題2:条件付き選択
**問題:**10冊の本から3冊選ぶ。ただし、特定の2冊は必ず含める。
解き方:
- 特定の2冊は確定
- 残り8冊から1冊選ぶ
**答え:**₈C₁ = 8通り
実生活での応用例
宝くじ(ロト6)
43個の数字から6個選ぶ:
₄₃C₆ = 6,096,454通り
当選確率は約600万分の1!
トーナメントの試合数
8チームの総当たり戦:
₈C₂ = 28試合
ピザのトッピング
10種類から3種類選ぶ:
₁₀C₃ = 120通り
電卓・エクセル・プログラムでの計算方法
関数電卓での計算
CASIOの場合
- 数字を入力(例:5)
- 「nCr」ボタンを押す
- 選ぶ数を入力(例:3)
- 「=」を押す
スマホの電卓アプリ
- iPhoneは横画面にすると科学電卓モードに
- 「C」や「nCr」ボタンを探す
Excelでの計算方法
COMBIN関数を使う
=COMBIN(5,3)
結果:10
実用例:複数の組み合わせを一覧化
| A列 | B列 | C列(数式) | 結果 |
|---|---|---|---|
| n=5 | r=0 | =COMBIN(A1,B1) | 1 |
| n=5 | r=1 | =COMBIN(A2,B2) | 5 |
| n=5 | r=2 | =COMBIN(A3,B3) | 10 |
| n=5 | r=3 | =COMBIN(A4,B4) | 10 |
| n=5 | r=4 | =COMBIN(A5,B5) | 5 |
| n=5 | r=5 | =COMBIN(A6,B6) | 1 |
プログラミングでの実装
Python
import math
result = math.comb(5, 3) # 10
JavaScript
function combination(n, r) {
return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r));
}
重要な性質と公式集

対称性:nCr = nC(n-r)
₅C₃ = ₅C₂ = 10
₁₀C₃ = ₁₀C₇ = 120
**意味:**5人から3人選ぶ = 5人から2人を外す
パスカルの三角形との関係
1 (₀C₀)
1 1 (₁C₀ ₁C₁)
1 2 1 (₂C₀ ₂C₁ ₂C₂)
1 3 3 1 (₃C₀ ₃C₁ ₃C₂ ₃C₃)
1 4 6 4 1 (₄C₀ ₄C₁ ₄C₂ ₄C₃ ₄C₄)
各数字が組み合わせの値になっています!
二項定理との関係
(a + b)ⁿ = Σ(nCr × aⁿ⁻ʳ × bʳ)
例:(a + b)³ = ₃C₀a³ + ₃C₁a²b + ₃C₂ab² + ₃C₃b³
よく使う公式まとめ
| 公式 | 意味 |
|---|---|
| nC0 = 1 | 何も選ばない方法は1通り |
| nC1 = n | 1つ選ぶ方法はn通り |
| nCn = 1 | 全部選ぶ方法は1通り |
| nCr = nC(n-r) | 対称性 |
| nCr + nC(r+1) = (n+1)C(r+1) | パスカルの法則 |
間違えやすいポイントと注意事項
よくある間違い1:順列と混同
❌ 間違い: 「5人から会長・副会長・書記を選ぶ」→ ₅C₃
✅ 正解: 役職が異なる → 順列 ₅P₃ = 60通り
よくある間違い2:0の扱い
**問題:**₅C₀ は?
答え:1(何も選ばない方法は1通り)
多くの人が「0」と答えてしまいますが、必ず1です!
よくある間違い3:重複組み合わせ
同じものを何度も選べる場合は、通常の組み合わせと違います。
**例:**3種類のアイスから重複を許して2個選ぶ → 重複組み合わせ ₃H₂ = ₄C₂ = 6通り
計算ミスを防ぐコツ
- 約分を先にする
- 階乗をすべて計算せず、約分できる部分を探す
- 対称性を利用
- ₁₀C₇ より ₁₀C₃ の方が計算しやすい
- 検算する
- nCr ≤ nPr であることを確認
- パスカルの三角形で確認
受験・資格試験での頻出パターン
大学入試での出題傾向
パターン1:単純な組み合わせ
- 委員選出
- グループ分け
- 図形の選択
パターン2:条件付き組み合わせ
- 「少なくとも1人は〜」
- 「〜を除いて」
- 「男女混合で」
パターン3:組み合わせ+確率
- くじ引き問題
- カード選択
- サイコロ問題
解法テクニック
「少なくとも」は余事象で
「少なくとも1個」= 全体 -「0個」
「ちょうど」は場合分け
「ちょうど2個」= その条件のみ計算
図を描いて整理
複雑な問題は視覚化が有効!
組み合わせCの実用例:身の回りの活用

スポーツ
サッカーのフォーメーション
23人から11人のスタメン選出:
₂₃C₁₁ = 1,352,078通り
料理・食事
定食の組み合わせ
主菜5種、副菜4種から各1種選ぶ:
₅C₁ × ₄C₁ = 20通り
ビジネス
プロジェクトチーム編成
10人から3人のチームを作る:
₁₀C₃ = 120通り
ゲーム・娯楽
ポーカーの役
52枚から5枚選ぶ:
₅₂C₅ = 2,598,960通り
麻雀の配牌
136枚から13枚選ぶ(実際はもっと複雑)
まとめ:組み合わせCはもう怖くない!
組み合わせCについて、基礎から応用まで完全にマスターできましたね!
絶対に覚えておくべきポイント:
✅ 組み合わせC = 順番を考えない選び方
✅ 公式:nCr = n!/(r! × (n-r)!)
✅ 順列との違い:順番の有無
✅ 対称性:nCr = nC(n-r)
✅ 計算のコツ:約分を先に
レベル別学習ガイド:
📗 初級者 → まず₅C₃までの計算をマスター
📘 中級者 → 条件付き問題にチャレンジ
📙 上級者 → 重複組み合わせや二項定理へ
実は組み合わせは…
日常生活で無意識に使っている考え方。 「今日のランチ何にしよう」「どの服を着よう」 これらすべてが組み合わせの思考なんです。
数式にすると難しく見えますが、本質はとてもシンプル。 「選ぶ」という行為を数値化しただけ。
この記事を何度も読み返して、組み合わせCを完全に自分のものにしてください!