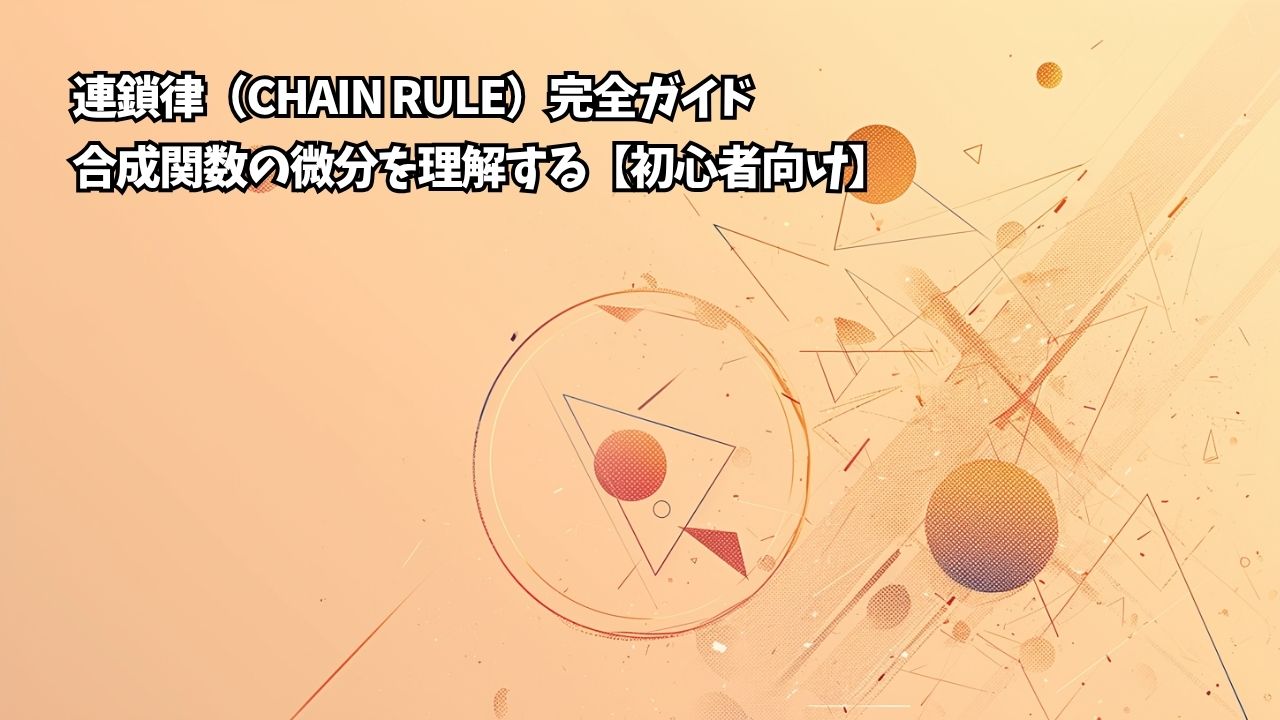数学の問題で「sin(x²)を微分せよ」という問題に出会ったことはありませんか?
「普通のsinなら微分できるけど、中にx²が入ってるとどうすればいいの?」と困った経験がある方も多いでしょう。
そんなときに使うのが連鎖律(チェーンルール)です。今回は、この微分積分学の最重要テクニックについて、初心者の方でも分かるように解説していきますよ!
連鎖律とは?基本を理解しよう
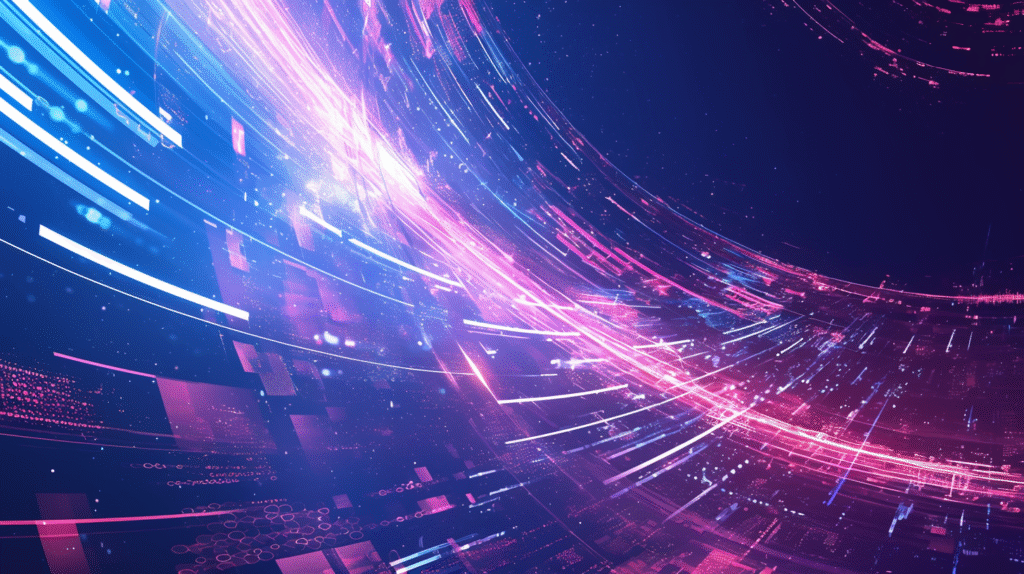
連鎖律は、合成関数を微分するための公式です。
合成関数って何?
合成関数は、「関数の中に別の関数が入っている」形の関数です。
例:
y = sin(x²)
これは、「x²を計算してから、その結果のsinを取る」という2段階の操作になっていますね。
別の見方:
- 内側の関数:u = x²
- 外側の関数:y = sin(u)
この2つの関数を組み合わせた形が合成関数なんです。
なぜ連鎖律が必要?
普通の微分公式では、合成関数を直接微分できません。
基本的な微分公式:
- (x²)’ = 2x
- (sin x)’ = cos x
でも、sin(x²)の微分は?これらの公式だけでは分かりませんよね。
そこで登場するのが連鎖律です。
連鎖律の公式
基本形
関数が y = f(g(x)) の形のとき:
dy/dx = f'(g(x)) × g'(x)言葉で言うと:
「外側の関数を微分して、内側の関数を微分したものをかける」
別の書き方
u = g(x) とおくと:
dy/dx = (dy/du) × (du/dx)分数の形で書くと、duが約分されているように見えますね(実際には厳密な約分ではありませんが)。
直感的な理解
例え話:
速度の変化を考えてみましょう。
- 時間が1秒変わると、距離が2m変わる(du/dx = 2)
- 距離が1m変わると、温度が3度変わる(dy/du = 3)
では、時間が1秒変わると、温度は何度変わる?
2 × 3 = 6度
これが連鎖律の考え方なんです。
具体例で理解しよう
実際の計算を見ていきましょう。
例1:y = sin(x²) を微分する
ステップ1:内側と外側を見分ける
- 外側:sin( )
- 内側:x²
ステップ2:それぞれを微分
- 外側の微分:(sin u)’ = cos u
- 内側の微分:(x²)’ = 2x
ステップ3:連鎖律を適用
dy/dx = cos(x²) × 2x = 2x cos(x²)例2:y = (x³ + 1)⁵ を微分する
ステップ1:内側と外側
- 外側:( )⁵
- 内側:x³ + 1
ステップ2:それぞれを微分
- 外側の微分:(u⁵)’ = 5u⁴
- 内側の微分:(x³ + 1)’ = 3x²
ステップ3:連鎖律
dy/dx = 5(x³ + 1)⁴ × 3x² = 15x²(x³ + 1)⁴例3:y = e^(2x) を微分する
ステップ1:内側と外側
- 外側:e^( )
- 内側:2x
ステップ2:それぞれを微分
- 外側の微分:(e^u)’ = e^u
- 内側の微分:(2x)’ = 2
ステップ3:連鎖律
dy/dx = e^(2x) × 2 = 2e^(2x)例4:y = ln(x² + 1) を微分する
ステップ1:内側と外側
- 外側:ln( )
- 内側:x² + 1
ステップ2:それぞれを微分
- 外側の微分:(ln u)’ = 1/u
- 内側の微分:(x² + 1)’ = 2x
ステップ3:連鎖律
dy/dx = 1/(x² + 1) × 2x = 2x/(x² + 1)多段階の合成関数
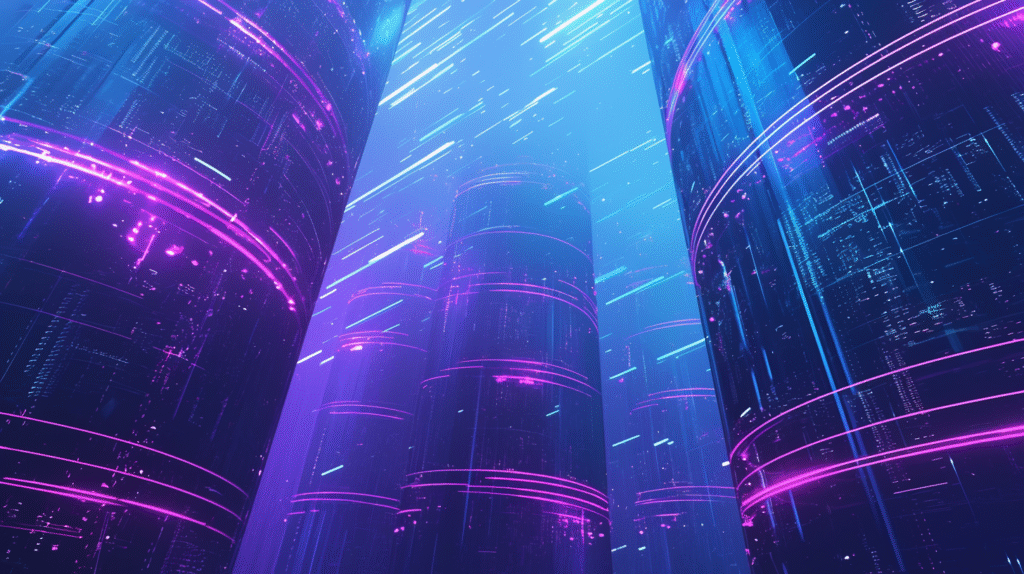
関数が3重、4重になっている場合もあります。
例:y = sin(e^(x²)) を微分する
3つの層がある:
- 最も内側:x²
- 中間:e^( )
- 最も外側:sin( )
連鎖律を2回使う:
dy/dx = cos(e^(x²)) × (e^(x²))' × (x²)'
= cos(e^(x²)) × e^(x²) × 2x
= 2x e^(x²) cos(e^(x²))考え方:
外側から順番に、玉ねぎの皮をむくように微分していきます。
よくある間違い
連鎖律でよくやってしまうミスを見てみましょう。
間違い1:内側を忘れる
問題: y = sin(3x) を微分
間違い:
dy/dx = cos(3x) ❌内側の微分(3x)’ = 3 を忘れています。
正しい:
dy/dx = cos(3x) × 3 = 3cos(3x) ✓間違い2:外側を先に計算してしまう
問題: y = (x + 1)² を微分
間違い:
y = x² + 2x + 1 に展開してから微分
dy/dx = 2x + 2 ❌(答えは合ってるが非効率)正しい:
連鎖律を使う
dy/dx = 2(x + 1) × 1 = 2(x + 1) = 2x + 2 ✓展開する方法も間違いではありませんが、複雑な式では連鎖律の方が簡単です。
間違い3:分数の微分で混乱
問題: y = 1/(x² + 1) を微分
間違い:
dy/dx = -1/(x² + 1)² ❌内側の微分を忘れています。
正しい:
y = (x² + 1)^(-1) と書き直して
dy/dx = -1(x² + 1)^(-2) × 2x = -2x/(x² + 1)² ✓積の微分・商の微分との組み合わせ
連鎖律は、他の微分公式と組み合わせて使うことがよくあります。
積の微分 + 連鎖律
問題: y = x · sin(x²) を微分
積の微分公式: (uv)’ = u’v + uv’
解答:
dy/dx = (x)' · sin(x²) + x · (sin(x²))'
= 1 · sin(x²) + x · cos(x²) · 2x
= sin(x²) + 2x² cos(x²)商の微分 + 連鎖律
問題: y = sin(x²)/x を微分
商の微分公式: (u/v)’ = (u’v – uv’)/v²
解答:
dy/dx = [cos(x²)·2x · x - sin(x²)·1] / x²
= [2x² cos(x²) - sin(x²)] / x²多変数関数の連鎖律
変数が複数ある場合の連鎖律です。
偏微分での連鎖律
z = f(x, y) で、x = g(t), y = h(t) のとき:
dz/dt = (∂z/∂x)(dx/dt) + (∂z/∂y)(dy/dt)例:z = x² + y², x = t, y = 2t のとき dz/dt を求める
解答:
∂z/∂x = 2x
∂z/∂y = 2y
dx/dt = 1
dy/dt = 2
dz/dt = 2x · 1 + 2y · 2
= 2t + 2(2t) · 2
= 2t + 8t = 10t実用例:深層学習の誤差逆伝播
連鎖律は、機械学習で非常に重要な役割を果たしています。
ニューラルネットワークでの連鎖律
構造:
入力 x → 層1: z₁ = w₁x + b₁ → 活性化: a₁ = σ(z₁)
→ 層2: z₂ = w₂a₁ + b₂ → 出力: y = σ(z₂)損失関数 L に対する重みw₁の勾配:
∂L/∂w₁ = (∂L/∂y) × (∂y/∂z₂) × (∂z₂/∂a₁) × (∂a₁/∂z₁) × (∂z₁/∂w₁)これが連鎖律の連続適用(バックプロパゲーション)です。
簡単な例で理解
y = σ(wx + b)、損失 L = (y – t)² のとき、∂L/∂w を求める
ステップごとに:
∂L/∂y = 2(y - t)
∂y/∂z = σ'(z) (z = wx + b)
∂z/∂w = x
連鎖律:
∂L/∂w = ∂L/∂y × ∂y/∂z × ∂z/∂w
= 2(y - t) × σ'(wx + b) × xこれがニューラルネットワークの学習の基礎なんですよ。
物理での応用例
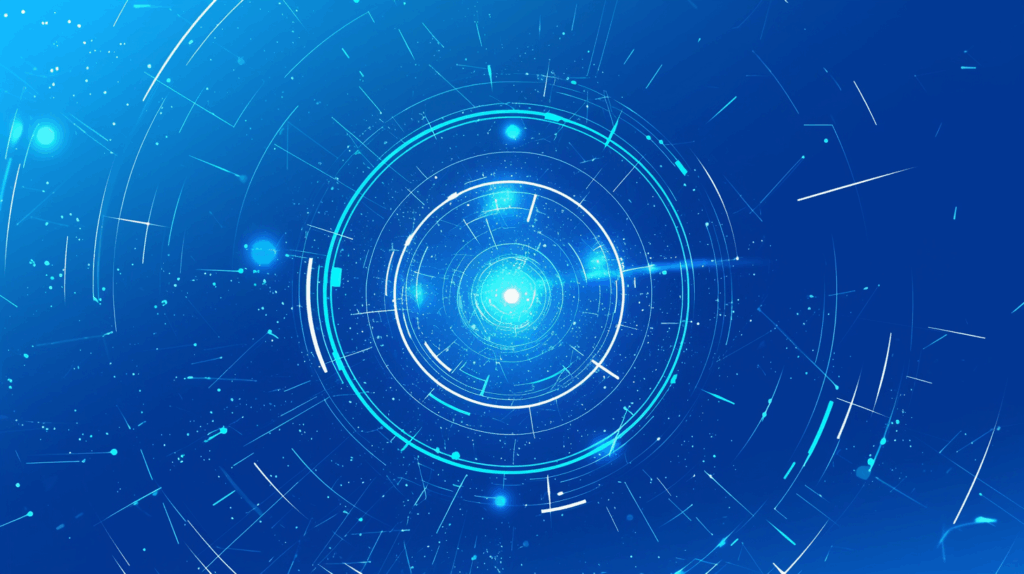
連鎖律は物理学でも頻繁に使われます。
例1:速度と加速度
位置: x(t) = sin(ωt)
速度: v = dx/dt
連鎖律を使って:
v = dx/dt = cos(ωt) × ω = ω cos(ωt)加速度: a = dv/dt
もう一度連鎖律:
a = dv/dt = -ω sin(ωt) × ω = -ω² sin(ωt)例2:熱力学
温度Tが時間tの関数、エネルギーEが温度の関数のとき:
dE/dt = (dE/dT) × (dT/dt)温度変化率が分かれば、エネルギー変化率も計算できますね。
パラメトリック方程式での微分
パラメータ表示された曲線の微分にも連鎖律が使えます。
例:x = t², y = t³ のとき dy/dx を求める
直接は求められないので、連鎖律を使う:
dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)
dy/dt = 3t²
dx/dt = 2t
dy/dx = 3t² / 2t = (3/2)t逆関数の微分
逆関数の微分も、連鎖律から導けます。
逆関数の微分公式
y = f(x) の逆関数を x = f⁻¹(y) とすると:
dx/dy = 1 / (dy/dx)例:y = x³ の逆関数 x = ∛y を微分
元の関数:
dy/dx = 3x²逆関数の微分:
dx/dy = 1 / (3x²) = 1 / (3(∛y)²) = 1 / (3y^(2/3))練習問題
理解を深めるための問題です。
問題1
y = cos(5x) を微分せよ
解答:
dy/dx = -sin(5x) × 5 = -5sin(5x)問題2
y = e^(-x²) を微分せよ
解答:
dy/dx = e^(-x²) × (-2x) = -2xe^(-x²)問題3
y = ln(sin x) を微分せよ
解答:
dy/dx = 1/(sin x) × cos x = cos x / sin x = cot x問題4
y = √(x² + 1) を微分せよ
解答:
y = (x² + 1)^(1/2)
dy/dx = (1/2)(x² + 1)^(-1/2) × 2x
= x / √(x² + 1)連鎖律の証明(興味がある方へ)
なぜ連鎖律が成り立つのか、簡単な証明を紹介します。
直感的な証明
y = f(u), u = g(x) とする
微小変化を考えると:
Δy ≈ f'(u) × Δu (yの変化は、f'(u)にuの変化をかけたもの)
Δu ≈ g'(x) × Δx (uの変化は、g'(x)にxの変化をかけたもの)
Δyを代入:
Δy ≈ f'(u) × g'(x) × Δx
両辺をΔxで割る:
Δy/Δx ≈ f'(u) × g'(x)
Δx → 0 の極限を取ると:
dy/dx = f'(u) × g'(x) = f'(g(x)) × g'(x)これが連鎖律です。
連鎖律を使いこなすコツ
上手に使うためのポイントです。
コツ1:内側と外側を明確にする
最初に、どこが内側でどこが外側かをはっきりさせましょう。
y = sin(x²)
└外┘└内┘コツ2:u = … と置き換える
複雑な場合は、内側の関数に名前をつけると分かりやすくなります。
y = sin(x²)
u = x² とおくと
y = sin(u)コツ3:段階的に計算する
一度にすべてやろうとせず、順番に計算しましょう。
- 外側を微分(内側はそのまま)
- 内側を微分
- かけ算する
コツ4:チェックする方法
答えが合っているか不安なときは、簡単な値で確認できます。
元の関数と微分した関数に、x = 0 や x = 1 などを代入して、数値微分と比較してみると良いですね。
よくある質問
Q: 連鎖律はいつ使うの?
A: 「関数の中に関数が入っている」ときは必ず使います。sin(x²)、e^(3x)、(x+1)⁵ など、カッコや指数・関数記号の中に変数の式がある場合ですね。
Q: 連鎖律を使わなくても答えは出せる?
A: 式を展開できる場合は展開してから微分することもできます。ただし、複雑な式では展開が大変なので、連鎖律を使う方が簡単ですよ。
Q: 三角関数の合成関数が苦手です
A: sin(○)の形なら、「外側はsinのまま微分してcosになる、そして○の微分をかける」と覚えましょう。○が何であっても手順は同じです。
Q: 深層学習を勉強するのに連鎖律は必須?
A: はい、誤差逆伝播(バックプロパゲーション)は連鎖律そのものです。理解していると、なぜそうなるのかが分かって学習がスムーズになります。
Q: 暗算でできるようになる?
A: 練習すれば、簡単な合成関数なら暗算でできるようになります。sin(3x)の微分は3cos(3x)、e^(2x)の微分は2e^(2x)、というように自動的に出てくるようになりますよ。
まとめ:連鎖律は微分の必須テクニック
連鎖律について、重要なポイントをおさらいします。
今日学んだこと:
- 連鎖律は合成関数を微分するための公式
- 基本形:dy/dx = f'(g(x)) × g'(x)
- 外側を微分して、内側を微分したものをかける
- 3重、4重の合成関数も同じ手順で微分できる
- 物理や機械学習で広く使われる
- 積・商の微分や偏微分とも組み合わせる
- 内側と外側を見分けることが大切
- 段階的に計算すると間違いにくい
連鎖律は、微分積分学で最も重要な技法の一つです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、何度も練習すれば必ずできるようになります。特に、深層学習やデータサイエンスを学ぶなら、連鎖律の理解は欠かせませんよ。
まずは簡単な例から始めて、徐々に複雑な問題にチャレンジしてみてください。パターンが見えてくれば、連鎖律を使った微分が楽しくなってくるはずです!
関連記事:
- 微分の基本公式一覧
- 偏微分入門ガイド
- 深層学習の数学的基礎