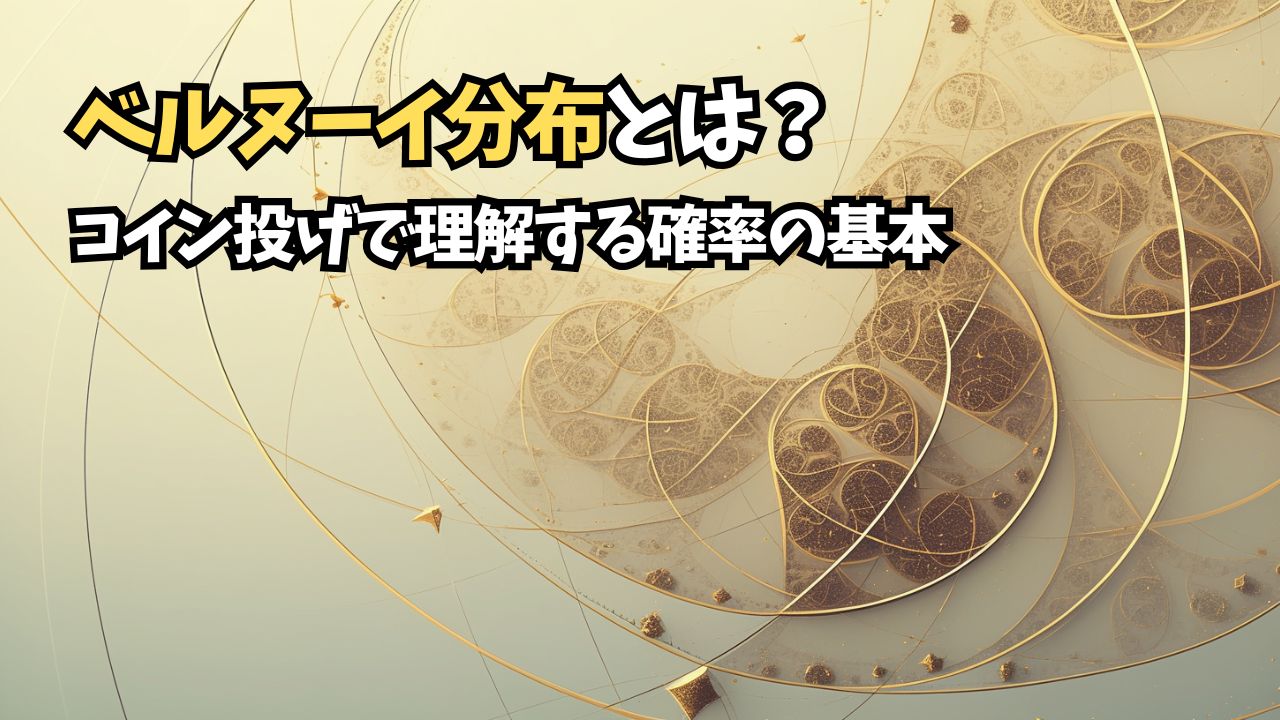「ベルヌーイ分布」という言葉を聞くと、なんだか難しそうって思いますよね。 でも実は、私たちの日常生活のあちこちに隠れている、とてもシンプルな確率の考え方なんです。
コインを投げて表か裏か。 試験に合格するか不合格か。 明日雨が降るか降らないか。
こんな「2つの結果しかない」出来事を数学的に表現したものが、ベルヌーイ分布です。 この記事を読み終わる頃には、「なんだ、そんなに簡単なことだったのか!」と思えるはずですよ。
そもそもベルヌーイ分布って何?

一言で説明すると
ベルヌーイ分布は、「成功」か「失敗」、「YES」か「NO」のように、結果が2つしかない試行(何かを試すこと)の確率を表す方法です。
スイスの数学者ヤコブ・ベルヌーイさんが考えたので、この名前がついています。 でも、名前は覚えなくても大丈夫。 大切なのは中身を理解することです。
身近な例で考えてみよう
コイン投げを例にしましょう。
普通のコインを投げたとき:
- 表が出る確率:50%(0.5)
- 裏が出る確率:50%(0.5)
これがベルヌーイ分布の最もシンプルな例です。
どちらか一方が必ず起きて、両方同時に起きることはありません。
ベルヌーイ分布の3つの特徴
特徴1:結果は必ず2つだけ
ベルヌーイ分布では、起こりうる結果は2つだけと決まっています。
3つ以上の結果がある場合は、ベルヌーイ分布とは呼びません。
良い例:
- サイコロで「6が出る」か「6以外が出る」か
- くじ引きで「当たり」か「はずれ」か
- 商品が「良品」か「不良品」か
ダメな例:
- サイコロの目(1〜6の6種類ある)
- じゃんけんの結果(グー・チョキ・パーの3種類)
特徴2:確率は変わらない
同じ条件で何回試しても、確率は一定です。 コインを100回投げても、101回目に表が出る確率は変わらず50%のままです。
「さっき5回連続で表が出たから、次は裏が出やすいはず」 こんな風に考えがちですが、コインに記憶はありません。
毎回、まっさらな気持ちで50%なんです。
特徴3:各試行は独立している
前の結果が次の結果に影響しないということです。
1回目の結果と2回目の結果は、完全に別物として扱います。
実際の活用場面

ビジネスでの活用例
品質管理
工場で製品を検査するとき、良品か不良品かを判定します。 不良品が出る確率が分かれば、100個作ったときに何個くらい不良品が出るか予測できます。
例:不良品率が2%の場合
- 1個の製品が良品である確率:98%
- 1個の製品が不良品である確率:2%
マーケティング
広告を見た人が商品を買うか買わないか。 クリック率やコンバージョン率の計算に使われています。
例:Web広告のクリック率が3%の場合
- クリックする確率:3%
- クリックしない確率:97%
医療・研究での活用例
新薬の効果を調べる臨床試験でも使われます。 薬が「効く」か「効かない」かを確率で表現します。
ただし、実際の医療現場では、もっと複雑な統計手法と組み合わせて使うことがほとんどです。
スポーツでの活用例
野球選手の打率も、実はベルヌーイ分布の考え方が基本にあります。 打席に立って「ヒット」か「アウト」か。
打率3割の選手なら:
- ヒットを打つ確率:30%
- アウトになる確率:70%
ベルヌーイ分布の重要な数値
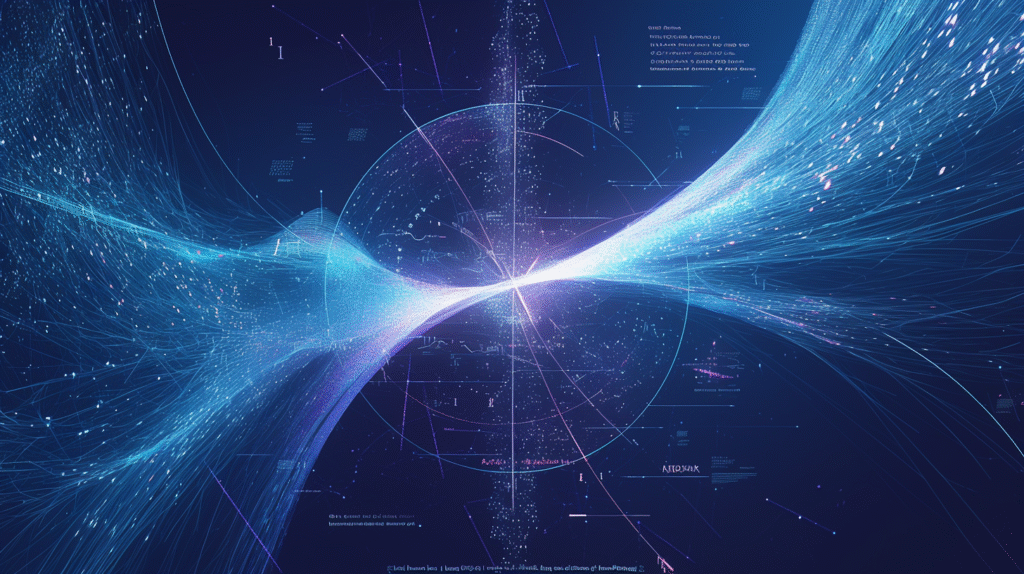
期待値(平均値)
「期待値」というのは、たくさん試したときの平均的な結果のことです。
成功を1、失敗を0として数値化すると、期待値は成功確率と同じになります。
例:コイン投げで表を1点、裏を0点とした場合
- 期待値 = 0.5(つまり平均すると0.5点)
100回投げたら、だいたい50回くらい表が出る、という意味です。
分散(ばらつき)
結果がどれくらいばらつくかを表す数値です。 成功確率が50%のときに最も大きくなります。
つまり、コイン投げのような五分五分の勝負が、一番予測しにくいということですね。
ベルヌーイ分布と二項分布の関係
ここで少し発展的な話をしましょう。
ベルヌーイ分布を何回も繰り返すと、「二項分布」という別の分布になります。
例えば:
- ベルヌーイ分布:コインを1回投げて表か裏か
- 二項分布:コインを10回投げて表が何回出るか
ベルヌーイ分布は二項分布の特別な場合(1回だけの場合)と考えることもできます。 親子関係みたいなものですね。
よくある誤解と注意点
誤解1:「確率50%なら、2回に1回は必ず起きる」
これは間違いです。 確率50%でも、10回連続で同じ結果が出ることもあります。 確率は「長い目で見たときの割合」であって、短期的な保証ではありません。
誤解2:「前の結果が次に影響する」
ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)と呼ばれる有名な勘違いです。 ルーレットで赤が5回続いたら、次は黒が出やすい? いいえ、確率は変わりません。
誤解3:「複雑な現象もベルヌーイ分布で表せる」
株価の上下や天気の変化など、複雑な要因が絡む現象は、単純なベルヌーイ分布では表現できません。 あくまで「2つの結果」で「確率が一定」の場合だけです。
実際に計算してみよう
簡単な計算例
コインを投げて表が出る確率が0.6(60%)の少し偏ったコインがあるとします。
このコインを1回投げたとき:
- 表が出る確率:0.6
- 裏が出る確率:0.4(1 – 0.6 = 0.4)
期待値:0.6(平均的には0.6回表が出る) 分散:0.6 × 0.4 = 0.24
応用計算
このコインを3回投げて、全部表が出る確率は? 0.6 × 0.6 × 0.6 = 0.216(21.6%)
意外と低いと思いませんか? 60%の確率でも、3回連続となると約20%まで下がってしまうんです。
プログラミングでの実装
プログラミングを学んでいる人のために、簡単な実装例も紹介します。
Pythonでのシンプルな例:
import random
def bernoulli_trial(p):
"""確率pで1を、確率(1-p)で0を返す"""
if random.random() < p:
return 1 # 成功
else:
return 0 # 失敗
# 確率0.7で成功する試行を10回実施
results = [bernoulli_trial(0.7) for _ in range(10)]
print(f"結果: {results}")
print(f"成功回数: {sum(results)}")
このように、実際にシミュレーションすることで、理論と実際の違いを体感できます。
まとめ:ベルヌーイ分布は確率の基本中の基本
ベルヌーイ分布について、だいぶ理解が深まったのではないでしょうか。
要点をまとめると:
- 結果が2つだけの試行を扱う確率分布
- 各試行は独立していて、確率は一定
- コイン投げが最も分かりやすい例
- ビジネスから研究まで幅広く活用されている
- 二項分布の基礎になる重要な概念
難しそうに見えた「ベルヌーイ分布」も、実はとてもシンプルな考え方でした。 この基本を理解しておけば、もっと複雑な統計の話も理解しやすくなります。
日常生活で「これって2つの結果しかないな」と気づいたとき、それはベルヌーイ分布の出番です。 合格か不合格か、成功か失敗か、YESかNOか。
世の中には、意外とたくさんのベルヌーイ分布が隠れています。 今日から、ちょっと違った目で確率を見ることができるようになったはずです。
統計学って、案外面白いでしょう?