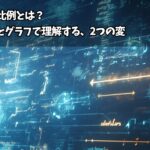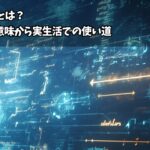「このピザ、8等分にカットしてあるけど、本当に同じ大きさ?」
「左右の靴、ちゃんと同じ形になってる?」
「この三角定規、友達のと全く同じ?」
実は、これらの「同じかどうか」を証明する方法があるんです。
それが「合同条件」という数学のルールです。
中学2年で習う合同条件。 「三辺相等」「二辺夾角相等」といった難しい言葉が出てきて、混乱した人も多いはず。
でも実は、合同条件は「パズルのピース」を見分けるようなもの。
コツさえつかめば、図形が同じかどうかを一瞬で判断できるようになります。
この記事では、合同とは何か、三角形の3つの合同条件、そして証明問題の解き方まで、数学が苦手な人でも分かるように解説していきます。
合同の基本:ぴったり重なる図形の秘密
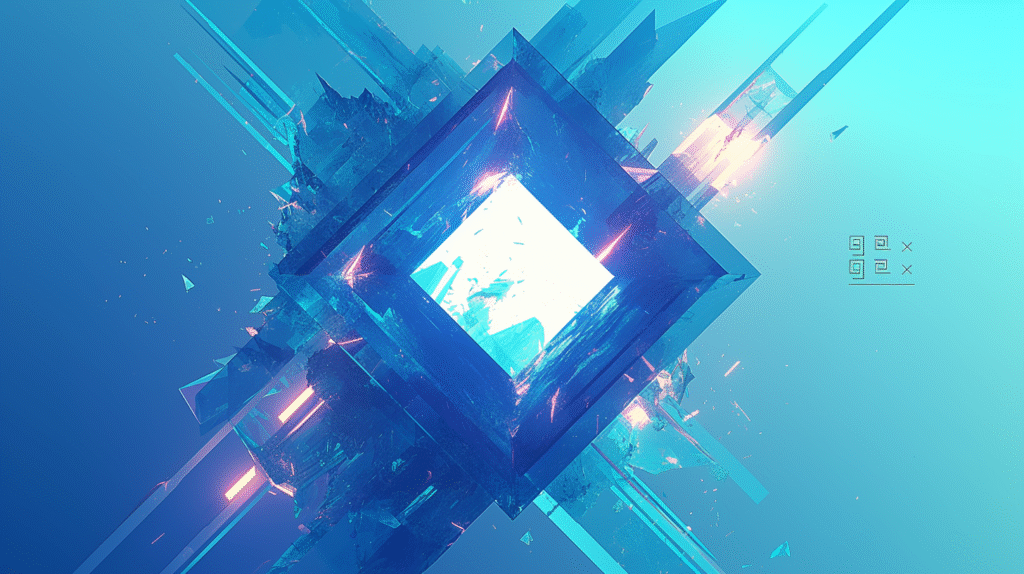
そもそも合同って何?
合同を一言で説明すると、こうなります。
合同とは: 「形も大きさも全く同じ図形」のこと
もっと簡単に言うと: 「コピーしたような図形」 「ぴったり重ね合わせられる図形」
具体例で考えてみましょう:
- トランプのハートのA 2枚 → 合同
- 左足と右足の靴底 → 合同(裏返せば)
- 同じ型で作ったクッキー → 合同
ポイント:
- 回転させてもOK
- 裏返してもOK
- でも大きさは変えちゃダメ
合同な図形の性質
合同な図形には、大切な性質があります。
対応する部分が等しい:
- 対応する辺の長さが等しい
- 対応する角の大きさが等しい
- 周の長さが等しい
- 面積が等しい
三角形ABCと三角形DEFが合同なら:
- AB = DE(対応する辺)
- ∠A = ∠D(対応する角)
- 周の長さも面積も同じ
記号の書き方:
- 合同は「≡」で表す
- △ABC ≡ △DEF
- 頂点の順番が大事!
合同と相似の違い
よく混同される「相似」との違いを理解しましょう。
合同:
- 形も大きさも同じ
- コピーのような関係
- 拡大・縮小はダメ
相似:
- 形は同じ、大きさは違ってもOK
- 拡大コピーのような関係
- 角度は同じ、辺の比が一定
例えで理解:
- 合同 → 同じサイズの写真2枚
- 相似 → L版とはがきサイズの同じ写真
この章のポイント:合同は「完全に同じ」図形。
回転や裏返しはOKだけど、大きさは変えられない。対応する部分はすべて等しくなる。
三角形の合同条件:3つの判定方法
条件1:三辺相等(さんぺんそうとう)
最も分かりやすい条件から始めましょう。
三辺相等とは: 「3つの辺の長さがすべて等しいとき、三角形は合同」
なぜこれで合同と言える?
- 3辺の長さが決まれば、三角形の形は1つに決まる
- 組み立て方は1通りしかない
実例で考える:
- 3cm、4cm、5cmの棒を3本用意
- これで三角形を作ると、誰が作っても同じ形
- だから合同!
覚え方: 「辺・辺・辺」→ すべて辺の情報
条件2:二辺夾角相等(にへんきょうかくそうとう)
少し難しい名前ですが、意味は簡単です。
二辺夾角相等とは: 「2つの辺とその間の角が等しいとき、三角形は合同」
「夾角」の意味:
- 「夾」は「はさむ」という意味
- 2辺にはさまれた角のこと
なぜこれで合同?
- 2辺とその間の角が決まれば、残りの頂点の位置が決まる
- コンパスと定規で作図すると、1つの形しかできない
実例:
- サンドイッチを斜めに切る
- 切り口の2辺と角度が同じなら、同じ三角形
覚え方: 「辺・角・辺」→ 角が辺にはさまれている
条件3:一辺両端角相等(いっぺんりょうたんかくそうとう)
3つ目の条件です。
一辺両端角相等とは: 「1つの辺とその両端の角が等しいとき、三角形は合同」
「両端角」の意味:
- 1つの辺の両端にある2つの角
- 辺を底辺と見たときの左右の角
なぜこれで合同?
- 1辺と両端の角が決まれば、残りの2辺の向きが決まる
- 2本の直線の交点は1つだけ
実例:
- 屋根の形を決めるとき
- 底辺の長さと両端の角度が同じなら、同じ屋根
覚え方: 「角・辺・角」→ 辺が角にはさまれている
二角夾辺は条件にならない?
よくある疑問:「角・角・辺」はダメなの?
実は、場合によります:
- その辺が「2角の間」なら → OK(一辺両端角と同じ)
- その辺が「2角の間じゃない」なら → ダメ
理由:
- 2角が決まれば、3つ目の角も決まる(内角の和180°)
- でも、辺の位置によっては大きさが変わる(相似になる)
この章のポイント:三角形の合同条件は3つ。
「辺辺辺」「辺角辺」「角辺角」と覚えよう。
それぞれ、なぜ合同になるか理解することが大切。
合同の証明:ステップバイステップで解く

証明問題の基本的な流れ
合同の証明には、決まった手順があります。
証明の4ステップ:
- 合同を示したい三角形を明確にする
- 等しい辺や角を見つける
- 合同条件に当てはめる
- 結論を述べる
例題: 「AB = AC の二等辺三角形で、BD = CD のとき、△ABD ≡ △ACD を証明せよ」
証明の書き方
実際の証明を書いてみましょう。
【証明】 △ABDと△ACDにおいて
仮定より
- AB = AC … ①
- BD = CD … ②
共通な辺だから
- AD = AD … ③
①②③より、三辺相等 したがって、△ABD ≡ △ACD
ポイント:
- 「〜において」で始める
- 理由を明確に書く
- 最後は「したがって」でまとめる
等しい部分の見つけ方
証明で重要なのは、等しい部分を見つけることです。
見つけ方のコツ:
- 仮定を確認
- 問題文に書いてある条件
- 「二等辺三角形」「平行四辺形」などの性質
- 共通部分を探す
- 共通な辺
- 共通な角
- 図形の性質を使う
- 対頂角は等しい
- 平行線の錯角・同位角
- すでに証明したことを使う
- 前の小問の結果
- 合同から導かれる性質
よく使う図形の性質
証明でよく使う性質をまとめます。
二等辺三角形:
- 2辺が等しい
- 底角が等しい
平行四辺形:
- 対辺が等しい
- 対角が等しい
- 対角線は互いに他を二等分
正三角形:
- 3辺がすべて等しい
- 3角がすべて60°
円:
- 半径はすべて等しい
- 円周角の定理
この章のポイント:証明は順序立てて書くことが大切。等しい部分を3つ見つけて、合同条件に当てはめる。図形の性質を活用しよう。
よくある間違いと攻略法
間違い1:対応順序を間違える
「△ABC ≡ △DEF」の意味を誤解しがちです。
よくある間違い:
- A→D、B→E、C→F が対応
- これを A→E、B→D と間違える
正しい理解:
- 書いた順番通りに対応
- △ABC ≡ △FED なら A→F、B→E、C→D
対策:
- 頂点に番号をつける
- 対応表を作る
- 色分けして考える
間違い2:見た目で判断する
「なんとなく同じに見える」では証明になりません。
ダメな例:
- 「図を見ると同じ大きさ」
- 「きっと等しいはず」
- 「対称だから合同」
正しい証明:
- 必ず3つの条件を示す
- 数値や記号で表現
- 論理的に説明
間違い3:条件の不足
2つの条件だけでは合同と言えません。
不十分な例:
- 2辺が等しい → まだ形が決まらない
- 2角が等しい → 大きさが決まらない
必要十分:
- 必ず3つの情報が必要
- 辺3つ、辺2つ角1つ、辺1つ角2つ
間違い4:合同条件の誤用
条件を正確に使えていない例です。
間違い例:
- 「二辺と一角が等しい」→ 角の位置は?
- 「一辺と二角が等しい」→ 角の位置は?
正確に:
- 二辺夾角(間の角)
- 一辺両端角(両端の角)
- 位置関係が重要
まとめ:合同条件で図形の世界が広がる
ここまで、図形の合同条件について詳しく見てきました。
押さえておきたいポイント:
合同の基本:
- 形も大きさも完全に同じ
- 回転・裏返しはOK
- 対応する部分がすべて等しい
- 記号は「≡」
- 相似とは違う(大きさも同じ)
三角形の合同条件:
- 三辺相等(辺・辺・辺)
- 二辺夾角相等(辺・角・辺)
- 一辺両端角相等(角・辺・角)
証明のコツ:
- 4ステップで順序立てて
- 等しい部分を3つ見つける
- 図形の性質を活用
- 対応順序に注意
- 論理的に説明