中国神話に登場する太陽の女神「羲和(ぎわ、またはぎか)」をご存知ですか?
彼女は10個の太陽を産んだ母神であり、同時に太陽を運ぶ車を操る御者でもあるという、不思議な二面性を持つ神様なんです。
古代中国の人々が空を見上げたとき、そこには羲和が龍車を駆って太陽を運ぶ姿が見えていたのかもしれません。また、東方の海で10個の太陽に水浴びをさせる慈愛深い母の姿も想像されていました。
この記事では、中国神話における太陽信仰の中心的存在である羲和について、その正体から原典での記述、射日神話との関連まで詳しく解説します。
羲和とは何者か
羲和(拼音:Xīhé)は、中国神話に登場する太陽にまつわる神です。
基本的な属性は以下の通り:
- 名前: 羲和(ぎわ/ぎか)
- 読み方: 「和」の字は呉音で「ワ」、漢音で「カ」と読むため、ギワとギカの両方の読み方があります
- 役割: 太陽の母、または太陽の御者
- 夫: 帝俊(ていしゅん、帝嚳とも)
- 子供: 10個の太陽
興味深いのは、羲和の神話には大きく分けて二つの系統があることです。
一つは「十日の母」としての羲和。もう一つは「日御(太陽の御者)」としての羲和です。
原典での記述
羲和の神話は、複数の古典文献に記録されています。それぞれの文献で描かれる羲和の姿は微妙に異なっており、神話の変遷を物語っています。
『山海経』大荒南経:太陽の母としての羲和
最も古い記録は『山海経』大荒南経です。
原文には次のように記されています:
「東南海之外、甘水之間、有羲和之國。有女子名曰羲和、方浴日於甘淵。羲和者、帝俊之妻、生十日。」
つまり、東南海の外、甘水のほとりに羲和国があり、そこに羲和という女性がいて、甘淵で太陽に水浴びをさせていた。羲和は帝俊の妻で、10個の太陽を産んだ、という内容です。
ここでの羲和は、明確に「太陽の母」として描かれています。
10個の太陽とは、古代中国の暦における「十日」を表しており、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸という十干に対応しています。
羲和が太陽を水浴びさせる「甘淵」は、同じ『山海経』の別の箇所で「湯谷」とも呼ばれる場所です。そこには扶桑という巨大な神樹があり、10個の太陽が湯浴みをしていたとされています。
これらの太陽は1日に1個ずつ扶桑の枝から昇り、10日で一巡りする「旬」という暦の単位の基になっています。
『楚辞』『淮南子』:太陽の御者としての羲和
一方、戦国時代の詩人・屈原が著した『楚辞』離騷には、全く異なる羲和の姿が登場します。
「吾令羲和弭節兮、望崦嵫而勿迫。」
これは「私は羲和に命じて鞭を止めさせ、崦嵫の山に迫らないようにした」という意味です。
ここでの羲和は、太陽車を操る「御者」として描かれています。
『淮南子』天文訓にはさらに詳しく、羲和が六頭の龍に引かれる車で太陽を運んでいると記されています。これはギリシャ神話の太陽神ヘーリオスが馬車で太陽を運ぶ姿と似ていますが、中国神話では馬ではなく龍が車を引くという点が特徴的です。
『尚書』堯典:天文官としての羲和
さらに後の時代、儒教の経典である『尚書』堯典では、羲和は神話から歴史へと降りてきます。
堯帝が羲和に命じて、太陽・月・星を観測させ、人々に農事暦を授けたという記述があります。
ここでは羲和は羲氏と和氏の総称とされ、羲仲・羲叔・和仲・和叔という4人の天文官に分けられています。彼らは東西南北の四方に配され、天を司ったとされています。
これは、太陽の母神あるいは御者だった羲和が、後の時代に官職として歴史化された例と考えられています。
射日神話との深い関連
羲和の10個の太陽は、中国神話で最も有名な射日神話と深く関わっています。
伝説によると、堯帝の時代、羲和が産んだ10個の太陽が勝手に一度に空に現れてしまいました。
通常は1日に1個ずつ交代で空を照らしていたのですが、10個が同時に現れたため、地上は灼熱地獄となり、草木は枯れ、人々は苦しみました。
困った堯帝は、天帝である帝俊に助けを求めます。帝俊は弓の名手である后羿(こうげい)を地上に遣わし、紅色の弓と白羽の矢を与えました。
后羿は、最初は威嚇によって太陽たちを元通りにしようとしましたが効果がなく、仕方なく9個の太陽を射落としました。こうして地上には1個の太陽だけが残り、平穏が戻ったのです。
この神話に登場する三足烏(さんそくう)は、羲和の子供である10個の太陽の正体とされています。
暦との密接な関係
羲和の神話は、古代中国の暦法と深く結びついています。
10個の太陽が交代で空を照らすという設定は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)を10日として一まとめにした「旬」という暦の単位の起源とされています。
現代でも、1ヶ月を3つに分けて「上旬」「中旬」「下旬」と呼ぶ習慣は、この十日説話に由来しているんです。
また、『尚書』堯典では、羲和(羲仲・羲叔・和仲・和叔)が天文を観測し、暦を制定する役割を担っていました。
このように、羲和は単なる神話上の存在ではなく、中国古代の時間認識や暦法の基礎と深く関わる重要な神格だったのです。
神話の変遷:母神から御者へ、そして官職へ
羲和の神話には興味深い変遷があります。
学者の御手洗勝は、羲和は本来、太陽神そのものであったと解釈しています。竜車を駆る太陽神だった羲和が、時代が下るにつれて太陽と御者が別々の存在と考えられるようになり、「太陽の御者」と「太陽の母」という二つの姿に分かれていったというのです。
さらに時代が進むと、神話人物としての羲和は、『尚書』において歴史上の天文官として記録されるようになりました。
これは中国神話全体に見られる傾向で、神話が歴史化される過程の典型的な例といえます。黄帝、后羿、鲧なども同様に、神話上の存在から歴史上の人物へと変化していきました。
現代への影響
羲和は古代の神話に留まらず、現代にも影響を与え続けています。
中国の太陽観測衛星「羲和号」
2021年10月、中国は初の太陽観測衛星を打ち上げました。
この衛星は当初「Chinese H-alpha Solar Explorer(CHASE)」と呼ばれていましたが、打ち上げ成功に伴い、中国神話の太陽神にちなんで「羲和号」と名付けられました。
数千年前の神話が、最新の宇宙開発にその名を残しているというのは、とてもロマンチックですね。
詩歌の中の羲和
羲和は、中国の詩歌において頻繁に登場するモチーフでもあります。
屈原の「吾令羲和弭節兮、望崦嵫而勿迫」(私は羲和に鞭を止めさせ、時の流れを遅くしようとする)という表現は、後の詩人たちに大きな影響を与えました。
唐の詩人・李白は「長歌行」で「大力運天地、羲和無停鞭」(天地は自然の力で動き、羲和の鞭は決して止まらない)と詠み、時間の不可逆性を表現しています。
また「日出入行」では「羲和!羲和!汝奚汩没于荒淫之波?」(羲和よ、なぜ太陽を海に沈めるのか)と呼びかけています。
このように、羲和は「時間の流れ」や「太陽の運行」を象徴する存在として、文学作品の中で生き続けているのです。
羲和に関する豆知識
河姆渡文化との関連
羲和のモチーフは、紀元前5000年〜紀元前3300年頃に杭州湾一帯に栄えた河姆渡文化にまで遡ると考えられています。
考古学者の林巳奈夫は、河姆渡文化の遺物に見られる「太陽を背負う一対の鳥」の図像が、太陽を運ぶ車を操る羲和の原型ではないかと指摘しています。
常羲との関係
『山海経』大荒西経には、帝俊のもう一人の妻「常羲(じょうぎ)」が登場します。
常羲は12個の月を産んだとされ、羲和と対をなす存在です。羲和が太陽(10個)を産み、常羲が月(12個)を産んだという構造は、太陽暦(十干)と太陰暦(十二支)の対応を示していると考えられています。
日本への影響
日本にも羲和の影響が見られます。
『日本書紀』には、推古天皇10年(602年)に百済の僧・観勒が暦本や天文書を伝えたという記録があり、そこには中国の暦法の影響が色濃く残っています。
また、平安時代の陰陽道においても、中国由来の天文思想が取り入れられており、その中に羲和の概念も含まれていた可能性があります。
参考情報
関連記事
この記事で参照した情報源
一次資料(原典)
- 『山海経』大荒南経・海外東経・大荒東経 – 羲和が太陽を産み、水浴びをさせる場面の記述
- 『楚辞』離騷・天問 – 屈原による羲和の御者としての描写
- 『淮南子』天文訓 – 羲和が六頭の龍に引かれる太陽車を御する記述
- 『尚書』堯典 – 羲和が天文官として暦を制定する記述
学術資料・研究論文
- 御手洗勝『中国思想史』 – 羲和の神話的変遷に関する研究
- 林巳奈夫『中国古代の神々』 – 河姆渡文化と羲和の関連についての考察
- 袁珂『中国神話伝説』 – 中国神話全般の研究
参考になる外部サイト
- Wikipedia「羲和」 – 基本情報の確認
- コトバンク「羲和」 – 日本語での解説
- 中国知網 – 中国の学術論文データベース
まとめ
羲和は中国神話における太陽の女神で、10個の太陽を産んだ母神であり、同時に太陽車を操る御者でもあるという二面性を持つ存在です。
主なポイントをまとめると:
- 『山海経』では帝俊の妻で10個の太陽の母として登場
- 『楚辞』『淮南子』では太陽車を操る御者として描かれる
- 『尚書』では4人の天文官に分かれて歴史化される
- 射日神話の10個の太陽は羲和の子供たち
- 「旬」という暦の単位の起源に関わる
- 2021年の中国の太陽観測衛星「羲和号」にその名が使われている
羲和の神話は、古代中国の人々の太陽信仰や時間認識、そして神話が歴史化していく過程を物語る貴重な資料なんです。
夜空を見上げたとき、あるいは朝日を眺めたとき、そこに羲和が龍車を駆る姿を想像してみると、古代の人々の豊かな想像力に触れることができるかもしれませんね。





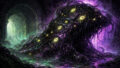

コメント