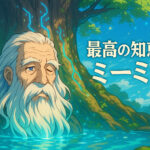高貴な生まれなのに、父の死で人生が一変してしまったら、あなたはどうしますか?
平安時代、そんな運命に翻弄された一人の女性がいました。彼女の名は「空蝉(うつせみ)」。光源氏からの求愛を拒み続けた、誇り高い女性です。
この記事では、源氏物語に登場する空蝉という女性と、彼女をめぐる物語について詳しくご紹介します。
概要
空蝉は、『源氏物語』に登場する女性の一人で、17歳の光源氏が出会った中流階級の女性です。
物語としての「空蝉」は、源氏物語全54帖のうち第3帖にあたります。第2帖「帚木(ははきぎ)」、第4帖「夕顔」とあわせて「帚木三帖」と呼ばれることもあるんです。
空蝉という名前は、実は本名ではありません。光源氏が彼女の残した着物をセミの抜け殻に例えて詠んだ和歌から付けられた通称なんですね。
彼女が主に登場するのは「帚木」「空蝉」「関屋」の三巻で、光源氏の若い頃に大きな影響を与えた女性の一人として描かれています。
空蝉ってどんな人?
空蝉は、とても慎み深く控えめな女性でした。
生まれと境遇
空蝉の人生は、まさにジェットコースターのような変化を経験しています。
元々の身分
- 父は中納言兼衛門督という高い地位の貴族
- 桐壺帝(天皇)への入内(宮中に上がること)さえ予定されていた
- 上流貴族の娘として何不自由なく育った
転落後の境遇
- 父の死により後ろ盾を失う
- 心ならずも伊予介(いよのすけ:地方官の次官)の後妻となる
- 受領階級(地方官)の妻という「下の身分」に零落
伊予介は彼女よりずっと年上で、前妻の娘(軒端荻)とほとんど同年輩という、かなりの年の差結婚でした。夫は空蝉を大切にしていましたが、当の空蝉は身分が下がったことを恥じており、夫への愛も薄かったのです。
外見と性格
空蝉の魅力は、派手な美しさではありませんでした。
外見的特徴
- 小柄な体格
- 決して美女とは言えない地味な容貌
- でも、立ち居振る舞いが際立っている
- 趣味が良く、教養が感じられる
性格
- 控えめで慎み深い
- 聡明で、自分の立場をよく理解している
- プライドが高く、品位を守ろうとする
- 悩み迷いながらも、最後まで矜持を保つ
実は、この空蝉のモデルは、作者の紫式部自身ではないかとも言われているんです。境遇や身分が似ていることから、そう推測されています。
光源氏との出会い
空蝉と光源氏の運命的な出会いは、ある偶然から始まりました。
きっかけは「雨夜の品定め」
光源氏17歳の五月雨の夜、友人たちと女性談義で盛り上がります。この有名な場面が「雨夜の品定め(あまよのしなさだめ)」です。
品定めの内容
- 頭中将、左馬頭、藤式部丞が集まる
- それぞれの女性経験を語り合う
- 「中の品」(中流階級)の女性が良いという話題になる
この話を聞いた光源氏は、中流階級の女性に興味を持ちます。そして翌日、偶然その機会が訪れるんです。
方違えでの運命的な出会い
平安時代には、陰陽道で不吉な方角を避ける「方違え(かたたがえ)」という習慣がありました。
光源氏は方違えのため、家臣の紀伊守の屋敷に泊まることになります。そこにたまたま、紀伊守の父(伊予介)の若い後妻、つまり空蝉も滞在していたんですね。
出会いの経緯
- 光源氏が紀伊守邸に方違えで訪れる
- そこに空蝉も滞在していると知る
- ちょうど「中の品」の女性に興味を持っていた光源氏
- 深夜、空蝉の寝室に忍び込む
- 強引に一夜を共にする
正直に言うと、これは現代の感覚では許されない行為です。でも当時の貴族社会、特に天皇の息子である光源氏の立場では、こうした強引な振る舞いが許されてしまう時代だったんですね。
セミの抜け殻のように
空蝉という名前の由来には、切ない物語があります。
忘れられない光源氏
あの一夜以来、光源氏は空蝉を忘れられませんでした。
そこで彼は、空蝉の弟・小君を自分の元で仕えさせ、彼を通じて文を送ります。でも空蝉の答えは冷たいものでした。
「お断り申し上げなさい」
なぜ、こんなにつれないのか? 光源氏は自分になびかない空蝉を、『竹取物語』のかぐや姫になぞらえるほど、執着していきます。
二度目の訪問
諦めきれない光源氏は、再び紀伊守邸を訪れました。
そこで彼は、継娘の軒端荻(のきばのおぎ)と碁を打つ空蝉の姿を覗き見します。
垣間見での発見
- 決して美女ではない空蝉
- でも、たしなみ深く魅力的
- 一方、軒端荻は美人だが気品に欠ける
光源氏は改めて空蝉に心惹かれ、小君の手引きで寝室に忍び込みます。
空蝉の逃避
しかし、光源氏の訪れを察した空蝉は、ある行動に出ました。
空蝉の選択
- 薄衣一枚を脱ぎ捨てる
- そのまま逃げ去る
- 後に残された軒端荻と光源氏が契ることに
光源氏は、女の抜け殻のような薄衣を持ち帰ります。そして、セミの抜け殻にことよせて、空蝉へ歌を送ったんです。
「空蝉の 身をかへてける 木のもとに なほ人がらの なつかしきかな」
(セミの抜け殻を残した木の下で、やはりあなたの人柄が恋しい)
これが、「空蝉」という名前の由来になったんですね。
なぜ空蝉は拒んだのか?
多くの女性が憧れる光源氏からの求愛を、なぜ空蝉は拒み続けたのでしょうか?
身分の違いへの自覚
空蝉は聡明な女性でした。だからこそ、現実をよく理解していたんです。
空蝉の思い
- 若く高貴で魅力的な光源氏には心惹かれる
- でも、身分が釣り合わない立場だと理解している
- 受領の後妻である自分の「身の程」をわきまえている
- 一度は身を許したが、それ以上は許せない
空蝉は光源氏に訴えます。
「数ならぬ身分の私とはいえ、こうもお見下しにするのは、それだけの身分の者ということですよ」
彼女は、高貴な生まれから転落した自分の境遇を深く恥じていました。だからこそ、光源氏との関係を続けることは、自分の誇りを捨てることだと考えたんですね。
娘時代なら…という後悔
空蝉の心には、もう一つの思いがありました。
「娘時代ならよかったのに」
もし父が生きていて、自分がまだ上流貴族の娘だったなら。そうしたら、光源氏との恋も堂々と受け入れられたかもしれない。
でも今の自分は、老いた地方官の後妻。この現実を変えることはできないのです。
光源氏にとっての空蝉
皮肉なことに、空蝉の拒絶が、彼女を光源氏にとって忘れられない存在にしました。
驕慢な貴公子だった光源氏にとって、自分を拒む女性は珍しかったんです。それまで多くの女性が光源氏の求愛に簡単に応じてきました。
でも空蝉は違いました。悩み迷いながらも、最後まで品良く矜持を守り通した。これが、始めは彼女を見下していた光源氏を感心させ、執着させる結果になったのです。
その後の空蝉
空蝉と光源氏の物語は、「空蝉」の巻で終わりではありません。
「関屋」での再会
その後、空蝉は夫に従って京を離れます。
時は流れ、「関屋」の巻で二人は再会するんです。でも、二人の関係が復活することはありませんでした。
出家という選択
やがて夫を亡くした空蝉は、出家という道を選びます。
出家の理由
- 継息子の紀伊守からの懸想(恋心)を避けるため
- 世俗の縁を断ち切りたいという思い
尼となった空蝉を知った光源氏は、彼女を二条東院に迎えて住まわせました。
これは、光源氏なりの空蝉への敬意の表れだったのかもしれません。恋愛対象としてではなく、一人の高潔な女性として、彼女を支えたんですね。
まとめ
空蝉は、運命に翻弄されながらも誇りを失わなかった女性です。
重要なポイント
- 源氏物語第3帖に登場する中流階級の女性
- 高貴な生まれから父の死で受領の後妻に転落
- 17歳の光源氏と出会うが、身分の違いから求愛を拒む
- 名前はセミの抜け殻に例えた歌に由来
- 控えめで慎み深く、矜持を守り通した人物
- 最終的には出家し、光源氏の二条東院で暮らす
空蝉の物語は、平安時代の女性たちの生き方の難しさを象徴しています。生まれた家の運命に左右され、自分の意志では選べない結婚。でもその中で、自分の誇りと品位を守ろうとした一人の女性の姿が、今でも多くの人の心を打つのです。
セミの抜け殻のように薄衣を残して消えた空蝉。でも彼女の生き方は、決して空っぽではありませんでした。むしろ、強い信念と誇りに満ちた、輝く人生だったと言えるでしょう。