名前の意味
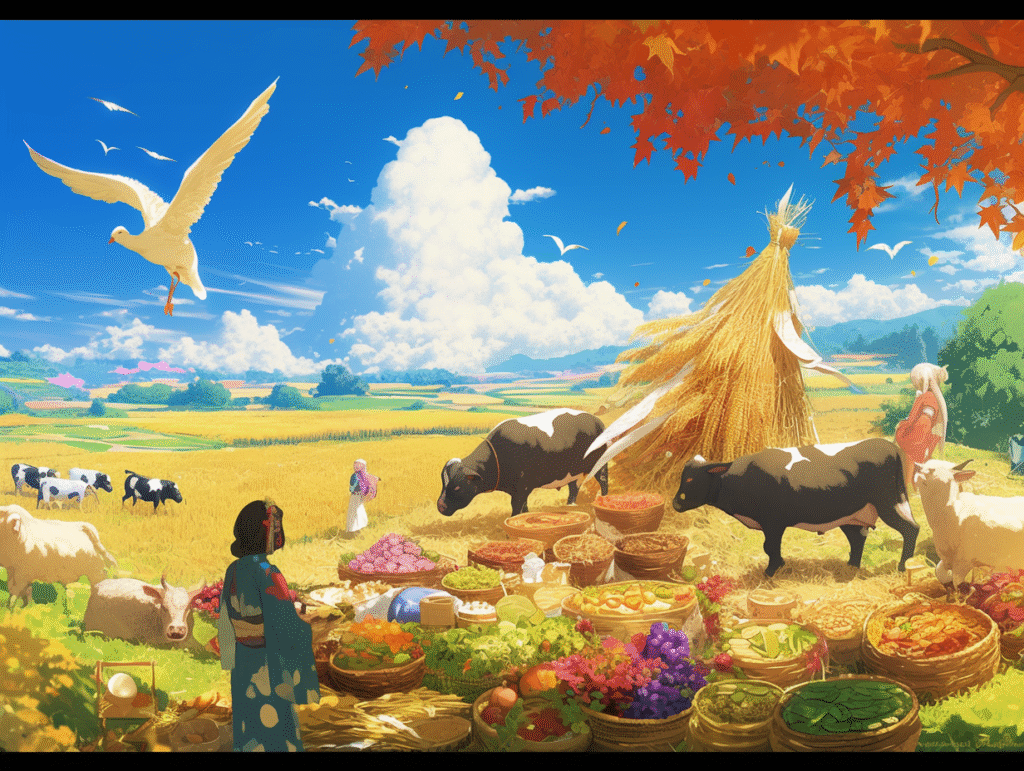
ウケモチノカミ(保食神)という名前の「ウケ(保食)」は、食べ物や穀物を意味する
これはウケモチノカミの食に関する力を表している。
神様の出自
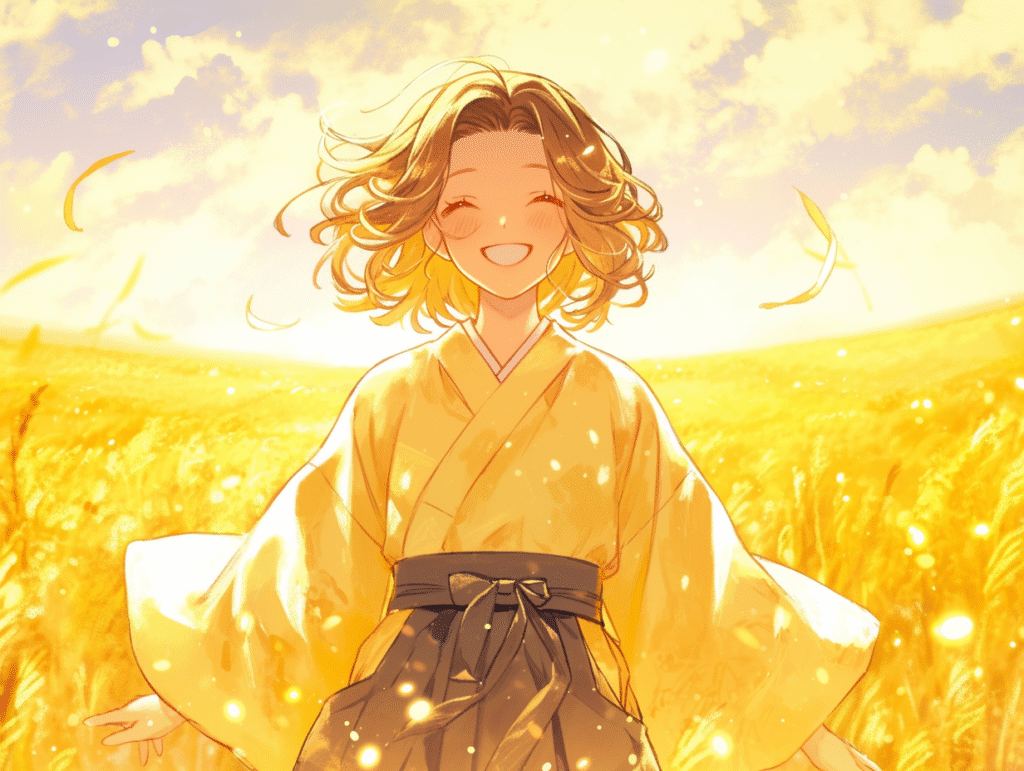
ウケモチノカミは『日本書紀』や『古事記』に登場する食物の神様です。
明確な父神や母神は伝えられていない。
名前や神格からウカノミタマ(宇迦之御魂神)やトヨウケノオオカミ(豊受大神)と同一視されることもあります。
神としての役割

ウケモチノカミの役割はシンプルですが、私たちの生活に欠かせないものです:
- 五穀の起源神:米・麦・豆・魚・肉など、あらゆる食べ物を生み出した
- 養蚕
- 農業
特に、ウケモチノカミは「食物」の根源的な神様と言えるでしょう。
神話と伝承
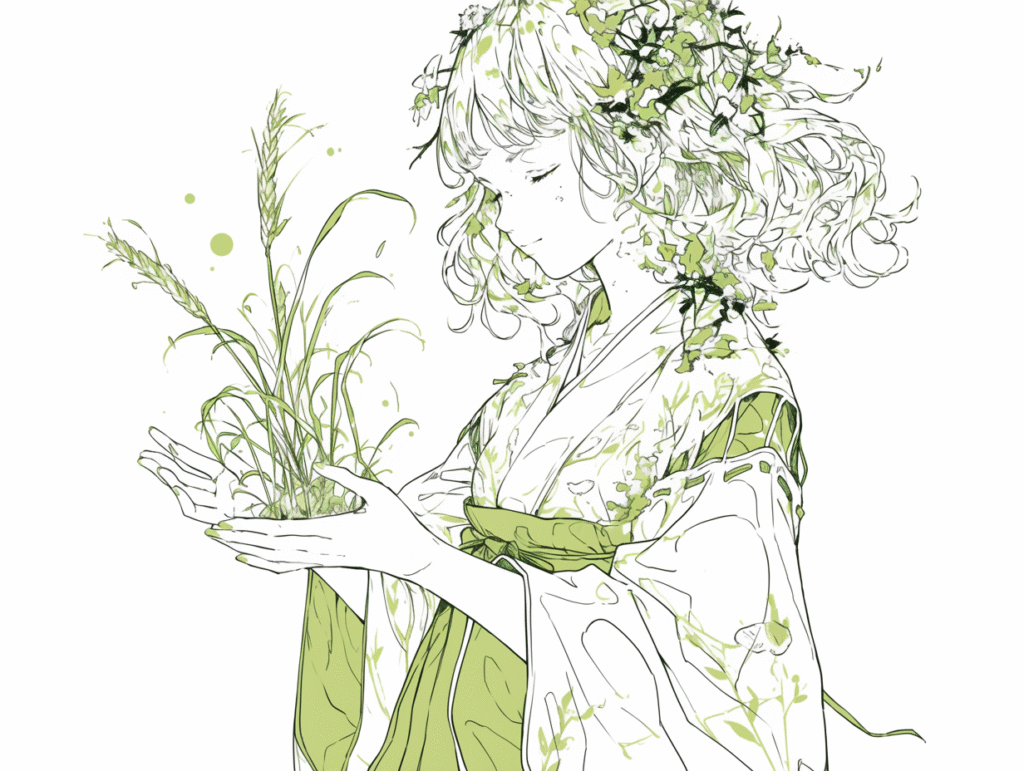
ウケモチノカミにまつわる神話は、少し悲しいながらも重要な意味を持っています。
- アマテラス(天照大神)が地上の様子を知るために月夜見命(つくよみのみこと)を派遣しました
- ウケモチノカミは訪れたツクヨミを歓迎し、自分の口や体からさまざまな食べ物(米・魚・肉)を生み出してもてなしました
- それを見たツクヨミは「口から出したものなど汚らわしい!」と怒り、ウケモチノカミを殺してしまいました
- このことをツクヨミがアマテラスに報告すると、彼女は激怒した
- こうして月と太陽は顔を合わせることは無くなった(昼と夜が交代制になった)
- この後、ウケモチノカミの遺体からは多くの食物が生まれました
- 頭からは牛と馬
- 額からは粟(あわ)
- 眉からは蚕(かいこ)
- 目からは稗(ひえ)
- 腹からは米
- 陰部からは大豆と小豆
- アマテラスは遺体から生まれた五穀を民の食物とし、田畑の種とした
この神話から昼と夜が交代制の理由や、五穀と養蚕の起源が説明されている。
神社とご利益

ウケモチノカミを祀る神社は全国にあり、特に食物や農業、養蚕(ようさん)に関する神社で重要な神様とされています。
また、同一視されたりするウカノミタマの稲荷社でも祀られている。
主な神社:
- 岩内神社(北海道)
- 竹駒神社(宮城県)
- 全国各地の稲荷神社や食物神社
主なご利益:
- 農業
- 漁業
- 狩猟
- 養蚕
- 牛馬畜産
- 航海安全
- 安産
- 産業開発
- 出世
- 開運招福
- 厄除け
食べることを守るウケモチノカミは、私たちの生活そのものを支える、身近でありがたい神様です。
また、ご利益はかなり幅広い。
まとめ
ウケモチノカミ(保食神)は食物と養蚕の神様です。
- 食物を生み出し、命を支える重要な神様
- 系譜は明確ではありませんが、その存在は食の象徴と言えます
- 神話では、命を失うことで豊かな恵みを生み出しています
- ご利益は、農漁業・牛馬畜産・産業開発・開運招福など
食べること=生きること。私たちは毎日、ウケモチノカミの恵みの中で生きているのです。







